第6話「鬼を人に返す」は、単なるネタバレ記事では伝えきれない“感情の地獄”が描かれていた。
仇と信じていた存在が「父の仇」だったと知った了助。神のように慕った男が、その刃で過去を断ち切った張本人だったと告げられた夜――彼の心に何が芽生えたのか。
この記事では、公式あらすじやSNSの一次情報をベースに、演出意図、人物の深層心理、そして「剣樹地獄」の意味を読み解きながら、第6話のすべてを徹底考察する。
- 剣樹抄 第6話に込められた感情と構造
- 了助・光圀・義仙の「地獄」をめぐる選択
- 語られなかった泰姫の沈黙の意味
- 了助の父親を殺したのは誰か?──真実を知った少年の叫び
- 義仙の「鬼を人に返す」覚悟──了助の運命を背負うということ
- 了助が知った「真実」と光圀の罪──信頼の崩壊と再生のはじまり
- 剣樹地獄とは何か?──タイトルに込められた残酷な比喩
- 剣樹抄 第6話の核心:告白・狂気・赦しの地獄
- 極楽組の正体が浮かび上がる──氷ノ介と鶴市の“壊れた信頼”
- 鍛冶屋の妻・お栄が選んだ「地獄」──愛が狂気になる瞬間
- 光圀の「償い」はどこへ向かうのか──神ではなく人として
- 語られなかった「泰姫」の想い──信じた人を止められない痛み
- 語られなかった「泰姫」の想い──信じた人を止められない痛み
- 剣樹抄 第6話の感情と構造を読み解くまとめ
- 剣樹抄 第6話の感情と構造を読み解くまとめ
了助の父親を殺したのは誰か?──真実を知った少年の叫び
この第6話が投げかけてくるのは、「真実は、いつ語るべきか?」という問いだった。
人を育てるとは、嘘を守ることなのか。信頼とは、幻想なのか。──その夜、了助の世界は音を立てて崩れた。
彼の「神様」だった光圀が、実は“父を殺した男”だったと知ったとき、心の奥に眠っていた鬼が、目を覚ました。
\剣樹抄・原作の地獄を体感せよ!/
>>>剣樹抄 原作本の購入はこちら!
/物語の真相に触れるなら今!\
光圀は、なぜ今になって「真実」を語ったのか
NHKの公式あらすじでは、第6話の副題は「鬼を人に返す」。この一文が示すのは、表面的な赦しではない。
嘘で守った心が、やがて腐る。それを知っていたからこそ、光圀はついに「告白」を決断する。
それは、正義でもなければ慈悲でもない。ただ、自分の罪と向き合う覚悟だった。
「あの子の目を、騙し続けることはできない」
そう語る光圀の言葉に、視聴者は“父のような後悔”を見出したのではないか。
真実を話すことは、自分の聖域を壊す行為だ。だが、そこからしか「人間関係の本質」は始まらない。
信じた人の裏切りは、裏切りじゃない。ただ、地獄だ。
了助は、光圀を「神様のような人」と信じていた。
それは、過去に父を亡くした喪失と、父親像の“代替”として光圀を見ていたからに他ならない。
だからこそ、その神が人だったと知ったとき──それは「信頼の裏切り」ではなく、“世界の崩壊”だった。
NHKプラスで配信された公式エピソードガイドでは、了助の動揺と叫びの演出に特に時間が割かれていた。棒を振り上げる姿、仏像を抱えて泣く姿。
「許さない!」と叫ぶあの声には、子供でありながら“許し”を知る哀しみが宿っていた。
そして光圀もまた、彼の目の前で「了助に殺される覚悟」を決めていた。それは懺悔でもなく贖罪でもない。
むしろ、“逃げ”だった。この感情の構造を描いた脚本と演出は、あまりにも静かで、残酷だった。
義仙が語る「楽をするな」の真意とは
その夜、すべての感情が渦巻く中で、静かに登場するのが義仙だ。
彼は光圀の懺悔に耳を貸さず、ただ一言だけを突き刺した。
「楽をするな」
この言葉は、今回のキーワード「鬼を人に返す」に対する、もう一つの答えだった。
人は、地獄から抜け出したくなる。罪を償いきれないとき、「死」を逃げ場に選ぶ。
しかし義仙はそれを、“光圀のわがまま”と切り捨てた。
「地獄を生きねばならぬのはお前だ、徳川光圀」
この台詞には、義仙自身の過去も含まれている。
剣に生き、地獄のような時代を彷徨い、そして光圀に救われた男が今度は、光圀を“生かす”ために戦う。
人を鬼にせず、人として地獄を歩かせる。これこそが、彼の「鬼を人に返す」作法だった。
了助を抱えて去る背中には、ただの剣士ではない、“感情の僧侶”としての覚悟が見えた。
それは暴力ではなく、再生の儀式だったのだ。
義仙の「鬼を人に返す」覚悟──了助の運命を背負うということ
義仙は剣を持たない。
かつて「斬ることでしか、自分の存在を証明できなかった」その男が、今は斬ることなく、人の運命を背負っている。
第6話での彼の役割は、単なる“助け舟”ではない。
義仙という男の過去と、光圀との因縁。そして、その延長線上にいる了助という少年の心──このすべてを背負って、彼は立っていた。
了助が知った「真実」と光圀の罪──信頼の崩壊と再生のはじまり
\光圀の“本当の顔”を追体験!/
>>>剣樹抄 原作をチェックしてみる!
/父殺しの真相がここにある!\
義仙の過去と光圀への恩──なぜ“介入”したのか
NHKの公式SNSでは、義仙(舘ひろし)の登場シーンがしばしば「無言の重圧」として描写されている。
言葉よりも、沈黙と立ち姿だけで“何を思っているのか”を語る男。
そんな義仙が、第6話で強く発した唯一の言葉が、「楽をするな」だった。
彼は語る。
「もし光圀に出会っていなければ、自分は人を斬るしかなかった。生き地獄を彷徨うしかなかった。」
義仙の人生には、「地獄」という言葉が何度も登場する。
それは剣術という暴力に生き、命を“糧”にしてきた己への戒めでもある。
そんな彼が、“恩人”である光圀を前にしても、甘さではなく、業を突きつけた。
「死んで楽になるな。生きて贖え」
この台詞は、義仙の過去があってこそ出てくる重みであり、「剣を捨てた剣士」が“口”で斬った瞬間でもある。
「剣を持たぬ剣士」が了助を抱えて去った夜の意味
義仙が了助を抱えて去る──その一連の流れは、アクションではない。
「地獄からの連れ出し」という祈りだった。
あのとき、了助の目はもう“少年の目”ではなかった。
愛した人に裏切られた怒り、そして「その怒りをぶつけるための暴力」──
その一歩手前で、義仙は了助を“奪った”。
それは介入ではない。感情を引き受けることだった。
了助の心を守るには、誰かが「殺す」必要があった。
光圀を殺すのではない。殺意そのものを“死なせる”必要があった。
義仙はその役を、自分の肩に担ったのだ。
そして、あのとき彼は「剣を持たず」に、最も人間らしい戦いをしていた。
NHKプラスでの再配信シーンでは、了助を肩に担ぎ、無言で去る義仙の後ろ姿がじっくり映し出されている。
あれは、戦士ではなく“看取り人”の背中だ。
誰にも殺させない。
少年に罪を背負わせず、光圀に贖罪を与えず、自らが「人の痛みの墓守」となる。
それが、義仙の“鬼を人に返す”という在り方だった。
彼は剣を持たない。
だがこの夜、誰よりも深く人を救い、そして誰よりも重く、人の闇を引き受けた。
剣樹地獄とは何か?──タイトルに込められた残酷な比喩
タイトルにも冠される「剣樹抄」という言葉。
第6話にして、ようやくその由来が明かされた。
それは仏教の地獄図のひとつ、「剣樹地獄」──
枝葉のすべてが“剣”でできた木が生い茂り、それに触れた鳥や獣は命を落とすという、血のように静かな地獄だ。
この概念が示すのは、「美しいものには棘がある」なんて軽い話じゃない。
これは、人の心の中に咲く“毒の花”だ。
剣樹抄 第6話の核心:告白・狂気・赦しの地獄
\剣樹抄・原作の地獄を体感せよ!/
>>>剣樹抄 原作本の購入はこちら!
/物語の真相に触れるなら今!\
地獄に咲く“剣の花”──感情を刺す構図と演出
第6話の中で、東海寺の罔両子(もうりょうし)が虫干ししていた屏風。
その絵柄として登場するのが、「剣樹地獄」。
NHK公式サイトでは言及されていないが、劇中のこのワンカットが視聴者に突き刺すメッセージは明確だ。
それは「心の中にも剣が生える」ということ。
愛が裏切られたとき、信じていた者に傷つけられたとき──
心の奥底から、言葉にならない“鋭さ”が生まれる。
それが憎しみか、怒りか、諦めか。
何にせよ、人間の感情というのは、あまりにも容易に「刃」に変わる。
そしてその剣は、自分を守るために生まれたはずなのに──
最終的には自分自身を切り裂いてしまう。
劇中、光圀の過去を暴露された了助が、何度も「信じない」と呟く姿は、その剣に貫かれる瞬間だ。
この痛みを、ただの「怒り」や「葛藤」として描かない演出が、剣樹地獄という言葉の意味を浮かび上がらせている。
“信じていた人”ほど、傷つける。
だからこそ、このドラマの世界には「救い」が必要なのだ。
人は誰しも「剣樹」を抱えて生きている
「剣樹抄」というタイトルには、もうひとつの意味がある。
それは、「抄(しょう)」という言葉の選び方だ。
“剣の木の記録”というよりも、「誰かの心に刺さった出来事の断片」──そんな響きがある。
つまりこの作品は、地獄のような事件を描いているのではなく、
“心の中に育ってしまった剣”とどう向き合うかの物語なのだ。
義仙が「鬼を人に返す」と言ったあのセリフ。
それは、「人の中の剣を、手放させること」にもつながってくる。
そして光圀も、了助も、泰姫も、鶴市でさえも──
全員が、自分の剣をどうするかで人生が変わっていく。
氷ノ介の剣は、まさに破壊の象徴だった。
名刀・骨喰藤四郎で辻斬りを繰り返し、「恐怖と混沌」という感情をばら撒いていた。
その背後にある怒りもまた、“剣樹”から生まれた痛みかもしれない。
誰の中にも「剣の枝」はある。
それを刈り取るのか、咲かせてしまうのか。
剣樹地獄は、どこか遠い場所ではない。
私たちの感情の奥底に、生えている。
このタイトルの意味に気づいたとき、「この作品がただの時代劇ではない」ことにようやく気づく。
そして気づいたあなたもまた、剣樹抄の“抄者”の一人なのだ。
極楽組の正体が浮かび上がる──氷ノ介と鶴市の“壊れた信頼”
表の世界では見えない“もう一つの炎”が、第6話で静かに揺れ始めた。
それは、極楽組という影の組織の内部で、信頼が音を立てて崩れていく様子だった。
鶴市と氷ノ介──もはや共犯ではない。むしろ、お互いに“刃”を向ける覚悟で動いている。
だがその理由は、金でも思想でもない。
互いに「信じられなかった過去」そのものが、今になって牙をむいたのだ。
氷ノ介の“炎”が向かう先はどこなのか
氷ノ介が欲しているのは、秩序の破壊だ。
第6話でも、彼は鶴市にこう告げる。
「徳川を憎む民の怒りを、破裂寸前まで膨れ上がらせろ」
この言葉は、もはや個人的な復讐ではない。
氷ノ介自身が、“怒り”という火薬の導火線を作っているという意味だ。
NHK公式サイトの登場人物紹介によれば、氷ノ介はかつて幕府に従っていた人物でもある。
つまり、一度は信じたものに裏切られた人間──その反動が、今の狂気を生んでいる。
そして彼が辻斬りに用いたのは、名刀・骨喰藤四郎(ほねばみとうしろう)。
「戯れに振るだけで骨まで砕ける」という、伝説の名を持つ刀だ。
氷ノ介は、それを“広告塔”のように使った。
──恐怖を、作品に変える。
──殺意を、政治にする。
このキャラクター造形は、ただの悪役ではない。
彼の炎は、「自分に剣を向けた世界」そのものに、燃え移っている。
だが問題は、その炎が“鶴市”という男にまで燃え移ったことだ。
鶴市はなぜ裏切りを選んだのか、それとも演技か
一見、第6話での鶴市は氷ノ介と決別するかに見える。
了助の前に現れ、「光圀の過去を知りたいだろう」と、毒のように真実を流し込んだ。
だがその一方で、光圀に向かってはこうも言っている。
「氷ノ介を3000両で売ってもいい」
この発言は、裏切りのようにも見える。
だが、本当にそうなのか?
NHKプラスでの該当シーンを見ると、鶴市の口元は微かに笑っている。
それは、策略の笑みか。絶望の笑みか。
氷ノ介にとって鶴市は、もともと「使い捨て」の存在だった。
第6話でも、「勝手なことをすれば焼き清める」と氷ノ介が鶴市に言い放つシーンがある。
鶴市は、それを恐れてはいなかった。
むしろ、その“破滅”に手を貸しているような節すらあった。
光圀に5000両での沈黙を持ちかけたことも、口封じではなく、「自分ごと地獄に引きずり込もうとする意志」だったのではないか。
鶴市は信じていない──光圀も、氷ノ介も、世界そのものも。
だからこそ、両者を“ぶつけさせる”ために、狂言回しのように動いているのだ。
そして了助という「第三の駒」をも、その渦に巻き込もうとした。
その姿は、ある意味で“冷静な破滅者”だ。
理性を失ってはいない。ただ、信頼を失った。
氷ノ介との壊れた関係性は、組織の内部崩壊を象徴している。
それは単なる裏切りではなく、「信じる」という行為そのものが、もう信じられないという悲劇なのだ。
鍛冶屋の妻・お栄が選んだ「地獄」──愛が狂気になる瞬間
誰かを想うことは、美しい。
けれど、その想いが「結果」を求め始めたとき──愛は、狂気へと変わる。
第6話のサイドストーリーとして静かに進行していた“鍛冶屋夫妻”の事件は、視聴者の心に鋭く刺さるもう一つの剣だった。
夫を想い、名を上げたいと願った妻・お栄の選択。
それは、地獄を知った者の手で“地獄を作り出す”物語だった。
名刀“骨喰藤四郎”に込められた死と欲望
光圀が名刀・骨喰藤四郎を引き合いに出して極楽組と交渉しようとしたのは、表の筋だ。
だがその刀が辻斬りに使われていた裏には、もっと人間臭い「欲望と虚栄」がうごめいていた。
鍛冶屋・康成の名刀は、本来ならば幕府に納められるべきものだった。
しかし火事によって破損したそれらの刀の修復作業をきっかけに、
妻・お栄は「夫の名を世に知らしめたい」と願う。
その一心で、お栄はなんと、極楽組に刀を流したのだ。
殺意を宣伝に。
血をブランディングに。
お栄の行動は、まさに“剣樹地獄”の象徴だった。
枝に咲いた剣は、やがて自分を貫く。
この行動を彼女がどこまで理解していたのかは、劇中では語られない。
しかし最終的にお栄は、自ら命を絶つ。
それは懺悔ではない。「もう帰れない」と悟った人間の、静かな決断だった。
お栄が見た未来と、見なかった現実
愛する人の“才能”を世界に知らしめたい。
それ自体は、美しい夢だったはずだ。
でもお栄は、その夢の先にいる「誰かが死ぬ未来」を、見なかった。
殺された者の顔。
家族の涙。
刀が使われる“現実”を、見なかった。
この構造は、社会そのものに通じている。
功績を欲し、承認を得たくて、人は“強さ”や“結果”に執着する。
けれどその裏で、誰かが何かを失っているかもしれないと、立ち止まって考えることは、どこまでも難しい。
お栄は、夫の腕を信じていた。
だけどその信頼が、「人を殺す手段」として使われていく現実に、耐えきれなかった。
NHKプラスの配信では、彼女が命を絶った場面は直接描かれていない。
しかしそれがかえって、「見えないままの痛み」として残った。
視聴者は、彼女の最期の感情を知らない。
だからこそ、彼女の“本当の動機”は、想像の中で静かに燃え続ける。
愛は、人を救う。
でも、過剰な愛は、信仰にも、呪いにもなり得る。
お栄は、夫を信じた。
その「信じる」という行為が、どこまでも深かったがゆえに、地獄へと落ちていった。
それがこのエピソードの、最も残酷な美しさだった。
光圀の「償い」はどこへ向かうのか──神ではなく人として
この第6話は、光圀が「神」ではなく「人」だったことを、容赦なく突きつける回だった。
それまで少年・了助にとって、光圀は“正義の象徴”であり、“父の代わり”だった。
だが、実の父を斬ったのがその光圀だったと知った瞬間、すべてが崩れた。
神の仮面がはがれたその下には、罪に震える一人の男がいた。
ここから始まるのは、「光圀の物語」ではなく、“光圀がどう人間として立ち続けるか”の話だ。
名に恥じぬ生き方とは、「死」ではなく「生き地獄」
「殺されてもいい」と、光圀は覚悟していた。
了助の手で、自分の命が絶たれれば──それがせめてもの償いになると思っていた。
だが義仙は、それを真っ向から否定する。
「それは、お前が楽をしたいだけだ」
この言葉は鋭い。
そして、恐ろしいほどに正しい。
死ぬことで贖罪した気になるのは、“罪の演出”でしかない。
本当に償うとは、「生きて、背負い続けること」だ。
NHK公式サイトのあらすじでは、このシーンの描写はごく短く、簡潔にまとめられている。
だが、NHKプラスでの配信では、この場面が異様に“静か”に描かれていたことが印象深い。
逃げ場のない空気、沈黙の間、照明の陰。
あれは処刑台ではなく、「心を裁く法廷」だった。
了助に跪く光圀は、自分の“尊厳”を剣に変えて差し出したのだ。
だが義仙はそれを許さなかった。
なぜなら、“殺される”ことが了助のためにならないと分かっていたから。
光圀に必要だったのは、裁かれることではなく、“生きて向き合い続けること”だった。
光圀と了助──破壊された信頼の再構築は可能か
信頼は、一度壊れたら戻らない。
では、壊れたまま進むことはできるのか?
この問いに対する答えは、まだ描かれていない。
だが、光圀の表情がほんの一瞬だけ揺れた場面──
それは、赦される未来を「望んではいけない」と、自らを律した表情だった。
了助にとって、光圀は「父の仇」だ。
でも同時に、育ててくれた“もう一人の父”でもある。
この矛盾は、簡単には解決しない。
だからこそ、「赦されないまま、関わり続ける」という関係が、唯一の答えになるのかもしれない。
義仙が了助を連れ去ったのは、光圀のためではない。
了助の心を“血”から救うためだ。
でもその裏で、義仙は光圀にも「生き地獄」という贈り物を与えた。
つまり、光圀はこれから、神ではなく人間として罪を背負っていく。
「水戸黄門」という名前に縛られた人物像の裏で、
このドラマ『剣樹抄』が描いているのは、“仏”になる前の“罪人”としての光圀なのだ。
了助が彼をどう見るのかは、今後の話だ。
だが、あの夜から始まった新しい物語が、光圀自身の人間性を問うたのは間違いない。
そして我々視聴者もまた、問われている。
人を赦せるのか?
自分の罪と向き合えるのか?
それこそが、“償い”という言葉の本当の意味ではないだろうか。
語られなかった「泰姫」の想い──信じた人を止められない痛み
この第6話を振り返ったとき、語られた“信頼の崩壊”も、“赦しの苦しみ”も、すべて男たちの物語だった。
了助、光圀、義仙、氷ノ介、鶴市──
剣を握り、罪を背負い、過去に向き合うのは、いつも男だ。
だが、何もできずに“見送るだけの人間の苦しみ”に、スポットは当たらない。
ここで忘れてはいけないのが、泰姫の存在だった。
語られなかった「泰姫」の想い──信じた人を止められない痛み
\泰姫の沈黙に隠れた真実を!/
>>>原作で彼女の心を読み解く!
/語られぬ者の地獄がここに!\
夫の「覚悟」を知りながら、何もできなかった女の叫び
光圀が「了助の父を殺した」と打ち明けることを決めたあの夜。
泰姫は、何かを察していた。
扉の前で立ち尽くし、何も言えず、何もできず。
けれど、その目には確かに「止めたい」という感情が宿っていた。
だが彼女は止めなかった。
止められなかった。
これは選択の物語ではない。
選択することすら許されない“傍観者の地獄”だ。
自らは剣を持たず、真実にも触れられず。
ただ、「夫が殺されるかもしれない」と知っていて、その背中を見送る。
それが泰姫という存在に課せられた業だった。
了助に語りかけたあの言葉──
「人には良いところと悪いところがある。光圀もそう」
このセリフの重みを、彼女自身がどれほど理解していたか。
そして、その“矛盾ごと愛してきた男”が、自分の手を離れていく瞬間。
泰姫の叫びは、声にならなかった。
正しさを選び続ける男と、隣に立ち続ける女の孤独
光圀という男は、正しさに呪われている。
罪を償おうとし、筋を通そうとし、常に“名に恥じぬ生き方”を選ぼうとする。
それは立派だ。
でも、そういう人間と共に生きることは、幸せとは限らない。
泰姫はそれを知っていた。
第5話で彼女がこぼしたあの一言。
「やっと、夫婦になれた気がする」
それは、ずっと距離があった証拠だ。
信頼していたし、愛していた。
でも、“光圀の中にある強すぎる正義”が、時に彼女を置いてきぼりにしていた。
第6話でその距離は、また広がった。
光圀が「死ぬ覚悟」を抱えて屋敷を出ようとしたとき、
泰姫は「行かないで」と叫ばなかった。
あの人はそうする、と分かっていたからだ。
正しい人と生きるには、自分の想いを殺すしかない。
それが泰姫の“生き地獄”だった。
このドラマは、「罪を背負う人間」の物語だ。
でも、“罪を背負う人を支え続けた人間”の苦しみも、確かにそこにあった。
泰姫は、戦わなかった。
でも、何もしなかったわけじゃない。
ただ、選ばなかった。
愛する人を信じたまま、“離される”痛みに耐えた。
この第6話でいちばん静かで、いちばん深い傷を負ったのは、
きっと彼女だった。
剣樹抄 第6話の感情と構造を読み解くまとめ
剣が刺さるのは、肉体だけではない。
この第6話「鬼を人に返す」が切り裂いたのは、登場人物たちの“心”だった。
光圀が語った「真実」は、了助の世界を破壊した。
だがその破壊は、再生の序章でもある。
信頼が壊れたあとに残るのは、空白ではなく「選択」だ。
許すのか、断ち切るのか、それとも共に背負うのか──
その選択を了助に与えたのが、義仙という存在だった。
剣を持たぬ剣士が背負ったのは、暴力ではなく、痛みの行き場だ。
「鬼を人に返す」とは、力で更生させるのではない。
痛みを理解し、怒りに飲まれない道を、静かに示すこと。
この回において最も胸を打ったのは、「死ぬ覚悟」と「生きる覚悟」の違いだった。
光圀が選ぼうとしたのは、死による償い。
だが義仙はそれを拒んだ。楽をするな、と。
生きることでしか背負えない罪がある。
そして、生きることでしか守れない少年の未来がある。
物語の端では、お栄という名もなき女性が、「誰かのために」と行動した結果、自らを滅ぼした。
その姿もまた、愛が地獄に変わる瞬間を描いていた。
剣樹地獄──この言葉が象徴するのは、人間の中にある“刺さるもの”だ。
信頼、愛、怒り、過去。
どれもが鋭く、どれもが切り裂く。
だがそれでも人は、剣の森の中を歩いていくしかない。
剣樹抄は、そんな「感情の地獄」の中で、誰かの手を取る物語だ。
それは派手なアクションでも、大仰なドラマでもない。
人間のどうしようもなさを、正面から描いた一編なのだ。
第6話は、物語の転換点だった。
キャラクターの内側を暴き、信頼を壊し、それでも希望を残した。
このあと、光圀と了助の関係がどうなるのか。
氷ノ介と鶴市の終着点はどこなのか。
そして義仙が了助に託した未来は、誰の救いになるのか。
この物語が“赦し”に向かうのか、それとも“断絶”に向かうのか。
答えはまだ見えない。
だが、それでも見届けたい。
なぜならこの物語は、「人間を描くこと」を諦めていないからだ。
剣樹抄 第6話の感情と構造を読み解くまとめ
\第6話の余韻を原作で深く!/
>>>剣樹抄の世界を原作で味わう!
/物語の裏側にある感情の刃!\
- 了助の父を殺した光圀の真実
- 義仙が託した「鬼を人に返す」覚悟
- 剣樹地獄が示す心の中の刃
- 極楽組内部で揺らぐ信頼と策略
- お栄の愛が引き起こした死の連鎖
- 光圀が選んだ“生き地獄”としての償い
- 信頼の崩壊と再構築の可能性
- 泰姫の沈黙に込められた別の地獄



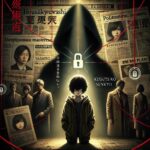

コメント