「たった一言で、人は殺せる」——そんな時代に生きている。
映画『俺ではない炎上』は、SNSの“正義”に晒された一人の男の逃亡劇を描いた、静かで激しい社会派サスペンスだ。
ただの冤罪劇ではない。観た者すべてに、「自分が“加害者”になっていたかもしれない」という戦慄を残す。
この記事では、原作・映画・主題歌を貫く「問い」の正体を、伏線とキャラクターの変化から徹底的に読み解く。
観る前に読むべき“感情の地図”として、あなたの中の炎を灯す一文になればと思う。
- 映画『俺ではない炎上』が描くSNS社会の恐怖と構造
- “誰もが加害者になり得る”現代のリアルと向き合う感情設計
- 共感と沈黙の狭間で揺れる“自分自身の居場所”の再確認
この映画が突きつけるのは、「あなたの無意識が誰かを壊している」かもしれないという事実だ
映画『俺ではない炎上』を観終えたあと、静かに頭を抱えた。
「これはただの冤罪サスペンスなんかじゃない」──そう思った。
この映画は、どこまでも〈自分〉を試してくる。
“俺ではない”は、他人事の仮面を被った自画像だ
タイトルの『俺ではない炎上』。
観る前は、「巻き込まれた側の苦しみを描く話なのかな」と軽く考えていた。
でも観終えたとき、その“俺ではない”という言葉が、自分の口から何度も出たことのある言い訳だと気づいた。
「俺はそんなつもりじゃなかった」。
「俺は知らなかった」。
「俺がやったわけじゃない」。
──全部、“俺ではない”ってことだ。
誰かが叩かれているとき、拡散されているとき、炎上しているとき。
自分はただ、横から見ていたつもりだった。
でもそれが「ただ見ていただけじゃなかった」としたら?
この映画は、そう問いかけてくる。
“無関係な傍観者”という仮面の下にある加害性。
主人公・山縣泰介が「なぜ自分がこんなことに?」と戸惑う場面、私たちは彼に同情しつつ、こうも思う。
「自分なら、きっと大丈夫」。
でも、山縣はごく普通の男だった。
家庭があり、仕事があり、特別な秘密もなく、ただ“顔が似ていた”という理由で地獄に落ちた。
つまり、「自分ではない誰か」が炎上したとき、
それが“自分”である可能性もあった。
この映画の恐ろしさは、炎上の理不尽さじゃない。
その理不尽さに、あなたが気づかないまま加担しているかもしれないという現実だ。
SNSという神殿で、人は誰かを裁くことでしか自分を保てない
SNSという言葉は、今や日常そのものになった。
つぶやき、シェアし、いいねを押し、バズった投稿をスクショして拡散する。
それ自体が悪いわけではない。
でも『俺ではない炎上』が描くのは、その“何気ない”行動の果てだ。
犯行声明ツイートが投稿され、そこに貼られた画像が「山縣泰介に似ている」と誰かが言った。
その言葉が拡散され、炎は一気に広がった。
本当かどうかなんて、誰も確かめない。
「この人、ヤバくない?」という言葉のほうが、真実よりも速く届く。
SNSは、誰かを断罪することで“自分の正しさ”を証明できる装置だ。
だから人は、自分が傷ついていなくても、他人の傷に石を投げる。
「誰かを責めていないと、自分が責められる気がするから」。
そのメカニズムを、この映画は丁寧に暴いていく。
そして、こう告げてくる。
「あなたが、最後に誰かを救ったのはいつですか?」
山縣を救おうとする人物は、ほんの一握りだ。
多くの人が沈黙する。
それは、映画の中の世界だけじゃない。
私たちのタイムラインでも、似た光景が日々流れている。
誰かが叩かれている。
それを見て、「うわー」と思いながら、スルーする。
あるいは、リツイートする。
『俺ではない炎上』が私たちに突きつけるのは、ただのサスペンスではない。
「正義の言葉」が人を殺す時代に、あなたはどう生きるのかという問いだ。
この映画を観たあと、あなたの発信する言葉の重さが、少しだけ変わっていたら。
それは、ただの映画じゃない。生き方を揺さぶる「問い」だった証だ。
伏線の巧妙さと叙述トリックが、観客の認知そのものを試してくる
この映画の構成を一言で言うなら、「認知の裏をかく設計」だ。
視点を少しズラすだけで、“真実”が“誤解”に変わる。
それは単なる叙述トリックではない。
“私たち自身の思い込み”を暴く、構造そのものがトリックになっている。
“すれ違う視点”が導く誤読の快感と恐怖
原作小説で特に評価が高かったのが、「時間軸のズレ」だ。
読者が読み進めている“現在”が、実は錯覚だったと気づく瞬間、脳が一度クラッシュする。
「あの人物とこの人物、同一人物だったの?」という気づきに、目の前の世界が裏返るような衝撃が走る。
そしてそのトリックは、映画版でも見事に再構成されている。
映像という“確定情報”で構成されるメディアにおいて、「観客の思い込み」を利用することは、ある意味で原作よりも難しい。
でもこの映画は、その困難に真っ向から挑んでいる。
例えば、娘の年齢。
たったそれだけの“ズレ”で、観客の認知は見事にひっくり返される。
「これは、いつの話だったのか?」と気づくその瞬間、時間軸の全てが塗り替わる。
まるで、自分の記憶が映画の中で改ざんされたような、奇妙な恐怖が広がる。
ここで重要なのは、“騙された”という感情よりも、“信じてしまった自分”への動揺だ。
映画はこう問いかけてくる。
「あなたは、本当に“見えていた”と思っているのか?」
この構造が、SNSという世界とシンクロしていることに気づくと、もう後戻りはできない。
ミスリードで読者を欺くのではなく、読者の思い込みを暴く仕掛け
『俺ではない炎上』のすごさは、ただ読者や観客を騙すのではなく、“騙される準備”をさせているところにある。
ミスリードのための演出が巧妙なのはもちろんだが、最も巧妙なのは、私たちがそれを「自然な情報」として受け入れてしまうよう設計されている点だ。
たとえば、主人公・泰介が誰かと話すとき、視線の動きやカメラアングルが、観客にある“前提”を植え付けてくる。
その前提が物語後半で裏切られたとき、「いや、でもあれは確かに……」と思い返すが、“確信”はどこにもなかったことに気づく。
この感覚。
それこそが、この作品が描く「情報の危うさ」そのものだ。
SNSで流れてくる“あの人が炎上した”という情報。
誰かが発した「こいつヤバい」のひとこと。
私たちは、それを“根拠”と感じてしまっていないか?
『俺ではない炎上』は、映画の中のトリックで、現実社会の“認知バイアス”を炙り出す。
そしてこう語る。
「あなたが信じた“誰かの発言”は、本当に正しかったのか?」
これは、構成の妙を語る記事でもなければ、脚本の巧さを称賛するだけの考察でもない。
この映画は、あなたの“信じたい欲望”を利用してくる。
そしてその果てに、「正義とは何か」「真実とは何か」という問いではなく、
「自分は“何を信じたかったのか”」という、もっと個人的で苦い問いを残していく。
この映画のラストで、自分の認知がひっくり返ったとき。
それはストーリーのどんでん返しじゃない。
“自分自身へのどんでん返し”なのだ。
原作と映画、それぞれが描いた“炎上”の正体とその向こう側
原作と映画、どちらにも触れて思った。
この作品は、「炎上」を描いているようで、“人間が炎上の中でどう壊れていくか”を描いている。
そしてその壊れ方が、原作と映画でまったく異なる質感を持っているのが面白い。
原作は「構造」で刺し、映画は「表情」で刺してくる
原作小説『俺ではない炎上』は、徹底して構造で攻めてくる。
時間軸のトリック、視点のすり替え、情報の制御。
読む側が「事実」だと思っていたものが、ただの誤解だったとわかる瞬間に、脳がグラつく。
たとえば、娘の年齢のズレに気づく場面。
言葉にすれば些細な情報のはずなのに、それが物語全体の認識を変えてしまう。
構造そのものが“炎上”のメタファーになっているのだ。
炎上とは、ほんのわずかな誤解が増幅され、爆発的に人を飲み込む現象。
原作は、それを読者の“脳”で体験させる。
一度バラバラになった物語が、終盤で収束していくとき。
「ああ、自分もこの錯覚を拡散していたかもしれない」と読者は気づかされる。
一方、映画は“感情”で刺してくる。
映像の中では、構造的トリックを文章ほど細かく積み上げることはできない。
その代わりに映画は、役者の“顔”に全てを賭けた。
山縣(阿部寛)の微妙な表情の揺れ。
サクラ(芦田愛菜)の冷たい視線の奥に潜む怒り。
誰かがカメラを見ずに沈黙するだけで、「あ、この人、何かを隠してる」と観客は“感じて”しまう。
その“感じてしまう”が、この映画最大の武器だ。
構造で“錯覚”を起こさせる原作に対し、映画は“感情”で先入観を植え付けていく。
そして、終盤になってその印象をバラバラに解体していく。
ある意味、映画のほうが観客を無防備にする。
「何も知らない自分」がどれほど危ういか、痛感させられる。
「嘘の自分」を演じさせられる恐怖を、映像はどう伝えたか
SNSで炎上すること。
それは、自分の人格が、誰かの“イメージ”によって書き換えられるということだ。
「こいつはこういう人間だ」という投稿が、数千、数万と拡散されたとき。
本当の“自分”は、その中にもう存在できない。
映画の中で、山縣は「犯人じゃない」という事実を持っている。
でも、その“事実”よりも早く広まったのは、“誰かが勝手に作った彼”だった。
この“乗っ取られる感覚”が、映像によってより生々しく伝わってくる。
顔写真が出回り、ニュースが「本人です」と断言し、誰かが「アイツだ」と決めつける。
もう何を言っても、誰も聞いていない。
そして山縣は、「俺ではない」と叫ぶことすら許されなくなる。
このとき彼が見せる、“嘘の自分を演じざるを得ない苦悶の表情”。
それこそが、今この時代にしか描けないホラーだ。
SNSでは、真実は遅い。
印象が“先に広まる”構造そのものが、現代的な地獄なのだ。
だからこそ、この映画の中で山縣が時折見せる「戸惑い」「怒り」「諦め」が、胸に刺さる。
そのすべてが、言葉にならないままスクリーンに焼き付けられていく。
原作は論理で、映画は感情で。
それぞれのメディアが、炎上というテーマに対してまったく異なる方法で斬り込んでいる。
そして、どちらもが「あなたも、燃やされる側になり得る」と語りかけてくる。
でもそれだけじゃない。
「あなたも、誰かを燃やしていたかもしれない」とも告げてくる。
原作と映画、それぞれの強さ。
それは、“他人事”でいられない何かを、読者と観客に刻み込む力なのだ。
主演・阿部寛と芦田愛菜の演技が、“人間の危うさ”をむき出しにする
この映画の強さは、ストーリーや構成だけじゃない。
主演2人──阿部寛と芦田愛菜の演技が、物語の「深度」を底から引き上げている。
彼らの演技を観て、改めて思った。
人は、こんなにも脆くて、怖くて、愛おしい存在なんだと。
山縣泰介は「僕たち自身の弱さ」そのものだ
阿部寛が演じる主人公・山縣泰介。
彼は、どこにでもいる営業部長だ。
家族がいて、部下との付き合いがあって、日常を丁寧に生きている男。
でも、そんな“普通の人間”が、ある日突然、SNSによって「殺人犯」にされる。
この非現実的な現実を、阿部寛は演技で地続きにした。
最初はただの戸惑い。
だが次第に、怒りと恐怖、そして諦めと疑念が混ざり合い、彼の表情はどんどん“壊れて”いく。
「なんでこんなことに…」と誰かに問う視線。
それを観客は、「もし自分だったら」と想像してしまう。
そして気づく。
山縣は僕たち自身だ、と。
無実なのに説明できない。
説明しても聞いてもらえない。
信じていた誰かが、少しずつ距離を置く。
その“孤独の深度”を、阿部寛は一切の大げさな表現なしで演じてみせる。
泣きわめかない。
怒鳴らない。
ただ、少しずつ何かを諦めていく表情だけで、観客の胸を締めつける。
とくに中盤、山縣が自分の写真がネットに拡散されたスマホ画面を見つめる場面。
そこでの“まばたきの回数の少なさ”が、静かな絶望を物語っていた。
心が現実から置いていかれる瞬間。
その演技に、何度も息を呑んだ。
サクラの“感情の爆発”が暴く、見ないふりしていた怒り
一方、芦田愛菜演じる“サクラ”は、正反対の存在だ。
彼女は冷たく、怒っていて、時に感情を爆発させる。
そして何より、観客にとって「理解しにくい存在」として描かれている。
その“理解できなさ”こそが、サクラというキャラクターの核心だ。
観客はつい、山縣に感情移入する。
「かわいそう」「理不尽だ」と。
でも、サクラの言動を見ていると、「あれ、山縣は本当に完全な被害者なのか?」と一瞬揺らぐ。
そして、その揺らぎが「思い込み」を炙り出す。
芦田愛菜は、感情の起伏を“断絶”として見せる。
怒りの直後に冷静。
微笑んだかと思えば、数秒後に目が完全に死んでいる。
この“反転”が、観客の心を揺らし続ける。
彼女が声を荒げる場面は少ない。
むしろ、声を抑えたときの怒りが、画面越しにビリビリと伝わってくる。
あるシーンでは、まるで何かを「吐き出すように」喋る。
その言葉が観客の胸に刺さるのは、彼女が“傷ついた経験者”の顔をしているからだ。
サクラの存在が浮き彫りにするのは、「見ないふりをしてきた社会の怒り」だ。
言葉を選ばずに言えば、
私たちが加害者だったかもしれないという事実に対して、サクラは怒っている。
山縣とサクラ。
その2人のコントラストが描き出すのは、“この社会が壊してきた人たち”の顔だ。
そして、それを見ている観客もまた、決して無関係ではいられない。
この映画における演技とは、「感情の代弁」ではなく、観客自身が“どの立場なのか”を問う装置なのだ。
だから観終えたあと、誰かにこう言いたくなる。
「あの2人の演技は、ただの演技じゃなかった」と。
主題歌「△おっかない△」が、観客の心に“炎”を残していく
映画のエンドロールが始まった瞬間、観客の中に“もうひとつの物語”が流れ始める。
それが、主題歌「△おっかない△」だ。
WANIMAによるこの曲は、ただのエンディングテーマではない。
物語の余韻を“言葉と音”で追体験させる、もう一つのメッセージだ。
WANIMAが鳴らすのは、言葉の暴力に晒された者の叫び
炎上とは、炎ではなく言葉で人を燃やす現象だ。
拡散、引用、タグ付け、嘲笑。
そのどれもが、「文字」だ。
そして、WANIMAの「△おっかない△」は、その“文字の凶器性”を、音楽に変えて突きつけてくる。
疾走感のあるロックサウンドの中に、不安と焦燥が散りばめられている。
怒っているのに、泣きそうで。
叫んでいるのに、声がかすれている。
この曲の不安定さは、まさに“炎上された側の心”そのものだ。
ある日突然、何者かに定義され、自分の声がかき消されていく。
気づけば、全ての発言が「言い訳」に聞こえるような空気の中。
「誰か、聞いてくれ」と叫ぶことすら、炎上の燃料になる。
WANIMAは、この苦しみを抽象化しない。
むしろ、“実在する痛み”として真正面から描いている。
「△おっかない△」という、いびつで奇妙なタイトルに込められたのは、
“子どものような怯え”と、
“大人としての諦め”が同居した複雑な感情だ。
そして、それが映画の物語と完璧に重なり合う。
自分の意思とは関係なく、誰かの物語にされてしまう恐怖。
音楽が、その感情の行き場をそっと支えてくれる。
KENTAの歌詞は「炎上の痛み」を通り越し、その先の“赦し”を歌う
この曲が特別なのは、痛みや怒りだけを描いていないからだ。
ラストに、“光”が差している。
ボーカルのKENTAが語った言葉が、すべてを物語っている。
知らない誰かの言葉に心を揺さぶられる痛みを、“最後の火”に変えて鳴らすことで、恐れを力に変え、未来を照らす希望へと導きたい。
“最後の火”という表現に、ゾクリとした。
この映画の中で、人を燃やしてきたのは「誰かの火」だった。
でも、KENTAはその火を「希望」に変えようとしている。
傷ついた者が、自分の声を奪い返す。
もう誰かに定義されるんじゃなく、自分で自分を名乗る。
そんな再生の意志が、この曲には確かにある。
映画のラストでこの曲が流れたとき、
観客の中に“もう一つのストーリー”が生まれる。
スクリーンに映らなかった、山縣のその後。
誰にも言えなかった、サクラの本音。
そして、観客自身が心に抱えてきた、名前のない痛み。
WANIMAの音が、それらをすべて肯定してくれる。
「わかるよ」と言ってくれる。
映画と音楽が、ここまで密接に呼応する作品は稀だ。
この主題歌は、“エンドロールで終わらない物語”を生んでしまった。
だから私は、映画を観終えたあと、
劇場を出る瞬間まで、耳に残るその旋律に、ずっと背中を押されていた。
痛みの中に、小さな“灯り”があった気がする。
「誰が加害者で、誰が被害者か」——その問いに答えはない、だからこの映画は痛い
映画を観終えたあと、ずっと考えていた。
この物語の中で、誰が悪かったんだろう?
山縣? サクラ? 初羽馬? それとも、炎上を面白がった大勢の誰か?
考えて、考えて、でも答えは出なかった。
それもそのはずだ。
この作品は、“加害”と“被害”を分けられない時代の物語なのだから。
映画を観終えたあと、もう一度SNSを開くとき、指が震えるかもしれない
この映画が描くSNSの世界は、どこまでもリアルだ。
誰かが怒っている。
誰かが謝っている。
誰かが笑っている。
誰かが沈黙している。
そのすべてに、「正義」が乗っかっている。
そして私たちは、毎日それを“見ている”。
でも、見ているだけで済んでいるだろうか?
この映画が投げかける問いは、じわじわと自分自身に向かってくる。
山縣のように「晒された側」になる恐怖。
そして、サクラのように“黙っていた誰か”に怒りをぶつけることの正当性。
どちらも、よくわかる。
どちらも、苦しい。
それがこの映画の痛みだ。
映画の終盤、何かが解決したようで、何も解決していないことに気づく。
真実が明かされても、壊れた関係は戻らない。
名誉が回復しても、失った時間は戻らない。
そして炎上に加担した“名もなき加害者たち”には、誰も責任を問わない。
──いや、問えないのだ。
なぜなら、それは「自分かもしれない」から。
だから観終わったあと、SNSを開く手が、一瞬止まる。
誰かを断罪する投稿を見て、「リツイートするべきか」と指が震える。
それだけで、この映画は“勝っている”。
“この映画は面白いか?”と問うこと自体が、もうズレている
『俺ではない炎上』は、間違いなく完成度の高い映画だ。
サスペンスとしても、構成としても、演出としても。
でもそれを「面白かった」と言ってしまうと、どこかで自分をごまかしている気がした。
この映画は、“良くできていた”かもしれない。
でも、“気持ちよく観れた”わけじゃない。
むしろ、観終わってからが本番だ。
誰のせいでもない“集団の無関心”。
拡散された言葉に乗って、ちょっとだけ面白がってしまった自分。
そこに潜む“加害性”に気づいてしまったとき、
「面白かった」とはもう、簡単には言えなくなる。
この作品が問うのは、映画の中の世界ではない。
今、ここで生きている“私たちの目の前の現実”だ。
その現実を、見ないふりしない人だけが、
この映画の“痛み”を受け止められる。
観終わったあと、誰かに語りたくなる。
でもそのとき、「何を語らなかったか」も、きっと大切なんだと思う。
「共感しなきゃ置いていかれる」時代に生きてる僕たちへ
この映画を観て、頭に残ったセリフはなかった。
でも、言葉にならなかった感情が、心にずっと居座ってる。
「わかるよ」って、簡単に言えない。
「許してあげなよ」とか、「悪くないじゃん」とも言えない。
なんでって?
だって、それを言った瞬間、誰かに置いていかれる気がするから。
“言葉にされる前”の感情は、誰にも守ってもらえない
映画の中で描かれていた“炎上”って、たぶんもうネットの話じゃない。
「空気を読む」とか「共感を示す」っていう、日常的な圧力にすり替わってる。
誰かが責められてるとき、「え、そうなの?」って一歩引いたら、
それだけで「おまえも加担してんの?」って空気になる。
共感できないと、“鈍い人”って扱われる。
それが怖い。
だから、みんな感情を急いで言葉にする。
「ムカついた」
「泣けた」
「胸が痛い」
誰よりも早く、“この感情のチーム”に入ろうとする。
でも、そのスピードの中でこぼれ落ちてる感情って、きっとある。
言葉にする準備ができてなかった想い。
まだうまく説明できない“違和感”。
映画の中で山縣が抱えていたのって、そういう感情だったんじゃないか。
「なんでこんなことになってるのか、自分でもわからない」
「怖い。でも何が怖いのかも、わからない」
その言葉にならない感情に、誰かが耳を傾ける前に──
もう、火はついてた。
だからこの映画が突き刺さるのは、「やらかした人」じゃなく、「黙ってた人」だった
『俺ではない炎上』って、加害者の物語でも、被害者の物語でもない。
“黙っていた人たち”の物語だ。
何も言わなかった人。
言葉を選んでるうちにタイミングを逃した人。
うまく共感できずに、ただ見てた人。
その人たちの“無言のグラデーション”を、この映画は描いてた。
だからこそ刺さる。
炎上した当事者よりも、「自分はただ静かにしてただけなのに」と思ってる人こそが、一番ぐらつく。
ネットの話に見えて、実は職場や学校の話にも重なる。
誰かがミスしたとき、うまく言葉にできなかった人たち。
「関わりたくなかった」
「どうフォローすればよかったかわからなかった」
そんな“モヤモヤの中にいた人”たちの感情を、
この映画は一切責めず、ただ見つめていた。
だから観終わったあと、「ごめん」も「わかる」も、どっちも言えなくなる。
でも、それが本当に人の感情だと思う。
共感しすぎず、共感しなさすぎず。
その真ん中にある、“うまく言えない思い”に目を向けたとき──
この映画は、初めて自分の話になる。
『俺ではない炎上』が描いた“誰でも炎上する時代”の恐怖と希望|まとめ
映画『俺ではない炎上』は、冤罪を描いたサスペンスでありながら、
「誰もが“無自覚な加害者”になりうる世界」を映し出している。
そしてそれは、もう映画の中だけの話ではない。
面白さの裏にある「社会の病理」と向き合えるか
この映画が怖いのは、炎上が起こる“仕組み”が理不尽だからではない。
その仕組みがあまりにも“自然”で、誰も気づかずに参加してしまうからだ。
誰かが炎上する。
見てるだけのつもりでも、リツイート一つ、スクショ一枚が、“燃料”になっている。
その無自覚さこそが、この映画が描く最大の“社会の病理”だ。
そして本作のすごさは、その病理を、“エンタメ”として語らせてくれることにある。
逃亡劇のスリル。
伏線の巧妙さ。
俳優たちの繊細な演技。
一見して“面白い”要素の中に、恐ろしいまでの現実が滑り込んでいる。
そして、それを楽しんでしまった自分に、後からゾッとする。
それでいい。
その違和感こそが、この映画の仕掛けた“二重構造のラストシーン”なのだ。
この作品を「他人事」にしないこと、それが私たちの唯一の救いかもしれない
この映画を観て、「ああ、怖かったな」で終わってしまったら、それは“敗北”だ。
怖いのは、ストーリーじゃない。
怖いのは、この物語が日常に限りなく近いという事実だ。
SNSで誰かが燃えている。
それを見て、「自分は関係ない」と思う。
けれども、“その無関心こそが”炎上の酸素だったのだと、
この映画は容赦なく突きつけてくる。
だからこそ、私たちにできることはただひとつ。
この作品を「他人事」にしないこと。
それが、唯一の希望かもしれない。
主題歌「△おっかない△」で歌われたように、
誰かに奪われた“言葉”を、もう一度自分で選び取る。
それが、「炎上の時代」を生きる私たちの小さな抵抗になる。
映画を観たあと、自分のSNSをもう一度見てみる。
そこにある投稿、引用、タグ、いいね。
それが「誰かの人生を動かしてしまっているかもしれない」と思った瞬間、
あなたの中で、この映画は終わらない。
『俺ではない炎上』。
でもたぶん──
「俺でもあったかもしれない炎上」だった。
- SNS炎上の構造と“無意識の加害性”を暴く社会派サスペンス
- 伏線と叙述トリックが観客の“思い込み”を試す
- 阿部寛と芦田愛菜が演じる“壊れていく人間”のリアル
- 主題歌「△おっかない△」が物語に“もう一つの痛み”を残す
- 加害者と被害者の境界が曖昧な現代を鋭く映す
- 沈黙していた“あなた”にも突き刺さる感情の余白
- “共感しなきゃ置いていかれる”時代の息苦しさと向き合う
- この映画を“他人事にしない”ことが、最初の一歩になる




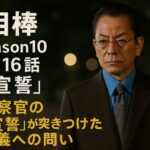
コメント