NHK大河ドラマ「べらぼう」に登場する女将たちに眉毛がない理由が話題になっています。
現代の感覚では驚くかもしれませんが、これは江戸時代の化粧文化「引眉(ひきまゆ)」に基づいた表現です。
この記事では、「べらぼう」の中で描かれる“眉なし”演出の背景や、江戸時代の女性たちの化粧や価値観、そして実際に眉を剃って挑む女優たちの姿に迫ります。
- 女将たちに眉毛がない理由と引眉の歴史的背景
- 「べらぼう」出演女優が見せたリアルな演技への覚悟
- 江戸時代と現代の“美意識”の違いとその価値観
「べらぼう」の女将たちが眉毛を剃っているのは引眉という江戸時代の慣習のため
ドラマ「べらぼう」に登場する女将たちに眉毛がないのは、単なる演出ではなく、江戸時代の文化的背景に基づいた表現です。
「眉毛がない女性」に違和感を覚える視聴者も多いかもしれませんが、実はこれは当時の既婚女性の一般的な化粧習慣でした。
その背景には、「引眉(ひきまゆ)」という日本独自の美容文化が存在していたのです。
引眉とは?既婚女性の身だしなみだった江戸時代の風習
引眉とは、眉毛をすべて抜いたり剃ったりして、描き直す化粧法です。
主に奈良時代から江戸時代にかけて広く行われ、特に既婚女性や子どもを持つ女性の象徴とされました。
眉毛を剃り落とすことは、未婚から既婚への転換、つまり大人の女性としての証とされていたのです。
眉をなくすことが“成熟”の証だった当時の常識
江戸時代では、20歳を過ぎても眉毛がある女性は「年増(としま)」と呼ばれ、時には“行き遅れ”と見なされることもありました。
そのため、未婚女性であっても世間体を気にして、あえて眉を剃ることで既婚のふりをすることもあったそうです。
このように、眉の有無は社会的な立場や年齢を表す記号でもあったわけです。
現代の感覚とのギャップに視聴者も注目
視聴者の中には「なぜ女将たちに眉がないのか」と疑問に思った方も多いでしょう。
しかし、これは「べらぼう」が時代考証を重視した作品である証拠でもあります。
単なる演出や特殊メイクではなく、歴史的事実に基づいた描写であることを知ると、より深く物語に入り込めるはずです。
実際に眉を剃って演じる女優たちの覚悟とリアル
ドラマ「べらぼう」では、眉毛がない女将たちの姿がリアルに描かれていますが、驚くべきはそれがCGや特殊メイクではないことです。
水野美紀さんや飯島直子さんらは、実際に自分の眉毛を剃って撮影に挑んでいるのです。
役に対する真剣な姿勢と、女優としてのプロ意識がにじみ出るエピソードです。
水野美紀や飯島直子のSNS投稿に見るプロ意識
水野美紀さんは、X(旧Twitter)にて眉を剃った自身の顔を「妖怪のようだ」とユーモアを交えて投稿し、ファンの笑いを誘いました。
「べらぼう」の現場では、モニターに映る小芝風花に見惚れていると、突然“妖怪”のような自分の顔がアップになり「ヒイッ!」ってなる。あたしだよ。
この投稿には、演技だけでなく遊び心も忘れない水野さんの魅力が詰まっており、多くの称賛の声が寄せられました。
特殊メイクではなく“地眉”を剃るという選択の裏側
女優の飯島直子さんも、Instagramにて眉のない顔で日常を過ごす姿を投稿。
普段の生活に支障をきたすこともある中でのこの選択は、役に対する覚悟の証と言えるでしょう。
一見些細な変化に見える眉毛の有無ですが、演じる側にとっては大きな挑戦であり、視聴者にリアリティを届けるための重要な要素となっています。
女優たちの挑戦が作品の深みを増している
眉を剃るという行為は、現代の女優にとってリスクもあります。
しかし「べらぼう」の出演者たちは、歴史のリアリズムに徹底的に向き合い、視聴者にリアルな江戸の空気感を届けようと努力しています。
そうした細部へのこだわりが、作品の説得力や奥行きを支えているのです。
江戸時代の女性の化粧と美意識:白粉・紅・お歯黒・引眉の意味
江戸時代の女性たちにとって、化粧は単なる身だしなみではなく、身分や立場を表す重要な表現でした。
その中でも「白粉(おしろい)」「紅(べに)」「お歯黒(おはぐろ)」「引眉(ひきまゆ)」は、時代を象徴する四大化粧法とも言えます。
「べらぼう」の世界観を理解するには、この江戸時代独特の化粧文化に注目する必要があります。
「白」「赤」「黒」だけだった江戸の化粧法
江戸時代の化粧に使われていた色は、基本的に白(白粉)・赤(紅)・黒(眉墨・お歯黒)の3色のみでした。
白粉は肌の白さ=美しさとされた時代の象徴であり、塗り方にも細かな作法が存在しました。
紅は唇や頬に使われ、艶やかさや色気を演出し、眉墨やお歯黒は成熟した女性としての品格を示す手段でした。
お歯黒と引眉で“妻”を象徴する化粧スタイル
お歯黒は、既婚女性が歯を黒く染める習慣で、貞節の証とも言われました。
鉄分を含むお歯黒水と染料の五倍子(ふし)を使って歯を染めることで、虫歯や歯周病の予防にも効果がありました。
また、引眉とセットで行われることが多く、結婚・出産後の女性の「しるし」として社会に認識されていたのです。
浮世絵にも描かれる“眉なし既婚女性”のリアル
浮世絵師たちは、既婚女性や母親を描く際には原則として眉なしで描くという暗黙のルールを守っていました。
ただし、20代女性には老けて見えないよう、眉を描くことも黙認されていたと言われています。
このように、化粧は単なる美的表現ではなく、「女性の履歴書」のような役割を果たしていたのです。
吉原の文化と引眉の関係:遊女と女将の役割の違い
「べらぼう」に登場する女将たちが眉毛を剃っている理由は、単に既婚女性だからというだけではありません。
その背後には、吉原という特別な社会の中で築かれた独自の文化と、遊女と女将の立場の違いが密接に関係しています。
引眉は、女将としての威厳や成熟を象徴する記号としても機能していたのです。
吉原における“女将”とはどんな存在か
吉原の女将とは、単なる店の管理人ではなく、女郎たちを育て導く教育係であり、経営者でもありました。
彼女たちは長年の経験を重ね、社会的な信頼と威厳を備えた「大人の女性」として描かれていました。
そのため、眉毛を剃り落とす引眉は、人生経験と母性的存在感を可視化する化粧だったのです。
なぜ遊女より女将に引眉が強調されるのか
遊女たちは「魅せること」が仕事であるため、化粧も華やかで若々しく見せる工夫が施されました。
一方、女将は客を迎える立場にあり、礼節と重厚感が求められる存在であったため、引眉を行うことで落ち着いた印象や貫禄を演出していたのです。
「眉がない=老け顔」ではなく、むしろ経験値の証としての意味合いがあったわけです。
「べらぼう」における引眉の演出がもつ意味
「べらぼう」の演出では、眉がないことで女将たちの人格や存在感が際立つように描かれています。
この細部へのこだわりは、時代劇としての信頼感と説得力を高め、視聴者の没入感を深めることに貢献しています。
眉の有無ひとつで人物の内面まで表現しているところに、「べらぼう」という作品の奥深さが現れています。
現代と違う江戸時代の“美の基準”
「べらぼう」の登場人物たちの化粧や風貌を見て、違和感を覚えた現代の視聴者も少なくないでしょう。
それは、江戸時代と現代とで“美の基準”が大きく異なっていたからです。
江戸時代には江戸時代なりの「理想の美人像」が存在しており、それを実現するための化粧が日常的に行われていました。
色白こそ美人の第一条件だった江戸時代
江戸時代において最も重要視された美の要素は、肌の白さでした。
そのため、白粉を顔全体に塗り重ね、より白く見せることが美意識の頂点とされていました。
白粉の塗り方にも厳格な手順があり、額→頬→鼻→口周り→首筋の順で何度も塗り重ねて仕上げていたそうです。
“目が小さいほど美しい”という逆転の価値観
現代では大きな目が好まれますが、江戸時代では「目が大きすぎるのは見苦しい」とされていました。
瞼に濃く白粉を塗り、目を小さく見せるように化粧するのが主流で、控えめな表情が上品と見なされていたのです。
このように、時代によって美意識は大きく変わることがわかります。
鼻筋の通った顔立ちが“理想的な女性像”
白い肌に次いで重視されたのが、鼻筋の通った整った顔立ちでした。
白粉を鼻筋に厚めに塗ることで、立体感を演出する化粧技術も用いられていたのです。
こうした工夫からも、江戸時代の人々がいかに「美しさ」にこだわっていたかがうかがえます。
眉毛がない“女将たち”から見える、世代間の“美意識ギャップ”と女の覚悟
「べらぼう」を見ていてふと感じたのが、女将たちの“眉なし”姿に宿る圧倒的な説得力。
いねやふじ、りつたちが眉毛を剃ってまで演じている姿は、単なる時代考証以上に、“生き様”そのものを表している気がしました。
現代なら、眉がない顔に不安を感じる人も多いですよね。アプリで加工して、なるべく「キレイ」に見せるのが当たり前な時代。
でも彼女たちは、「見せたい自分」よりも、「生きてきた時間そのもの」を素直に出している気がするんです。
“盛る”よりも“削る”――大人の女性が持つ静かな強さ
眉を消すって、実はすごく勇気がいること。
でも、それをあえてやるということは、「私はもう、飾らなくてもいい」と言える自信や覚悟のようなものを感じます。
ふじやいねが見せる“怖さ”や“包容力”は、その眉のない顔だからこそ成立しているのかもしれません。
若さや可愛さだけじゃない、“削ぎ落とされた美しさ”がそこにはありました。
現代女性にも刺さる、“自分を受け入れる”というメッセージ
20代、30代の私たちにとって、年齢を重ねることにネガティブな気持ちを抱く瞬間って、少なくないですよね。
でも「べらぼう」の女将たちを見ていると、歳を重ねること=弱くなることじゃないって、優しく背中を押してくれている気がします。
“隠す”美しさから、“出す”美しさへ。
眉毛ひとつで、そんな価値観の変化まで感じさせてくれるのが、「べらぼう」という作品のすごさだなと思いました。
べらぼう、眉毛ない、なぜ――江戸の文化と時代考証を知ることで見える魅力【まとめ】
「べらぼう」に登場する女将たちの“眉毛がない”姿は、初見では驚きを覚えるかもしれません。
しかし、それは単なる奇抜な演出ではなく、江戸時代の文化や美意識を正確に再現した表現なのです。
引眉やお歯黒といった風習を知ることで、当時の人々の価値観や社会構造までもが浮き彫りになります。
さらに、実際に眉を剃って撮影に臨む女優たちの覚悟にも注目したいところです。
現代では“盛る”ことが重視されがちな中、“削ぐ”ことで役に命を吹き込む彼女たちの姿は、観る者に強いインパクトを与えます。
時代劇だからこそできる表現、そしてその背景にある史実に触れることで、「べらぼう」の世界はより奥深く、より魅力的に感じられるでしょう。
“なぜ眉毛がないのか”という疑問を入り口に、江戸文化の知識が深まり、
その過程で現代の私たちが忘れがちな「覚悟」「品格」「成熟」についても、気づかされるきっかけになるはずです。
「眉がない」――そこに込められた歴史と思想は、ただの演出を超えて、物語に深い説得力を与えているのです。
- 女将たちの“眉なし”は江戸時代の化粧文化「引眉」に由来
- 引眉は既婚・出産経験者の身だしなみとされていた
- 「べらぼう」出演女優たちは実際に眉を剃って撮影に挑戦
- 水野美紀や飯島直子のSNS投稿が注目を集めた
- 江戸時代の女性美は「白い肌」「細い鼻」「小さい目」が理想
- 眉の有無が未婚・既婚を示す重要な社会的サインだった
- 女将は“貫禄と品格”を表す存在として引眉が強調されている
- “盛る”現代とは逆の“削る”美意識に見る大人の覚悟

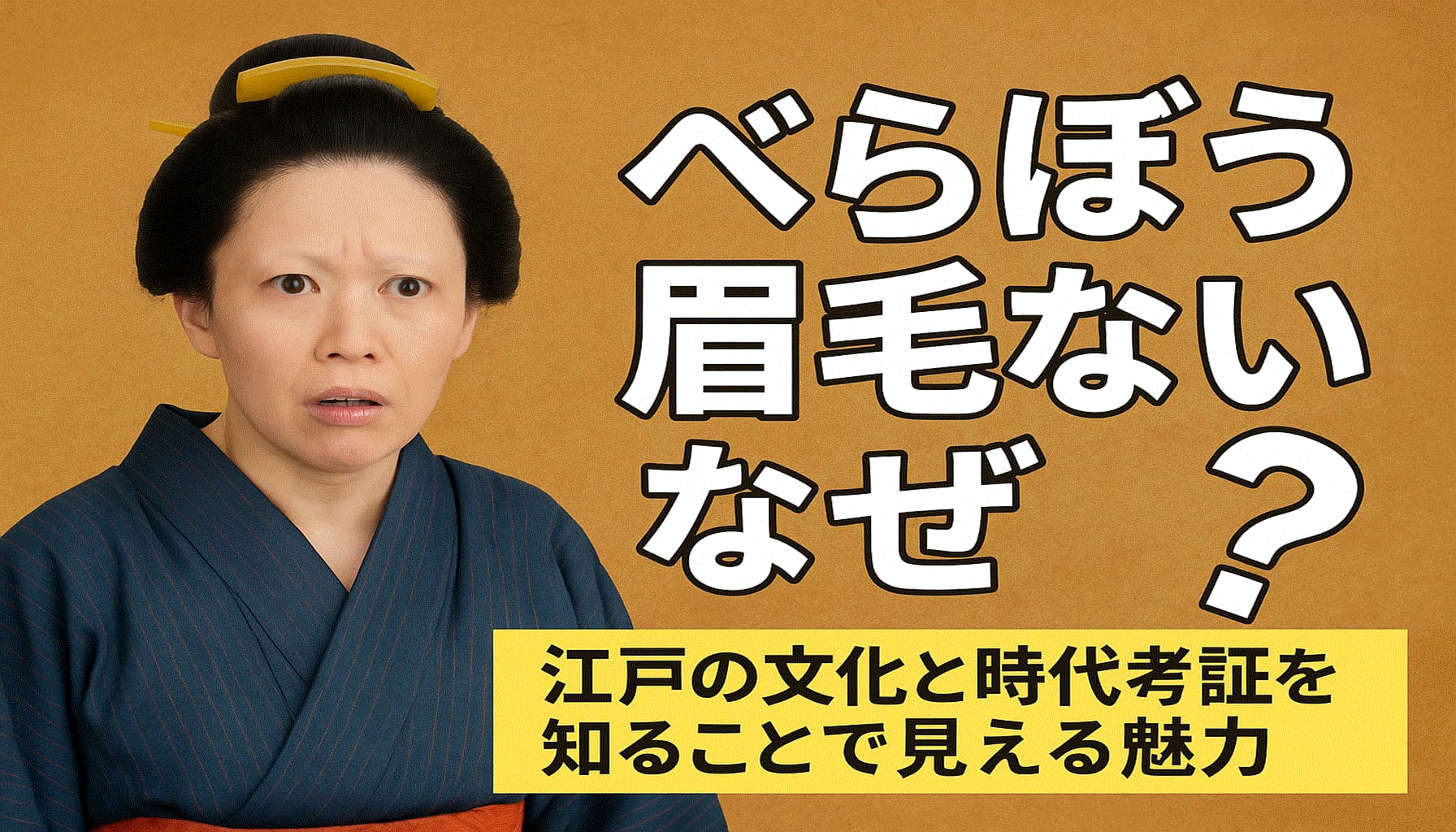



コメント