江戸の闇にひそむもの――それを、誰よりもリアルに、そして愛らしく描いた絵師がいた。
鳥山石燕。『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』にも登場する彼は、ただの浮世絵師ではない。妖怪という“目に見えない存在”に形を与え、日本人の想像力に一石を投じた、いわば“妖怪図鑑の父”だ。
この記事では、石燕の人物像と作品、そして彼が現代日本の妖怪観にどう影響を与えたかを解き明かす。『ゲゲゲの鬼太郎』や『妖怪ウォッチ』も、ルーツを辿れば、すべて石燕に行き着くのだ。
- 鳥山石燕が築いた妖怪画の世界とその革新性
- ドラマ『べらぼう』における石燕像と片岡鶴太郎の演技
- 現代の心にも潜む“妖怪”という感情のかたち
鳥山石燕とは?──妖怪画の原点を築いた浮世絵師
江戸の夜は、今よりずっと暗かった。
闇が深ければ、人は“何かが潜んでいる”と想像してしまう。
その「想像」に輪郭を与えたのが、鳥山石燕という絵師だった。
狩野派から独立し、妖怪の“見える形”を描いた
石燕(せきえん)こと、鳥山石燕は1712年頃に生まれた。
名門・狩野派で鍛えられた筆の力と、江戸庶民の想像力を結びつけた――この一点に、彼の革命性がある。
生家は幕府に仕え、芸術にも理解のある裕福な家系だった。彼は絵の正統を学びつつも、「正統」では届かぬ何かを知っていた。
絵の才能に恵まれながらも、世に出たのは遅咲き。60歳を過ぎてから発表した『画図百鬼夜行』が、大ヒットした。
それは単なる妖怪の絵ではない。誰もが心のどこかで感じていた“見えない気配”を、絵という形で可視化した試みだった。
妖怪を1体ずつカタログ化した革新性
石燕のすごさは、既存の絵巻物にあった「群れとしての妖怪」ではなく、“1体1体をキャラクターとして成立させた”ところにある。
『画図百鬼夜行』では、妖怪たちに名前をつけ、性格や出典までも書き添えた。これは、後の図鑑文化・キャラクター文化の先駆けともいえる。
河童には皿と甲羅、猫又には二股の尾。彼が描いたビジュアルイメージが、今の「妖怪の見た目」を形づくっているのだ。
さらに、続編となる『今昔画図続百鬼』『今昔百鬼拾遺』『百器徒然袋』では、石燕自身の創作妖怪も登場しはじめる。
“存在しない何か”を、まるで実在するかのように描く――これは、現代のフィクション作家やキャラクターデザイナーにも通じる美学である。
「妖怪とは、姿なき不安や感情の、擬人化である」――その定義が、石燕の筆から始まった。
“闇の中にある、温かみ”を描いた画風
石燕の妖怪たちは、決して恐怖を煽るだけの存在ではない。
目を細めて笑う、肩の力の抜けた“どこか憎めない”妖怪も多い。
その秘密は、彼が発明した「拭きぼかし」技法にある。
版木を濡らして色を滲ませることで、輪郭のはっきりしない、幻想的な存在感を表現した。
“怖いけど、ちょっと愛しい”――そんな妖怪たちは、夜の不安に寄り添う存在へと変貌を遂げた。
石燕が描いた妖怪は、「恐怖」ではなく、「共感」や「可笑しみ」の感情を引き出す。
つまり彼は、妖怪を“外にあるもの”から“内にあるもの”へと移動させた、思想の革命家でもあったのだ。
石燕が描いた4つの妖怪画集とその世界観
「見えぬものを、どう描くか」――それは、絵師にとって最大の挑戦であり、芸術の根源でもある。
鳥山石燕は、それを“妖怪”というフォーマットで回答した。
しかも一枚では終わらない。彼は全4冊の画集を通して、妖怪たちを体系化し、世界観を拡張していった。
第一作『画図百鬼夜行』:名前だけで想像を膨らませた図鑑
1776年、江戸の町に異様な本が現れる。
『画図百鬼夜行』――妖怪たちが1体ずつ描かれ、名前だけが添えられた、不気味で魅力的な“絵本”だ。
ここで石燕がしたことは、「妖怪に定義と顔を与える」という革命だった。
それまで“化け物”として漠然と語られていた存在に、明確なビジュアルと名称をつけた。
「ぬっぺふほふ」「猫また」「飛頭蛮(ろくろ首)」など、今なお語られる妖怪たちの“初出の姿”が、この本にある。
まるで図鑑のように整然と並んだ異形たちは、読者の想像力を刺激し、“恐怖”というより“好奇心”を誘った。
第二作以降はプロフィール付き:創作妖怪の始まり
『画図百鬼夜行』が評判を呼ぶと、石燕は続編を発表していく。
『今昔画図続百鬼』(1779年)、『今昔百鬼拾遺』(1781年)、そして『百器徒然袋』(1784年)へと続く妖怪絵巻は、妖怪に“物語”や“由来”を与えるようになる。
そこからは石燕の創作魂が爆発する。
- 「煙々羅」──煙そのものが妖怪となった存在。
- 「百々目鬼」──体中に目を持つ怪物。
- 「暮露暮露団」──ボロ布団が化けた付喪神。
これらは古典の引用だけでなく、石燕の空想から生まれた“創作妖怪”であり、フィクションとしての妖怪文化の始まりだった。
特に『百器徒然袋』における、使い古しの道具が魂を得て妖怪となる「付喪神(つくもがみ)」の登場は、“モノに心が宿る”という日本的感性の具現化だ。
付喪神、酒呑童子、猫又――時代とともに変わる妖怪たち
石燕の画集では、さまざまな階層の妖怪が描かれている。
『今昔画図続百鬼』では能や歌舞伎にも登場する有名妖怪・酒呑童子や橋姫も登場し、読者層を広げていく。
“恐怖”だけでなく、“語り継がれる存在”として妖怪を再定義していったのだ。
そして注目すべきは、これらの妖怪たちが単なる“異形”ではなく、どこかユーモラスで、生活に寄り添う気配を持っていること。
「あれ、こんな奴、近所にいそうだな」――読者にそう思わせる距離感が、石燕の妖怪画にはある。
だからこそ、昭和に水木しげるが、令和に『妖怪ウォッチ』が生まれる文化土壌となった。
石燕が撒いた種は、200年以上経った今も、日本人の心で芽を出し続けている。
『べらぼう』で描かれる鳥山石燕像とその役割
NHK大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』において、鳥山石燕は若き絵師・唐丸(のちの捨吉)に“絵の心”を伝える師として描かれている。
彼は単なる妖怪画家ではない。目に見えぬ感情や痛み、孤独を拾い上げ、それを線と色で表す存在として、物語の中に佇んでいる。
その描き方は、まさに「べらぼう」な自由さの中に、“見えないものと向き合う覚悟”が込められていた。
妖怪を描くことで“見えないもの”を引き出す役目
劇中で石燕が語る妖怪は、どこか生きづらさを抱えた登場人物たちの心に呼応している。
「姿が見えないから、怖い。でも、姿がわかれば、付き合い方がわかる」
このセリフの裏には、“人間の感情そのものが妖怪である”という解釈がある。
悲しみが“濡女(ぬれおんな)”となり、怒りが“鬼”になる。
妖怪は、誰かの心の中に棲んでいる存在なのだ。
そうした哲学を、石燕は若き絵師・捨吉にそっと託してゆく。
片岡鶴太郎が演じる意味──“描く者”としてのシンクロ
そして、そんな石燕を演じるのが、俳優であり、画家でもある片岡鶴太郎であるということ。
これは、偶然ではない。
鶴太郎もまた、かつては“笑い”という舞台に立ち、その後、自らの内面と対峙しながら筆を執ってきた。
水墨画や陶芸、書の世界で“言葉にならないもの”を形にしてきた男が、石燕という「見えぬものを描く」人物を演じる――そこには深い共振がある。
彼の芝居には、台詞の外に“余白”がある。
それはまるで、石燕の描く妖怪の“ぼかし”のような、強すぎない存在感。
見る者に「これは何か」と問いを残し、心に棲まわせるような演技だった。
“師”としての石燕、そしてその後継者たちへ
ドラマの中で、石燕の出番は多くはない。
だが、その立ち姿、その絵筆の動き、その“まなざし”は、物語の基調音として響き続ける。
蔦屋重三郎とは深い関係を築くことはなかったが、彼の門弟たちが、後に蔦屋のもとで江戸出版文化を支える存在となってゆく。
つまり、石燕は“未来を描く”ための礎を築いた存在だった。
そしてその精神は、弟子へ、絵へ、そしてこの物語を観ている私たちへと受け継がれていく。
妖怪を描いた絵師は、実は“人の心”を描いていた。
片岡鶴太郎の演技は、その本質を、声高ではなく、静かに、しかし深く伝えていた。
なぜ石燕の妖怪は現代にまで影響を残しているのか?
時代は移り変わっても、人の不安や願い、怒りや悲しみは変わらない。
それらの「目に見えない感情」を、石燕は“妖怪”という姿で描いた。
だからこそ、彼の描いた妖怪は、200年を経てもなお、色褪せない。
むしろ時代が進むごとに、その輪郭はくっきりとしていった。
“恐ろしさ”ではなく“奇妙さ”や“可愛さ”へのシフト
石燕の妖怪たちは、決して“怖いだけ”ではない。
目を細めた笑みを浮かべる者、ぽてっとした体で転がる者、道具に命が宿っただけの無害な者たちもいる。
その“可笑しさ”や“人間臭さ”こそが、石燕妖怪の最大の魅力だ。
恐怖で遠ざけるのではなく、奇妙さで引き寄せる。
それはまるで、「自分の中にある怖さ」とうまく付き合っていく方法のようでもある。
こうして石燕の妖怪たちは、時代と共に“キャラクター”へと変貌を遂げていく。
水木しげる、妖怪ウォッチへ受け継がれる系譜
昭和に入ると、漫画家・水木しげるが登場する。
彼は『ゲゲゲの鬼太郎』を通して妖怪を大衆文化へと昇華させたが、その元ネタの多くは石燕の画集から取られている。
特に『画図百鬼夜行』『百器徒然袋』などは、水木自身が熱心に読み込んでいたという。
“ぬらりひょん”や“一反木綿”など、今や国民的存在となった妖怪たちも、石燕が道を拓いたおかげで生まれたキャラクターなのだ。
そして平成・令和と続く現代では、アニメ『妖怪ウォッチ』が子どもたちの間でブームとなる。
あの愛らしくデフォルメされた妖怪たちのルーツも、辿れば石燕の妖怪観に行き着く。
妖怪は“感情のアイコン”として今も生きている
現代人にとっての妖怪とは、もはや“恐れるもの”ではない。
「あ、今ちょっと自分、妖怪“イライラ鬼”になってるな」とか、「仕事で“忙殺神”が降りてきたな」といった風に、
感情の状態を“妖怪”で表現する、という使い方さえされている。
つまり、石燕が作り上げた妖怪たちは、“怖がられるもの”から“共に生きる記号”へと進化したのだ。
これは、彼の描いた妖怪に“物語”と“人間味”があったからこそ、可能になった変化である。
妖怪とは、時代ごとの“不安”の形であり、また“愛着”のかたちでもある。
石燕の筆は、ただ異形を描いたのではない。「人が、人をどう理解するか」を、妖怪という鏡で映して見せたのだ。
現代にも潜んでいる…「心の妖怪」とのつきあい方
鳥山石燕が描いた妖怪たちって、実は、昔の話でもファンタジーでもないんです。
むしろ今の私たちが、日常の中でふいに感じるモヤモヤとかザワザワとか――そういう「見えない感情」を、形にしてくれてる存在。
なんだか最近、会社で人の顔色ばかり気にして疲れちゃったとき。
SNSで誰かのキラキラ投稿を見て、自分だけ取り残された気がしたとき。
そんなときに顔を出すのが、現代版“妖怪”なんじゃないかなと思うんです。
「忙殺鬼」「自己嫌悪ぬっぺふほふ」…見えない何かに名をつける
石燕は妖怪に名前をつけて、特徴を書き添えました。
それって実は、自分の中の得体の知れない不安に「名前」を与えて、正体を知ってあげる作業でもあったのかも。
「あ、今日の私は“イライラ百々目鬼”に取り憑かれてるな」と気づけたら、ちょっと距離がとれる。
石燕の妖怪図って、実は“感情とのいい距離感のとり方”を教えてくれてるのかもしれません。
正体がわかれば、こわくない。妖怪と“共にいる”という知恵
怖いと思ってたものでも、名前がわかって、性格がわかって、「あ、意外と悪さしないじゃん」って思えたら――
それって、ちゃんと“共にいる”準備ができたってことなんですよね。
石燕の描いた妖怪たちも、どこか人懐っこかったり、ちょっと抜けてたり、笑ってしまうものも多い。
そういう妖怪たちが、現代の私たちにそっと教えてくれてる気がします。
「怖がるんじゃなくて、見つめてごらん。そしたら、うまく付き合っていけるよ」って。
「妖怪は心の鏡」──鳥山石燕と現代のつながりを考えるまとめ
鳥山石燕は、ただ異形の絵を描いた浮世絵師ではない。
人の心に潜む、目に見えない“感情のかたち”を、絵という技術で可視化した表現者だった。
そのまなざしは、決して“恐れ”ではなく、“観察”と“理解”に満ちていた。
『画図百鬼夜行』を皮切りに、妖怪たちに名前を与え、個性を与え、物語を紡いでいった。
それは、人々が自分自身の中にいる「なにか」に気づき、付き合っていくための手引きでもあった。
そう考えると、石燕が創ったのは「妖怪図鑑」ではなく、“感情と共生するための辞書”だったのかもしれない。
彼の筆を継ぐように、水木しげるが漫画という形で、子どもたちの心に妖怪を根付かせた。
そして令和の今、私たちはまた妖怪と出会っている。ゲームの中で、アニメの中で、あるいは…自分の心の中で。
『べらぼう』の中で描かれた石燕像は、そんな妖怪と共に生きる“知恵の伝道者”だった。
演じた片岡鶴太郎は、その静かな情熱を、言葉より深く、表情と筆先で私たちに伝えてくれた。
「妖怪とは、あなたの中にいる“見えない気持ち”の姿かもしれない。」
そのことに気づいたとき、石燕の妖怪たちは、きっとあなたにこうささやく。
「もう、こわがらなくていいんだよ。」
- 鳥山石燕は妖怪画を体系化した江戸の絵師
- 妖怪に名前と性格を与えた“図鑑化”の先駆者
- 代表作は『画図百鬼夜行』を含む4つの画集
- 妖怪を恐怖だけでなく愛嬌ある存在として描写
- ドラマ『べらぼう』で片岡鶴太郎が石燕を演じる
- 石燕の妖怪観は現代の感情表現にも通じる
- 水木しげるや妖怪ウォッチにも影響を与えた
- 妖怪とは“心の鏡”であり共に生きる存在
- 見えぬ感情に形を与えることで怖さが和らぐ
- 石燕の作品は現代人の心の支えとなり得る

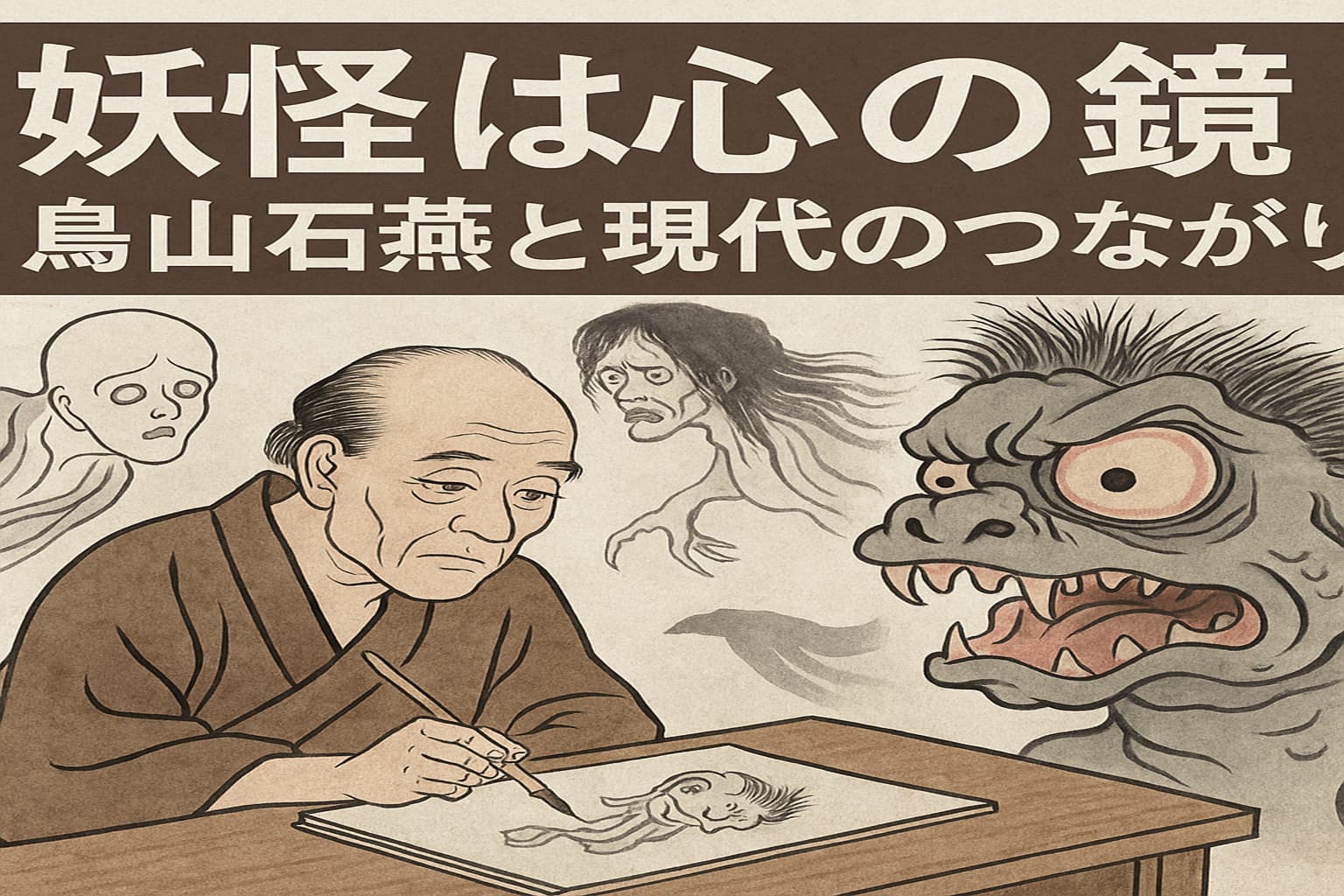



コメント