「妖怪の正体なんて、突き止めたところで救われるわけじゃない」──そう思って観ていた『かわおとこ』の終盤、涙腺が崩壊した。
これはただの水難事故でも、企業の不正を暴くミステリーでもない。あの淵に引きずり込まれたのは、川ではなく「後悔」という名の沈黙だった。
相棒season20 第7話『かわおとこ』は、右京と冠城が“妖怪ハンター”となり、川に巣食う闇を追う物語。しかし、その正体に辿り着いたとき、浮かび上がるのは「見なかったことにした大人たち」と「傷を背負わされた子ども」の物語だ。
- 『かわおとこ』に込められた“見て見ぬふり”の罪の本質
- 少女・百花がついた嘘の裏にある家族への想い
- 右京と冠城の対比が浮き彫りにする“優しさのかたち”
川男の正体は“無関心”だった──悲劇を招いた沈黙の連鎖
川の底には、死体より重い「無関心」が沈んでいた。
相棒season20 第7話『かわおとこ』は、少年の事故死をめぐる“妖怪騒動”を通じて、人が「知らなかったことにする」罪をあぶり出す物語だ。
誰もが真実に触れながら、誰も声を上げないまま、次の犠牲者が生まれる。
“妖怪”とされた男の正体と、彼が背負った罪
少女・百花が目撃した“かわおとこ”は、黒い作業服と釣り用の胴長を着た男だった。
その正体は、荻野という若手社員を亡くした上司・高部。
彼は、死んだ部下の意志を継ぎ、工場排水による水質汚染を黙々と調べ続けていた。
しかし彼の姿は、幼い百花の目に“妖怪”として映り、弟・悠太の悲劇を引き寄せた。
正義の継承者だった彼が、皮肉にも怪物のシンボルとなったことに、このエピソードの皮肉がある。
右京は、高部にこう告げる。
「あなたは二度、見て見ぬふりをしました」
事故直後、彼には止めるチャンスがあった。
だが高部は、正面から社長に逆らう勇気を持てなかった。
彼の“沈黙”が、部下を死なせ、少年を危険に追いやった。
殺していないのに、罪を背負う。
見逃しただけで、責任が生まれる。
この物語は、加害者でなくても「罪」を背負う覚悟を問う。
汚染を知りながら止めなかった社長と上司の責任
すべての発端は、4ヶ月前の貯水タンクの破損事故。
本来であれば報告されるべき事態を、社長・笹沼は「様子を見よう」と黙殺した。
そして荻野は、自主的に調査を始め、命を落とす。
企業の論理が、ひとつの命を見殺しにした瞬間だった。
だが問題は、その場にいた上司・高部もまた、黙っていたことだ。
組織の圧力の前で、正しさは声を失った。
右京の視線は厳しい。
「止めることができた。あなたは黙った」
無関心は、罪だ。
幽霊でも妖怪でもない。
人間の選択の積み重ねが、“かわおとこ”という幻を生んだ。
百花の目に映ったそれは、大人たちの「逃げた背中」そのものだったのだ。
「川にいたのは妖怪」──百花の嘘が守ろうとしたもの
「弟は、川男に引っ張られたんだよ」。
そう語った少女・百花の目には、涙がなかった。
その言葉は、嘘だったかもしれない。でも、あの子なりの祈りでもあった。
姉としての罪悪感と、母を守りたかった気持ち
弟・悠太が事故に遭った日、百花はこう言った。
「宿題があるから川に行けない」。
でも、それはただの嘘だった。
本当は、一緒に遊ぶのが億劫で、ゲームがしたかった。
その“ささいな自分勝手”が、弟の命を脅かした。
そして母は、責められた。
無数の匿名が、ネットに母親の顔写真を貼りつけ、「親失格だ」と嘲笑った。
子どもだった百花に、その暴力が届かないはずがない。
だから彼女は“妖怪”という言葉で、何かを守ろうとした。
弟は川男にやられた。だから誰も悪くない。
私の嘘も、母の過ちも、全部帳消しにできる。
──百花の中にいた妖怪は、誰よりも優しかった。
ネットリンチが突きつけた、子どもへの暴力
SNSは容赦なかった。
事故の直後、“母親の顔写真”“家族構成”“過去の投稿”までが晒された。
真実かどうかではなく、誰かを叩ける材料になった瞬間、それは“正義”になる。
百花は、自分の母親がその“標的”になったのを見ていた。
責められて、泣いて、それでも謝り続ける母。
だからこそ、「妖怪のせいにしてあげたかった」のだ。
嘘だった。
でも、それは優しさだった。
この物語で一番大人だったのは、百花だったのかもしれない。
右京がその嘘に気づきながら、最後まで優しく接した理由が、そこにある。
子どもが、自分の罪と、大人の過ちの両方を背負って生きている。
この物語は、“嘘”の中に宿った“真実”を、ちゃんと見つけてくれる。
右京の“妖怪ハンター”ぶりが光った今回、そこに隠された哲学
「僕たちの目には見えなくとも、それがこの世に存在していないと断定することなど、誰にもできないんですよ」。
それは右京の口から語られた、“妖怪”に対する本気の言葉だった。
冷徹な理論家である彼が、怪異に心を奪われる──そこに、右京という人物の“ギャップ”が現れる。
「存在を否定できないもの」への興味と探究心
右京が妖怪の話にここまで乗るとは思っていなかった。
だが過去にも幽霊回ではたびたびその片鱗を見せている。
「超常現象」という言葉に、彼の知的好奇心が反応するのだ。
その姿勢は決して「信じている」ではない。
「否定できないから、探してみる」という、徹底した“知の探究者”としての態度だ。
百花が描いた妖怪の絵が、マイナーな妖怪図鑑と一致したとき。
右京は一気にテンションを上げ、妖怪の存在に「論理」で近づこうとする。
彼の“狂気”すれすれの知識欲が、視聴者の心に火をつける。
科学で説明できないことに目を向けるという姿勢。
それは“人の心の闇”を扱う探偵には、最も必要な素質なのかもしれない。
幽霊から妖怪へ──右京の超常現象シリーズの系譜
相棒にはこれまで、幽霊や心霊をテーマにした回がいくつか存在した。
だが、妖怪を真正面から扱ったのは、今回が初めてだ。
幽霊が“過去”の影を象徴する存在だとすれば、
妖怪は“自然”や“民間伝承”という、もっと広い領域と結びついている。
右京がそこに足を踏み入れたということは、“物語としての相棒”の可能性をさらに押し広げたということでもある。
そして今回の右京は、楽しそうだった。
妖怪図鑑を読み、妖怪の姿を聞き出し、フィールドワークに熱中する。
“妖怪ハンター右京”という肩書きが、思いのほかしっくりくるのはなぜだろう。
見えないものに価値を置く。
ありえないものを、一度は信じてみる。
その優しさこそが、右京が“誰も気づかない真実”を掘り起こしてきた理由なのかもしれない。
冠城卒業カウントダウン──“最多相棒”が見せた意外な顔
この『かわおとこ』は、冠城亘が右京の相棒として125話目に出演した記念すべきエピソードだ。
歴代最多──その事実にふさわしく、今回の冠城は“らしさ”と“意外性”の両方を見せてくれた。
でも、それが“最後の春”になるかもしれないという事実が、どこか寂しい。
釣りの知識が事件を解く鍵に
今回の事件解決において、最初の突破口になったのは「釣り用の靴の痕跡」だった。
川辺に残された特徴的な足跡を見て、すぐに「ピン付きのウェーダー」と言い当てたのが冠城だった。
「渓流釣りが趣味なんです」。
その言葉に、右京がほんの少し驚く顔を見せる。
釣り好きの反町隆史のキャラクターと、冠城亘がようやく重なった瞬間だった。
彼の個人的な趣味が、ちゃんと事件解決に貢献する。
この“相棒らしさ”こそが、冠城の魅力の本質かもしれない。
冠城125話目、コスプレと趣味で彩るラストイヤー
釣り人の装備をまとい、作業員の変装まで披露。
『かわおとこ』の冠城は、過去最大級に“コスプレ要素”が強い。
でも、それがまったく浮かないのは、冠城という男の“柔らかさ”があるからだ。
シリアスな展開のなかで、ふと出てくる冠城の表情や仕草が物語に“呼吸”を与えてくれる。
右京が“硬”なら、冠城は“柔”。
そのバランスが、このコンビの最大の魅力だった。
この回の放送と同時に、冠城がseason20で卒業するというニュースが流れた。
それが現実味を帯びるほどに、彼の“ふつうさ”と“人間らしさ”が愛おしくなる。
冠城というキャラクターがいたから、右京の“怪物性”が際立った。
彼の125話目は、“最多”の重みだけじゃない。
ひとつの時代の“終わりの始まり”を告げる静かな節目だった。
相棒20『かわおとこ』が伝えた、“見なかったことにする罪”という名の妖怪
妖怪なんていなかった。
でも、見ようとしなかった人々の“影”が、確かにそこに立っていた。
『かわおとこ』は、ホラーではない。
これは、人間の“視線の逸らし方”を描いたドラマだ。
子どもが嘘をついてまで守ろうとしたもの
百花は、ずっと抱えていた。
「本当は弟と川に行きたくなかった」。
それを言えなかった。
彼女は、自分の“都合”が家族の未来を壊したと感じていた。
だから、「川男のせいにした」──それは、嘘だった。
でも、母を守るため、そして自分自身の罪悪感を受け止めるための、精一杯の言葉だった。
嘘に見えて、そこに込められた想いは真実だった。
この物語で百花は、何度も“ごめんなさい”を繰り返す。
その姿は、大人よりも誠実だった。
右京の最後の台詞に滲む、“見過ごさない大人”としての矜持
右京は、誰も責めなかった。
でも、誰の責任も「なかったこと」にはしなかった。
それが、彼の信念だ。
高部に向けて放った言葉──
「あなたは、二度、見て見ぬふりをしました」
その静かな一撃は、真正面から「無関心という名の罪」に斬り込むものだった。
“正義”という言葉を口にしない代わりに、
“目を逸らさない”という行動を貫く。
それが右京の“正しさ”であり、“優しさ”でもある。
この回で描かれた妖怪とは、つまり──
- 誰かの小さな違和感に目を向けない大人たち
- 現実から逃げ、沈黙で正当化する組織
- “守るべきもの”を、子どもに背負わせる社会
右京は、その“見えない妖怪”を暴いた。
だからこそ、あの川の水は、少しだけ澄んで見えた。
静かに流れる“見えない川”──職場や日常にも潜む“かわおとこ”
『かわおとこ』を見終わって、ふと考えてしまった。
――あの川、実は自分の職場にも流れてるんじゃないか?って。
見えてないフリ、してない? 誰かの“異変”に気づいてるのに
たとえば、職場の同僚がいつもより口数が少なかった日。
後輩が明らかに無理して笑ってたとき。
「あれ?」と感じながら、自分の仕事に集中するふりしてスルーしたこと、誰しも一度はあるんじゃないかな。
右京が言った「あなたは二度、見て見ぬふりをした」という言葉、
実は日常の“ちいさな選択”にも刺さってくる。
気づけたのに、声をかけなかった。
止められたのに、面倒くさくて黙ってしまった。
そういう場面が、現代の“川男”を生み出してるのかもしれない。
「誰も責めないけど、誰も助けなかった」っていう空気
会社でも、学校でも、家庭でも。
誰かが倒れたとき、責任の所在を追いかける前に、
まず周囲の空気がこうなる。
「誰も悪くない。でも、誰も助けなかったよね?」
この空気こそが、“かわおとこ”の正体だと思う。
そしてそれは、組織や社会のなかで、しれっと人を溺れさせていく。
『かわおとこ』が描いたのは、決して特殊な事件じゃない。
むしろ、日常のすぐそばに潜む「知らんぷりの連鎖」だった。
だからこそ、この物語はただの妖怪ミステリーじゃなく、
“あなたの隣に流れてる川”を、そっと見せてくれる回だったのかもしれない。
右京さんのコメント
おやおや…「妖怪退治」が、いつの間にか「人間の良心との対峙」にすり替わっておりましたねぇ。
一つ、宜しいでしょうか?
この事件の本質は、“かわおとこ”なる妖怪ではなく、誰も声を上げなかったことにございます。
少年が溺れた川には、有害物質が、過去の隠蔽が、そして沈黙が流れておりました。
見ようとすれば、気づけたはずです。止められたはずです。
ですが、皆が「様子を見よう」と目を逸らした。
なるほど。そういうことでしたか。
百花さんが“妖怪”のせいにしたのは、自分のせいにしたくなかったからだけではありません。
無責任なネットの声から、母親を守りたかった。それだけのことです。
子どもが、大人の代わりに責任を背負う。
感心しませんねぇ。
いい加減にしなさい!
「気づいていたけど、言えなかった」──その言い訳が、どれだけの犠牲を生むか。
人は誰しも、心のなかに“かわおとこ”を棲まわせているのかもしれません。
それでは最後に。
淹れたてのアールグレイを口に運びながら、僕はこう思いました――
「見えないものを、見ようとする意思」こそが、人間の知性ではないでしょうか。
『かわおとこ』まとめ──妖怪が映したのは、私たちの心の闇だった
『かわおとこ』を見終えたあと、静かに自分の中の“川”を覗いてしまった。
流れは見えないけれど、たしかにそこに“沈黙”が沈んでいた。
この物語が見せた妖怪は、人間のかたちをしていた。
「それでも川は、何も言わずに流れていく」
人が罪を見過ごしても、悲劇を起こしても。
川は、すべてを飲み込み、何も言わずに流れていく。
その静かさが、むしろ恐ろしく感じられるほどだった。
百花の嘘も、母の苦悩も、企業の隠蔽も。
川はすべて知っていた。
でも、口を閉ざしていた。
だからこそ、目を逸らさなかった右京と冠城の姿が際立った。
この静かな戦いの中に、“本当の正義”の形がある。
この物語は、“正義”の形を問い直すためにある
法律に触れない行動。
逮捕されるわけでもない沈黙。
でも、それが人を死なせてしまうこともある。
『かわおとこ』は、その境界を描いた。
悪意のない不作為が、誰かの命を奪うことがある。
この物語は、“それでも正しくあろうとすること”の尊さを描いた。
右京の静かな怒り。
百花の涙の告白。
そして、冠城の優しい目線。
この回に登場するすべての“視線”が、誰かを見つめ、誰かを救おうとしていた。
妖怪はいなかった。
でも、“妖怪を見た”と言った少女の気持ちは、確かに存在していた。
最後に、あえてこう言いたい。
『かわおとこ』は、「見えないものを見ようとする物語」だった。
その姿勢こそが、相棒という作品の核心なのだと思う。
- 川に潜む“妖怪”の正体を通して描かれる人間の無関心
- 少女・百花が嘘をついてまで守ろうとした家族の姿
- 右京の哲学「見えないものを否定しない」の深み
- 冠城の趣味と人間味が光る、最多登場記念の節目回
- ネットリンチや企業の隠蔽が現代社会の“妖怪”として浮かび上がる
- 見過ごす罪、沈黙の連鎖が悲劇を招く構造に警鐘
- 日常に潜む“見て見ぬふり”の川を私たちは歩いている
- 優しさと痛みが交差する、静かで濃厚な回




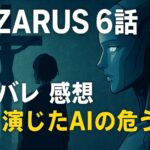
コメント