朝ドラ『あんぱん』に登場する「東京高等芸術学校」は、主人公・嵩が夢をかけて挑む舞台だ。
その架空の名前の裏にあるのは、アンパンマンの生みの親・やなせたかしの実体験、そして「旧制東京高等工芸学校図案科」という実在の学び舎の存在。
本記事では、作中の芸術学校が象徴する“夢と現実の接点”を深掘りしつつ、実在モデルやロケ地、そして当時の若者たちが抱えた葛藤までを読み解いていく。
- 東京高等芸術学校の実在モデルとその背景
- やなせたかしの進路が嵩の物語に与えた影響
- 夢と現実をつなぐ“工芸教育”の意味と力
東京高等芸術学校のモデルは旧制東京高等工芸学校図案科だった
『あんぱん』の嵩が目指した学校には、「夢を現実に引きずり下ろす覚悟」が詰まっている。
その架空の校名には、実在した旧制東京高等工芸学校・図案科の記憶が溶け込んでいる。
やなせたかしが青春を捧げたあの学び舎が、嵩の物語に静かに息づいているのだ。
やなせたかしが通った「図案科」とはどんな場所だったのか?
やなせたかしが進学したのは旧制東京高等工芸学校 図案科。現在の千葉大学工学部デザインコースにあたる。
場所は当時、東京・千駄木にあり、その後、戦後の移転で千葉県へ。
ここで彼は、単なる“絵描き”ではなく、社会に通用する表現者としての足腰を鍛えられることになる。
図案科は、「図案」という名前の通り、商業美術・工業デザイン・広告・舞台美術など、今でいうグラフィックやインダストリアルデザインを実践的に学ぶ場所。
「芸術家を育てる」のではなく、「世の中で“役に立つ”デザインを創れる人材」を育成するという思想があった。
だからこそ、戦時下という息苦しい時代の中でも、やなせたかしは“表現”を仕事にする手がかりを掴めたのだ。
工業デザインを学ぶための“実学の場”でありながら、芸術の芽が息づいていた
「絵で食えるわけがない」と言われた時代。
そんな昭和初期に、やなせたかしは“絵を仕事にする”という無謀な夢を、この学校で形にしていった。
それは夢と現実の折衷案なんかじゃない。
「アートを諦めない実学」という、新しい概念への挑戦だった。
教室では、デッサンも、レタリングも、商品のパッケージも描かされた。
決して自由ではない。けれど、制限の中で工夫する力こそが、“プロの表現”を生むと教わった。
その経験は、のちの『アンパンマン』にも確かに刻まれている。
戦後、広告、雑誌編集、舞台装置…どんな表現フィールドに身を投げても、やなせの線は「生きる目的」を帯びていた。
図案科は、夢を“覚悟”に変える学校だった。
なぜ“芸大”ではなく“工芸学校”だったのか?夢と食い扶持の狭間で
芸術を学ぶとき、人は必ずこう問われる。「で、それで食っていけるのか?」
やなせたかしは、その問いから逃げなかった。
嵩が進んだ道は、夢を見るだけの場所じゃない。“生きる”ための選択肢だった。
当時の芸術と就職のリアル――「絵じゃ食えない」の本当の意味
昭和初期、「芸術=自己表現」だけでは、社会に居場所がなかった。
東京美術学校(現・東京藝術大学)は、“芸術家”になる者たちが集まる場所。
だが、そこに進むには裕福な家庭の支えか、世間の風を無視できる胆力が要った。
対して、工芸学校は「生活のための芸術」だった。
やなせが選んだ図案科では、商業美術や装丁、広告、工業デザインといった「売れる絵」「役立つ絵」を学べた。
つまり――生きるためのペンの動かし方を、最初から叩き込まれる場だった。
劇中の嵩にも、伯父・寛がこう言う。
絵で飯は食えん。けんど、本の挿絵や広告の仕事なら“かも”しれん。
その一言に、やなせの青春の全部が凝縮されている。
好きなことを“現実”に変えるために選んだ道
工芸学校を選んだのは、“妥協”じゃない。
それは、「夢を諦めずに、現実と握手する」ための戦略だった。
「好きなことで生きていく」と声高に叫ぶのではなく、静かに、しかし着実に、それを“職業”へと変えていったのだ。
嵩が受験の掲示板を前にして迷う姿は、単なる進学の話じゃない。
それは、「自分の人生に責任を持て」という、魂への要求だった。
芸大ではなく工芸学校。アートではなくデザイン。夢想ではなく仕事。
その選択の一つ一つが、嵩というキャラクターに血を通わせている。
そしてその背後には、やなせたかしの歩んだ、“諦めなかった過去”がある。
ロケ地・東京農工大学農学部本館が放つ、昭和の匂いと希望の光
『あんぱん』で嵩が通った“東京高等芸術学校”。そのロケ地に選ばれたのが、東京都府中市にある東京農工大学農学部本館だ。
1934年竣工のこの建物は、アール・デコ様式の息吹と、戦前の空気を今なお留めている。
その古びた壁、まっすぐ伸びた階段、どこか湿った空気感が、昭和初期の若者の「焦り」や「希望」と絶妙に重なる。
アール・デコ建築と「時計台」の象徴性――校舎が語る物語
東京農工大学の農学部本館は、内田祥三――東大・安田講堂の設計者でもある名建築家の手による。
正面にそびえる時計台は、まるで“時間”そのものが嵩を見守っているようだ。
若者たちの夢と不安が交錯するこの場所で、時間は残酷にも進み続ける。
だからこそ、掲示板の前に立つ嵩の姿が痛々しいほど美しい。
「自分を信じるしかない瞬間」というのは、たいてい誰にも見られたくないものだ。
でも、それを真正面から撮る。それが『あんぱん』のやり方だ。
「掲示板の前」の演出が見せた、嵩の心の戦争
劇中の名場面――嵩が掲示板を見る前に、伯父・寛が勝手に「不合格だ」と決めつけて叫ぶあのシーン。
「胸を張って高知に帰れ!おまんのことを笑うやつはこのわしが許さん!」
あの言葉には、期待という名の呪いと、家族の優しさの暴力が詰まってる。
嵩は、まだ掲示板を見ていない。それなのに、大人たちは勝手に彼の物語を完結させようとする。
それが「若さ」という孤独の本質だ。
合格発表の場所は、ただの掲示板じゃない。“他人の物語”から抜け出し、“自分の人生”を始めるための出口だった。
そして彼はその掲示を見て、こう思う。
「俺の名前があった。それは、誰かの期待じゃなく、俺自身の選択だった」
この場所にしか出せない、空気がある。
ロケ地を選んだ制作陣の執念。舞台が語るストーリー。建物が、セリフを語っている。
「ワッサワッサ」に込められた、自由な魂と抑圧の記憶
『あんぱん』第27話、図案科の教室に響いたヘンテコな歌。
「ワッサワッサ」と繰り返す、意味不明なフレーズ。
だが、それは“馬鹿げた替え歌”なんかじゃない。
意味不明な歌の裏にある、自由への抵抗と創造の喜び
座間先生(演:山寺宏一)が言う。
「この歌は、図案科に代々伝わる名曲や。自由に解釈してええ」
生徒たちが戸惑うのも無理はない。だが、その不可解さこそがメッセージだった。
“意味がわからないこと”を受け入れる力。
それは、当時の日本に最も欠けていた価値観だった。
言論が縛られ、表現に検閲が入り、創造よりも忠誠が求められた時代。
そんな時代に、「ワッサワッサ」は“存在していい意味不明”だった。
この歌を生徒たちが一緒に口ずさむ場面は、明らかに“連帯”の演出だ。
正しいかどうかじゃない。「おかしいと思っても笑い飛ばす」――それが創造の始まりだ。
実在した図案科の歌「ワッサン」から見える“芸術教育”の原点
やなせたかしの自伝『アンパンマンの遺書』によれば、
この「ワッサワッサ」の元ネタは実在する図案科の歌「ワッサン」にある。
歌詞はデタラメ。リズムもおかしい。
でも、それでいい。それがいい。
学生たちは、校舎の隅で、小さな声で、半笑いでこの歌を歌っていた。
それは“体制への反発”じゃなく、“感性を殺さないための遊び”だった。
絵を描くより前に、自由であることを体に刻む。
それが、図案科という教室の魂だった。
ドラマで座間先生が軍人に歌を咎められる場面。
彼は毅然と言い返す。「これは図案科の伝統や」と。
この演出は、“表現すること自体が抵抗だった時代”を、象徴的に描いている。
笑いと歌に込められた、命がけの軽やかさ。
それが「ワッサワッサ」だった。
“健太郎”という鏡――やなせたかしと風間完、そして嵩の青春
嵩が試験会場で出会った男、辛島健太郎。
博多弁で豪快に笑い、試験の待合室で絵の話をぶつけてくる彼は、ただの“友達役”に収まらない。
その背後に見えるのは、やなせたかしの現実――かつて机を並べた、天才・風間完の姿だ。
出会いが人生を変える――机を並べた仲間の存在意義
やなせたかしの青春には、ひとりの男がいた。
その名は風間完。戦後、日本画壇でその名を轟かせた芸術家だ。
彼とやなせは、旧制東京高等工芸学校図案科で同期だった。
描くスピード、構図の巧みさ、色使いの深さ――
やなせは風間の才能に、嫉妬と敬意を同時に抱いていた。
その記憶が、ドラマの健太郎というキャラクターに焼き直されている。
嵩が健太郎に惹かれるのは、表面的な明るさじゃない。
「俺には描けない線を、この人は引く」――その静かな衝撃が、友情の土台になっている。
健太郎は“けんちゃん”だったのか?友情というスパイス
作中、健太郎は「けんちゃん」と呼ばれる。
あんぱん=やなせたかしの物語において、「けんちゃん」は実は複数の意味を背負っている。
やなせ本人の兄・ちひろ、友人、そして「ケンちゃんからフクちゃんへ」――主役交代の痛み。
健太郎は、物語の中で“支える側”に回る。
掲示板の前で合格できなかった彼が、嵩の肩を叩いてこう言う。
「世話になったばい」
あの瞬間、健太郎はただの“敗者”ではなく、“橋渡し役”になった。
嵩の才能、嵩の物語が動き出すために、彼はそこにいた。
やなせたかしにとっての風間完も、そうだった。
自分より先を行く誰かの存在が、筆を握らせる。
だからこそ、嵩と健太郎の関係は、物語を前に進める。
それはただの“友情”じゃない。
才能と才能がぶつかり合って生まれる、沈黙のリスペクトなんだ。
「芸術を選ぶ」という決断に潜む、親の沈黙と“背中”の物語
『あんぱん』の中で描かれる進路の話は、嵩ひとりの物語じゃない。
静かに、でも確かに揺れていたのは――見守る大人たちの表情だった。
夢を応援するふりをして、内心は反対していたかもしれない
伯父・寛の台詞にある「絵じゃ飯は食えん」。
これはただの心配じゃない。自分が背負えなかった夢の“名残”でもある。
本当は、寛自身もなにかを「諦めてきた」大人だったんじゃないか。
だからこそ嵩が本気で絵に向き合ったとき、それがまぶしくて、怖くて、そして羨ましかった。
口では「やめとけ」と言いながら、背中を押す。
その矛盾こそが、“親世代”のリアルなんだ。
応援じゃなく、“覚悟”を試していたのかもしれない
嵩にとっては進学だけど、大人たちにとっては「この子が、本当にこの道を選ぶか」の確認作業だった。
あの掲示板の前で、嵩は自分で未来を見た。
そのとき、寛はもう何も言わない。言葉より“沈黙”で認める。それが本物の「応援」だった。
夢を語る若者の後ろで、口を閉じる大人たち。
『あんぱん』が描いたのは、“夢”の物語であると同時に、“バトン”の物語でもある。
進学の決断に、一番揺れていたのは本人ではなく、支える側だった。
そしてその揺れは、どこか、優しかった。
あんぱん×東京高等芸術学校まとめ:夢を描くことに、理由なんていらなかった
ドラマ『あんぱん』で描かれた「東京高等芸術学校」は、架空の学校だけれど、そこに込められた想いは確かに本物だった。
やなせたかしという一人の表現者の原点に触れることで、嵩の物語がただのフィクションではなくなる。
それは、時代を超えて響く、“夢を見ること”への許可証のようなものだ。
嵩の選んだ道に重なる、やなせたかしの足跡
やなせたかしは、たしかに夢を叶えた人だった。
でも、それは一発逆転のサクセスストーリーじゃない。
日々の選択と、現実とのすり合わせの末に生まれた、等身大の奇跡だった。
図案科で学んだ商業美術、戦時中の迷い、戦後のどん底――
それでも彼は、「描くことをやめなかった」。
その覚悟と継続こそが、嵩の選んだ道に重なっていく。
そしてその道は、ただ彼一人のものではなかった。
誰かに笑われても、無意味と言われても、やり続ける価値のある道。
「現実的な夢」を叶えるために――今も息づく“図案科”の魂
「絵を描いて生きていきたい」。
この一言がどれほどの重みを持つか、やなせも嵩も知っていた。
だからこそ、彼らは“芸術”ではなく、“工芸”を選んだ。
現実のなかに芸術を溶かし込むために。
夢を、“職業”に変えるために。
そして、それは今も続いている。
千葉大学のデザインコースにも、図案科の精神は受け継がれている。
「美しさ」よりも、「役に立つ創造」。
夢を社会と結びつける力こそが、図案科の魂だ。
嵩の物語は、終わっていない。
そして、それを見た私たちの“次の一歩”も、まだ始まったばかりだ。
- 東京高等芸術学校のモデルは旧制東京高等工芸学校図案科!
- やなせたかしの青春が嵩の進路に重なる構成
- 「夢」と「現実」を繋ぐ“工芸”という選択肢
- 図案科で培われた生きるための表現力
- ロケ地・東京農工大学が放つ昭和の空気感
- 歌「ワッサワッサ」に込められた自由のメッセージ
- 健太郎という存在が映す“才能と友情”の光と影
- 支える大人たちの沈黙と本音にも注目
- 夢を描くことの意味を改めて問い直す物語



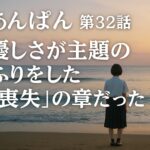

コメント