NHK朝ドラ『あんぱん』第72話では、嵩(北村匠海)がついに高知新報の社会部に採用されるという、大きな転機が描かれた。
投稿漫画を通じて見出された彼の才能は、思わぬかたちで未来を動かす。のぶ(今田美桜)との静かな対話、そして“描くこと”への没頭が、画面越しに観る者の胸を熱くする。
本記事では、この第72話の構成と感情の揺らぎ、そしてその裏にある“物語設計”の妙に迫る。
- 嵩が採用に至るまでの“描く理由”とその重み
- のぶとの沈黙が描く、信頼と共犯関係の深さ
- 創作が仕事になる瞬間に宿るリアルな覚悟
嵩の採用は“運”ではない。描き続けてきた過去の積み重ねが今を拓いた
その夜、嵩が呼び出された高知新報の編集部は、張りつめた空気に満ちていた。
時計の針が深夜に差しかかる頃、言葉少なに「この挿絵、描ける?」と差し出された原稿用紙。
描けるか描けないかではなく、描くしかなかった。
漫画投稿の伏線がここで回収される
ここで忘れてはならないのが、嵩のこれまでの“無名の努力”だ。
何者でもなかった彼が、日々漫画を投稿し続けていた過去。
それは、誰にも読まれず、誰にも届かないかもしれないという不安を抱えながら、何年も続けてきた“孤独な創作”だった。
その記憶を思い出したのが、のぶだった。
過去の投稿作が、今ここで、目の前の現実を変えた。
このドラマはいつもそうだ。前振りに見えた日常が、じつは“人生を変える伏線”になっている。
嵩の絵に宿っていたのは、技術でも構図でもない。
“誰にも見てもらえないかもしれない夜”に描き続けてきた執念。
それが紙面を埋め、編集部の一人に「任せてみたい」と思わせたのだ。
報われたのは才能ではない。積み重ねた“時間”だった。
これは夢が叶う物語ではない。“選ばれる”のではなく、“手を伸ばし続ける”物語だ。
「挿絵を描くだけじゃない」──嵩が見せた“報道”への覚悟
この回で特筆すべきは、「描くこと」そのものが、ただの作業ではなかったこと。
嵩は、言われるがままに挿絵を描いていたようでいて、その一枚に“記事の空気”を感じ取り、色と線をのせていた。
つまりこれは、ただの“仕事”ではなかった。
嵩はすでに、“報道”という営みに、片足を踏み込んでいた。
伝えるとは何か。絵にするとは何か。その意味を問いながら、締切のプレッシャーに追い詰められながら、それでも筆を止めなかった。
そこには、ただ夢中なだけではない“覚悟”がにじんでいた。
「この1枚を誰かが見て、少しでも感じてくれるかもしれない」。
そんな小さな希望が、嵩の手元に火を灯した。
編集長は言った。
「ようやるなあ。……ええもん描くやん」
このひと言は、評価ではなく“共犯者の承認”だった。
絵を描くことで、紙面の一部に命を与えた嵩は、ついに新聞の世界に迎え入れられる。
それは、ドラマ的なサクセスでも奇跡でもなく、
「描いてきたからこそ、描けた」という、“ただそれだけの必然”だった。
努力は報われる。けれど、それは“必要な時に、必要な人が見てくれた”ときだけだ。
この夜、嵩は「描くこと」で、世界に触れた。
報道という“現実”のフィールドで、彼の線がひとつ、確かに未来へとつながった瞬間だった。
のぶが陰から見守った夜、“共犯者”としての距離感が深く沁みる
第72話で最も静かで、最も強いシーンは、のぶが何も言わずに嵩を見守る場面だった。
手元のペンが走る音、紙の擦れる音、締め切りの気配、編集部の空気。
そこに“のぶのまなざし”が重なる。
のぶは声をかけない。
けれど、その沈黙には明確な意思があった。
──見守る。信じる。助けない。邪魔もしない。
ただ見ているだけじゃない、のぶの“背中を押す沈黙”
のぶにとって、嵩の才能は“過去に気づけなかったもの”だった。
漫画投稿を思い出し、自らの手でその場所へ嵩を連れてきた。
その時点で、のぶはただの“応援者”ではなく、物語の“共犯者”になっていた。
のぶが一歩下がって見守る姿勢には、「私の手柄じゃなくていい」「彼が選ばれれば、それでいい」という純粋さがにじむ。
そして、のぶ自身もまた編集の現場に生きる者として、“夢中で描く人間”の孤独を知っている。
だからこそ、語らず、動かず、ただそこに“存在する”という選択をした。
それは背中を押すための、いちばん美しい沈黙だった。
このドラマはよく沈黙を描く。
言葉よりも表情、表情よりも“空気”で感情を伝える。
第72話ののぶの姿は、その極致だった。
ふたりの関係性に漂う、決して言葉にならない“信頼”の表現
のぶとの嵩の距離感は、“恋”という枠では語れない。
そこにあるのは、“言葉の届かないところでつながっている”という、もっと根源的な信頼だ。
ふたりはもう、お互いの“選択”を尊重できる関係にいる。
それは、「あなたの人生に口を出さない」ことでもあり、「でも何かあったら黙って隣に立つ」覚悟でもある。
まるで編集と作家のような、距離と温度。
そっと支えることも、静かに待つことも、時に才能を輝かせるために必要な役割になる。
のぶの沈黙は、嵩にとって“壁”ではなく“背中を預けられる空気”だった。
この夜、ふたりの間に言葉はなかったけれど、関係はさらに深まった。
だからこそ、この物語は感動的なのに、泣けるわけではない。
“あったかい余韻”として胸に残る。
のぶという存在が、“他人の人生にそっと関わる力”の象徴になっている。
そして我々も、誰かのそばで、ただ静かに立つことができる人間でありたいと、そう思わせてくれる。
“描くこと”が生きること──嵩の原点が静かに証明された回
嵩はこの夜、なにかに追い込まれていたわけじゃない。
“描け”と命じられたわけでも、“描けなきゃダメ”と言われたわけでもない。
それでも彼は机に向かい、無心で絵を描き続けた。
その姿にあったのは、「選ばれるため」ではなく、「描かずにはいられない」という衝動だった。
第72話は、嵩というキャラクターの“原点”が初めて可視化された回だ。
描くことが好き。描くことで救われる。描くことで世界と繋がれる──その静かな真実が、絵の線ひとつひとつに刻まれていた。
締め切りに追われながらも、筆を止めなかった理由
締め切りという制限時間は、時に創作を破壊する。
けれど嵩は、この夜、その時間制限の中でこそ、“描くこと”の核心にたどり着いた。
呼び出されたのは突然だった。
心の準備もない。ペン先に確信があるわけでもない。
でも彼は、その瞬間に“描くモード”へ切り替えられた。
それは、日常的に「描く」ことを習慣として積み重ねてきた者にだけ許される反射神経だ。
まさに“描くこと”が、彼の呼吸であり、歩き方であり、生き方になっている証明だった。
誰のためでもない。ただ、「間に合わせたい」「間に合わなきゃ、この記事が死ぬ」という思い。
その気迫が、編集部の空気を変えた。
そして、誰もが彼を“記者の一人”として認識し始める。
作品の中で「夢中になる」ということのリアルな描写
夢中になる。
その状態は、テレビで描くにはあまりにも地味だ。
汗をかいているわけでも、叫んでいるわけでも、ドラマチックなBGMが流れるわけでもない。
でもこの回の嵩は、画面の“静けさ”を通して、「夢中」という状態を見せてくれた。
目の動き、指のリズム、呼吸の深さ。
誰にも届かないかもしれない一枚に、全力を注ぐ人間の“集中”がそこにあった。
「好きだから、描く」じゃない。
「描かずには、生きてる気がしない」から、彼は描いた。
そういう人間がひとりでもいる世界は、ちょっとだけ美しい。
この第72話は、嵩というキャラクターの“輪郭”を初めてくっきりと描いた回でもある。
これまでどこか受け身で、自信なさげだった彼が、
「これなら、やれるかもしれない」と、誰に言うでもなく自分に向かって思えた一夜だった。
描いた絵は、新聞という“現実”に刷られる。
それは、彼の“過去の孤独”が、今ようやく“社会に届いた”ことの象徴でもある。
この夜、嵩はただ描いただけじゃない。
「自分がここにいてもいい」という、静かな肯定を手に入れたのだ。
『あんぱん』が描く“創作と仕事”のリアル──やなせたかしの魂がここに宿る
“描くこと”をテーマに据えながらも、『あんぱん』はそれを決して夢物語として描かない。
どこまでも現実的に、淡々と、しかし深く。
創作が仕事になる瞬間、それは「誰かの期待を背負うこと」であると、本作は語る。
この第72話で、嵩は挿絵という形で「仕事としての創作」を初めて経験する。
今までは、自分の好きなものを好きなように描いていた。
でもこの夜は違った。その絵は、誰かの記事の一部として組み込まれ、新聞というメディアに刷られる。
つまり、「穴を埋める」という“責任”を負うことになる。
挿絵も、新聞も、人生も「埋めなければならないページ」
嵩が編集部に入ったとき、紙面の一部が空いていた。
締め切りは迫っている。時間も人手も足りない。
彼が描くのは、ただの絵ではない。新聞という“現実”の欠けたパーツだった。
ここで見えてくるのは、創作と仕事の間にある「責任感」という接点だ。
「おもしろいから描く」のではなく、「誰かのために描く」こと。
そして、誰かのために描いた絵が、社会に刷られ、街に流れる。
それはまさに、やなせたかしがかつて歩んだ道でもある。
『アンパンマン』を描く前、やなせは長く“挿絵画家”だった。
戦後の雑誌、新聞、広告に命を吹き込む、名もなき描き手。
その魂が、嵩の描いた一枚一枚に静かに重なっていく。
そして、彼もまた、「誰かのページを埋めることで、自分の人生も埋めていく」のだ。
“高知”という地で再構築される、現実とフィクションの接点
ドラマ『あんぱん』は、やなせたかし夫妻の人生をベースにしながらも、あくまでフィクションだ。
しかし物語の舞台が「高知」であること、それがリアルな温度を帯びさせている。
“紙面を埋める嵩”という描写の背後に、“実在した若き日のやなせ”の気配がある。
やなせたかしもまた、日々締め切りに追われ、描いて、刷って、暮らしていた。
夢を売る前に、現実の穴を埋める仕事をしていた。
そしてその先に、『アンパンマン』という奇跡が生まれた。
第72話は、“創作は夢ではなく、積み重ねである”という事実を、静かに語っている。
だからこそ、この物語は甘くないけれど、優しい。
現実を生きる人に向けて、「それでも描き続けよう」とそっと伝えてくる。
挿絵を描く嵩の手元に、“やなせの面影”が重なるような気がした。
物語の中で現実を語り、現実の中で物語を信じる。
『あんぱん』はそのどちらも諦めずに描いている、稀有な朝ドラだ。
「描くこと」は孤独の肯定──誰にも気づかれない夜に灯った、小さな火
第72話を観ていて、不思議と胸がざわついた。
絵を描く嵩の姿に、どこか“部屋にひとりの自分”を重ねていたのかもしれない。
誰に見せるでもなく、誰に求められたわけでもない。
ただ、ひとりで何かに向き合っていた夜。
あの机にいたのは、嵩だけじゃない
このシーン、きっと嵩だけの話じゃない。
かつて、何かを一人で作っていたことのある人間なら、あの空気に既視感を覚えたはず。
部屋に灯る明かり。筆が進まずに止まった時間。机の上の資料。
誰にも褒められなくていい。認められなくてもいい。ただ、それでもやめなかった。
その時間こそが、「描くこと」の本質だったんじゃないかと思う。
孤独を言い訳にせず、孤独を味方につけていた過去の自分。
あの机の前にいた嵩に、そんな人間の影がいくつも重なって見えた。
評価されることと、誰かを想って描くことは違う
嵩は採用された。評価された。
でも本当に描いていたのは、その“結果”のためじゃない。
「この1枚が、誰かの目に触れて、ちょっと心が動けばいい」
その“誰か”すら、はっきり見えていないかもしれない。
でも、それでも描く。
そういう「届けたい気持ちのない対象にすら、絵は向けられる」ってことを、この回はそっと教えてくれた。
評価されたいわけじゃない。たぶん、ただ描きたかった。
その“ただ”の強さが、妙に胸に刺さった。
描くことは、何者かになる手段じゃなく、
「自分という存在に向き合うための、静かな儀式」だった。
このドラマの凄さは、そういう部分にちゃんと光を当ててくること。
誰もいない部屋でも、描いた線が、自分の中の何かをつなぎ止めてくれる。
それが“生きてる感じ”ってやつかもしれない。
『あんぱん』第72話が教えてくれた、“迷い”を越える静かな強さ──まとめ
第72話は、特別な事件が起きたわけではない。
誰かが死ぬわけでも、大恋愛が爆発するわけでもない。
それでも画面の中で確かに何かが変わった。嵩という一人の若者が、「迷い」から「覚悟」へと一歩踏み出した夜だった。
その変化は声にならない。
でも、じっと見ているとわかる。嵩の目の奥、肩の角度、手のスピードが、ほんの少しだけ前を向いていた。
「やってみよう」と誰にも言わず、自分の中でそっと決めたその瞬間こそが、本作の醍醐味だ。
選ばれたのではない、選びにいった者の物語
採用された、と言えば聞こえはいい。
けれどこの回が描いているのは、“誰かに認められる”ことよりも、“自分で自分を信じる”ことのほうだった。
嵩は自ら、机に向かい、線を引き、記事の一部を埋めた。
「自分にできることが、ここにある」と確信できたその瞬間、彼はもう“選ばれていた”。
それは誰かの評価の結果ではなく、自分自身の行動で掴み取った位置だった。
この回を観ていた私たちもまた、「選ばれるのを待つだけの存在じゃない」と気づかされる。
選ばれなくても、やっていい。届かなくても、描いていい。
その一歩が、自分の人生を少しだけ動かす。
嵩の背中は、そんな“静かな勇気”を映し出していた。
そして、観る者に宿る「自分もまた、走り出せるかもしれない」という余韻
この物語のすごさは、結末よりも余韻にある。
観終わったあと、ふとスマホを置いて、少しだけ考え込む。
「自分にも、描きかけのページがあるな」──そんな気持ちになる。
誰もが何かを描きかけのまま放っている。
夢、やりかけの仕事、始められていない挑戦。
でも、嵩のように、誰に言われるでもなく、そっと筆を取ることはできる。
この第72話が与えてくれるのは、“勇気”ではなく“静かな決意”だ。
やるか、やらないか。声高に叫ぶのではなく、ただ一人、静かに「やる」と決める。
その決意の美しさが、この物語の芯になっている。
そして私たちもまた、そんな決意を自分の中に持てるのだと教えてくれる。
嵩が走り出したこの夜、私たちもまた、心の中で小さな一歩を踏み出した。
『あんぱん』はただの朝ドラじゃない。
“日常の中にある決意”を描く、ささやかで強い物語なのだ。
- 嵩が高知新報の社会部に採用された転機の夜
- のぶの“沈黙の応援”が信頼の関係性を描く
- 描くこと=生きることという嵩の本質が表現された
- 挿絵が“仕事”に変わる瞬間と責任の重み
- やなせたかしの魂を感じさせる創作と仕事のリアル
- 「描く」ことが孤独の中の希望であるという独自視点
- 夢や評価よりも“積み重ね”が人生を動かす鍵である
- 誰にも見られない夜の努力が、未来を切り拓く




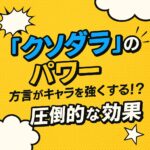
コメント