25年続いたドラマが、まだ“初めて”を見せられることがあるのか?
『相棒 season24』の初回スペシャルは、まさにその問いに答える一撃だった。杉下右京が人間国宝に“弟子入り”するという、前代未聞の展開。だが、それは奇をてらった演出ではない。25年という歳月がたどり着いた、“信念の物語”の進化形だった。
本記事では、25周年という節目において『相棒』がなぜ今もなお進化を続けられるのか。その裏にある、俳優・水谷豊と脚本家・輿水泰弘の「矜持」と「哲学」に迫る。
- 右京が弟子入りした理由と物語の背景
- 25年続く『相棒』が進化を止めない理由
- 特命係が持つ現代社会へのメタファー
右京が弟子入りする意味──それは“正義”を再確認する物語だった
25年続く『相棒』が、初回スペシャルで見せた展開に、僕は心の骨が折れる音を聞いた。
杉下右京──誰よりも論理的で冷静な刑事が、「人間国宝に弟子入り」する。そんな馬鹿な、と思う前に、僕は静かに背筋が伸びるのを感じた。
これは“奇をてらったスタート”じゃない。
右京が師匠の家に住み込み、講談の世界に身を投じるこの設定こそ、「正義」を問い直すための再起動ボタンだった。
初回スペシャルに仕掛けられた、前代未聞の構造
まず注目すべきは、物語の導入構造。
講談師・人間国宝をめぐる殺人事件──そこまでは、『相棒』らしい社会性ある謎解きだ。
だが今回は違う。右京はただ調査に訪れるのではない。自ら“内弟子”として名乗りを上げ、前座修行を始める。
しかも、屋敷に住み込む。正義を語る立場の彼が、今度は“語り”を学ぶ立場に回る。
この構造、完全に倒置法だ。積み上げてきた論理と理性のキャラクター像を、一旦“壊して”みせる。
だが、それこそが相棒ワールドの“進化の作法”だ。安定を崩し、軸を確認する。そうやって、この物語は25年続いてきた。
水谷豊自身が言う。「毎年驚かされるが、今回は歴代最高レベルの意表」。
演じる本人すら「心底驚いた」と語る展開に、僕ら視聴者は黙って身を委ねるしかない。
講談という伝統芸能が映し出す“時代”と“業”の正体
なぜ“講談”だったのか? なぜ“芸”の世界を舞台に選んだのか?
それは講談という芸能が、まさに「語り=正義」の表現だからだ。
講談師は、物語を語る職業である。
一方で、右京もまた“物語を構築する刑事”だ。
事件の背景、犯人の心理、社会との接点… すべてを紡いで「真実という一席」を語ってきた。
つまり今回、右京は講談師と“役割”で対峙するのではなく、“構造”としてぶつかり合う。
さらに、講談という世界は「伝統」と「しがらみ」に満ちている。
世襲、嫉妬、弟子と師匠の上下関係… そこに生まれる人間模様は、“芸の世界”というよりも“社会の縮図”だ。
『相棒』が描き続けてきたのは、常に「人間の業」だった。
欲、嫉妬、プライド、そして正義感。 その複雑な絡まりを、今回は講談の舞台に投影した。
舞台が変わっても、根底のテーマは変わらない。
右京が入ったのは芸の世界ではなく、「もう一つの日本社会」だった。
なぜ今、右京は弟子として修行を選んだのか?
それでも疑問は残る。
なぜ、今このタイミングで、右京は“弟子入り”という人生を選んだのか?
それはきっと、自らの“正義”を見つめ直すためだった。
25年、右京は正義を貫いてきた。「右京の正義」は、彼の根幹だ。だがそれが、揺らがなかったとは言えない。
時代が変わり、権力の形も、悪の形も多様化した。
そんな中で、正義の“語り方”もまた、問い直される時代に入った。
だから右京は、「語りのプロ」に弟子入りした。
言葉で人の心を動かし、真実にたどり着く。 その方法を、講談の世界から学び直そうとしている。
それは決して迷いではなく、さらに強く、深く、正義を貫くための“再鍛錬”だ。
正義は、更新されてこそ守られる。
だから右京は、また“学び直す”。
25周年の『相棒』は、物語として“初心”に戻ったのではない。
初心に戻る“覚悟”を、物語そのものが見せてくれたのだ。
『相棒』が25年続いてなお、面白い理由
普通、ドラマは長く続けば続くほど、視聴者が“展開を読めるようになる”ものだ。
キャラのパターン、演出の癖、脚本家の定番オチ──。
ところが『相棒』は違う。25年経った今でも、「まさかそう来たか」と言わせる。
それは偶然じゃない。奇跡でもない。作品を支えてきた“設計者たち”の執念の結果だ。
毎年「先が読めない」脚本を生み出す輿水泰弘の凄み
シリーズの初回スペシャル──その多くを手がけてきたのが、脚本家・輿水泰弘だ。
今回も彼の手による「講談師編」は、まさに伝説級。
寺脇康文は言う。「またスゴイものを書いてきたな、と震えた」
演じる側が震える脚本。観る側を黙らせる伏線と構成。
『相棒』がすごいのは、“一話完結の刑事ドラマ”という枠組みで、毎年「未知」を生み出し続けている点だ。
普通ならネタ切れになる。
だが輿水は、社会の表層ではなく、「深層のテーマ」に切り込んでくる。
今回も、殺人事件の背景に“芸の継承と衰退”、“人間国宝の重圧”、“弟子と師の呪縛”が潜んでいた。
事件が描かれているようで、その実、描かれているのは「人間そのもの」。
これが、輿水泰弘の“世界の切り取り方”なのだ。
“事件”ではなく“世界観”を描き続けてきたから
25年間、『相棒』が変わらず描いてきたのは「事件」じゃない。
常に、今この国がどうなっているのか、という“時代の空気”だった。
政治と警察の軋轢、官僚機構の閉鎖性、正義の二重構造、報道の信頼性、AIと倫理、LGBTQと家族──。
『相棒』はずっと、“社会”と対話してきた。
右京がその目で「何を見て、何に怒るか」こそが、この作品の指針だ。
ドラマでありながら、時に「社会の鏡」として機能する。
だからこそ、25年という長さが「重み」になる。
続いてきたからこそ、描けるテーマがある。
そして、続けてきたからこそ、積み上げた信頼がある。
「普通を積み上げる」ことが、実は最も難しい
水谷豊が語る一言がある。
「“普通”がいちばん難しい」
この言葉に、『相棒』の本質が詰まっている。
変化球じゃない。ド派手でもない。
当たり前の事件に、当たり前に立ち向かい、当たり前のように真実を突く。
その“普通”の積み上げが、いちばん難しくて、いちばん視聴者の心に残る。
25年、ただ“奇抜さ”では勝負してこなかった。
代わりに、「今の日本で起きている問題」と向き合ってきた。
時に政治家が震え、時に視聴者が泣いた。
右京の一言が、誰かの心に刺さり、言葉にならなかった痛みを代弁する。
これこそが、25年視聴され続けてきた理由だ。
『相棒』は、ドラマである前に「信頼される語り部」だった。
そして今、その語り部は、語りの原点に立ち戻っている。
それが「講談」という選択であり、
それが「弟子入り」という構造だったのだ。
水谷豊と寺脇康文、それぞれの“相棒観”の進化
『相棒』の25年は、キャラクターの成長の歴史でもある。
だが、それは「変化」の話ではない。
右京と薫、それぞれが“何を信じてきたか”という物語の軌跡だ。
25年の重みを背負った2人の俳優──水谷豊と寺脇康文。
彼らが今、新たに語る“相棒観”には、役を生きる者にしか語れないリアルな言葉が詰まっている。
水谷豊が語る「右京の正義」とは何か
「右京は警察官という職業を選んだ瞬間から、一貫して“右京の正義”を胸に刻み続けてきた」
これは水谷豊自身の言葉だ。
25年同じ役を演じるというのは、演技を超えた“信仰”に近い。
役者としてではなく、人間として「右京という人物」を信じ続けた男──それが水谷豊だ。
彼にとって“正義”とは、世間的な倫理ではなく、「右京の目線」で世界を切り取ること。
時に冷徹に、時に優しく。だが絶対に揺るがない。
この“ブレなさ”こそが、相棒ワールドの核となってきた。
だが、今回の初回スペシャルでは、その右京が講談師の内弟子となる。
新たな世界に身を投じ、自ら語りを学び直すという展開は、右京自身の“正義の再定義”を意味している。
それを受け入れ、楽しみながら演じる水谷豊の姿に、僕は静かな敬意を覚えた。
寺脇康文が震えた“初期の薫”のセリフに込めた想い
一方で、薫という男もまた、この25年で多くの顔を見せてきた。
特に注目したいのは、今回の初回スペシャルに「初期の薫のセリフ」が戻ってきたという点だ。
寺脇康文は、それを読んで「震えた」と語る。
初期の軽快さ、どこか青臭い情熱、それでも芯にある人間臭さ──。
そのすべてが、再び脚本に込められていた。
だが同時に、そこには「成長した薫」も存在していた。
昔のままではない。
14年という空白と変化を経て、それでも「薫であり続ける」という矜持。
そこに、キャラクターを演じる役者としての“進化”と“対話”がある。
「変わらない」ことと「変化しない」ことは違う。
薫という人物は、時代とともに揺れながらも、信じるべきことだけは守ってきた。
その絶妙なバランスを、寺脇は芝居に込めている。
芝居に“打ち合わせはいらない”という信頼関係
今回、驚くべき裏話が明かされた。
水谷と寺脇は、シーズンごとのキャラクター構成や芝居について、ほとんど打ち合わせをしないという。
演技プランのすり合わせも、口合わせもしない。
その理由はただ一つ──
2人とも「右京と薫」として、今そこに生きているからだ。
これは、役者として極めて稀有な信頼関係だ。
リアルタイムで息を合わせ、目の前の事件に反応していく。
だからこそ、右京と薫の“相棒感”は、ただの演出を超えたリアリティを持つ。
それは25年積み上げた“現場の空気”であり、“人生の共鳴”だ。
この関係性があるから、『相棒』は変わらず、でも止まらず、前に進める。
水谷と寺脇──。
この2人がいる限り、『相棒』はきっと、“事件”ではなく“信念”を描き続けてくれる。
『相棒』が描いてきた「時代」とは何だったのか
『相棒』というドラマは、事件を解決するドラマではない。
むしろ、「事件を通して“いま”を解剖する物語」と言った方が正確だ。
25年間、描き続けてきたのは、“正義”よりも“空気”だった。
その空気とは、時代の揺らぎ、社会のひずみ、人の内面──。
今年のseason24にも、変わらぬその視線が刻まれている。
政治と権力構造──今シーズンに見える社会の投影
今シーズンも、特命係を取り巻く人間模様は濃厚だ。
甲斐峯秋、衣笠副総監、社美彌子──。
一見、“おなじみのメンバー”たちが織りなす駆け引き。
だがそれは、毎年新たな「構造の揺れ」として描かれている。
たとえば今期、衣笠は特命係の“廃止”を虎視眈々と狙っている。
一方で、甲斐はあくまで“庇護者”としての立場を貫く。
その間で、特命係の存在意義が再び問い直されている。
この関係性は、まるで「組織と個人」の現代的テーマを体現しているようだ。
権力の論理、現場の正義、情報操作、裏工作──。
表には出ない“圧”が、日常を静かに歪ませていく様子が描かれる。
『相棒』は、「巨大な正義」を信じない。
信じるのは、いつだって「目の前の事実」だ。
“暇か?”の裏にある、変わらぬ日常の温度
一方で、このドラマが描き続けてきた“日常”もある。
それが、角田課長の「暇か?」という一言。
あの台詞ほど、『相棒』の本質を表す言葉はない。
どんなに時代が変わっても、警視庁の廊下の片隅では、変わらない人が、変わらない声で挨拶をしてくる。
この“変わらなさ”が、視聴者にとっての拠り所になる。
ドラマというより“生活の中の景色”として存在しているのだ。
今回、角田にも“ある変化”が訪れるという。
その変化が何かはまだ明かされていないが、きっと僕らにこう問うてくるだろう。
「あなたは、自分の“暇か?”を、大切にしていますか?」
事件の裏に、“人の暮らし”がある。
それを忘れないのが、このドラマの美学だ。
25年の変化と、変わらないもの
『相棒』の歴史を振り返ると、そこには明確な“変化”がある。
キャストが入れ替わり、テーマが深化し、脚本も進化してきた。
だが、驚くほどに“変わらない核”もある。
それが、「正しさではなく、誠実さを選ぶ」姿勢だ。
右京は完璧主義者ではない。
ミスもするし、葛藤もする。
でも、どんなに面倒な道でも、「誠実に真実に向き合う」ことだけは決して捨てない。
それは、変化の多い現代において、視聴者が安心して「託せる正義」になっている。
25年、それはずっと変わらなかった。
そして、これからも変わらないと信じられる。
『相棒』が描いてきた“時代”とは、
「人は、何を信じ、何を守るべきか」を問い続けた時間だった。
だからこそ、25周年という節目は、単なる記念ではない。
それは、「問い続けた者たちへの、ひとつの答え」なのだ。
相棒 season24と共に歩む「人生100年時代」の物語
「人生100年時代ですから」──。
今回の初回スペシャルで、杉下右京が放つこのセリフは、ただの時事ネタではない。
この一言には、“物語はいつでも始められる”という強烈なメッセージが込められていた。
それは、水谷豊本人の言葉と重なっていく。
「100年あると考えると、まだ何が起きるかわからない。それを楽しみにできるのが幸せだ」
25年間、同じ役を演じ続けてきた俳優が語る“新たな始まり”。
そこには、どんな年齢でも、“再挑戦していいんだ”という希望が宿っている。
右京の「まだ何かが始まる」セリフが突き刺さる理由
杉下右京という人物は、若くはない。
ベテランの領域に入り、人生の半分以上を「特命係」に捧げてきた。
それでも彼は、今回“弟子入り”という新たな道を選んだ。
人間国宝の家に住み込み、前座として修行する。
それは“新章”というよりも、“人生のリブート”だ。
この展開が突き刺さるのは、今を生きる僕たちが「再スタート」に恐れを抱いているからだ。
年齢、経験、立場… 様々な“しがらみ”が、動けなくしてしまう。
でも右京は、それらを全部背負った上で、もう一度学び始める。
それが“かっこいい”と感じるのは、僕らが心の奥で「変わりたい」と願っているからだ。
自分の物語に“続きを信じる”力をくれるドラマ
寺脇康文は、あるインタビューでこう語っていた。
「豊さんの“これから何かが始まる”という言葉に、頭をガツンとやられた」
誰だって、無意識のうちに“終わり”を意識してしまう。
年齢とともに、何かが閉じていく気がする。
だけど『相棒』は、その考えを軽やかに裏切ってくれる。
25年のキャリアを背負った右京と薫が、「まだやれる」「まだ続ける」と前を向く。
それだけで、画面越しの僕らも「自分にも続きを書けるかもしれない」と思える。
『相棒』という物語は、
「人生に“次のページ”がある」と教えてくれるドラマだ。
私たちはなぜ『相棒』を観続けるのか?
なぜこんなにも長く、『相棒』は支持され続けるのか?
それは、事件が面白いからでも、キャラが立っているからでもない。
“人生”に付き合ってくれている感覚があるからだ。
2000年にこのドラマが始まってから、私たちの生活も変わった。
進学、就職、恋愛、離別、子育て、転職、病気、老い…。
そのすべての途中に、いつも“特命係”がいた。
人生が動くとき、そっと画面の向こうで彼らも歩いていた。
つまり、視聴者にとっての『相棒』とは、“記憶に寄り添う存在”なのだ。
毎年10月に、特命係が帰ってくる。
それは「おかえり」と言いたくなる瞬間であり、「また一緒に歩こう」と思わせてくれる。
『相棒』season24──。
これは、“過去の総集編”じゃない。
むしろ、“未来の予告編”だ。
人生の先にまだ物語があると、信じたくなる。
特命係という「はみ出し者チーム」が、このドラマの心臓だった
事件があるから動くんじゃない。
このチームが存在していること自体が、もうすでに社会にとって“異物”なんだ。
特命係──
正規ルートから外れ、警視庁内で浮きまくっている部署。
だがその「異物感」こそが、25年の『相棒』を支えてきた。
正義の“正道”にいないからこそ、見えるものがある
特命係は、いつも半分「外」から組織を見ている。
本来の警察のルールに縛られず、忖度も出世も二の次。
だからこそ、正義の“汚れた地図”を遠くから眺められる。
情報が隠され、保身が優先される現代社会で、
特命係のポジションは「正義の監視者」ではなく「監視者を見張る者」なんだ。
それって、めちゃくちゃ危険で、孤独で、でも必要。
だから、上層部にはずっと目の敵にされ続ける。
それでも生き残ってきたのは、特命係が「何も持たない」から。
組織の論理を背負ってないから、動ける。
そして、その空白を、右京と薫という“信念と感情”が埋めてきた。
「馴れ合いじゃない」──信頼を超えた共犯関係
右京と薫の関係は、親友じゃない。
互いに理屈が違って、価値観も衝突する。
だけど、それぞれの“譲れないもの”を知っている。
それを壊さないギリギリの距離感で、相棒として成立している。
信頼っていうより、共犯に近い。
正規ルートから逸脱する危険な調査、誰も守ってくれない取材、上司への正面突破。
どれも「一人ではできないけど、二人ならやれる」ギリギリの綱渡り。
それが『相棒』の本質だった。
組織の外でしか救えない“真実”がある。
だからこそ、右京は薫を、薫は右京を「選び続けた」。
このドラマの魅力って、華やかな推理やセリフ回しの中に、
こういう“職場の孤立”とか“チームの異端性”みたいな
リアルな「居場所の不安」も潜んでる。
観てる側は気づいてないかもしれないけど、
どこかで感じてるんだと思う。
──「この人たち、自分の職場にもいそうだな」って。
会社でも、学校でも、チームでも。
声の大きい人や、決定権を持つ人の後ろで、
本当の問題を拾ってくれる“少数派の存在”がいる。
それが認められるには時間がかかる。
でも、いなかったら困る。
『相棒』の特命係は、その象徴なんだ。
『相棒 season24』に見る「信じ続ける力」とは──25周年まとめ
25年──。
ひとつのドラマが、ここまで続くというのは、もはや事件だ。
しかし『相棒』という作品は、その“積み重ね”を単なる継続にしなかった。
むしろ、その歳月を武器に変え、「いま、この時代」を描いてきた。
その最新形が、season24だ。
25年の積み重ねが、今を描く強さに変わった
25周年の今シーズンは、「初心回帰」などではない。
それは、25年の信頼と蓄積があるからこそ、“新しいこと”ができるという証明だった。
右京が講談師に弟子入りする展開は、衝撃的で、ある意味“前代未聞”。
だがその裏には、長年観てきた視聴者だからこそ響く“説得力”があった。
「右京なら、やるかもしれない」と思わせるキャラクターの厚み。
それがあるから、物語の冒険が成立する。
つまり、“積み重ね”は、挑戦の基盤になる。
それは、ドラマだけでなく、僕たちの人生にも言えることだ。
“正義”と“進化”は両立できるという証明
今の時代、「正義」は疑われやすい。
誰かの正しさが、誰かを傷つけることもある。
だからこそ、『相棒』がずっと問い続けてきた「正義とは何か?」というテーマは、より重みを増している。
それは、声を荒げることではない。
派手なアクションでも、復讐でもない。
ただひたすらに、事実に向き合い、嘘を許さず、目をそらさない。
右京のスタンスは、いまや「誠実さの代名詞」だ。
そしてその正義は、進化することを恐れない。
講談という新たな文脈を取り入れ、師弟関係という構造に挑み、
それでも「右京の正義」はブレない。
正義と進化は、共に歩ける。 『相棒』は、それを見せてくれる。
物語を信じた先にあるもの
なぜ、『相棒』を25年も観てしまうのか。
なぜ、今年も「帰ってきた」と思ってしまうのか。
それはきっと、このドラマが“信じる力”をくれるからだ。
自分の人生、自分の選択、自分の正しさ。
そのすべてを問い直しながらも、「それでいい」と背中を押してくれる。
それは、右京のセリフだったり、薫の人間臭さだったり、角田課長の「暇か?」だったりする。
日常に差し込まれる“物語の灯り”が、僕たちを照らしてくれる。
25年の『相棒』には、そうした灯りが無数にある。
そしてseason24は、その灯りをもう一度、“未来”へ向けて差し出してくれている。
物語を信じること。
それは、誰かを信じる力であり、自分を諦めない力だ。
だから僕は、今年も観る。
そしてきっと、来年も。
右京さんのコメント
おやおや…ついに四半世紀。実に感慨深い節目ですねぇ。
一つ、宜しいでしょうか?
今回の初回スペシャルで最も特異だったのは、私自身が“弟子入り”という立場を選んだことです。
従来の捜査手法を捨て、講談という芸の世界に身を置く。これは単なる潜入捜査ではなく、自らの「語る力」を問い直す旅でもありました。
講談師とは、言葉で人を動かし、真実を語る者。
そして刑事もまた、証拠を積み、論理を編み、誰かの心を揺さぶる言葉を探し続ける職業です。
つまり今回は、芸と捜査の境界を越えて、「語ることの責任」そのものを問われた事件だったのです。
なるほど。そういうことでしたか。
25年もの歳月が流れても、我々はまだ成長できる。挑戦もできる。信念も、更新できる。
そのことを、この一件が教えてくれました。
ですが、だからといって「変わらないでいい」という免罪符にはなりません。
伝統の中に隠れた歪み、名声の裏でこびりついた慢心。
それを見逃すことは、“正義”の名に値しませんねぇ。
いい加減にしなさい!
自らの地位を「芸の極致」と履き違え、弟子を使い捨て、命までも操作するような思考。
それは芸でも正義でもなく、ただの驕りです。
人間国宝である前に、人間であるべきだったのです。
それでは最後に。
——私は、紅茶を一杯淹れながら、こう思いました。
「正義」とは、完成された理論ではなく、毎日選び直す姿勢なのだと。
25年の節目に、ようやくその“初歩”に立ち返ったような気がします。
これからも、真実に向かう道を一歩ずつ歩んでいきたいですねぇ。
- 右京が講談師に弟子入りする衝撃展開
- 講談という伝統芸能が描く“正義”の再定義
- 25年間で積み上げた信頼と進化の軌跡
- 水谷豊と寺脇康文が語る「役と共に生きる覚悟」
- 特命係という“異端チーム”の社会的意味
- 「人生100年時代」に希望を灯す物語
- 日常と社会をつなぐ“信じる力”の物語構造
- 正義と変化は共存できるという証明
- 右京さんの総括に込められた誠実さの本質

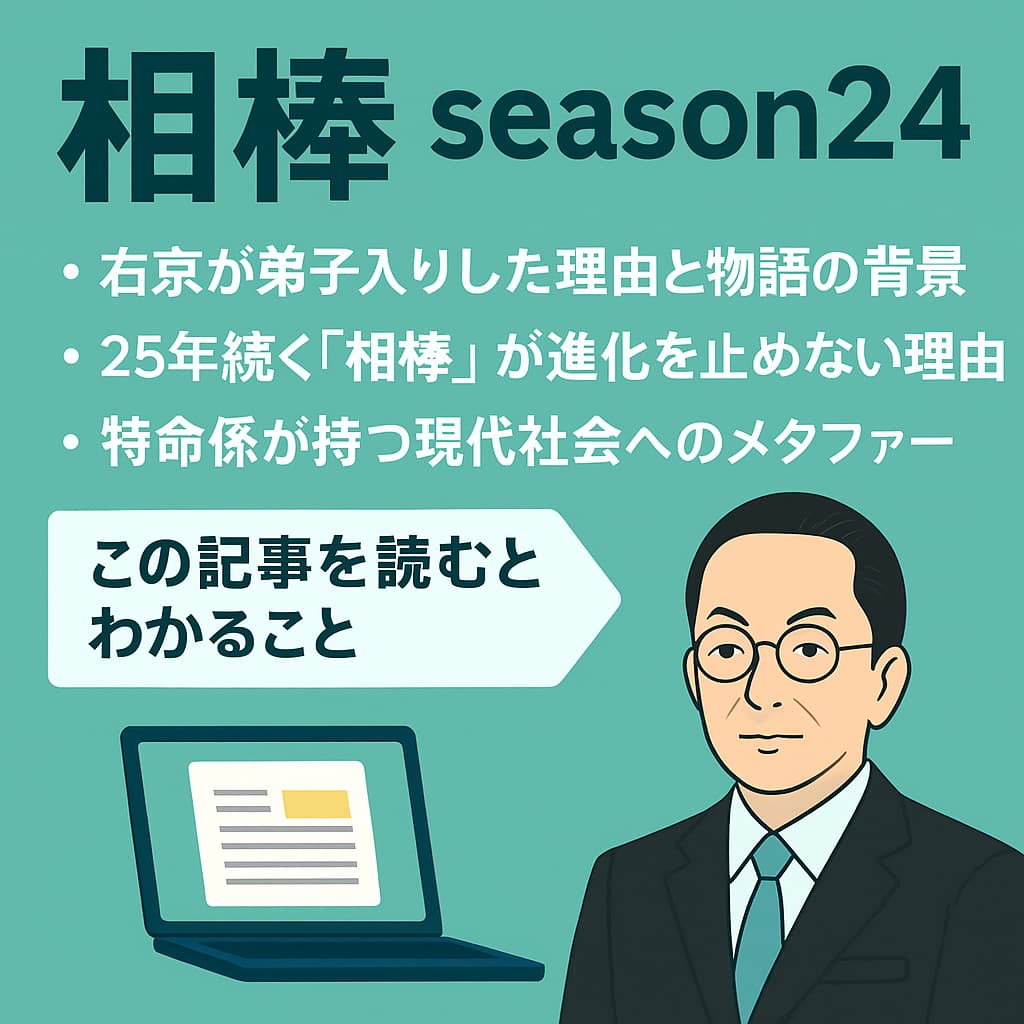



コメント