300回記念となった『いわんや悪人をや(後篇)』は、事件の真相以上に「正義とは何か」「誰が悪人なのか」を静かに問う物語だ。
瀬戸内米蔵、片山雛子、社美彌子──“正しい側”にいた人々が背負った罪と選択。その終着点は、誰も裁けず、誰も救われない場所だった。
この記事では、物語の核心を追いながら、「善悪の境界」「赦しの限界」「愛と国家の矛盾」を読み解く。
- 『いわんや悪人をや(後篇)』が描く“救いなき正義”の本質
- 瀬戸内米蔵・片山雛子・社美彌子が抱えた罪と信仰の交錯
- 右京と冠城が直面した「悪人のいない世界」の意味
真実が明かされても、誰も救われない──白骨遺体事件の結末
白骨が語ったのは「死の理由」ではなく、「生きてきた証の重さ」だった。
『いわんや悪人をや(後篇)』で明らかになったのは、坊谷一樹の死が単なる公安の闇ではなく、“模倣された他者の人生”に起因するものだったということだ。
常盤臣吾──この男の存在が物語を一変させる。彼は亡命スパイ・ヤロポロクの影を背負いながら生き、やがてその影に飲み込まれた。
坊谷を殺したのも、ヤロポロクを名乗ったのも、そして社美彌子の人生を再び狂わせたのも、彼自身だった。
\救われなかった真実を、最初から最後まで確かめる/
>>>相棒Season16 DVDはこちら!
/白骨が語った“答えのない結末”へ\
ヤロポロクと常盤臣吾、二重の“亡命”が意味するもの
常盤は、ヤロポロクに“似ている”という理由だけで、運命を歪められた男だった。
彼にとっての亡命とは、国家から逃げることではなく、「自分という存在」から逃げ出すことだった。
ヤロポロクを名乗り、ロシアの影を背負い、公安に狙われ、ついには殺人を犯す。
その末に残ったのは、誰かに似せた“偽の人生”だけだった。
彼は自分を「誰かになりたかった」と語る。
だが、それは同時に、“誰にもなれなかった”という絶望の裏返しでもある。
ヤロポロクという亡霊は、もはや国家やスパイの物語ではない。人間が「自分を演じ続けた末に失うもの」を象徴している。
彼が坊谷を殺したのも、憎しみではなく、認識の破綻だったのだ。
世界を見失った者が犯した罪は、もはや理屈で説明できない。
社美彌子の涙が語る、“愛の代償”という名の国家犯罪
社美彌子が常盤に向けたビンタは、怒りでも悲しみでもなかった。
それは、自分が信じていた「愛」という幻想を壊すための行為だった。
ヤロポロクの死を受け入れ、娘を守りながら生きてきた彼女の前に、再び“ヤロポロクの顔をした男”が現れる。
その瞬間、彼女はもう一度あの記憶の中に引き戻される。
常盤が送った手紙の筆跡は偽物だった。
だがその偽りに、彼女はしばらく気づかない。
それは筆跡ではなく、“もう一度信じたかった”という欲望が目を曇らせたからだ。
公安に仕える彼女は、常に国家と個人の板挟みの中にいる。
だがこの事件では、国家のためでも、任務のためでもなく、“一人の女としての弱さ”が露わになる。
その弱さこそが人間らしさであり、同時に国家にとって最も危険な欠陥でもある。
愛を持つことが罪になる世界で、彼女は再び罰を受けた。
右京の沈黙が示す、「真相」と「赦し」の距離
右京が事件の全貌を語り終えた時、彼はいつものように“断罪”しなかった。
それは、今回の事件において、裁かれるべき者が誰なのか、誰もわからなかったからだ。
常盤は狂っていた。社は苦しんでいた。公安は沈黙していた。
そして瀬戸内もまた、「人を救おうとした結果、また一人の罪人を生んでしまった」と自覚していた。
右京の沈黙は、赦しと無力の境界線にある。
真実を知っても、人は救われない。
だが知らなければ、同じ罪がまた繰り返される。
その矛盾を抱えながら、右京はただ静かに墓の前に立つ。
「いわんや悪人をや」──善人でさえ救われるのなら、悪人はなおさら。
しかし、この世界では、善人も悪人も同じように罰を受ける。
真実が明かされても、救いの鐘は鳴らない。
残るのは、“知ってしまった者の孤独”だけだ。
片山雛子の出家は救いか、逃避か──政治と信仰の交錯点
静寂の中で鐘が鳴る。袈裟に身を包んだ女の姿は、まるで罪を脱ぎ捨てたように見えた。
だが、その一歩先にあるのは救いではない。“信仰をも利用する才覚”だった。
『いわんや悪人をや(後篇)』における片山雛子の出家は、単なる贖罪ではない。
それは、政治という檻から逃れ、別の形で権力を掌握するための「転生」だった。
\片山雛子という女の“再生の演出”を見届ける/
>>>相棒Season16 DVDはこちら!
/信仰と野心が交差する瞬間をもう一度\
得度式に込められた“再生の演出”
得度式の場面は象徴的だ。瀬戸内米蔵の寺で、蓮妙が導師を務める。
白い袈裟、沈黙、花びら、そして報道陣。
そのすべてが、“再生という名の演出”に見えて仕方がない。
片山雛子は世間の注目を自らの“葬式”に変えた。
政治家として死に、信仰者として生まれ変わる──その構図こそが、彼女の最大の戦略だ。
式の最中、蓮妙が静かに言葉をかける。
「出家とは、すべてを捨てること。あなたにそれができますか?」
雛子は微笑みながら「俗世など、もう十分に見ました」と答える。
その一言が、この女の底の浅さと深さを同時に暴く。
信仰ではなく、“再生の物語を演出する力”。
彼女は仏ではなく観客を見ている。
テレビカメラのレンズの向こうにいる“国民”こそ、彼女の聴衆だった。
「妙春」となった雛子が示した、女性としてのしたたかさ
得度後の名は「妙春」。
柔らかくも、どこか艶めいた響き。
この命名に、瀬戸内米蔵の意図があるのか、彼女自身の演出なのかは明らかではない。
だが、いずれにせよこの新しい名は、「片山雛子」という政治的ペルソナの延長線上にある。
右京との会話で、雛子は言う。
「人はどんなに生まれ変わろうとしても、過去からは逃れられません。」
まるで自嘲のような台詞だが、そこには“計算された哀しみ”がある。
彼女は常に、弱さを演出し、相手に同情と隙を生ませる術を知っている。
政治の世界では男たちの論理に囲まれていた。
だが、信仰の世界では“女性”であること自体が力になる。
その転換点を見抜いていたのが、妙春という新しい仮面だ。
祈りながらも、彼女の目はどこか遠くを見ている。
信仰を手段にしても、涙の見せ方を間違えない。
その冷静さが、“悪女ではなく、戦略家”としての雛子を確立している。
信仰の皮を被った「野心」の構造
この後篇で雛子の出番は決して多くない。
だが、彼女の存在は物語全体を支配している。
瀬戸内の祈り、社の涙、右京の沈黙──すべての構図の中心に、“再生を演じる女”がいる。
雛子はもう政界に戻る気はない。
だが、彼女の視線は常に“影響力”に向いている。
国家や宗教といった枠組みの中で、自分が“物語”になることを本能的に理解している。
それはもはや政治ではなく、“信仰の物語を操作する芸術”だ。
妙春という名前が象徴するのは、信仰を利用して再生する“女神”の皮膚。
そしてその奥には、何も変わらない野心が静かに息づいている。
瀬戸内が「あなたは本当に変わりましたね」と言うと、
彼女は微笑んで答える。「ええ。けれど、変わらないものもあります。」
その言葉のあと、カメラがゆっくりと引く。
僧衣の下に隠された人間の欲望が、あまりに静かで、あまりに美しい。
片山雛子の出家──それは贖罪ではなく、“信仰という名の再選挙”だった。
瀬戸内米蔵と蓮妙が見届けた、“正義の死”
寺の鐘が鳴る。瀬戸内米蔵は静かに目を閉じ、蓮妙はその横顔を見つめていた。
政治家として、僧として、そして罪人として生きてきた男の祈りは、もう誰のためでもなかった。
『いわんや悪人をや(後篇)』の終盤で描かれるのは、「正義の終わり」を見届ける者たちの沈黙だ。
正義はもはや理念ではなく、ただの廃墟だった。
その瓦礫の中で、瀬戸内はなおも祈り続ける。
蓮妙はその祈りを見守りながら、かつて政治の世界に生きたこの男の“残響”を聞いている。
\瀬戸内米蔵が祈り続けた“正義の最期”を見る/
>>>相棒Season16 DVDはこちら!
/法と信仰のあいだに残った沈黙へ\
罪を背負いながらも祈りをやめない者たち
瀬戸内米蔵という人物は、シリーズを通して「信念と罪の両立」を体現してきた。
政治を捨て、僧となり、罪を償う——それでもなお、彼は完全には清められない存在だ。
前篇で白骨が掘り起こされ、後篇で常盤臣吾という狂気が明らかになった今、
瀬戸内の祈りはもう意味を失っているようにも見える。
だが、蓮妙は言う。「意味のない祈りこそ、最も強い祈りです。」
この一言が、物語全体の核心を突いている。
祈りとは、誰かを救うためではなく、自分が人であり続けるための行為なのだ。
瀬戸内の祈りには、政治的意図も贖罪の演出もない。
それは、もはや自らの存在を保つための“呼吸”に近い。
その姿を見つめる蓮妙の表情には、慈悲と絶望が同居している。
彼女は理解している。
人が罪を悔いるとき、その悔いがまた新たな罪を生むという循環を。
だからこそ、二人の祈りはどこか美しく、同時に救いようがない。
法と信仰、国家と個人が交わる場所
瀬戸内と蓮妙が立つ寺は、まるでこの国そのものの縮図だ。
法(政治)と信仰(祈り)が交差し、互いに矛盾しながらも共存している。
瀬戸内は法を知る者でありながら、信仰に救いを求めた。
蓮妙は信仰を知る者でありながら、人間の愚かさを捨てきれなかった。
二人が交わす言葉は少ない。だがその沈黙の中に、「国家」という巨大な虚構に抗おうとした人々の記憶が漂っている。
政治という舞台から遠ざかった瀬戸内にとって、寺は安息の地であるはずだった。
だが、その寺が再び事件の中心となった今、彼に安息はない。
彼は理解している。
国家の中に“悪人”はいない。
あるのは、誰かの正義が他人を傷つけるという構造だけだ。
その構造に抗うために、彼は僧となった。
だが、法を離れても、人は罪を離れられない。
蓮妙は最後にこう言う。
「善人でも悪人でも、祈りは届きません。ただ、生きる者の手を離れた声が、どこかで響くのです。」
瀬戸内は頷き、静かに合掌する。
それは赦しでも悟りでもなく、ただの諦念だった。
この瞬間、「正義」は死に、祈りだけが残った。
そしてその祈りは、この国に残された最後の“正義の形見”となる。
右京と冠城が直面した、“悪人”のいない世界
すべての真相が明らかになったあとも、右京の表情は静かだった。
だが、その沈黙には、かつてないほどの重さがあった。
『いわんや悪人をや(後篇)』で特命係が辿り着いたのは、悪人のいない事件だった。
誰もが誰かのためを思い、誰もがその「正しさ」によって壊れていった。
正義が誰かを殺す。
その残酷な構図の中で、右京と冠城は異なる方法でその痛みに触れていく。
\“悪人のいない世界”で右京が立ち尽くす理由/
>>>相棒Season16 DVDはこちら!
/正義に疲れた人間たちの現実を直視する\
正義を貫く者の孤独
右京にとって、正義とは理性と真実の積み重ねだ。
だがこの事件では、その理性が何の救いにもならなかった。
常盤臣吾の狂気も、社美彌子の沈黙も、瀬戸内の祈りも、片山雛子の計算も、
どれも「正しいことを信じた結果の崩壊」だった。
右京はその全てを見届けながらも、誰も裁けない。
彼がいつも求めているのは真実であって、断罪ではない。
だが今回は、その真実ですら人を救えなかった。
真実を知ることが、誰かを傷つける。
知らないままでいる方が、まだ人は優しくいられる。
右京はその逆説の中で立ち尽くしていた。
ラストシーンで、墓の前に立つ右京の姿は、かつてのどんな事件よりも人間的だ。
理性ではなく、感情で世界を見ている。
その表情に、長い年月の中で失われた“正義の温度”がわずかに戻っていた。
「悪人をや」──善人でさえ救われるのなら、悪人はなおさら。
右京はその言葉を反芻しながら、きっと自分にも問いを投げかけていた。
自分の正義は、誰かを苦しめていないか。
特命係としての正義を貫くことは、同時に「誰も救わない」選択でもある。
それが右京という男の、最も深い孤独だ。
冠城の激情と右京の理性──対比が示す「現代の葛藤」
冠城亘は、右京とは正反対の反応を見せる。
彼は怒りを抑えきれず、正義を裏切る者たちに声を荒げる。
「なぜそんなことをした!」
その叫びには、理屈ではない人間の痛みがある。
冠城は法務官僚出身として、制度の中で正義を信じてきた。
だが、その制度が人を殺し、沈黙を強いた現実を前にして、
彼は初めて「正義の限界」に直面する。
右京は静かに言う。
「あなたはまだ、正義を信じているのですね。」
冠城は答えない。
ただ、唇を噛みしめる。
その対比が、この二人の物語を鮮烈に描き出している。
右京は信じることをやめたわけではない。
ただ、信じることの代償を知っている。
冠城はまだ、その代償を払う途中にいる。
その差こそが、二人を“相棒”たらしめている。
右京の理性と冠城の情熱、二つの視点が揺れることで、
このドラマは単なる推理劇から、“現代における倫理のドキュメント”へと変わった。
冠城はラストで、事件後の沈黙の中に立ち尽くす。
その表情は怒りでも安堵でもない。
世界を少しだけ理解してしまった者の顔だ。
右京が彼に紅茶を差し出し、
「熱いうちにどうぞ」と微笑む。
その一瞬だけ、二人の間に小さな赦しが生まれる。
だがそれは、長い孤独の始まりでもあった。
二人が立っているこの場所には、もう悪人はいない。
いるのは、正義に疲れた人間たちだけだ。
そして右京は静かに言う。
「正義のない世界で、人は何を信じるべきなのでしょうね。」
その声は、まるで現代社会そのものに響いているようだった。
“悪人のいない世界”とは、善人が責任を放棄した世界のことだ。
「正しくあろうとする人」ほど報われない──それでも祈る理由
この物語を貫く痛みは、「正しく生きようとした者ほど深く傷つく」という一点に集約されている。
『いわんや悪人をや(後篇)』が描いたのは、悪人の断罪でもなく、真相の解明でもない。
それは、“正義に疲れた人間たち”がそれでもなお祈る姿だった。
瀬戸内米蔵は罪を知りながらも祈りを捨てられなかった。
片山雛子は出家という演出の裏で、まだ“人に見られること”を手放せなかった。
社美彌子は愛を抱いたまま沈黙し、冠城は怒りを抑えきれず、右京は赦しの言葉を探し続けた。
彼らは誰も報われない。
しかしそれでも祈る。
なぜなら、祈りだけが人を人に戻す最後の行為だからだ。
\それでも人が祈る理由を、物語で確かめる/
>>>相棒Season16 DVDはこちら!
/正しく生きようとした者の行き着く先へ\
善悪を超えてなお、人は何にすがるのか
「悪人を救う仏がいるなら、国家を救う仏はどこにいるのでしょうね。」
右京のこの台詞が、シリーズ300回という節目に投げかけられた最大の問いだ。
国家も宗教も、人を救うためにあるはずだった。
だが現実には、どちらも人を縛り、沈黙させ、壊していく。
正義は制度に絡め取られ、善意は形骸化し、祈りはマスコミの演出になる。
それでも人は祈る。
それでも誰かを信じたいと願う。
なぜか。
それは、「信じる」という行為そのものが、人間の最後の自由だからだ。
右京が祈るのは、赦しのためではなく、問い続けるためだ。
冠城が怒るのは、憎しみのためではなく、世界を諦めたくないからだ。
そして瀬戸内や雛子が沈黙するのもまた、祈りの一形態だ。
善悪の区別が曖昧なこの世界で、人はもはや「正しいこと」を選べない。
選べるのはただ、「何を信じるか」だけだ。
その選択の苦しみを受け入れることこそが、“生きるという祈り”なのだ。
300回記念回が示した“相棒”という哲学の到達点
『相棒』というシリーズは、単なる刑事ドラマではない。
それは20年にわたって、「人はどこまで他人を理解できるか」という問いを描き続けた哲学作品だ。
300回記念となるこのエピソードで描かれたのは、“理解を超えても、なお寄り添う”という境地だ。
右京と冠城は事件を解決しても、何も変えられない現実に直面する。
だが、それでも二人は同じ場所に立ち続ける。
紅茶を淹れ、言葉を交わし、再び歩き出す。
彼らが選んだのは、赦しではなく、“共に問い続けること”だった。
それが“相棒”という関係の本質であり、この300回記念が到達した真理でもある。
悪人はいない。
善人もいない。
ただ、罪を抱えながら生きる人間がいるだけだ。
そして、その人間の愚かさを受け入れるところから、世界はようやく始まる。
瀬戸内の祈りも、雛子の微笑みも、右京の沈黙も、同じ一点で交わる。
それは、“祈り続けるという人間の尊厳”だ。
誰も救われない物語の中で、それでも歩き続ける者たち。
その姿こそ、『相棒』という長い祈りの結晶である。
そして、我々もまた問われる。
「いわんや悪人をや」──
あなたの中の悪人は、もう救われたか。
この物語が一番突きつけてきたのは、「観ている側の正義」だった
後篇を見終えたあと、胸に残るのはカタルシスではない。
むしろ、どこにも置き場のない感情だ。
怒っていいのか、同情していいのか、それとも黙って受け入れるべきなのか。
『いわんや悪人をや(後篇)』が本当に問いかけてきたのは、登場人物の善悪ではなく、観ている側が握りしめている「正義の感覚」だ。
\“裁く側”に立たされた自分を確かめる/
>>>相棒Season16 DVDはこちら!
/観ている側の正義が試される物語へ\
「かわいそう」と思った瞬間、もう裁いている
常盤臣吾は狂っていた。
だが、その人生を辿ったとき、完全に切り捨てることはできなかった。
社美彌子の涙は痛々しかった。
だが、その沈黙が誰かを死なせた可能性も否定できない。
瀬戸内米蔵の祈りは誠実に見えた。
だが、その理想が新たな罪を生んだのも事実だ。
ここで視聴者は必ず揺れる。
「悪いのは誰だ」と考えながら、同時に「でも、気持ちはわかる」と思ってしまう。
その瞬間、自分もまた裁く側に立っている。
同情は赦しのようでいて、実は線引きだ。
理解は優しさのようでいて、評価でもある。
このドラマは、その無自覚な正義を容赦なく炙り出す。
「正しい側に立ちたい」という欲望の正体
右京は誰も断罪しない。
だが、それは優しさではない。
彼は知っている。
正しい側に立ちたいという欲望そのものが、次の悲劇を生むことを。
この後篇には、明確な悪役がいない。
その代わり、「正しくあろうとした人間」が大量に出てくる。
国家のため。
愛する人のため。
信じる理念のため。
そのすべてが正しく、同時にすべてが誰かを壊している。
視聴者も同じだ。
「こうするしかなかった」と思った瞬間、誰かの選択を免責する。
「それでも許されない」と思った瞬間、別の誰かを切り捨てる。
この往復運動こそが、物語の外にいる我々の“相棒的立場”だ。
だからこの後篇は、観終わったあとにスッとしない。
答えをくれない。
代わりに、自分がどんな正義を欲しがっているのかだけを突きつけてくる。
悪人を救うかどうかよりも前に、
「自分は誰を悪人にしたがっているのか」。
その問いを抱えたまま沈黙するしかない――
それこそが、『いわんや悪人をや(後篇)』という物語の、本当の終わり方だ。
「いわんや悪人をや(後篇)」が残したメッセージまとめ
終わってみれば、この物語は誰の勝利でもなかった。
善人は報われず、悪人も罰されない。
真実は明らかになったが、そこに安堵はない。
残されたのは、“正義とは何か”という問いの余韻だけだった。
『いわんや悪人をや(後篇)』は、300回記念という節目にふさわしく、
このシリーズが20年かけて積み上げてきたテーマ──
「人はどこまで他人を救えるのか」「正義は誰のためにあるのか」──を再び掘り下げた。
そして、その答えをあえて提示しないことで、作品は一つの“完成”を迎えた。
\300回記念回が残した問いを、映像で噛みしめる/
>>>相棒Season16 DVDはこちら!
/“正義とは何か”をもう一度考えるなら\
瀬戸内米蔵の祈りは、もはや罪の贖いではない。
片山雛子の出家は、救済のためでも逃避のためでもない。
社美彌子の沈黙は、愛のためでも任務のためでもない。
彼らはそれぞれ、自分の中の「悪」と共に生きる道を選んだ。
右京と冠城は、その選択を責めない。
むしろ、その“人間らしさ”を見届ける立場にいる。
特命係が事件を終えても、真実を突き止めても、
世界が少しも良くならないという現実を、二人は知っている。
だからこそ、彼らは歩き続ける。
紅茶の香りの向こうで、わずかに息を整えながら。
それは“希望”ではなく、“問いを止めないことそのものが希望”だからだ。
この物語に“悪人”はいなかった。
いたのは、自分の正義を信じた人間たち。
そしてその信念が、他人を、そして自分自身を傷つけた。
瀬戸内が語った「人は善にも悪にもなりうる」という言葉。
その意味を右京は、冠城は、そして我々も噛みしめる。
正義が誰かを救うとは限らない。
だが、正義を求めることをやめた瞬間に、人は人でなくなる。
『相棒』という作品が300話を迎えてなお進化し続けるのは、
この“終わりのない問い”を抱え続けているからだ。
「いわんや悪人をや」──この言葉はもはや仏典の引用ではない。
それは、この時代を生きる我々への祈りだ。
誰もが何かを信じ、何かを裏切りながら、それでも生きていく。
その過程そのものが、贖罪であり、救いである。
そして右京の声が、最後に響く。
「善人なおもて往生を遂ぐ──いわんや悪人をや。」
その一言に、20年の時間と、300話分の祈りが凝縮されている。
それは終わりではなく、次の“問い”の始まりだ。
人はなぜ正しくあろうとするのか。
その答えを探す旅は、これからも続いていく。
右京さんの事件総括
おやおや……これはまた、ずいぶんと後味の残る事件でしたねぇ。
一つ、宜しいでしょうか。
今回、我々が解き明かしたのは「誰が殺したのか」ではありません。
むしろ、「正しくあろうとした人間が、どこで道を踏み外したのか」――その過程でした。
常盤臣吾は、悪意から人を殺したわけではありません。
彼はただ、自分という存在を失い、誰かになろうとした。
それがどれほど危うい行為か、彼自身が最後まで理解できなかっただけです。
なるほど。そういうことでしたか。
社美彌子さんは、国家と愛の間で沈黙を選びました。
その沈黙は、決して卑怯さではありません。
ですが同時に、人の命を救えなかったという事実からも、逃れられない。
瀬戸内米蔵氏は祈り続けました。
罪を背負い、正義を失い、それでもなお祈る。
それは贖罪というより、人であることをやめないための抵抗だったのでしょう。
「善人なおもて往生を遂ぐ、いわんや悪人をや」。
この言葉は、悪人を甘やかすためのものではありません。
人は誰しも、善と悪の両方を抱えて生きている――
その事実から目を逸らすな、という厳しい戒めです。
いい加減にしなさい!
正義を名乗るなら、自分が誰かを傷つけていないか、
まずそこから疑うべきでしょう。
今回の事件には、明確な救いはありません。
ですが、救いがないからこそ、考え続ける価値がある。
真実を知ることは、必ずしも人を救いません。
それでも我々が真実を求めるのは、
知らずに正義を振りかざすことの方が、よほど罪深いからです。
紅茶を飲みながら考えましたが……
正しさとは、誰かを裁くためにあるのではない。
自分が間違えるかもしれないと、立ち止まるためにあるのかもしれませんね。
この事件が残したものは、答えではありません。
問いです。
そして、その問いを抱え続ける覚悟こそが、
我々が人間であり続けるための条件なのでしょう。
- 真実が明かされても誰も救われないという構造を描く
- 常盤臣吾と社美彌子の“亡命”が人の存在の崩壊を象徴
- 片山雛子は信仰をも政治利用する再生の演出者
- 瀬戸内米蔵と蓮妙が見届けたのは“正義の終焉”
- 右京と冠城が立つのは“悪人のいない世界”の孤独
- 正しくあろうとする者ほど報われず、それでも祈る姿を描く
- 観る者自身の“正義の欲望”を試す哲学的構成
- 右京の総括が示す、正義とは疑う勇気のこと

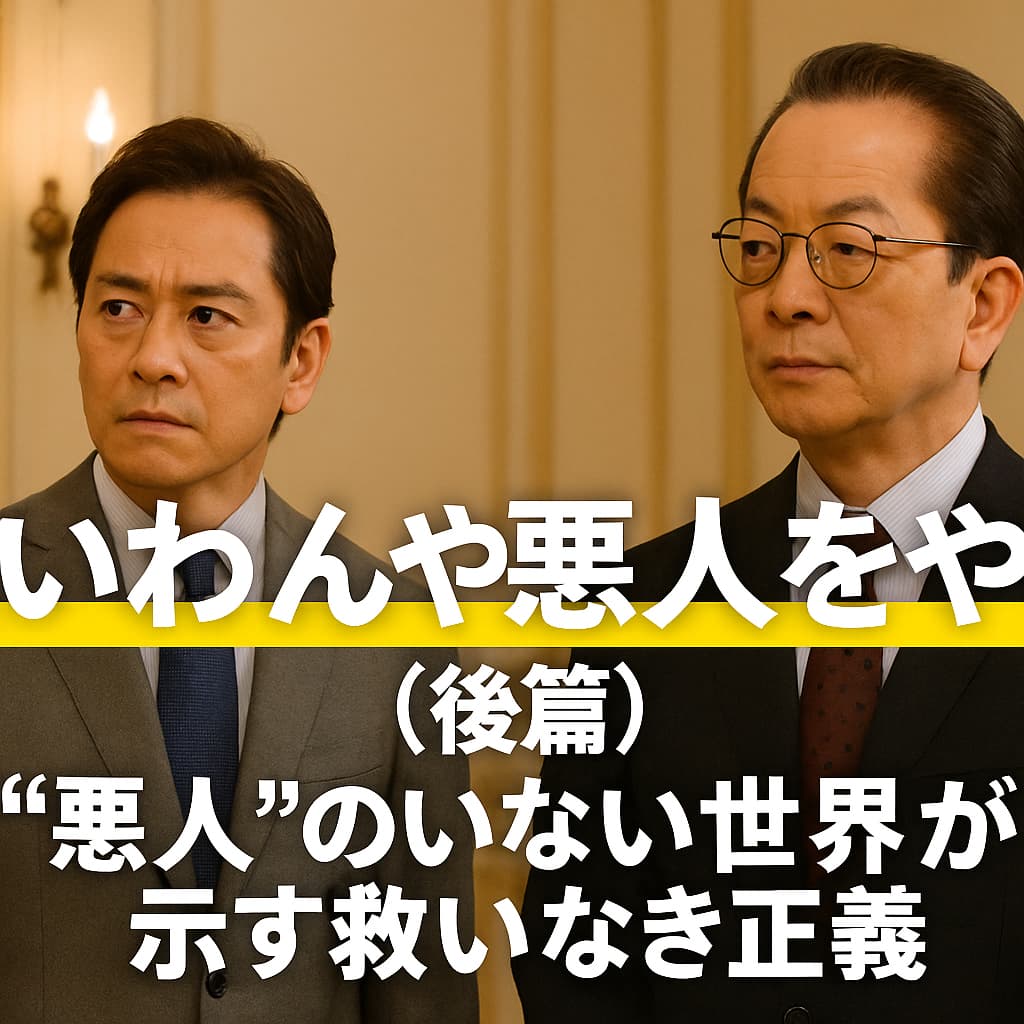



コメント