2025年大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』で、えなりかずきが演じる松前道廣が大きな話題を呼んでいます。
松前道廣は、蝦夷地を治めた松前藩の第8代藩主。文武に長けながらも遊興に溺れ、ついには「永蟄居」の処分を受ける波乱の生涯を送りました。
本記事では、松前道廣の史実とドラマでの描写、そして松前藩の特異な統治体制を通して、えなりかずきの演技に込められた“歴史の裏側”を掘り下げます。
- 松前道廣の実像と蝦夷地支配の歴史的背景
- えなりかずきのキャスティングが持つ演出的意義
- 松前藩が抱えた交易制度と密貿易の構造的矛盾
松前道廣はなぜ「永蟄居」となったのか?史実が語る失脚の真相
2025年の大河『べらぼう』で、えなりかずきが演じる松前道廣が視聴者の心に強烈な焼き印を残した。
この男は鉄砲を片手に笑い、女郎を金で買い、吉原で遊び尽くし、最終的には永蟄居──つまり出仕も外出も禁じられた終身謹慎の刑に処された。
だが、ここで問い直したい。彼は“ただの暴君”だったのか? いや、それだけじゃこの男の影は描ききれない。
若くして藩主になったが藩政に関心を持たず
松前道廣が藩主になったのは、なんと12歳のときだった。
宝暦4年(1754年)生まれの彼は、父・松前資広の跡を継ぎ、明和2年(1765年)に藩主の座につく。
時代は江戸中期、蝦夷地をめぐる国防が本格化し始めた時期。松前藩はロシア南下の最前線という重圧を背負っていた。
にもかかわらず、彼は政治に背を向けた。興味を持ったのは藩政ではなく、遊興と酒、そして女。
わかる。12歳で背負わされた重荷に、心が育つ暇などなかったのだ。
父の死=責任の始まり。まだ文字を書く手も震えるような少年が、藩主の印鑑を持たされた。その時点で、彼の“心の椅子”はすでにグラついていたのかもしれない。
幕府からの度重なる警告とついに下った処罰
道廣の行動は次第にエスカレートしていく。
吉原通い、妓楼主との癒着、女郎の身請け、そして江戸での過度な浪費。
3万石の小藩がどうやってそんな金を?と疑問に思うが、その裏には「抜け荷」──つまり密貿易が囁かれている。
場所は蝦夷、幕府の目も届かぬ北の果て。松前藩はアイヌ交易や海産物の利権を独占していた。それを“商売”ではなく、“遊興費”に使い始めた。
寛政4年(1792年)、ついに幕府が動いた。隠居命令である。
「そろそろ、もういいだろう」──そんな空気だったのだろう。しかし、道廣は黙らなかった。隠居後も好き勝手に振る舞い、噂は江戸にまで届く。
文化4年(1807年)、ついに「永蟄居」の処分が下る。藩主であっても、これは極刑に近い。
出仕禁止、外出禁止、死ぬまで謹慎。牢獄ではない。だが“生きながら死ぬ”罰だった。
それはまるで、物語のエンディングロールが始まったのに、スクリーンの中でまだキャラが立ち尽くしているような、不気味な終わり方だった。
松前道廣は、愚かな藩主だったのか?たしかに。
しかし同時に、未熟なまま責任を背負わされた少年の末路でもある。
ドラマ『べらぼう』で、えなりかずきが“良い人”のイメージをかなぐり捨ててこの役を演じる意味は、そこにある。
人は弱さを抱えたとき、どこまで壊れてしまうのか。
それを“べらぼう”なまでに演じる。演技とは、時に歴史を超えて、心を折りにくる。
えなりかずきが演じた“狂気の藩主”──ドラマ『べらぼう』での再構築
あの“えなりかずき”が、鉄砲を持って部下を脅す。
『渡る世間』で優しく小言を言ってた彼が、今では笑いながら「お前の女房に一発かましてやろうか」と言う。
視聴者は一瞬、目を疑った。だが、その違和感こそが、このキャスティングの醍醐味だった。
鉄砲で部下を脅す?異様な描写の背景にある意図
ドラマ『べらぼう』第21話。
酒宴の席で、松前道廣(えなりかずき)が部下の妻に鉄砲を向けるシーンが描かれた。
これは創作ではない。史実の彼も、宴の場で“余興”と称して部下を弄び、遊興を娯楽のように消費していた。
ただ、それを視聴者が「えなりかずき」で見るというのが、最大の衝撃だった。
つまりこれは、「この人ならそんなことしないはず」と思わせた上で、その信頼を真っ向から裏切る演出なのだ。
優しそうな顔、丁寧なしゃべり、昭和の息子像──そんな“えなり”を借りて、暴君・道廣の本性を描く。
それは裏切りではない。 人間の二面性を見せつけるための手法なのだ。
暴力は暴力でしか描けないが、狂気は“常識人の仮面”をかぶったままのほうが、怖い。
その怖さが、ドラマに深みを与えた。
「良い人」のイメージを覆すキャスティングの妙
日本の大河ドラマでは、ときおり“意外な人選”が話題になる。
だが、今回の「えなりかずき=暴君」というキャスティングは、近年まれに見る“ギャンブル”だった。
結果、それは成功した。
なぜか?視聴者が彼を“信じて”いたからだ。
信じた人物が裏切ったとき、物語は最も深く心に刺さる。
これは演出の常套手段だが、それをここまでナチュラルに、説得力を持ってやれる俳優はそう多くない。
しかも、えなりの演技は“暴君”を誇張しない。
笑顔で銃を構え、丁寧な言葉で狂気を語る。狂っているのに、筋が通っているように見える。
それが余計に怖い。だって、「優しい顔をした加害者」は、現代にもいるからだ。
彼の演技は、観る者にこう問いかけてくる。
「人は、どこまで“見た目”で安心してしまっているのか?」
このキャスティングの妙は、単なる話題作りではなく、“人間を疑うこと”の重要さを視聴者に訴える構造そのものだった。
だからこそ、あのシーンは忘れられない。
えなりかずきは、「いい人」のイメージを壊したのではない。
いい人でも狂えるという現実を、見せつけたのだ。
そしてそれが、“暴君”というキャラクターに、皮肉なリアリティを与えた。
松前藩とは何だったのか?石高ゼロの交易国家という異質な藩制
江戸時代、日本中の大名たちは“米”で統治されていた。
だが──松前藩は石高ゼロだった。
米を持たない藩。それでも300年、生き延びた異端の藩。
その秘密は、「交易」で築かれたもう一つの経済国家という姿だった。
石高ではなくアイヌ交易で成立した経済構造
松前藩の領地は、今の北海道──当時の蝦夷地。
寒冷で稲作に適さない土地にあって、藩は幕府から“アイヌ交易”の独占権を与えられていた。
米がないなら、魚で生きろ。昆布で生きろ。毛皮で生きろ。
それが松前藩のリアルなサバイバルだった。
アイヌと交換した物資は、本州に流れ、そして金に化けた。
しかしその裏には、過酷な支配と搾取があった。
場所請負商人は、アイヌの自由な交易を奪い、「場所」という名の経済植民地を作った。
労働は強制され、文化は封じられ、反発が起きた。
代表例が、クナシリ・メナシの戦い(1789)。
松前藩による交易独占に抗議して、アイヌが蜂起した出来事である。
これは「反乱」ではない。自分たちの生活を守るための声だった。
だが、歴史の記述ではその声は小さくされる。
それでもこの戦いは、松前藩の統治の根幹にあった矛盾──“支配する側とされる側”の非対称性──を炙り出した。
“場所請負”による漁業利権と幕府の北方政策との狭間
17世紀後半から、松前藩の収入は“場所請負”という制度にシフトした。
これは、商人に交易・漁業地を貸し出し、運上金(今でいう使用料)を藩が徴収する方式。
藩が労せずして金を得る。だが、それは請負人と現地民の対立を常態化させた。
交易は搾取へ、経済は不信へ、信頼は敵意へと変わる。
18世紀末、ロシアの南下圧力が高まると、幕府はその“歪んだ経済”に懸念を示し始めた。
そして、文化4年(1807年)、幕府は蝦夷地をすべて直轄領とし、松前藩を一時的に廃した。
国防の最前線で“交易国家”を運営するリスク。
それがいかに不安定で、政治的に無責任な構造だったかが、露呈した瞬間だった。
アイヌとの摩擦、抜け荷の横行、請負人の暴利──それらを「統治」と呼べるのか。
いや、それは“行政の皮をかぶった商売”だったのだ。
松前藩とは、統治と交易がズブズブに溶け合った、異端のミニ国家だった。
だからこそ、道廣のような人物が生まれたのかもしれない。
支配者なのに、政治家ではなかった男。
その舞台となった松前藩自体が、“不完全な国家”だったという証だ。
暴君の資金源は「抜け荷」か?遊興費と密貿易の闇
松前道廣──暴君、色狂い、放蕩者。
だがここで浮かぶ疑問がある。その豪遊資金は、いったいどこから湧いてきたのか?
松前藩は石高ゼロ。農地も米もない。しかもわずか3万石の小藩。
なのに道廣は、吉原で女郎を身請けし、江戸で絢爛たる浪費三昧。
その金の出所に、黒い影がチラつく──「抜け荷(密貿易)」である。
吉原通いと豪遊を支えた裏金の噂
道廣の吉原通いは、すでに史実としても確認されている。
妓楼主と馴れ合い、女郎を“私物”にし、身請け(金を払って自由にする)までしていた。
その費用、当時で300両以上──現代の貨幣価値にして数千万円単位。
それを複数人分、何度も支払う。
藩主としての給料では到底足りない。
では、その原資はどこから来たのか。
──ここで登場するのが、「抜け荷」という言葉だ。
幕府の目をかいくぐって、海産物や薬、毛皮などを密かに江戸や国外に売りさばく。
もちろん公式には禁じられていたが、蝦夷の果てにある松前藩はその監視が極めてゆるかった。
場所請負人との癒着、港の“目こぼし”、そして運上金の水増し報告。
つまり、制度のスキマで利益をかすめ取る、いびつな経済構造がそこにあった。
遠隔地の利を活かした密輸と松前藩の脆さ
松前藩はその立地──北海道南端という“遠さ”──ゆえに、幕府の統治からこぼれていた。
それは時に自由であり、時に無法だった。
藩の経済は、「監視されないこと」が最大のアドバンテージだった。
海の向こうで何をしていても、幕府に届くのは報告書だけ。
その空白地帯を最大限利用したのが、松前道廣だった。
商人と結託し、密輸を黙認し、あるいは加担する。
それで得たカネで、江戸に豪邸を建て、吉原で見栄を張る。
政治より、快楽のほうが“儲かる”と彼は知っていた。
それがどれほど藩の信用を損ねたか。どれほどアイヌとの関係を悪化させたか。
──彼は気にしなかった。
だが、それは「見逃されていた」のではない。単に、幕府の優先順位が低かっただけだ。
文化4年(1807年)、幕府はついにその“放任”を終わらせる。
蝦夷地の全域を直轄領にし、松前藩を一時解体。
そして道廣には、永蟄居の命。
それは、単なる遊び人の処罰ではなかった。
「国家にとって危険なビジネスモデルを野放しにできない」──その宣告だったのだ。
松前道廣の“金”は、蝦夷の闇から生まれた。
そして、その闇こそが、松前藩の矛盾と限界を象徴していた。
快楽を支えた金が、やがて自らを焼く油になる──そんな人間の縮図が、ここにはあった。
江戸の自由と文化の奔流──蔦重の時代に松前道廣が投げかけた影
『べらぼう』の舞台、18世紀末の江戸。
狂歌に黄表紙、戯作に芝居──町人文化が最も“自由”だった時代。
その奔流のなかで、ひときわ異質な存在感を放ったのが、蝦夷地からやってきた暴君・松前道廣だった。
自由の都に、封建の影が差す。それは文化と権力の衝突だった。
狂歌、黄表紙、町人文化と異界・蝦夷地の対比
江戸の町人たちは、今でいう「推し活」に夢中だった。
山東京伝の黄表紙を買い漁り、狂歌の会に集い、書き損じの反故紙をネタに笑った。
文化が“支配されていなかった”時代。だからこそ面白かった。
そこに突如、異界のような存在が登場する──蝦夷地の藩主、松前道廣。
アイヌを搾取し、領民を顧みず、吉原に金を垂れ流す。
江戸の町人たちが、言葉と筆で自分の表現を拡張していたとき、道廣はそれを「遊興」で踏みにじっていた。
彼の存在は、江戸文化の“裏返し”だった。
だからこそ、ドラマ『べらぼう』で道廣が登場することで、江戸の自由がより際立つ。
「自由」を知るために、「不自由」の象徴が必要だった。
それを体現したのが、えなりかずき演じる松前道廣なのだ。
山東京伝、恋川春町らが描いた“異世界”としての北方
『べらぼう』第21回には、黄表紙作家たちの“蝦夷地ネタ”が登場する。
たとえば──
- 恋川春町の『悦贔屓蝦夷押領』
- 山東京伝の『御存商売物』
これらはただの笑い話ではない。
蝦夷地を“架空の異世界”に見立て、強欲や支配、滑稽さを風刺した文学だった。
“奥蝦夷女王”が雲に乗って昆布を運ぶ。
“歌舞伎の大見得を切る鯛の味噌ず”が登場する。
つまり、蝦夷=想像の世界=政治批判の道具という構図が成立していた。
この中に、松前道廣というリアルな存在を放り込むことで、ドラマは驚くべき効果を得る。
想像と現実が繋がり、物語に“芯”が通る。
笑いと風刺の裏に、支配された現実の重さがにじみ出るのだ。
『べらぼう』の世界は、自由と不自由がせめぎ合っている。
蔦重ら文化人の躍動の裏で、松前道廣という“時代のノイズ”がその世界を乱している。
だが、乱されて初めて、文化の輪郭は浮かび上がる。
狂歌の軽やかさに、蝦夷の重苦しさがぶつかって、物語は深くなる。
その対比こそが、この回の構造美だった。
えなりかずき×松前道廣の化学反応が大河に与えた意味とは
視聴者の頭の中には、えなりかずき=「常識人」「いい人」のイメージがこびりついている。
それを真っ向からぶち壊したのが、今回のキャスティングだった。
“暴君”を演じさせるなんて、狂気か、それとも計算か。
結論から言えば──これ以上ないほどに成功した賭けだった。
視聴者の固定観念を裏切るキャスティングの挑戦
「えなりくんが、そんな悪いことするわけないじゃん」
そう思わせておいて、女郎を身請けし、鉄砲を構え、部下を脅す。
ここにあるのは、「裏切りの演出」ではなく「感情の逆走」だ。
善人の仮面が一枚ずつ剥がれ、裏から暴君の顔が覗く。
この視覚的・感情的ギャップが、視聴者の心を鷲掴みにする。
そして、“人は見かけによらない”という古典的な真理を、最も現代的な形で突きつける。
このキャスティングの妙は、役の説得力ではなく、視聴者の「期待」と「違和感」の交差点に仕込まれていた。
それを理解していたからこそ、制作陣はえなりかずきに賭けたのだ。
“いい人”が“暴君”を演じる時、物語は深くなる
「悪そうな人が悪いことをする」のは、ただの再現。
でも「いい人が悪いことをする」とき、そこには“物語”が生まれる。
葛藤、二面性、誤解、暴走──人間の“揺れ”が発生する。
えなりかずきは、その“揺れ”を演じることができる稀有な存在だ。
なぜなら、彼には“国民的な信頼”という前提があるから。
その信頼を壊す瞬間、ドラマは次の段階へ進む。
善悪の境界が曖昧になる時、視聴者は自分の感情を問われる。
「なぜ、自分はこの男に安心していたのか?」
そこには、「人間を見る目」を試すような不気味なリアリティがある。
『べらぼう』という作品の本質は、“絢爛たる文化”ではなく、“人間の裏と表”を炙り出すことだったのかもしれない。
そして、それを最も明確に体現したのが、松前道廣という役だった。
えなりかずきが演じたからこそ、暴君はただの“悪役”では終わらなかった。
人が壊れるプロセス、人が権力に溺れる瞬間、そして人の顔が変わる恐ろしさ。
それを見届けた視聴者の中に、何かが確実に残った。
それこそが、大河が本気で仕掛けた「べらぼう」な問いかけだった。
“暴君”の中にこぼれた人間味――道廣という一人の“こども”
松前道廣を見ていて、時折ふと、こんな感情がよぎる。
「この人、ちゃんと大人になれなかったんじゃないか」って。
江戸の町で文化人たちが狂歌を詠み、言葉を磨き、自由を遊んでいた時代。
同じ時代に、北の果てでひとり、権力という名の“おもちゃ”で遊んでいた藩主がいた。
鉄砲を笑いながら構える姿も、吉原で女郎を身請けして得意げな姿も、
どこか、“自分の心を持て余してるこども”に見えた。
感情の扱い方を、誰にも教わらなかった
12歳で藩主。重すぎる家督、北の最前線、幕府のプレッシャー。
だれも、彼に「不安になっていい」とは言ってくれなかったはず。
だから感情が育たない。
怒りはすぐ爆発し、寂しさは酒と遊びで消そうとする。
共感や対話という手段を持たない子どもは、やがて“支配”を覚える。
それが一番、手っ取り早くて、傷つかなくて済むから。
“哀しみ”が憎しみにすり替わるとき
『べらぼう』では、えなり演じる道廣に“反省”も“悔い”も見えない。
でも、その目の奥には、「わかってほしい」という衝動が時折のぞく。
笑っているのに、なぜか苦しそう。
権力を振るうその手が、どこか空をつかもうとしている。
たぶん彼は、ずっと孤独だった。
愛される術も、信じる術も、教わらなかった。
だから憎しみで人を動かそうとした。哀しみが、攻撃に変わってしまった。
道廣の中にあるのは、「暴君」という仮面を被った、幼いままの魂かもしれない。
そう思うと、この物語が少しだけ、切なくなる。
人はみな、自分の居場所を探していた。
江戸の町人も、蔦重も、山東京伝も。そして、松前道廣も。
ただ、道廣はそれを探す方法を間違えた。
でも間違えたって、生きていた。その事実が、すべてだ。
べらぼう・松前道廣・えなりかずきの交差点──歴史×演技×構造のまとめ
“暴君”と呼ばれた松前道廣。
“いい人”の象徴だったえなりかずき。
その二つが『べらぼう』という歴史と文化の奔流の中で交差した時、ただの人物描写ではない「歴史装置」が生まれた。
ここでは、改めてその意味を整理して終えたい。
松前道廣はただの「悪役」ではない
確かに、道廣の振る舞いはひどい。
放蕩、搾取、暴力、そして永蟄居という末路。
だがその内面には、「責任を背負わされたこども」「感情を持て余した統治者」の姿があった。
“悪役”という言葉では切り捨てられない、人間の未成熟さと孤独がそこにはあった。
そしてえなりかずきは、その“矛盾”を正面から演じきった。
視聴者が抱く「裏切られた感情」こそが、この役の本質だ。
人は外見では測れない。人は“過去”でつくられている。
そのメッセージが、観る者の感情に刺さった。
交易、支配、文化…蝦夷の地が照らす日本史の盲点
松前道廣というキャラクターは、“人物”であると同時に、“構造の象徴”だった。
石高ゼロの藩、交易国家、アイヌ支配、場所請負制度、そして密貿易。
それは、教科書に書かれない「もう一つの日本史」だった。
『べらぼう』が道廣を描いたことで、蝦夷の地が歴史の主役に引き上げられた。
都市文化と周縁、言葉の自由と沈黙の支配──
その対比が、視聴者の歴史観に「問い」を投げた。
問いは答えを要求しない。ただ、見つめ直すことを促す。
それこそが、この物語が届けたかった本質だろう。
歴史は、記録ではない。
記憶されるためには、感情に刻まれなければならない。
松前道廣は、その“記憶される悪役”として、見事に爪痕を残した。
そしてその役を背負ったえなりかずきは、俳優としての進化と覚悟を、誰よりも静かに証明してみせた。
べらぼうに、見事だった。
- 松前道廣は蝦夷地を支配した松前藩の第8代藩主
- 遊興と暴政により幕府から永蟄居を命じられた
- えなりかずきが“暴君”役に挑戦し話題に
- 石高ゼロの松前藩は交易によって成立していた
- アイヌ交易や場所請負に依存する不安定な統治構造
- 抜け荷や密貿易が藩財政と道廣の豪遊を支えた可能性
- 江戸の町人文化と蝦夷の支配構造の対比が描かれる
- 道廣は悪役でありながら“成長しきれぬ子ども”の姿も
- 俳優えなりの“裏切り”演技が作品に深みを与えた
- 『べらぼう』は歴史の盲点に光を当てた意欲作

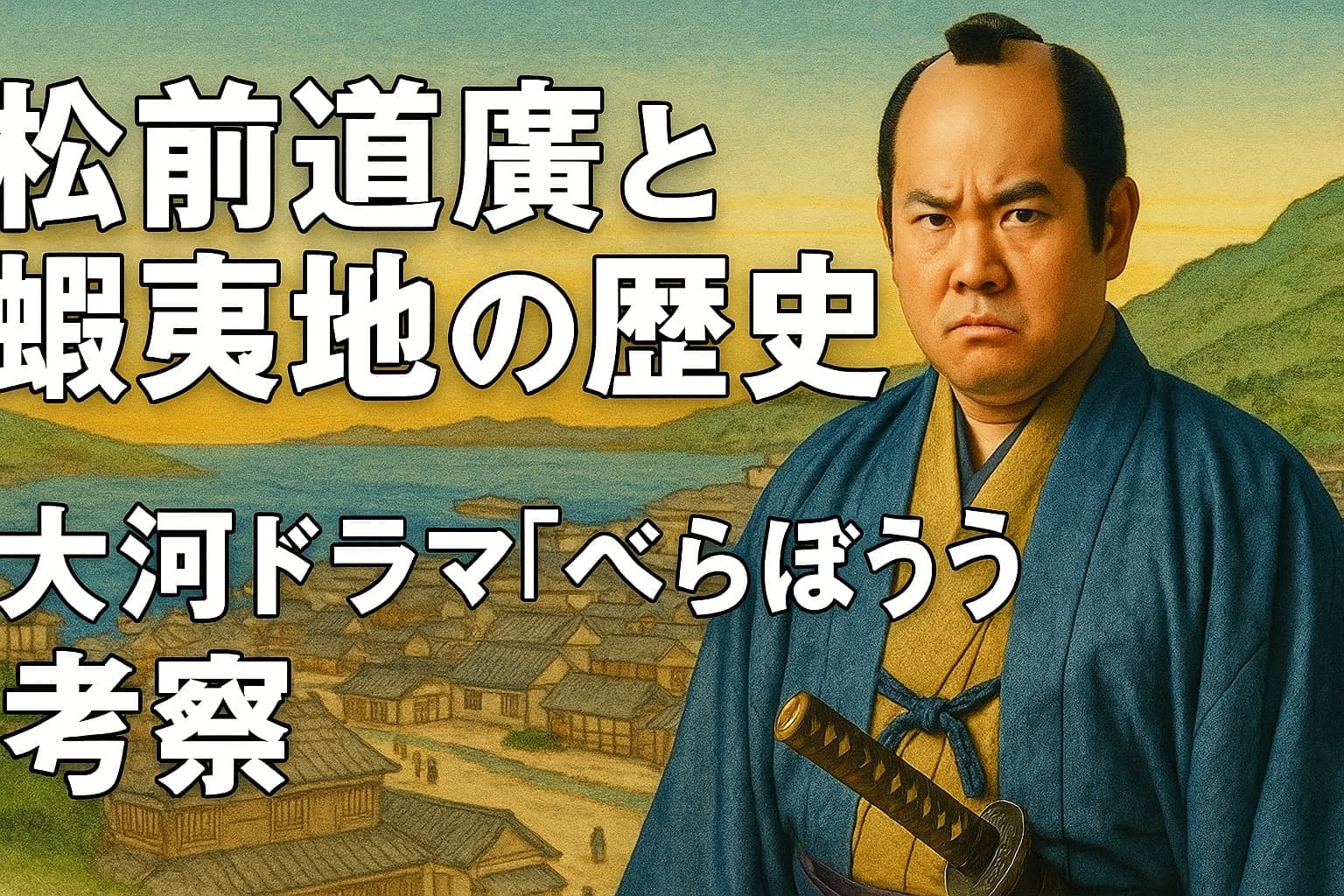



コメント