「結婚するかどうか」ではない。誰のために生きるのか──それが、この第7話の本当の問いだ。
ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』第7話では、勝男と鮎美、それぞれが「親」との関係に向き合い、自分の人生を“誰が決めるのか”というテーマが強烈に浮かび上がる。
この記事では、第7話で描かれた家族との確執、誤解、沈黙の痛み、そしてそこから絞り出される一言一言を丁寧に読み解きながら、視聴者の心に残った“選択”というテーマを深掘りしていく。
- 家族の中にある沈黙とすれ違いの正体
- 勝男と鮎美が選んだ“自分の人生”の意味
- 性別役割や親の期待からの脱出方法
「自分の人生は自分で決める」──鮎美がたどり着いた答え
「親のために生きる人生」と、「自分のために生きる人生」。
そのどちらかを選ばなければいけない瞬間が、人にはある。
第7話で描かれたのは、まさにその「岐路」に立つ鮎美の姿だった。
母の呪縛を断ち切った鮎美の一言
「私、自分の人生、自分で決めたい」──。
この一言が、第7話最大の“解放”だったと思う。
物語の終盤、鮎美はついに母親に対して、これまで一度も言葉にできなかった本音を口にする。
「私はお母さんの自慢の娘にはなれないけど、それでも自分で選んで生きていきたい」。
このセリフは、単なる反抗ではない。
母の期待と押しつけに応えてきた自分を終わらせるための“宣言”だ。
あの瞬間、彼女ははじめて「母に見せたい自分」ではなく、「本当の自分」を母の前に差し出した。
それがどんなに怖いことか。
どんなに傷つくかわからないことか。
それでも言わなければ、一生、誰かの物語の“脇役”で終わってしまう。
“いい子”という檻を破る強さ
「いい子でいよう」という感覚は、ある意味“生きるためのスキル”だ。
空気を読み、期待に応え、波風を立てないように振る舞う。
だがそれは、大人になるにつれて、自分の首を絞める「檻」に変わっていく。
鮎美は幼いころから「母をがっかりさせないこと」が人生の軸になっていた。
だがその“忠誠心”の正体は、母が父に抱えていた怒りや不満、絶望といった感情を、子どもなりに察して背負った結果なのだ。
つまり、鮎美が「いい子」を演じてきたのは、母を守るためだった。
皮肉なことに、それは母の「理想の娘」という役割に、自分を押し込める結果となった。
だが、顔合わせでの混乱、勝男との対話、姉との距離、そして何よりも「自分がどう生きたいのか」を突きつけられた今、
鮎美はようやく、その檻の鍵を、自分の手で開けた。
「親のために結婚する」「親のために別れない」「親の顔を立てる」──そんな思考のすべてを、一度リセットする。
彼女が選んだのは、「親の望む幸せ」ではなく、“自分の納得できる人生”だった。
これは、わがままでも反抗でもない。
大人として、自分の足で立つための第一歩だ。
母親が廊下で泣き崩れるその横で、姉がぽつりとつぶやく。
「鮎美が自分の気持ちを言うの、初めて聞いたわ」
その言葉が、すべてを物語っていた。
この回は、鮎美が“自分の声”を取り戻す物語だった。
そしてその声は、誰のためでもない、「自分の人生」を歩むための声だ。
勝男が向き合えなかった「父」という壁
人は誰でも、親の前では子どもに戻ってしまう。
大人になった今でも、父の前で言いたいことが言えない──それは、勝男だけの話ではない。
しかし『じゃあ、あんたが作ってみろよ』第7話では、その“逃げ”がついに限界を迎える。
無言の父と、フリーズドライ味噌汁の示す距離
父という存在は、不器用で、厳しくて、言葉が足りない。
それは、多くの昭和的家父長像の典型でもある。
勝男の父もまた、息子に失望しながらも、言葉ではなく「態度」でそれを示す。
「もうお前には何も期待しちょらん」
そう言い放った直後、台所では母が無言で食器を洗っている。
勝男はそこでフリーズドライの味噌汁を見つける。
それは象徴的だった。
「あれだけ手料理に口出ししてた親父が、こんなインスタント味噌汁を受け入れてる」
つまりそれは、父もまた、静かに“変わろうとしている”かもしれないというサインだったのだ。
だが勝男は、その変化に気づきながらも、正面から受け止める勇気を持てなかった。
親に逆らうことも、話し合うこともできず、ただ逃げる。
だから彼は、嘘をついてまで場を取り繕おうとした。
なぜ勝男は嘘で取り繕ってしまうのか?
「鮎美とは結婚しない」「実はもう別れてる」──。
それは事実でもあり、嘘でもある。
本当の問題は、「別れたこと」ではなく、「それをどう受け止めるか」なのに、勝男はその核心を避けてしまう。
彼が父に向かって発する言葉のすべてが、どこか他人行儀で、遠回しだ。
一方、父はといえば「黙って何も言わない」という手法で怒りを伝える。
親子なのに、こんなにも言葉が足りない。
この構図は、ただの家庭内のすれ違いではない。
「男とはこうあるべき」「弱音を吐かないのが男だ」という、古い価値観に縛られた父と、それに無意識に影響されてしまった勝男との“連鎖”なのだ。
勝男が泣くのを我慢する癖、口下手な理由、言いたいことが飲み込まれていく瞬間──。
そのすべてが、父を見て育った「無言の学習」の結果だった。
勝男の「ダメさ」には、根拠がある。
彼はずっと、「父のようにならないように」と思いながら、結果的に“父のコピー”になってしまっていた。
「勝男は勝男やろ?」
義姉のこの一言が、勝男の中で何かを揺らす。
それでも、まだ彼は父と向き合えない。
なぜなら、彼にとって“父と向き合うこと”は、自分の弱さをさらけ出すことだからだ。
この第7話では、鮎美が自分の母と“対決”を果たしたのに対し、勝男はまだ“途中”にいる。
向き合う覚悟のない者には、何も変えられない。
そのことを、勝男自身が一番わかっている。
だからこそ、彼の沈黙は視聴者の胸に、妙な“痛み”として残る。
家族の中にある性別バイアスとその刷り込み
「男のくせに怖いの?」「女の子なのにそんなことするの?」
何気ない一言に、人は知らず知らずのうちに傷ついている。
第7話では、“キャッチボール”というささやかな遊びが、性別にまつわる固定観念を揺さぶる装置として描かれた。
キャッチボールを通して描かれる“女らしさ”への違和感
公園で勝男が兄家族と再会するシーン。
兄の娘・真鳥がキャッチボールを楽しむ姿に対し、「お人形遊びのほうが好きじゃないの?」と語る親たちの反応。
それに対して、兄はハッキリと否定する。
「真鳥は真鳥のまま、好きなもんを選ばせてやりたい」
この言葉は、勝男にとってもひとつの“答え”だった。
自分がこれまで生きてきた世界──そこでは「男だから」「女だから」という分類が無意識のうちに作用し、言葉や行動の選択肢を狭めてきた。
それは鮎美にも通じる。
彼女は、母親から「いい娘」としての在り方を強いられ、「誰かに選ばれる」ために生きるよう仕向けられてきた。
だが、それは本当に“幸せ”と呼べる生き方なのか。
このドラマは、そんな問いを静かに、でも確かに投げかけてくる。
「好きなことを選ぶ自由」が奪われてきた背景
「男だから泣くな」「女なんだから目立つな」──。
こうした価値観は、口に出さずとも、家庭の中で日常的に“刷り込まれて”いく。
勝男が父親に言いたいことを言えないのも、
鮎美が「自分で決めたい」と口にするまで時間がかかったのも、
根っこにあるのは、性別によって期待される“役割”に縛られてきた過去だ。
とくに家庭という“最も身近な社会”では、親の価値観がそのまま子に流れ込む。
勝男の父が「男はこうあるべき」を無言で押し付け、
鮎美の母が「女の子はこう生きなさい」と口に出す。
この連鎖を、誰かがどこかで止めない限り、人は自由になれない。
兄の「真鳥は真鳥でいい」という言葉は、その連鎖を断ち切る“新しい父親像”だった。
そして、勝男がその言葉を聞いて何かに気づいたように見えたのも、
この回の中で最も希望の光が差し込んだ瞬間だった。
ドラマは、ジェンダーの問題を声高に叫ぶのではなく、
ひとつの家庭のやり取りの中で、静かにその問題を突きつけてくる。
遊園地、キャッチボール、弁当、そして味噌汁。
日常の中にある小さな会話にこそ、性別の“刷り込み”が潜んでいる。
そして、もしあなたが「本当にそれ、自分で選んだ?」とふと感じたなら──。
それはもう、誰かの価値観ではなく“自分の人生”を始める準備ができた証かもしれない。
「顔合わせ」が映した両家の歪みと希望の欠片
「顔合わせ」とは、単なる形式的な儀式ではない。
それは、家族同士が“どう関わって生きてきたか”、その背景すべてが浮き彫りになる“鏡”だ。
第7話の顔合わせシーンは、まさにその鏡が割れていくような瞬間だった。
仲の悪い鮎美一家、沈黙の多い勝男一家
両家の家族がホテルの宴会場に集まる。
緊張感、形式、探り合い。
その中に、「家族」の本質がにじみ出る。
まず、鮎美側の家族。
釣りで遅れてくる父、それを嫌味のように暴露する姉。
表面上は礼儀を取り繕っていても、家庭内の“対話不全”はすぐに露呈する。
母親がすぐに“家柄”に話を持ち込み、勝男のことを見下した態度を取る。
その背景には、自分が満たされなかった人生を、娘の結婚で取り返そうとする歪んだ感情が透けて見える。
いわば「鮎美を通じた代理戦争」。
その土俵に鮎美を立たせておきながら、彼女の意思は完全に無視されていた。
一方の勝男一家。
こちらは逆に、“言わないことで秩序を保つ家族”だった。
話題は避け、感情は隠し、会話は控えめ。
とくに勝男の父は、何かにつけて話を遮り、息子に話す隙を与えない。
母は気を遣いすぎて、誰の味方なのか分からない状態。
勝男は「俺から切り出すから」と言ったものの、結局、核心には触れられなかった。
こうして“本当に話すべきこと”は、宙ぶらりんのまま空気の中に消えていった。
あの場で“本当の気持ち”を言えなかった意味
あの顔合わせで、誰か一人でも「素のままの気持ち」を言葉にしていたら──。
結果は変わっただろうか?
おそらく、変わらなかった。
なぜなら、この家族たちは“本音を言わないこと”を前提に生きてきたからだ。
だからこそ、顔合わせという「異物」が持ち込まれたことで、かえって各々の歪みが露わになった。
誰もが何かを言いかけて、言わずに飲み込む。
見ている側としては、歯がゆくて、イライラして、もどかしい。
だが、そこには現実のリアリティがある。
「言えば壊れるかもしれない」からこそ、みんな黙ってしまう。
けれど、壊れるのを恐れて黙っていても、何も守れない。
むしろ、その沈黙が“関係を破壊する”のだ。
皮肉なことに、顔合わせで“ちゃんと話せなかった”からこそ、
鮎美と勝男はそれぞれ「自分の言葉で語る」ことの大切さに気づく。
別れた後の“再決断”に至るには、あの崩壊が必要だった。
本当の顔合わせは、他人の前じゃなく、自分自身との対話の中にある。
それをやっと理解できるまでに、二人は遠回りした。
だけどその遠回りこそが、人を大人にする。
それでも人は、関係を“終わらせる”ことで始まる
「終わり」が訪れるとき、人は初めて“本音”に向き合える。
関係を壊さないように守ってきた嘘、曖昧な言葉、押し殺した感情。
それらすべてが、別れという現実の前で、ようやく剥がれ落ちていく。
「別れる」ことでようやく出せた本音
夕食の席で、勝男がようやく父母に語った言葉は、驚くほど静かだった。
「鮎美とは結婚しない。もう別れてる」
この告白に、感情的な高ぶりはなかった。
だが、それが“本物”だった。
結婚を前提に話を進め、同棲までしていた相手と別れた。
本当はもっと早く言うべきだったことを、ようやく口にした。
父親は「平気な顔しちょるな」と冷たく言い放つ。
勝男は「平気じゃない」と答えるが、その声には悲しみと覚悟が滲んでいた。
この会話こそ、勝男にとっての“決別”だった。
父との関係でも、鮎美との関係でもなく、「自分の中にある弱さとの決別」だ。
あえて口に出すことで、彼はようやく前に進める。
「終わらせる」ことでしか、見えない景色がある。
未練と希望の同居──勝男と鮎美のすれ違い
そしてラスト。
勝男が帰宅すると、鍵が空いていて、部屋の中に光が灯っている。
スリッパが用意され、あたたかさだけが残る室内。
だが、鮎美はもうそこにはいない。
このシーンは、未練と再出発が同時に描かれた、静かで美しいエンディングだった。
彼女は自分で決断し、出て行った。
だが、部屋に残された小さな気遣いは、「あなたを憎んでいない」「終わらせるけど感謝している」という無言のメッセージでもある。
一方の勝男は、まだ“取り残された者”として立ち尽くす。
言葉では決着をつけたはずなのに、心はまだ追いついていない。
このギャップこそが、「終わりに伴う本当の痛み」なのだろう。
人は、別れを通してようやく「自分が何を失ったのか」に気づく。
それは、後悔ではない。
自分自身をようやく客観視できる状態に、やっと立てたという証だ。
そしてこのドラマが優れているのは、「別れた=終わり」ではなく、
別れを“始まり”として描いていること。
勝男は変われるのか。
鮎美は、これから何を選ぶのか。
関係を一度リセットすることでしか築けない、新しい人生がある。
それを視聴者にそっと差し出してくれた、そんな第7話だった。
勝男の「泣けなさ」が教えてくれた、“感情を持つ男”の不自由さ
感情って、誰もが自由に表現できるものだと思ってた。
でも実は、「男なんだから」「大人なんだから」っていう空気の中で、泣くことすら許されない人たちがいる。
この第7話を見ていて、勝男ってその典型なんじゃないかと思った。
口数も少なくて、何かを我慢してるような目。
でも、ちゃんと見てるとわかる。本当は感情であふれてるのに、出し方がわからないだけなんだ。
ここでは、そんな「泣けない男・勝男」の奥にある“不自由さ”に、少し踏み込んでみたい。
泣くことも、怒ることも、笑うことすら“選べない”男たち
このドラマ、実は最初からずっと「勝男が泣けない男」だってことが描かれてる。
感情がゼロなわけじゃない。むしろ泣きそうなシーンは山ほどある。
けど、決して涙をこぼさない。ぐっと飲み込む。
それってつまり、「男は泣くな」の呪いを、勝男自身が誰よりも深く背負ってるってことなんだと思う。
たとえば遊園地の絶叫コースター。勝男が本気で怖がってるのに、周りの子どもに「男のくせに」と言われる。
あの瞬間、笑いに包まれてるけど、「男は強くあれ」っていう社会の空気が、見えない鎖のように首を絞めてるのがよく分かる。
子どもの頃から「泣くな」「情けない」と言われ続けて育った男たちって、
泣くタイミングすら分からなくなる。
怒ることも、甘えることも、「男らしさ」フィルターを通して許される範囲でしか表現できない。
それって、ある意味“感情の牢屋”に閉じ込められてる状態だと思う。
勝男が泣けるようになる日は、来るのか?
この第7話でも、勝男はたぶん何度も泣きたかった。
鮎美に「もう自分で選ぶ」と言われたとき。
父に「もういい」と突き放されたとき。
自分の部屋に戻って、明かりのついた室内を見たとき。
でも彼は、ひとつも泣けなかった。
大人の男が泣くって、いまだにどこかで“許されないこと”のように思われてる。
でもほんとは、人間ってもっと柔らかくていい。
強くなれない日があっていいし、誰かに「今日つらかった」と言えたっていい。
勝男が「泣くことを選べる男」になる日が来たら、
それはきっと、彼が“他人の期待”ではなく、“自分の感情”に従って生きられるようになった証なんじゃないかと思う。
それってつまり、この物語の本質そのもの。
自分の人生を、自分で作ってみろよ──って話だ。
「私は私でいいやん」と言える人が、家族を救っていく
このドラマ、家族みんながめんどくさい。
傷つけあって、黙って、すれ違って、それぞれが不器用すぎる。
そんななかで、ぽんっと空気を変える人がいた。
それが、勝男の兄の奥さん──義姉だ。
今回の第7話、何気ないセリフで彼女が一番「大人」だったように感じた。
“男のくせに怖いの?”に対する、たった一言の革命
遊園地で、絶叫マシンから降りた勝男に向かって、姪っ子が言った一言。
「男のくせに怖いの?」
ありがち。だけど、この手のセリフは小さなチクリとした痛みを伴う。
それに対して義姉が言ったのが、これ。
「男でも女でも、怖いものは怖い」
あの言葉には、社会の無言のバイアスをふわっとほぐす力があった。
押しつけるでもなく、責めるでもなく。
ただ、誰かを守るように。
もしかしたら、あの場で勝男が一番「自分を否定されなかった瞬間」だったかもしれない。
「おいしいよ」って言ってもらえる安心感
義姉がつくったお弁当を食べながら、勝男がぽろっと言う。
「俺、親父が母さんの料理に文句言うの、ほんと嫌だった」
この言葉に対して、義姉は静かに笑いながら返す。
「私は勝男くんが食べてくれて、うれしいよ?」
このシーン、見逃しがちだけど、とても大きな意味を持ってた。
料理を「ダメ出し」する文化に育った勝男が、はじめて「喜ばれる」という経験をした。
「完璧じゃなくても、誰かの役に立てる」っていう感覚。
それは、勝男にとって自己肯定感の“再インストール”みたいなものだったはず。
“中和剤”として存在する人が、家族を救っていく
義姉って、勝男の家の中で唯一、怒らず、責めず、否定しない人だった。
強く主張しないけど、静かに空気を変える。
たぶんこの人がいなかったら、兄ももっと“父のコピー”になってたかもしれない。
彼女の存在は、家庭内の「当たり前」に対して、さりげなく「それってほんとに必要?」と問いかける役割だった。
ドラマの中で直接的に語られないけど、ああいう人がいるから、家族って完全に壊れずにすんでるんだと思う。
「私は私でいいやん」と自然に言える人。
その空気は、まわりにも伝染する。
この第7話、鮎美も勝男も“自分を選ぶ”決断をした。
それができたのは、きっと誰かがそっと「選んでいいんだよ」と言ってくれてたからだ。
声高じゃなく、やさしく、空気みたいに。
義姉は、家族を「引っ張る人」ではない。
けど確実に、家族を“腐らせない人”だった。
それが、どれほど貴重な存在か。
たぶん勝男は、これから気づくんだと思う。
『じゃあ、あんたが作ってみろよ 第7話』から見える“家族と向き合うということ”まとめ
第7話で描かれたのは、結婚や別れといった表面的な出来事ではない。
もっと奥にある、家族という“最も近くて遠い存在”とどう向き合うかというテーマだった。
そこには誰もが無関係ではいられない、「親と子の関係」「沈黙の重さ」「選ぶことの自由」が詰まっていた。
家族を壊すのは裏切りじゃない、「沈黙」だ
家族が壊れる原因は、実は浮気や借金といった“大事件”ではない。
本当の原因は、日々積み重なる“言わなかったこと”の蓄積だ。
「言っても無駄だと思った」「角が立つからやめた」「気まずくなるのが嫌だった」
そうやって、感情はいつの間にか“沈黙”に変わっていく。
勝男が父に対して本音を言えなかったのも、鮎美が母に長年逆らえなかったのも、すべて「言わずにやり過ごす」関係が習慣化していたから。
だが、それはやがて関係の“酸素”を奪っていく。
裏切りよりも怖いのは、「気持ちが見えなくなること」なのだ。
だからこそこのドラマは、優しく、でも強くこう語りかけてくる。
「壊れたくないなら、沈黙を選ぶな」と。
言葉を交わす勇気が、家族の未来を変える
勝男がついに父に「別れていた」と打ち明けた瞬間。
鮎美が母に「私は自分で選びたい」と言い切った瞬間。
それは、傷つく覚悟を持った者だけが踏み出せる“本当の会話”だった。
言葉を交わすというのは、簡単なことではない。
特に家族という、長い歴史と感情の地層が積もった関係の中では、
一言が爆発を引き起こすこともあるし、沈黙より苦しいこともある。
けれど、それでも言葉を差し出すしかない。
本音がぶつかって初めて、家族は“変わる”可能性を持つ。
『じゃあ、あんたが作ってみろよ』第7話は、その希望を丁寧に描いた。
すれ違い、誤解、無理解。
それでも、ほんの少しだけ言葉を交わすことで、人は自分の人生を取り戻せる。
このドラマが描く家族は、不完全だ。
でも、“不完全でもいい”と伝えてくれるその優しさこそが、今を生きる私たちに必要なものなのかもしれない。
- 家族の沈黙が関係を壊していく過程
- 勝男と鮎美が自分の言葉を取り戻す物語
- 性別役割の呪縛とその連鎖を断ち切る選択
- 「顔合わせ」が露呈した両家の歪み
- 別れによって浮かび上がる本当の感情
- 泣けない男・勝男の内面と感情の牢屋
- 義姉の存在が家族の空気を静かに変えていた
- 「自分の人生は自分で決める」ことの重み

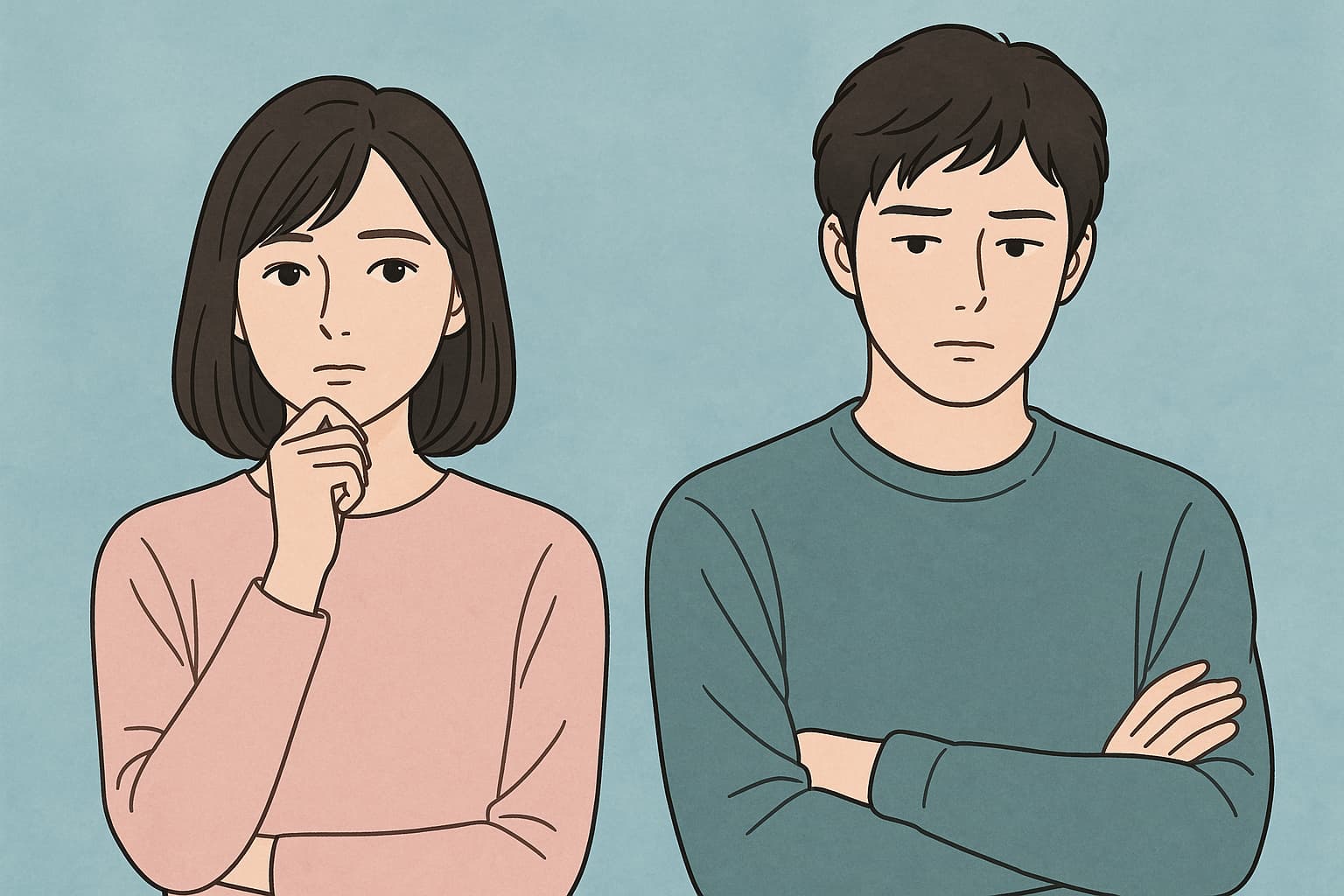



コメント