「科学は嘘をつかない」──そう信じていた男の前に、その信念を試す“知的な狂気”が立ちはだかる。
第10話で『最後の鑑定人』は、新たな局面へと突入した。
疑われた者、仕組まれた罠、揺らぐ記憶──すべてが「科学」を使って描かれた“冤罪のシナリオ”だった。
本記事では、公式あらすじ・キャスト情報・SNSでの反応をもとに、第10話で浮かび上がった“構造”と“感情”、そしてこの先に待つ“核心”を読み解いていく。
- 第10話で浮かび上がる真犯人の正体と動機
- 科学を使った冤罪とチームの信頼関係の描写
- 尾藤の記憶喪失に潜む心理的な意味と再生の兆し
「最後の鑑定人」第10話、浮かび上がる真犯人──科学が暴いた“復讐の設計図”
第10話でついに姿を現した“黒幕”は、予想を裏切る存在だった。
公式発表でも言及された通り、今回の事件は単なる放火ではなく、科学的知識を武器にした緻密な“冤罪工作”だった。
そしてその狙いは、尾藤宏香を潰すこと──いや、科警研という組織全体に対する“復讐”だったのではないか。
耳紋が示した意外な犯人──元科警研・下垣満行の正体
今回、土門誠(藤木直人)が突き止めた決定的な証拠は、“耳紋”という極めて科学的な痕跡だった。
防犯カメラに映ったキャップ姿の男。その人物の耳の形状から、過去のデータと照合し、一致したのは元・科警研職員の下垣満行(中島多朗)──
彼は数年前、研究費の不正使用で懲戒免職となり、以来、消息を絶っていた。
その下垣がなぜ、今になって戻ってきたのか?
科学と信頼の“砦”を、内側から壊すためだった。
そしてその破壊は、偶然でも衝動でもなく、“設計された破滅”だったのである。
研究費不正・論文改ざん・データ改竄…犯人の“動機”は科学への復讐だった
下垣が仕掛けた“科学トラップ”はあまりにも精密で、視聴者の想像を遥かに超える。
- 尾藤のロッカーにアルミニウム粉末を仕込み
- 部長室に盗聴器を設置
- テルミット反応を誘発する装置を設置
- 論文データをサーバーから改ざん
これらすべてが、「尾藤が犯人に見える構図」として成り立っていた。
だがその真の動機は──尾藤個人への恨みではない。
自らを切り捨てた“科学の組織”そのものへの逆襲だった。
科学によってキャリアを失い、人生を壊された男が、科学を逆手に取り、かつての同僚たちを内部から崩壊させようとした──
その執念が、この“第10話の衝撃”の核だった。
「科学は嘘をつかない」の裏切り──土門が立ち向かったもの
土門がこれまで口にしてきた信念──「科学は嘘をつかない」。
その言葉は、今話で大きく試されることになる。
下垣の手法は、科学の正確さを逆手に取って、“偽の真実”を作り出すものだった。
証拠はすべて正しい。だが、その“正しさ”が嘘を語るよう仕組まれていた。
土門は、科学を信じながらも、「人を疑わないこと」「信じること」を選んだ。
そしてその選択が、最終的に“真犯人”の存在を導き出す鍵となった。
だが、事件はまだ終わっていない。
下垣の部屋に残されていたのは、遺体と共にあった一枚のメモ──「土門へ H」。
そして、その後にかかってきた“あの電話”。
「君を苦しめたい。ただそれだけだ。──ゲームは、これからだ」
第10話で明かされたのは、“幕引き”ではなく“第二幕の始まり”だった。
科学と嘘の物語は、次なる展開へと向かっていく。
尾藤宏香はなぜ狙われたのか?記憶喪失と冤罪の“リアルな地獄”
彼女は、なぜ狙われたのか? なぜ記憶を失い、罪を背負わされたのか?
『最後の鑑定人』第10話は、尾藤宏香(松雪泰子)という人物を軸に、“科学を信じた人間が陥る地獄”を描いている。
今回の放火事件──いや、もはや殺人未遂すら視野に入るような犯行は、すべて「尾藤を陥れるため」に設計されていた。
しかも、それは偶然や衝動ではなく、耳紋照合・化学反応・ハッキング──すべてを使いこなす“科学の亡霊”によって練り込まれていた。
アルミニウムの痕跡、盗聴器、テルミット反応…すべてが仕組まれていた
土門(藤木直人)たちが再調査で突き止めた事実の数々は、あまりに冷酷だった。
尾藤のロッカーからはテルミット反応に必要なアルミニウムの粉末が検出され、犯行に使われたスイッチは、部長室に仕掛けられた盗聴器によって遠隔操作が可能だった。
この時点で「状況証拠」は完全に尾藤を指していた。だが、その“完璧さ”こそが土門に違和感を抱かせた。
公式のあらすじ(TVer番組ページより)でも、「土門たちが再検証を進める中、ある映像から不審な人物の存在を発見する」という記述がある。
つまり、視聴者にも“伏線”として公開されていたこのヒント──“キャップ姿のID不一致の男”こそが、尾藤をハメた本当の犯人だった。
事件は個人的な怨恨ではなく、「科学を使ったフレーミング=偽装のテクノロジー犯罪」だったのだ。
尾藤が“記憶を無くした”理由──そこに科学的な違和感はなかったか
ここで忘れてはならないのが、尾藤が「事件の直後に記憶を失っていた」という設定だ。
これは単なる“ドラマ的な演出”に見えて、実はかなりの“違和感”を孕んでいる。
科学的に見れば、急性ストレスや薬物投与が原因で一時的な記憶障害を起こすことはある。
が、尾藤の記憶喪失は、あまりにも都合が良すぎた。
彼女は「自分が何をしていたか覚えていない」ことで反論の手段を失い、
さらに「科学に身を置く者」という立場が、“論理で武装された攻撃”に対して何一つ防御できなかった。
記憶がないことが、科学の“武器”となって彼女自身に突き刺さってくる──。
「何もしていない自分が、何を証明すればいいのか」
それはまるで、空白の履歴書を突きつけられたような絶望だったはずだ。
最終回前にして最大の崖っぷち、土門と尾藤の関係性が問い直される
そしてこの第10話は、単なる犯人探しの枠を超えて、「土門と尾藤の信頼関係」を試す物語でもあった。
刑事たちがガッツポーズを決めるほど「状況証拠で決まり」と言える中、
土門だけは、「君は何もしていない」と言い切り、彼女を見舞う。
科学の世界に生きながらも、土門は「人を信じるという、非科学的な判断」を選んだ。
「科学が壊した人間を、科学で救う」──その信念を背負って。
この信頼は、次回以降さらに揺さぶられる。
なぜなら、尾藤を救ったはずの“科学の力”が、再び土門自身を狙いはじめるからだ。
エピソードの最後、「H」と記されたメモ、そして電話口で語る謎の声──
「君を苦しめたい。ただそれだけだ」
この物語はまだ、終わっていない。
土門誠の“孤高”から“チーム”への進化──科学者に必要なものは何か
科学とは、事実を積み上げる行為だ。
そして、事実を突きつける行為でもある。
だが『最後の鑑定人』第10話で描かれたのは、その科学を扱う人間たちが、どうやって“他者”と関わっていくのかという物語だった。
バラバラだった鑑定チームが一つになる瞬間
かつての土門(藤木直人)は“孤高”だった。
自分のやり方に絶対的な自信を持ち、他人と交わることを避けていた。
だが、尾藤の疑惑、下垣の犯行、科警研の内なる闇に直面した第10話で、彼の立場に変化が現れる。
土門は一人で解決する道を捨て、仲間に“頼る”ことを選んだ。
ここで特筆すべきは、高倉柊子(白石麻衣)をはじめとする鑑定チームの面々──
- 相田直樹(迫田孝也):冷静な法的視点を持つ弁護士
- 都丸勇人(中沢元紀):デジタル分析の若きプロフェッショナル
- 嵐山信幸(栗原類):独自の観察眼で裏を読む空気読み職人
彼らは、土門の導きではなく、“自発的に”動き出した。
誰に命令されたわけでもなく、尾藤を信じ、土門の孤独に加勢した。
それは“チーム”という言葉の本当の意味を、物語に与える瞬間だった。
相田・都丸・嵐山…それぞれが“信じる力”を土門に返した
興味深いのは、今回の話で中心になったのが“科学”ではなく“関係性”だった点だ。
たとえば、相田の言葉。
「違法捜査があれば、法廷で詳らかにする」
これは法に基づいた正義であり、同時に土門の行動を“信頼している”という意思表示でもある。
都丸は、若き技術者としての意地を見せた。
尾藤が濡れ衣を着せられる一方で、下垣が残したデータの痕跡から“別の真実”を探り出そうとする。
嵐山は、一見飄々としながらも、チームの緊張を和らげ、必要な時に核心を突く。
“感情的な論理”を扱うのが彼の強みであり、科学にはできない部分を補っている。
彼らは皆、土門という男の“不器用な誠実さ”を知っている。
だからこそ、第10話ではそれぞれの方法で彼を支え、補い、時に導いた。
支配ではなく共鳴。
それが、科学を扱うチームの理想の姿なのだ。
「僕は君を救いたいんだ」──藤木直人が体現した“科学者のやさしさ”
第10話で、もっとも印象的だったセリフ。
「僕は君を…君を救いたいんだ」
これは尾藤に向けた言葉だが、同時に自分自身への宣言でもある。
科学は誰かを救えるのか?
それとも、科学は“嘘を暴く”だけの冷たい道具なのか?
土門はこの問いに、“感情”で答えた。
論理ではなく、覚悟だった。
だからこそ、彼の言葉には重みがある。
そしてそれは、演じる藤木直人の“静かな演技”によって、さらに説得力を帯びた。
視線、声のトーン、間の取り方。
すべてが、「この人は誰かを傷つけたくない」という思いを映していた。
科学は冷たいが、それを使う人間には“温度”がある。
土門というキャラクターは、“やさしさをまとった科学者”として、この物語を支えている。
孤高だった背中に、仲間たちの影が並んだ。
そして次回、彼らの“チームとしての強さ”が、さらなる試練に挑む。
“H”の意味と堀部圭亮の電話──終わらないゲームの幕開けか
第10話のラスト数分──それは、物語の“結末”ではなかった。
むしろそこには、新たなプレイヤーの登場と、さらなる“知的ゲーム”の始まりが潜んでいた。
尾藤を救ったはずの土門のもとに届いた一通のメモ、そして一本の電話。
すべての真相が明らかになったと誰もが思ったその瞬間、物語は急に“深度”を変えた。
メモに刻まれた「土門へ H」…犯人はまだ“観察”している
下垣満行が死亡していた部屋に残された、たった一枚の紙。
そこに記されていたのは、「土門へ H」の文字──。
この“イニシャル H”が、物語の構造を一気に書き換えた。
つまり、下垣は真犯人ではなかった。少なくとも、すべての“企み”の頂点にいたわけではない。
Hと名乗る人物がいて、土門に対して何かを「伝える権利」を持っている。
それは、言い換えれば「科学者・土門」を選んだ者がいるということだ。
爆破、放火、冤罪、データ改ざん──すべては“テスト”だったのか?
下垣は、もっと大きな計画の“駒”にすぎなかった可能性が濃厚となった。
ラストシーンの“電話の声”に込められた不気味なメッセージ
そして、最後にかかってきた一本の電話。
土門が受話器を取ると、聞こえてきたのは女性の声だった。
一瞬、知り合いのように思わせたその声は、やがて変わり、男の声へと転調する。
「科学は嘘をつかない…そんな幻想を、君はまだ信じているのか?」
この言葉は、“科学そのもの”をテーマとした本作の根幹を突き崩す問いかけだ。
語り手の声の主は、堀部圭亮。
この第10話で突如として“裏の黒幕”のように現れたこの男は、
登場人物でもなく、容疑者でもなく、証人でもなかった。
だが、すべてを“見ていた者”として、完全に次元の違う存在感を示してきた。
その声はまるで、神の視点だった。
プレイヤーを観察し、誘導し、そして試す──土門誠を。
第10話以降が本番?「科学は幻想だ」という問いが始まる
本作は、最初から「科学を信じるか」「人を信じるか」という対立構造を持っていた。
だが、第10話で“科学すら嘘をつく”という現実が突き付けられた今、物語の論点は「科学の限界」へと移行していく。
「科学は万能ではない」「誰かの意志によって捻じ曲げられる」
──そう語った“声”は、今後土門をどう追い詰めていくのか。
今回のエピソードは明らかに“前半の終章”であり、ここから後半が“本当の勝負”だ。
第10話までに張られてきた伏線たちは、すべて「人を救う科学」の物語だった。
だが、これから始まるのはきっと──
「科学が人を壊す」可能性との戦いなのだ。
土門の孤独は終わったが、闘いは終わらない。
次回、誰がHなのか──そして、その目的とは何か──
『最後の鑑定人』は、いよいよその核心へと歩を進める。
尾藤宏香が“記憶をなくした”本当の理由──忘れることでしか生きられなかったのかもしれない
第10話でようやく冤罪が晴れた尾藤宏香。
でも──それで終わりとは、どうしても思えなかった。
「記憶をなくした」という彼女の状態は、ただの物語上の装置じゃない。
むしろそこにこそ、このドラマが問いかけている“もう一つのテーマ”が潜んでいた気がする。
記憶喪失は“装置”じゃない、“逃避”だ
普通に考えれば、記憶をなくすって相当な衝撃があったからだろうとか、トラウマとか、そういうふうに説明できる。
でも尾藤のケースは違った。あまりに都合よく、あまりに静かに、“忘れていた”。
誰かに何かをされて消されたというよりも、自分で“閉じた”ような印象があった。
たぶん彼女は、もう覚えていたくなかったんじゃないか。
研究者としての自分、仲間との関係、自分の書いた論文が裏切りの材料になったこと。
覚えていれば、壊れる。 だから、忘れた。
そんな気がした。
過去を握りしめる科学者と、手放すしかなかった人間
この対比が鮮やかだったのは、やっぱり土門との関係。
土門は“過去に何があったか”を絶対に明らかにしようとする。科学とはそういう営みだから。
でも尾藤は、その“明らかにされること”に耐えられなかった。
科学は過去を照らすけど、その光にさらされる人間には、まぶしすぎる時もある。
「なぜ忘れたのか」は、問いじゃない。
「忘れることでしか、自分を守れなかったんだろうな」としか言えなかった。
それでも土門は言う。
「僕は君を…君を救いたいんだ」
忘れた人間を、過去に引き戻す言葉。
それはやさしさか、それとも残酷か。
たぶんこの物語は、“真実を明らかにすること”と“それでも生きていくこと”のバランスを問いかけてる。
そして尾藤は今、ようやく“記憶を戻す準備”が整ったのかもしれない。
誰かが「信じる」と言ってくれる世界でなら、思い出しても壊れないかもしれないから。
「最後の鑑定人」第10話の感想と評価まとめ:科学は人を救えるのか
第10話放送後、SNSでは驚きと混乱、そして高評価の声が飛び交った。
視聴者の感情が大きく動いたのは、犯人の正体や衝撃的なラストだけではない。
むしろ、「この物語は何を描こうとしているのか?」という問いを、心に突きつけられたからだ。
SNSの声:「まさかの新キャラ」「袴田じゃなかった衝撃」
もっとも多かった反応は、以下のようなものだ。
- 「袴田が犯人じゃないの!? 完全に騙された」
- 「堀部圭亮の使い方がずるい。ここで出すか」
- 「イニシャルHってそういうこと?怖すぎる」
キャストの“ミスリード演出”が大成功だったことが、視聴者の反応から見て取れる。
さらに、尾藤が記憶を失っていたことで「彼女が本当に無実なのか?」という緊張感が最後まで持続。
真相が明かされても“釈然としない空気”が残る構成は、ミステリー作品として極めて高い完成度だった。
脚本構成の巧みさと“チームで解決する物語”としての完成度
第10話が優れていたもう一つの点は、ストーリーの“編成技術”である。
序盤の混乱、尾藤への疑惑、盗聴器・テルミット・ハッキングといった科学技術の羅列。
これらが中盤以降、次々と繋がりながら「下垣という人物像」へと収束していく。
さらに、物語の中心が“土門個人”から“チーム全体”へと移行していく展開は、視聴者に安心感と爽快感を与えた。
高倉、相田、都丸、嵐山──脇を固めるキャラが生きたことで、作品自体に厚みが増した。
科学がテーマでありながら、最終的に“人間同士の信頼”が物語を動かす構造になっている点が秀逸だった。
科学は幻想か、それとも希望か──本作が問いかけたもの
「科学は嘘をつかない」──この作品が何度も繰り返してきたフレーズ。
しかし、第10話でそれは“幻想”かもしれないという揺らぎに変わる。
科学を武器に、人は誰かを救うことも、壊すこともできる。
だからこそ必要なのは、“何を信じるか”という姿勢だ。
土門が最後に下した判断は、科学の力にすがるのではなく、
「信じたい人を、信じ抜くこと」だった。
それは科学ではなく、人間にできる唯一の答えかもしれない。
そして、このドラマ自体が投げかけている。
「科学を信じて生きていくのか、それとも、科学を疑って生きていくのか」
どちらを選ぶにしても、『最後の鑑定人』はその選択の重さを視聴者に刻みつけてくる。
- 第10話で明かされた真犯人の正体と動機
- 科学を使った冤罪工作という構造の精密さ
- 耳紋照合による“科学的追跡”の見どころ
- 尾藤宏香の記憶喪失が持つ心理的な意味
- 科学と感情が交錯する土門とチームの成長
- “H”のメモと謎の電話が示す新たな黒幕の存在
- 科学は嘘を暴くか、それとも嘘を作るのか
- SNSでも話題を呼んだ衝撃的な展開と配役
- 独自視点で考察された“忘却と再生”の物語

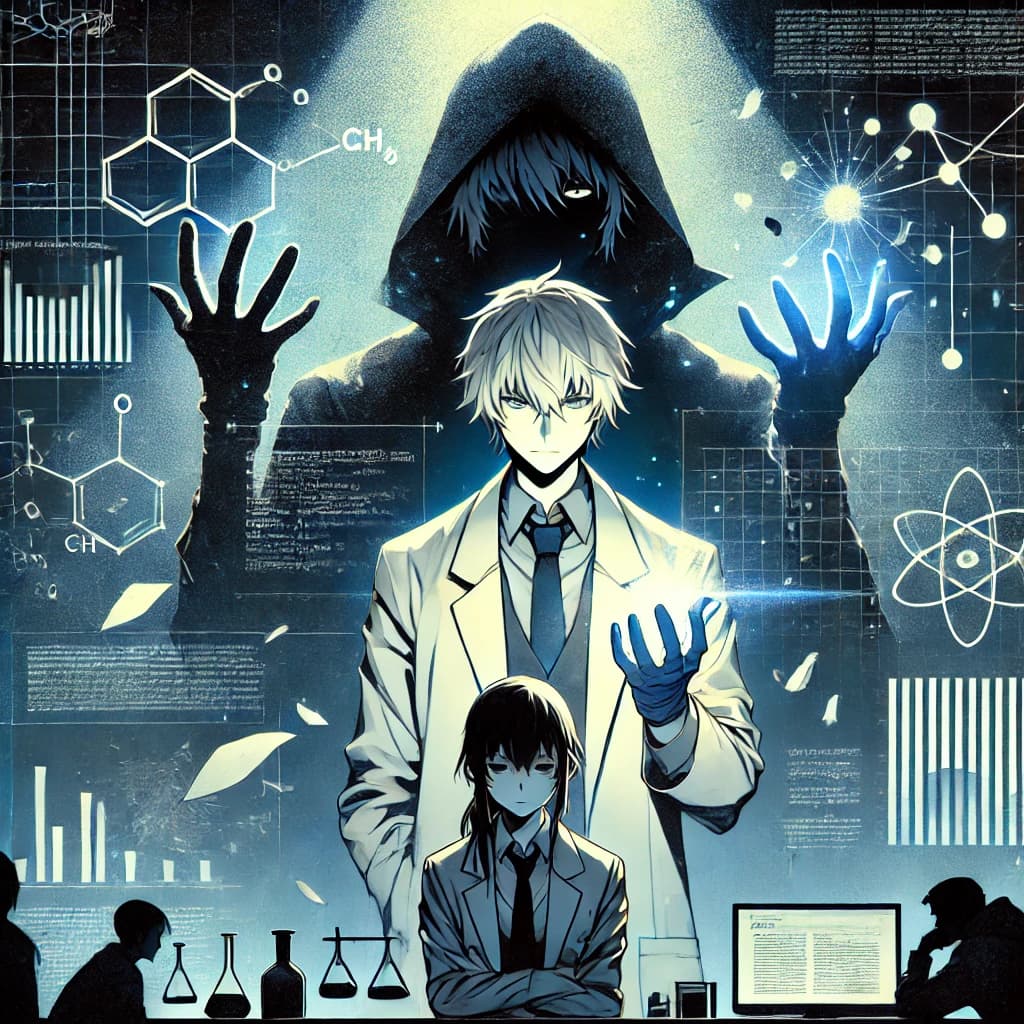



コメント