2025年大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第17話「乱れ咲き往来の桜」では、物語が大きく動き出します。
耕書堂が江戸で一大ブームとなる中、旧友・新之助との再会や、出版業界との摩擦、そして“往来物”という新たなジャンルへの挑戦が描かれました。
この記事では、第17話の展開をあらすじ・登場人物の動き・見どころを交えて丁寧に解説し、視聴者が見逃した感情の機微や意味を深掘りします。
- 第17話で描かれた“往来物”出版の意義と蔦重の戦略
- 登場人物たちの再会と、その中で揺れる想いと信念
- 留四郎(水沢林太郎)の“沈黙の演技”が物語に与える深み
往来物で江戸に勝負を挑む!蔦重の逆転策とは
本の力で時代を揺らす――蔦重が選んだのは、派手な勝負じゃない。
それは“読み書きを広めるための地味な本”――往来物。
だが、その選択が、やがて出版業界を揺るがす“革命の一手”になるとは、誰も予想してなかった。
耕書堂ブームの裏で始まる出版戦争
芝居に“本重”として登場したことで、蔦重の耕書堂は江戸でバズりまくる。
「細見を急ぎます」のセリフが町娘の間で流行り、本屋の店先に人が押し寄せる光景が描かれた。
でもな、浮かれてる暇なんてなかったんだ。
地本問屋――つまり既得権益の連中が動き出す。
「耕書堂の彫りは受けるな」という圧力。
蔦重の“言葉”に惹かれた職人・四五六だけが、こっそり手伝ってくれる。
この時点で、もうただの出版じゃない。
これは“本を巡る生存競争”だ。
誰が本を作るのか、誰に届けるのか――すべてが戦いなんだ。
新たな販路“地方”を開拓する蔦重の野心
再会した旧友・新之助が持ち帰ろうとしていた大量の“往来物”。
それが、蔦重の脳内で火をつけた。
「市中で売れないなら、地方を攻めればいい」――
吉原の親父たちを説得し、越後の豪農、信濃の商人、村の庄屋……。
この展開、痺れたね。
エリートの頭脳じゃなく、遊郭育ちの“しぶとさ”で道を拓く。
蔦重って男、バカみたいに理想ばっかり見てるようで、
実はめちゃくちゃ現実的な策士なんだよ。
誰もやらなかった“往来物”で、逆転する気満々。
その背中がマジで格好良かった。
新之助との再会がもたらす、蔦重の原点と未来
「蔦重、立派になったな」
その声に振り返った瞬間、蔦重の心に、かつての“青臭い夢”が蘇る。
第17話最大の“静かな衝撃”――それが、新之助との再会だ。
源内の意思を継ぐ者たちの対話
新之助は、うつせみ(今は“おふく”)と共に江戸を離れ、
とある村で読み書きを教えながら暮らしていた。
「学がねぇと、商人や役人にやられる」
――このセリフ、完全に刺さった。
金でも名声でもねえ。
“生きるための力”としての知識。
それを、地べたから教えてる新之助。
そして蔦重は思い出す。
源内が「知を広めろ」と言っていたあの目を。
再会は、過去じゃなく未来を照らす。
読み書きを広める“本の力”に目覚める瞬間
往来物――手習いの本。
それが子どもたちにとって、世界を広げる鍵になる。
でも、江戸の本屋はその需要に目を向けていなかった。
「このジャンル、まだ誰も本気でやってねぇ」
気づいた蔦重の目が変わる。
商売としての“勝ち筋”を見つけた男の顔になったんだ。
でもな、それだけじゃない。
あいつは、そこに“恩返し”という感情を乗せた。
源内への、新之助への、自分を育ててくれたすべての人たちへの。
この瞬間、「売るための本」が「生かすための本」へと進化した。
それがこの再会の、本当の意味だった。
誰袖(たがそで)として登場、福原遥の存在感
あの“かをり”が帰ってきた。
もう「振袖新造」じゃない。
立派な花魁――名を「誰袖(たがそで)」と変え、吉原に咲いた一輪の強き桜。
振袖新造から花魁へ、成長した「かをり」
名前を変えるってのは、ただの通過儀礼じゃねぇ。
あの子が、女として“覚悟を決めた”証明なんだ。
福原遥の演技がまた凄ぇ。
目元に柔らかさを残しつつも、言葉に滲む気迫が完全に“芯のある女”だった。
ただ、切なかったな。
あの目は、まだ蔦重を見てるんだよ。
でも、その想いは届かない。
蔦重はもう、夢という名の大火事に飛び込んじまってる。
誰袖の眼差しが、声にならない愛情で溢れてた。
それがもう、胸を抉るんだ。
蔦重との関係と、“想い”が揺れる展開に注目
福原遥は、器用じゃない。
でも、だからこそ、一つひとつの仕草に“感情のにじみ”がある。
誰袖は、きっとわかってる。
蔦重が“自分を選ばない”ってことも。
それでも、そこにいてくれる。
声をかけるでもない、手を伸ばすでもない。
ただ、そばにいる。
この“諦めと希望の狭間”が、誰袖の美しさなんだ。
物語はまだ、ふたりを交差させる。
そのとき、想いが爆ぜるのか、それとも静かに終わるのか。
それを見届ける理由だけでも、このドラマを追い続ける価値がある。
市中 vs 蔦重、出版利権を巡る攻防戦
耕書堂が火を吹き始めた瞬間、市中問屋がザワついた。
理由は単純。「自分たちの利権が揺らぐ」から。
つまりこれは――ビジネスの潰し合い、**戦争だ**。
彫師たちにかかる圧力と、四五六の職人気質
「耕書堂の仕事は受けるな」
そんな圧力を、彫師たちに水面下でかけてくる市中の問屋連中。
これがリアルすぎて、観てて胃が痛くなる。
でもよ、そこに意地で一枚噛んだ男がいる。
彫師・四五六。
こいつが渋い。痺れる。最高。
「俺にとっちゃ、作品は娘みてぇなもんなんだ」
この一言、職人の矜持そのものだ。
金でも立場でもない。
「いい仕事をしたい」「いい本を残したい」――
その一点だけで、牙をむく。
圧力なんてクソ喰らえ。
そういう職人魂が、今の時代にも必要なんじゃねぇか?
地本問屋の反撃と“往来物”市場の争奪戦
往来物――手習い本。
そのジャンルに蔦重が参戦したことで、地本問屋たちは完全に動揺する。
なぜなら、このジャンルは“枚数勝負”。
数で勝たれたら、市中は死ぬ。
そして、蔦重はこう言った。
「俺は、市中に売るつもりはねぇ。地方に売る」
まさに、発想の逆張り。
既存の土俵で勝てないなら、自分で土俵を作る。
これが“吉原の出版社”の底力だ。
地本問屋たちは焦る。
それでもプライドが邪魔して動けない。
そんな中で、静かに確実に“本”を動かす蔦重。
この構図がもう、痛快で痛烈で、最高に熱い。
水沢林太郎演じる留四郎の献身が光る場面
名は知られなくていい。
褒められなくていい。
でも、自分の仕事が、誰かの夢を支えているなら――それで十分。
そんな想いを背負って立つのが、奉公人・留四郎だ。
“裏方”として支える若き奉公人の信念
「彫師の腕が悪ければ、せっかくの作品が台無しになる」
留四郎が口にしたこの一言に、全てが詰まってた。
派手な主張じゃない。
でも、“わかってる奴だけが言える台詞”なんだよ。
彼は、蔦重の本がどれだけの情熱で作られてるかを、
横でずっと見てきた。
だからこそ、手を抜けない。
印刷所の職人が断ってきたとき、次郎兵衛が「他にもいるだろ」って言った。
そのときの留四郎の眼差し。
あれは、“本気”で生きる者の目だった。
水沢林太郎、静かにやるじゃねぇか。
芝居に宿る静かな熱量と、蔦重との絆
言葉少なに、でも確かに“蔦重の隣”にいる。
それが留四郎の役割であり、彼の存在理由だ。
水沢林太郎の芝居、すごいぞ。
表情じゃない。台詞じゃない。
“沈黙の中に揺れる呼吸”で演じてる。
それがあるから、視聴者はこう思う。
「あいつがいなかったら、耕書堂は回ってなかったな」って。
この役は、間違いなく**水沢林太郎の代表作になる**。
なぜって、“裏方の尊さ”を、全力で体現した役だからだ。
誰も気づかない場所で、黙って動く。
でもそれが、誰かの夢を支えてる。
留四郎――お前こそ、この物語の“支柱”だ。
蔦重に惚れるということは、“報われなさ”と生きるということ
この第17話を観ていて、ふと胸がギュッとなった瞬間があった。
それは、誰袖の静かなまなざしでも、留四郎の気づかいでもない。
蔦重の周りにいる人たちが、みんな一様に「この人のそばにいたい」って顔をしてたんだよ。
でもな、誰ひとりとして、「自分のために」蔦重を引き止めない。
その姿が、なんだかとても美しくて、でも残酷だった。
「一緒にいたい」よりも、「前に進んでほしい」と願える強さ
誰袖も、留四郎も、ふじも、いねも。
みんな、蔦重が夢に向かってまっすぐ進む背中を見てる。
そして、それに“置いていかれる”ことを受け入れてる。
自分に振り向いてくれなくてもいい。
そばにいられなくてもいい。
それでも、「この人が夢を叶える瞬間を見たい」って思える。
――それって、恋じゃないのか?
応援って、簡単に言うけどさ。
本当に相手を思うなら、“自分が報われない覚悟”がいるんだよな。
蔦重という“炎”に集まる蛾たちの、それぞれの覚悟
蔦重って男は、正直“火”みてぇなやつだ。
触れると熱いし、危なっかしい。でも、目が離せない。
あいつを好きになるってことは、
「燃える」ことと、「焦げる」ことが表裏一体なんだ。
でも、それでも惹かれてしまう。
そして、焼かれても、心に何かを残して去っていく。
それが、今この物語のまわりに集まる人たち――
名もなき“蔦重の支持者たち”の、切なくも美しい在り方なんじゃないかって思った。
報われなくてもいい。
その夢が叶うなら。
そう思える人間たちが支えてるからこそ、蔦重って男の背中が“まっすぐ”に見える。
べらぼう第17話まとめ|往来物と人の縁が物語を動かす
第17話は、江戸という街の中で、言葉が持つ力と、人と人との縁がどれほど物語を動かすかを見せつける回だった。
派手な戦や大事件がなくても、一冊の本、一人の想いが、時代を動かすことがある。
それを信じる者たちがいたからこそ、蔦重は「往来物」という地味な選択に、確かな火を込めた。
出版の未来は「知と情」が繋いでいく
蔦重が選んだのは、“売れる本”じゃない。
“残すべき本”だ。
「読み書きができれば、騙されなくて済む」
そんな新之助の言葉に、江戸の華やかな街で生きる蔦重が、深く頷いた。
これまで本は“娯楽”だった。
でもこの回で、「生きるための知」としての本へと進化する瞬間が描かれた。
そしてそこに集う人々――職人、奉公人、花魁、旧友。
皆が口を出さずとも、知と情で蔦重の夢を支えていた。
この物語は、血の通った人間たちが繋ぐ出版の物語だ。
次回18話「歌麿よ、見徳は一炊夢」への期待
第18話の予告に現れたのは――ついに、あの男。
浮世絵の鬼才・喜多川歌麿。
蔦重とどう出会い、何を描くのか。
そしてその“夢”が、どんな代償と覚悟を伴うのか。
「見徳は一炊の夢」――つまり、
徳を求めた者の生き様は、儚い夢のようだという意味。
そのタイトルからして、次回はまたひとつ、物語の炎が激しくなるのは間違いない。
江戸の片隅で、本気で生きようとした者たちの物語。
第17話はその“起点”だった。
さあ、ここからが“べらぼう”の真骨頂だ。
- 第17話は「往来物」と“縁”が物語を動かすターニングポイント
- 耕書堂と市中問屋の出版戦争が本格化し、蔦重は地方流通へ活路を見出す
- 旧友・新之助との再会が、蔦重に“知を広める本”の価値を再認識させる
- 誰袖(福原遥)の成長と蔦重への想いが静かに胸を打つ
- 職人・四五六や奉公人・留四郎の無言の支えが耕書堂を動かす
- 水沢林太郎の“引きの演技”が留四郎の献身を体現
- 主役ではない者たちの“報われぬ愛と信念”がドラマを深める
- 次回、第18話はついに喜多川歌麿登場で物語が加速

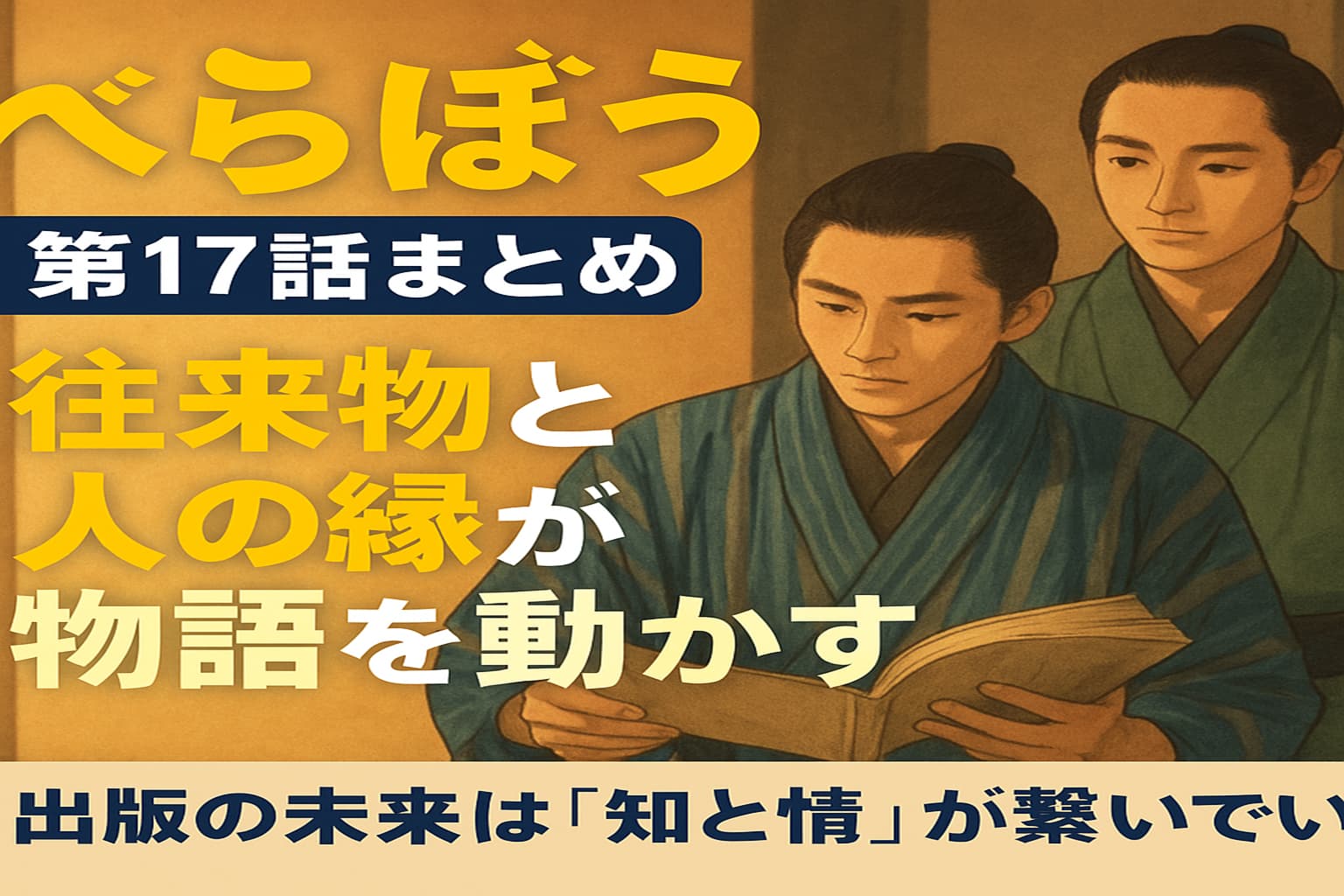



コメント