2025年のNHK大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』は、初回から視聴率が12.6%と苦戦のスタートを切った。
第8回には一桁台に突入し、第18回では9.4%という大河ワースト圏の数字を記録。だがそれは単なる“数字の沈下”ではない。
この記事では『べらぼう』の視聴率がなぜ低迷したのかを徹底解剖し、そこに潜む“物語の構造的欠陥”と“時代の潮流”を浮かび上がらせる。そして、復活への鍵はどこにあるのか──答えは、江戸の風に舞っている。
- 『べらぼう』の視聴率が低迷した具体的な理由
- 視聴率回復の鍵となる今後の展開とNHKの戦略
- “表現と統制”を描く物語の深層と現代的な問い
- 『べらぼう』の視聴率はなぜここまで低いのか?【結論:複合要因のミスマッチ】
- 視聴率低迷の真因①:江戸“出版文化”は重みに欠ける?テーマの非大河性
- 視聴率低迷の真因②:「べらぼう」というタイトルが足を引っ張った?
- 視聴率低迷の真因③:キャスティング戦略のズレ──横浜流星の評価は割れた
- 視聴率低迷の真因④:物語と演出が“朝ドラ寄り”になりすぎた
- 視聴率低迷の真因⑤:SNSと口コミの“熱”が足りなかった
- 視聴率低迷の真因⑥:大河離れと“配信時代”の評価構造
- 反撃の鍵①:物語が“戦い”を始める──松平定信との検閲バトル
- 反撃の鍵②:歌麿・写楽・北斎──スターたちの登場が流れを変える
- 反撃の鍵③:NHKのプロモーション戦略と“祭りの再設計”
- 『深すぎるテーマは視聴率を下げるのか?』──現代視聴者が“見るに堪えない”と感じる瞬間
- べらぼうの視聴率は復活できるのか?物語の炎はまだ消えていない【まとめ】
『べらぼう』の視聴率はなぜここまで低いのか?【結論:複合要因のミスマッチ】
2025年、NHKが放った大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』。
そのスタートダッシュは、意外にも鈍かった。
初回視聴率は12.6%。かつて20%を超えるのが常識だった“大河の看板”にしては、あまりにも静かな船出だった。
しかし、問題はそのあとだ。
第2回で12.0%、第3回で11.7%、第4回で10.5%、そしてついに第8回で一桁台の9.8%を記録。
最低記録は第17回の9.5%──この数字が意味するのは、ただの“失敗”ではない。
『見なくても損しない』と、視聴者に判断されたということだ。
それはある意味、どんな酷評よりも致命的だ。
熱がない。火がついていない。燃え上がるものがない。だから、誰も手を伸ばさなかった。
<べらぼう視聴率>
| 話数 | 放送日 | 世帯視聴率 | 個人視聴率 |
|---|---|---|---|
| 1話 | 1月5日 | 12.6% | 7.3% |
| 2話 | 1月12日 | 12.0% | 7.0% |
| 3話 | 1月19日 | 11.7% | 6.8% |
| 4話 | 1月26日 | 10.5% | 6.1% |
| 5話 | 2月2日 | 10.6% | 6.1% |
| 6話 | 2月9日 | 10.2% | 5.9% |
| 7話 | 2月16日 | 10.0% | 5.8% |
| 8話 | 2月23日 | 9.8% | 5.9% |
| 9話 | 3月2日 | 10.4% | 5.9% |
| 10話 | 3月9日 | 10.6% | 6.1% |
| 11話 | 3月16日 | 9.6% | 5.7% |
| 12話 | 3月23日 | 9.9% | 5.7% |
| 13話 | 3月30日 | 9.6% | 5.6% |
| 14話 | 4月6日 | 10.8% | 6.5% |
| 15話 | 4月13日 | 9.9% | 5.6% |
| 16話 | 4月20日 | 9.6% | 5.3% |
| 17話 | 5月4日 | 9.5% | 5.6% |
初回から失速した視聴率推移:12.6%→9.5%への軌跡
視聴率の数字は、ただの棒グラフじゃない。
そこには、“毎週、心を奪われるかどうか”という視聴者の静かな選択がある。
第1話の12.6%は、まだ期待が残っていた数字だ。
けれど回を追うごとに、その期待が剥がれ落ちていく。
注目すべきは、第8話で9.8%、第17話で9.5%と着実に“空気”になっていったこと。
SNSの投稿数、話題性、Twitterトレンド──どれもが鈍かった。
誰かが語りたくなる熱源が、どこにもなかった。
戦も、裏切りも、血もない。
それでも魅せられる物語はある──が、『べらぼう』はまだそこに届いていなかった。
数字だけでなく“熱量”が足りなかった序盤展開
本質は数字じゃない。
“なぜ人が語らないのか”。ここに尽きる。
序盤のストーリーは、ひたすら静かだった。
蔦屋重三郎の少年時代、家族の思い出、貸本屋としての歩み──
丁寧だが、火花は散らない。
脚本は森下佳子。決して凡庸ではない。だが「最初の5分で心を掴む」構造にはなっていなかった。
視聴者は物語の予兆を探していた。でも、その“波”は来なかった。
「この先、何か起こりそうだ」という期待感を設計できていなかった。
だからこそ、“数字の下降”は予測できたし、“空気化”も避けられなかった。
これは、誰のせいでもない。けれど、誰も止められなかった流れだ。
視聴率低迷の真因①:江戸“出版文化”は重みに欠ける?テーマの非大河性
大河ドラマに必要なものは何だ?
戦か。陰謀か。血か。歴史を動かした英雄の“宿命”か。
『べらぼう』は、それらすべてをあえて外した。
主人公は蔦屋重三郎──江戸の本屋だ。
戦わない。死なない。政(まつりごと)もしない。
彼が闘ったのは、“言葉と絵の力”であり、出版と風俗という“文化の戦場”だった。
これは挑戦だった。だが、結果はついてこなかった。
なぜか──理由は単純だ。
それが「大河的じゃなかった」から。
歴史転換期でも戦でもない──物語の“火薬”が弱かった
『べらぼう』の舞台は、18世紀後半の江戸中期。
そこにあるのは平穏な町と、読み物と、吉原遊郭。
言ってしまえば、戦国や幕末のような劇薬がない。
天下が動かない。国が変わらない。斬り合いもない。
視聴者が“歴史ドラマ”に求めるものと、物語が差し出したものが乖離していた。
もちろん、題材としては新しい。江戸文化の裏側を描くという意味では、知的好奇心をくすぐる。
だが、視聴者の多くは「ドラマチックな歴史のうねり」に身を投じたくて大河を見るのだ。
そこに“本屋の成り上がり譚”をぶつけた。
挑戦はわかる。でも、その爆薬は、湿っていた。
蔦屋重三郎の人物像は魅力的だが、大河ファンが求める“熱戦”とのギャップ
蔦重という男は、間違いなく面白い。
歌麿や写楽といった天才を世に出し、文化を武器に時代を塗り替えた異端児。
だが、その“面白さ”を視聴者が受け取るには、時間と文脈が必要だった。
序盤では彼の“偉業”の片鱗すら見えず、ただの青年が貸本屋で奔走する日々。
「これ、朝ドラじゃないの?」──そんな声もSNSに散見された。
大河ファンが求めるのは、運命に抗う男たちの“激突”だ。
だが蔦重は、まず「紙の流通」と「町人の信用」から始める。
そこに“燃え上がるドラマ”を感じられなかった人が、離れていった。
設定が弱いのではない。
“語り口”がまだ追いついていなかった。
この主人公がどんな地雷を踏み、どんな夜を這いずり回るのか──
その“戦い”が見えなかった段階で、多くの視聴者は「静かなドラマ」と誤読してしまった。
視聴率低迷の真因②:「べらぼう」というタイトルが足を引っ張った?
タイトルは、作品の“顔”だ。
一行で物語の魂を撃ち抜く、最初で最後の言葉の刃。
だが、『べらぼう』というタイトルは──視聴者にとって刃ではなく“霧”だった。
「え、なんの話?」という第一印象。
『真田丸』や『西郷どん』のように、“誰の物語か”が一発でわかるタイトルではない。
『べらぼう』──その語感は軽妙でユーモラス、だが中身が伝わらない。
“江戸ことば”の意味が視聴者に伝わらないジレンマ
制作側は、「べらぼう=“桁外れな、突き抜けた人物”という肯定的な意味」を込めたと言う。
だが一般には、「べらぼうめ!」と罵倒語の印象が強く、ネガティブな語感で受け取られてしまった。
特に初見での印象は致命的だ。
ドラマ紹介を見ても「江戸の本屋の話」「文化人の群像劇」といった説明が曖昧で、何が面白いのかピンと来ない。
興味を引くどころか、「ふわっとしてるな」とスルーされた。
“見たくなる要素”が、タイトルから何ひとつ伝わらない。
これは「インパクトで勝負したい」という冒険だったのかもしれない。
でも、その冒険は、言葉を知らない世代には届かない。
「タイトルで観る気が削がれた」という声のリアリティ
SNSやYahoo!コメントでは、こんな声が並んだ。
- 「“べらぼう”って何のドラマ?内容が想像できない」
- 「蔦屋重三郎のことだと気づいたのは、3話見た後だった」
- 「大河ドラマと思わなかった。コントかと思った」
タイトルで“誤読”された。それが『べらぼう』最大の不幸だった。
名は体を表す──タイトルがドラマの核心を語らない時、人は“勝手に解釈”する。
そして、多くの場合、その解釈は物語の本質から遠ざかる。
ドラマというコンテンツが、どれだけ中身を磨いても。
入口の鍵が曇っていたら、人は中に入ってこない。
『べらぼう』という選択は、意欲的だった。だが──
それが視聴率という冷酷な指標において“足を引っ張った”のは、否めない事実だ。
視聴率低迷の真因③:キャスティング戦略のズレ──横浜流星の評価は割れた
“主役”は、作品のエンジンだ。
その演技が、物語の温度を決める。空気を決める。鼓動を作る。
そして、NHKはこの2025年大河の主役に横浜流星を選んだ。
これが、視聴者の心を二つに割った。
若年層に人気、SNSでも強い。だが──大河の主戦場は“そこじゃない”。
若年層に強いが大河の主戦場“中高年層”に響かない
大河ドラマは日曜夜8時、NHKの“家族視聴”の象徴的枠だ。
視聴者の中心は50代以上、そして“歴史ファン”層。
その層にとって、横浜流星はまだ「新しすぎる存在」だった。
「誰?」という戸惑い。
「現代劇では映えるけど、大河の主役はまだ早いんじゃ?」という声。
彼の“良さ”を受け取れる層と、主たる視聴者の層が、うまく重ならなかった。
さらにその演技スタイル──繊細で柔らかく、どこか抑制された芝居。
それは時に「淡泊」に映った。
「芯がない」「声が届いてこない」──そんな声がネットを駆けた。
ベテラン俳優の“遅すぎる登場”が支えきれなかった初動
『べらぼう』には、渡辺謙、石坂浩二、小日向文世、佐藤浩市と、骨太なベテラン俳優が脇を固める。
だが──彼らの本格的な出番は、中盤以降だった。
視聴率の初動が勝負を分ける今、“序盤にベテランの存在感が欠けていた”のは痛かった。
「誰かが支えてくれるだろう」では足りなかった。
主演が“信頼”を得る前に、視聴者は離脱した。
キャスティングには意図がある。若者を引き込みたい、イメージを刷新したい。
わかる。わかるが──
大河という舞台で“冒険”するには、代償が大きすぎた。
視聴率という数字は、容赦ない。
「まだ大河を引っ張れるほどの“信頼資本”を持っていなかった」
──それが、横浜流星の最大の壁だったのかもしれない。
視聴率低迷の真因④:物語と演出が“朝ドラ寄り”になりすぎた
ドラマには“匂い”がある。
脚本の構成、台詞回し、登場人物の描き方……
それらの積み重ねで、「これは大河だ」「これは朝ドラだ」と、視聴者は無意識に空気を嗅ぎ取る。
『べらぼう』には、確かに“大河ではない何か”の香りがした。
それは、朝ドラの香りだった。
「これは朝ドラ?大河なのか?」という声が示すジャンル感の混乱
序盤の『べらぼう』は、明るい音楽、軽妙なナレーション、コミカルな掛け合い。
まるで“朝8時の15分枠”を1時間に拡張したようなトーン。
しかも、主人公は下町の青年、夢を追いかける成り上がり。
こうなると、「朝ドラみたいだな」という印象を持つのは、自然なことだ。
実際にSNSではこんな声が並んだ。
- 「テーマもテンポも朝ドラっぽくて、大河の荘厳さがない」
- 「なんか軽い。日曜夜に見るテンションじゃない」
- 「“朝ドラでやった方がよかった”って、母が言ってた」
ジャンルの境界線が曖昧になると、視聴者の期待も揺れる。
「これは何を見せられているんだ?」という違和感が蓄積される。
その違和感こそが、数字の下落にじわじわと効いてくる。
“コミカルな情緒”が荘重な期待とすれ違う瞬間
もちろん、コメディタッチや人情劇が悪いわけではない。
実際、森下佳子は『ごちそうさん』で朝ドラの名作を生んだ。
その“巧さ”は今作にも息づいている。
だが──“朝ドラの手法”を“日曜夜の大河”にそのまま持ち込んだことが問題だった。
重厚な人間ドラマを期待していた層は、肩透かしを食らった。
ゆるやかに、優しく、笑って泣ける……
それが『べらぼう』の魅力だとしても、“大河の尺”に求められるのは緊張感だ。
1年間を通して語るドラマに必要なのは、「来週が気になる」という構造。
そこが弱いと、どれだけ丁寧に作っても“流れてしまう”。
つまり──
『べらぼう』は、空気のように優しすぎた。
それが、“視聴率”という荒波では致命傷になった。
視聴率低迷の真因⑤:SNSと口コミの“熱”が足りなかった
今の時代、“数字”より先に物語の熱を可視化するものがある。
それが──SNSと口コミだ。
語られる数、引用されるセリフ、トレンド入りの速度。
そこに火がつけば、作品は視聴率以上に広がる。
だが、『べらぼう』には──その炎がなかった。
「演出が軽い」「主人公に共感できない」──ネットで交わされた本音
Twitter(X)やYahoo!コメントを覗くと、こうした声が散見された。
- 「横浜流星の演技が軽くて、大河に合ってない」
- 「1話観たけど、正直“何を描きたいのか”がわからなかった」
- 「映像は綺麗。でも、それだけ。心が動かない」
共感でも、怒りでもいい。
“感情を動かす何か”が、視聴者の言葉を引き出す。
しかし『べらぼう』に対しては、「語りたい」と思わせる衝動が生まれなかった。
語られない作品は、忘れられる。
そしてそれが、じわじわと視聴率に効いてくる。
バズらない作品は“空気化”する:現代の大河が直面する新たな壁
かつての大河は、テレビの前に人を座らせた。
だが今は違う。
SNSで“観る理由”を与えない作品は、埋もれる。
『鎌倉殿の13人』では、「義時の狂気」「頼家の壊れ方」など、毎週“燃える”ワードが生まれた。
視聴者はスクショを貼り、台詞を引用し、感情を共有した。
だが『べらぼう』には──“切り取られる場面”が少なかった。
話題にしやすい演出、象徴的な台詞、意外な展開──
そういった“SNS映えする仕掛け”が欠けていた。
これは時代の変化だ。
テレビドラマは、もはや“黙って観て評価される”メディアではない。
SNSで広がり、語られ、再生されることで、初めて存在感を得る。
『べらぼう』は、そこに乗り遅れていた。
それが、視聴率以上に深刻な“沈黙”を生んだのだ。
視聴率低迷の真因⑥:大河離れと“配信時代”の評価構造
視聴率が“絶対指標”だった時代は、もう過ぎ去った。
今、ドラマの“真の浸透度”は、リアルタイムではなく「後から観る」視聴習慣に隠れている。
『べらぼう』は、そこに引っかかっている。
テレビの数字は低くてもNHKプラスでは過去最高──何が起きている?
2025年、NHKの見逃し配信サービス「NHKプラス」で、『べらぼう』は歴代最高レベルの再生数を記録したという。
リアルタイムの視聴率は一桁台なのに、配信では“ちゃんと観られていた”。
このギャップが意味するもの──
それは、「時間通りにテレビの前に座る時代」が、終わりかけているという現実だ。
「子どもと一緒には観づらいから、夜中にスマホで観た」
「週末にまとめてNHKプラスで観てる」
──こうした“視聴の分散”が、大河でも起きている。
「家族で見るには気まずい」時代の変化がもたらした視聴行動の分散
『べらぼう』は、吉原遊郭や風俗文化を真正面から扱う。
テーマとしては重要だ。だが──
“家族で安心して観る”には、やや刺激が強すぎた。
特に子育て世代の家庭では、「日曜夜8時」の共有時間に選ばれにくい。
それがテレビ視聴の“数字”を押し下げた要因のひとつになった。
では、観られていなかったのか? そうじゃない。
観る場所が、変わっただけ。
テレビ→スマホ、家族一緒→ひとり視聴、リアルタイム→深夜・週末まとめ見。
視聴行動の変化に、評価指標が追いついていない。
NHKはそれを理解している。
だからこそ、「視聴率だけで作品を測らない」という姿勢を取り始めている。
だが──
“視聴率が下がってる”という事実だけが、世間に広がっていく。
配信で伸びていても、それは“裏側の成果”でしかない。
そこに『べらぼう』の不運があった。
──時代は変わっているのに、“評価の物差し”だけが、古いままだった。
反撃の鍵①:物語が“戦い”を始める──松平定信との検閲バトル
ドラマは“何を描くか”より、“いつそれが始まるか”が勝負を分ける。
そして『べらぼう』は──ようやく「戦い」を始めた。
その相手は、時の老中・松平定信。
蔦屋重三郎が挑むのは、刀でも、金でもない。
“出版と言論”をめぐる命がけの検閲バトル。
反権力・出版統制──命懸けの戦いがようやく動き出す
江戸後期、松平定信は“倹約と道徳”を重んじ、表現の自由を徹底的に締め付けた。
その刃は、風刺、絵、出版、戯作へと向かう。
それはつまり──蔦屋重三郎の人生そのものへの否定だ。
第17回以降、『べらぼう』の物語は急速に動き出す。
蔦重が版元として花開き、名を上げ、そして……権力に狙われる。
「筆で人を笑わせるな」「絵で権力を茶化すな」
──それは、蔦重にとって“死刑宣告”にも等しい思想統制だった。
ここにきて、やっと『べらぼう』は燃え始めた。
「本屋の戦」は、ここからが本番だったのだ
戦国の大将には刀があった。幕末の志士には思想があった。
では、蔦屋重三郎には何があったか?
紙と、筆と、人を信じる勇気だ。
この戦いは、視聴者に問う。
「表現とは何か?」
「言葉は誰のものか?」
歴史上、彼は処刑されなかった。だが、それはギリギリの攻防だった。
友は追放され、仲間は斬られ、絵師たちは潜伏した。
蔦重はその中で、「それでも俺は売る」と言い続けた。
この構図が、ついにドラマとして浮き上がってきた。
権力vs文化、老中vs版元、検閲vs出版。
“言葉の戦国”が、今、始まろうとしている。
──そして、こういう構図には、視聴者の心が再び“火を灯す”のだ。
反撃の鍵②:歌麿・写楽・北斎──スターたちの登場が流れを変える
視聴率とは“物語の熱”の体温計だ。
そして、その温度を一気に上げるものがある。
“誰が登場するか”という爆発力。
『べらぼう』には、そのカードがある。
──それが、喜多川歌麿、東洲斎写楽、葛飾北斎。
染谷将太×喜多川歌麿、そして写楽キャストのサプライズは?
物語中盤、ひとりの青年が登場する。
名は“唐丸”──しかしその正体は、喜多川歌麿であることが徐々に明かされていく。
演じるは染谷将太。
独特の色気と危うさを持つ役者が、“江戸の反骨の絵師”を演じる。
ここにきて、視聴者の間にザワつきが生まれた。
「あ、いよいよ来たぞ」と。
そして次に待ち構えるのが、“正体不明”の東洲斎写楽。
誰が演じるのか。どんな演出で登場するのか。
これは、視聴者の予想を超える“キャスティング・サプライズ”が仕込まれている可能性が高い。
写楽は、浮世絵史の最大のミステリー。
その正体を“誰に託すか”は、ドラマ最大の仕掛けになり得る。
歴史ファンもアートファンも惹きつける“第二の幕”
蔦重の物語は、いわば「編集者の物語」だ。
そして彼が見出した“スター作家たち”が、物語を加速させる。
絵で世を斬る男たち。
禁じられた色と線で、女と社会と権力を描き出す男たち。
彼らの登場は、物語に“爆薬”を投げ込む。
歴史ファンは、歌麿や北斎の描かれ方に注目する。
アートファンは、浮世絵の表現と演出美術に惹かれる。
そしてドラマファンは、「この回だけは観たい」と思う。
キャラクターの磁力が、視聴率を引き戻す。
『べらぼう』の第二幕は、“天才たちの化学反応”が火種になる。
それはもう──江戸の話ではない。
創作と反骨と承認欲求に生きる、“現代の俺たち”の物語になる。
反撃の鍵③:NHKのプロモーション戦略と“祭りの再設計”
大河ドラマとは、ただの作品じゃない。
“1年間続く国民的な祭り”だ。
視聴率が落ちても、空気が冷えても──NHKはその火を消さない。
『べらぼう』でも、プロモーションという名の“再点火”が始まっている。
公式SNSと地域タイアップが支える“視聴のリカバリー”
NHKは、公式X(旧Twitter)やInstagramを通じて積極的にオフショットや裏話を発信している。
現場の雰囲気、キャストの素顔、撮影風景──それらがファンの温度を上げる。
さらに、舞台である江戸・浅草や台東区と連携した企画展もスタート。
「蔦重の夢が息づくまち・台東区」として、地元と一体になったプロモーションが展開中だ。
視聴率はテレビの前だけで決まらない。
“生活の中にドラマを混ぜ込む”ことで、「見てみようかな」の第一歩が生まれる。
祭りの担い手として、横浜流星は生きるか──今後の起爆点
主人公・蔦重を演じる横浜流星。
序盤では“大河の重み”とフィットしきれなかった彼が、ここにきて変わり始めている。
目の奥に宿る火が強くなってきた。
演技のトーンも調整され、声に芯が通り、芝居が物語を動かし始めている。
横浜流星が、“ドラマの顔”として再評価されるタイミングが来ている。
それはつまり、視聴率の反転ポイントにもなり得る。
さらに、今後の展開には話題性の高いゲスト出演者も噂されている。
写楽のキャスト発表、生田斗真や片岡愛之助などの投入タイミング──
“視聴者の関心を一気に引き寄せる爆弾”は、まだ眠っている。
NHKはわかっている。
『べらぼう』は、従来型の大河じゃない。
ならば“従来型の広げ方”では届かない。
それを理解した上で、SNS、地域、配信、ゲスト──
四方から“視聴者を取り囲む”プロモーションへと動いている。
あとは、物語の熱と、登場人物の声に──誰かが火をつけるだけだ。
『深すぎるテーマは視聴率を下げるのか?』──現代視聴者が“見るに堪えない”と感じる瞬間
『べらぼう』の視聴率が低迷した理由は数あれど、
その根っこにあるのは「テーマが重すぎた」という事実だと思ってる。
“言論と統制”“文化と抑圧”──大河が背負いすぎた現代性
このドラマの本質は「笑いを奪われることへの抵抗」だ。
吉原も浮世絵も、出版も──ぜんぶ“表現と自由”を巡る戦いとして描かれてる。
それはつまり、現代の俺たちが日々感じている息苦しさ、窮屈さ、炎上社会の延長線。
SNSの発言一つで消される時代に、「べらぼう」は“観るのがキツいドラマ”になってしまった。
“正しすぎる物語”は、娯楽に向かない──というジレンマ
娯楽とは何か? ドラマとは何か?
それを視聴者に問いかけすぎる作品は、時に“見捨てられる”。
『べらぼう』は、それでも笑わせようとする。
でもその笑いは、明るさではなく「ギリギリ生き抜く人間の意地」から来るものだった。
楽しくない、のではない。
重すぎるのだ。
じゃあ、軽くすべきだったのか?──答えはNOだ
この物語が持っている問いは、必要な問いだ。
「誰が言葉を殺し、誰が物語を残すか」
「笑いは、罪なのか?」
それを1年かけて描く大河があってもいい。
視聴率がどうであれ、こういう作品は残ってほしい。
それが“べらぼう”というタイトルの意味なんだろう。
普通じゃない。異端。重い。でも、確かに届く。
そんな作品だからこそ、今、数字に負けずに語り続ける意味がある。
べらぼうの視聴率は復活できるのか?物語の炎はまだ消えていない【まとめ】
視聴率は、確かに厳しい。
12.6%から始まり、9.4%まで落ち込んだ。
SNSの反応も、トレンドの動きも、鈍かった。
だが──
『べらぼう』という物語は、まだ終わっていない。
むしろ、ようやく“火薬に火がついた”ところだ。
検閲という圧政、創造という抵抗。
その間で燃え上がる人間たちの叫びと矜持。
数字には表れない熱が、物語の中に確かにある。
“視聴率”では測れない視聴体験の再定義を──大河ドラマの新しい形
テレビで見る人、NHKプラスで後から見る人。
SNSで語る人、静かに録画して観る人。
大河ドラマの視聴体験は、もう一つの形に変わり始めている。
視聴率が低いことは、事実だ。
でも、“観ている人がいない”わけじゃない。
その“別の熱量”を、数字だけで断じることはできない。
批判は受け止める。その上で問いかける。「何を残すドラマか?」
『べらぼう』は問う。
「表現とは何か?」
「誰が物語を残すのか?」
それは、今この瞬間に生きる俺たちへの問いでもある。
ドラマは、戦国も描ける。江戸も描ける。でも──
“未来”も描ける。
視聴率だけでは終わらせない。
俺は、そういう作品を見届けたい。
“べらぼう”──桁外れで、異端で、でも心を揺らす。
その物語が、どんな風に燃え尽きるか。
俺はこの目で、最後まで見届ける。
- NHK大河ドラマ『べらぼう』は初回視聴率12.6%から右肩下がり
- 視聴率低迷の背景に、題材の地味さや演出の朝ドラ寄り傾向
- 主演・横浜流星の起用が従来の大河ファン層とミスマッチ
- 「べらぼう」というタイトルの伝わりにくさも要因の一つ
- SNS上での話題性不足が空気化を招き、視聴率に影響
- 一方でNHKプラスでは再生数好調、視聴環境の変化が顕著
- 物語後半では検閲と出版の対立という“戦い”が本格化
- 歌麿や写楽などスター登場により今後の注目度も上昇中
- NHKは地域・SNS・キャスト強化で反転攻勢のプロモーションを展開
- 数字を超えて問われる「表現とは何か?」という普遍的テーマ

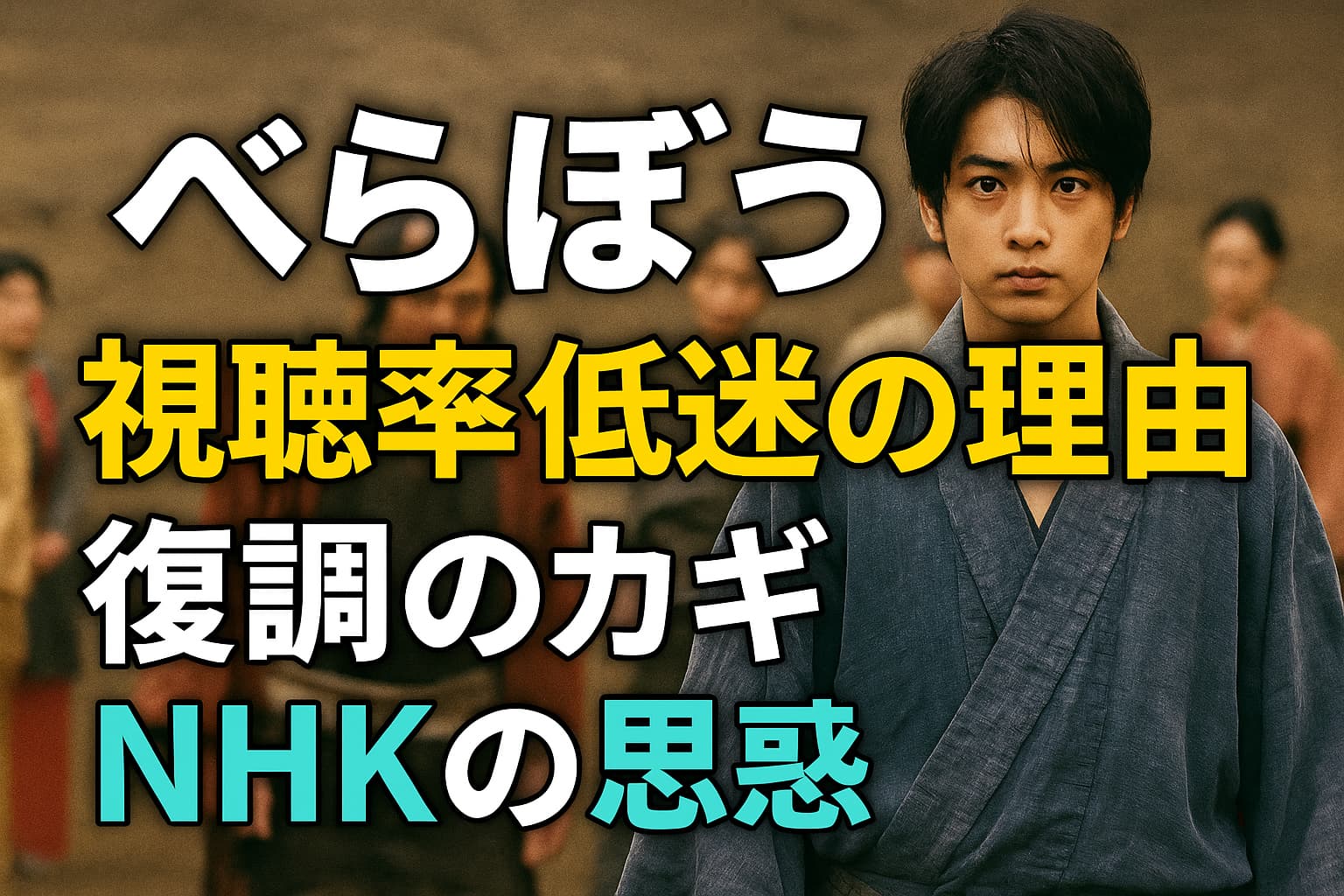


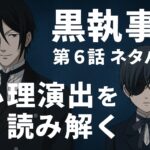
コメント