「大追跡~警視庁SSBC強行犯係~」第5話は、双子の兄弟が引き裂かれた過去と、残酷な親の存在を軸に展開される濃密なヒューマンサスペンスだ。
殺されたのは暴力団構成員で虐待の加害者。だが、その殺意の理由に「正義」と「贖罪」が交差する。
この記事では、犯人・純一が犯した罪の裏にある“もう一つの動機”と、「感情が構造化された脚本」の妙を徹底的に読み解く。
- 双子の兄弟が背負った過去と殺意の真相
- 「アンガーハンマー」に込められた感情の正体
- SNS炎上が映し出す現代社会の非情さ
倉田純一が父親を殺した理由は“弟を守るため”だった
警察ドラマが「誰がやったか」を追い続ける時代は終わった。
今、物語が問うのは「なぜやったのか」。
第5話の真実は、まさにその問いへの壮絶すぎる答えだった。
兄・純一の人生は“奪われ続けた人生”だった
半グレ集団に属し、犯罪すれすれの縁で生きてきた男・倉田純一。
彼の輪郭は一見して「どうしようもないヤツ」でしかない。
だが、カメラが向けたのはその表層ではなく、過去の“深部”だった。
純一は、虐待と育児放棄の果てに児童養護施設へ送り込まれ、そこから別々の家庭に引き取られる。
弟・純二――今の浜田響――は東京の裕福な家庭で音楽の道へ。
一方の純一は、静岡の地方都市でくすぶるように生きる。
この兄弟の差は、才能の差じゃない。
“運”と“環境”だけが全てを決めたんだ。
そして、久しぶりの再会。
口では毒を吐きながらも、彼は演奏を聴いた瞬間に立ち尽くす。
「あいつは努力してた」と絞り出す。
その一言に、人生を奪われ続けた者の、嫉妬でも怒りでもない、“尊敬”が滲んでいた。
弟・響の才能と成功に込めた「代償としての希望」
ピアニストとしてステージに立つ弟を見て、兄は何を思ったのか?
それは「自分がなれなかったもう一つの人生」だった。
そして同時に、自分たちの過去を“贖う存在”としての希望でもあった。
ただし、その希望に水を差したのが、実父・倉田一郎。
ヤクザあがりで、息子の存在をネタに母親をゆすり、さらにこう言い放つ。
「耳が聞こえなくなったのは俺がぶん殴ったからだ。今度は右も聞こえなくしてやる」
それはつまり、「お前たちは一生、俺の支配下にある」という宣言だ。
響がどれだけ成功しようが、父の存在が彼を潰す。
その現実に、純一は――動いた。
殺意は計画的ではなかった。
でも、彼の中では“最も直線的な救いの手段”だった。
殴っても殺しても、自分が傷つくことは怖くない。
でも、弟の未来が奪われることだけは、「絶対に許せなかった」。
殺意の正体は「怒り」ではなく「祈り」だったのか
ここで見逃してはいけないのは、彼が最後に放ったこの一言だ。
「俺バカだからさ。他の方法なんてなんも思いつかなくてさ」
怒りじゃない。
この言葉には、「誰かの役に立ちたかった」という切なる祈りが宿っている。
自分が負の連鎖を断ち切り、弟を守れたなら、それだけでいい。
赦されなくてもいい。それが彼の“正義”だった。
この物語が提示したのは、法の外側にあるもう一つの倫理だ。
人を殺してしまった彼が、その瞬間だけは“誰かのために”生きた。
「そんな正義は間違ってる」と言いたい気持ちはわかる。
でも同時に、「間違いだとしても美しかった」と感じてしまう自分も、確かにいる。
このドラマは、善と悪のラベルを貼ることを許さない。
ただ、その狭間で、人の心が何に動かされ、何に傷つき、何を救いと感じるのかを丁寧に描いた。
だからこの第5話は、「ただの殺人事件」ではない。
それは、“誰かを救うための、最も悲しいラブストーリー”だった。
「アンガーハンマー」という伏線が語る、双子の断絶と接続
たった一つのアカウント名が、物語の深層を撃ち抜いた。
「アンガーハンマー」――怒りと破壊を意味するその名の下で、兄・純一は弟・響のSNSに誹謗中傷を繰り返していた。
だがそれは、ただのネットリンチとは根本的に違う。
誹謗中傷コメントに隠された“純一の叫び”
誹謗中傷の言葉には、毒がある。
けれど、純一の投稿には、もっと違うものがにじみ出ていた。
「死ね」「親ガチャ成功野郎」――そう罵りながらも、彼は毎回、弟の演奏動画をフルで見ていたんだ。
アンチがファンであるという矛盾。
否、それは「愛しさ」と「嫉妬」が混ざり合った兄の歪んだ表現だった。
純一は、響が努力で勝ち取った世界を「運」だと信じたかった。
そうしないと、自分の人生の惨めさに“意味”がなくなるからだ。
でも、演奏を聴いた瞬間に、それは崩壊する。
「あいつは努力してた」
その事実を否定できずに、強く当たるしかなかった。
「アンガーハンマー」は、嫉妬ではなく、自傷だった。
再会の瞬間に芽生えた感情は、憎しみではなく“羨望”
再会の場面。
ふたりは最初、軽口を叩き合う。
でも、その裏で交差していた感情は、おそらく観ていた誰もが気づいたはずだ。
「兄が、弟に会えて本当にうれしかった」
殺された父が吐いた「お前の邪魔者は消した」という留守電。
この一言に「憎しみ」が感じられなかったのは、演出の妙だ。
むしろそこにあったのは、“弟に自分を許してもらいたい”という願いだった。
さらに重要なのは、純一が響の演奏曲をスマホにダウンロードしていたという事実。
それは感動の証だ。
心が動かなければ、そんな行動はしない。
つまり、彼は響に救われていた。
皮肉だが、音楽家・響の演奏が、兄を殺意へと導いた。
だがそれは逆に言えば、「誰も守ってくれなかった自分が、弟だけは守りたかった」という、自己救済の最終手段だったのかもしれない。
「アンガーハンマー」は破壊の名を借りた、兄弟再生の序章だった。
このアカウントに気づいた瞬間、ただのサスペンスは、人間の心の断面図へと変わった。
そしてその断面は、痛ましいほどに美しかった。
SSBCが描く“追跡者”たちの心情変化も見逃すな
この物語の骨子は「犯人を追う刑事たち」だ。
けれど、今作の警察たちはただのロジックマシーンじゃない。
SSBCの面々は、事件を“人間のドラマ”として受け止める感情を持っている。
八重樫(遠藤憲一)の兄との対比が描く「鏡としての双子」
まず特筆すべきは、捜査一課長・八重樫の描き方だ。
今回のキーワードの一つは「双子」だが、それを象徴的に見せたのが、八重樫自身も“二卵性双生児”だったという演出だ。
彼にはマグロをさばく寿司職人の兄がいて、性格も仕事も正反対。
にもかかわらず、互いを認め合っている姿が、物語の裏テーマを照射していた。
そう、“違ってもいい”、でも“どこかでつながっている”。
そんな彼が、事件の核心に迫るとき、語った一言が刺さる。
「動機が知りたい。双子にしか分からない何かがある。俺、分かるんだよ」
これは完全に彼の“感情”から出たセリフだ。
論理ではなく、感覚。
SSBCのチームが優れているのは、この“感情による補完”を否定しないところにある。
警察側の感情移入が捜査を“物語”に変えた瞬間
通常の刑事ドラマでは、刑事たちは常に“感情を切り離す”よう求められる。
だが「大追跡」では、感情を抱くことそのものが捜査の起爆剤となる。
伊垣や青柳が響とその母に感じた違和感。
それは、言葉で語られない“空気”を読む力だった。
「なんか変だ」という直感から、物語は核心へ進む。
特に象徴的だったのは、八重樫が自らの兄弟関係を重ねて、響と純一を理解しようとした姿。
警察官としての「職務」ではなく、人間としての「共鳴」だった。
この姿勢が、響や純一という“加害者”であり“被害者”でもある存在を、断罪するのではなく「理解しようとする物語」へと昇華させた。
刑事たちの人間味が、物語に深みを与えている。
SSBCというチームが“ただのプロファイリング集団”で終わっていない理由は、ここにある。
冷静な分析と、感情の揺らぎ。
その両方を持つ彼らこそ、“現代の追跡者”なのだ。
響のSNS炎上が突きつける“社会の非情さ”
人を殺したわけでも、罪を犯したわけでもない。
それなのに、SNSで叩かれ、人格を踏みにじられる。
第5話は、現代社会の「もう一つの暴力」を鋭く描いた。
殺人と無関係な弟が叩かれる理不尽
事件の報道後、響のSNSが炎上する。
「ヤクザの息子」「双子の兄が殺人犯」――そんな肩書きだけで、人々は容赦なく叩きにかかる。
だが彼は何もしていない。
むしろ、幼い頃に引き裂かれた兄に会い、再会を喜んだだけだった。
社会は真相を見ない。
誰かを裁きたいだけだ。
“関係がある”というだけで、容易に“共犯者”のレッテルが貼られる。
これはドラマの中だけの話ではない。
現実でも、何かしら「加害者の身内」として報道された人が、私刑的に炎上するケースは数え切れない。
その本質は「憂さ晴らし」であり、「正義の名を借りた集団リンチ」だ。
第5話は、この非情な社会構造に静かに警鐘を鳴らしていた。
それでも彼がピアノを弾く理由に涙する
そんな中でも、響はSNSにこう綴る。
「炎上しても、自分の音楽を誰かに届けたい。もう一度、兄に聴いてもらいたいから」
この一文で、涙が溢れた。
“赦し”を求めているのではない。“届く”ことを信じているのだ。
ピアノは、響にとって武器ではなく、唯一の祈りだ。
過去に引き裂かれ、再会できたと思った兄が、再び遠くに行ってしまう。
その悲しみに打ちひしがれながらも、響は「それでも弾く」と決めた。
その姿は、もはや演者ではない。
彼自身が“演奏”そのものだった。
SNSの炎上は、声の暴力だ。
でも、その暴力に屈することなく、音で応えるという彼の選択に、人間の“強さ”と“優しさ”を見た。
彼が再びピアノに向かうその姿は、「過去」と「怒り」に勝つ唯一の方法を提示していた。
それは、音を鳴らし続けること。
このシーンが放つメッセージは重い。
人は過去を選べない。
けれど、未来に何を届けるかは、自分で決められる。
なぜ「大追跡」は感情をここまで深く揺さぶるのか
刑事ドラマは数あれど、「大追跡」は群を抜いて異質だ。
派手な演出もなければ、謎解きだけがメインでもない。
それでも、視聴後に心がずしんと重くなる。
構造の巧さ:事件・親子・双子・社会の四重構造
この回の脚本が巧妙なのは、「一つの事件」を通して複数の軸を並列に走らせていることだ。
- 事件の構造:誰が殺したか、なぜ殺したか
- 家族の構造:親と子、兄と弟、育ての親と実の親
- 双子という鏡:異なる環境が生んだ“同じ魂”の分岐
- 社会のまなざし:炎上・差別・見えない暴力
これらがすべてひとつの事件に凝縮されている。
それが、視聴者の“心の複数箇所”を同時に揺らす。
単なる殺人事件じゃない。
この構造を読み解けば、視聴者自身の中にも「怒り」「悲しみ」「羨望」「赦し」が渦巻くのがわかる。
人間ドラマとしての完成度が高すぎる。
そして、それを脚本が理屈じゃなく感情で語っている。
視聴者が“正義とは何か”を問われる作劇の仕掛け
この回のラスト、「兄が弟のために殺した」という構図に、視聴者の心は揺れる。
殺人は罪だ。誰が何と言おうと、正当化はできない。
けれど、“だからこそ”葛藤が生まれる。
純一の「俺、バカだからさ」という言葉は、論理を放棄してるようでいて、感情の“正義”に正直すぎる。
法では裁かれるかもしれない。
でも、視聴者の多くはこう思ったはずだ。
「でも、誰かが響を守らなきゃいけなかったんじゃないか」
この“モヤモヤ”を、視聴者に預けたまま物語は幕を下ろす。
決着を与えない。
それは、視聴者自身が「正義とは何か」を考える余白を残すためだ。
そしてこの構造が、エンタメを“体験”に変える。
「観た」ではなく、「心を揺さぶられた」になる。
それが、「大追跡」の本質。
このドラマは、事件を追ってるんじゃない。
“人間”を追跡しているんだ。
八重樫と純一――“もう一つの双子”が語る未完の物語
この第5話、実は一見関係なさそうな“サイドの会話”が物語の心臓部とリンクしている。
そう、八重樫(遠藤憲一)と彼の兄、寿司職人の雅彦の存在だ。
ふざけたように見える“マグロの解体ショー”のシーン、あれこそが脚本家の仕掛けた伏線だった。
「違っても、繋がってる」ことを体現する兄弟
雅彦は八重樫と正反対の人間だ。
穏やかで、柔らかく、寿司を握る男。
一方、弟は警察官。厳しさと責任の中で生きている。
正反対だが、“否定し合っていない”。
むしろ、お互いを誇りに思っているのが会話から伝わってくる。
この兄弟が描かれたことで、純一と響の“歪んだ双子”とのコントラストが際立った。
「環境が違えば、こんな未来もあったかもしれない」
そんな“IFの物語”を静かに提示する装置だった。
そしてもうひとつ――八重樫は言っていた。
「俺、分かるんだよ。双子にしか分からない何かがある」
これは、ただの捜査官の勘ではない。
実体験として、“双子の絆の不思議さ”を知っている男の言葉。
理屈じゃない、体に刻み込まれた感覚が、捜査を越えて物語に染み出していた。
語られない“記憶の差”が生む切なさ
兄・純一は、弟・響のことをずっと覚えていた。
でも響は、思い出していなかった。
これは、重い。
純一の中には、響との時間が“かけがえのない過去”として生きていた。
だが、響の中では、それは“なかったこと”になっていた。
この記憶のズレが、彼らを決定的に引き離していた。
八重樫兄弟との違いはここにある。
マグロをさばこうが、犯人を追い詰めようが、彼らの間には「確かな記憶」がある。
だから、ぶつかっても失わない。
純一と響には、その記憶が途切れていた。
“もう一度繋がろうとした瞬間に、過去が牙を剥いた”。
悲劇は、再会の直後に起きたのではない。
再会が叶ったこと自体が、引き金だったんだ。
この物語、もし響が覚えていて、「おかえり」って言えていたら――。
もし純一が、「俺のこと覚えてる?」と笑えたなら――。
結末は、違っていたかもしれない。
第5話には、“交差しなかった未来たちの影”が静かに重なっていた。
それを教えてくれたのが、八重樫の存在。
物語の中で最も“描かれなかった大事な部分”を、無言で浮かび上がらせたのは、彼だった。
「大追跡 第5話」双子の物語が問いかけた正義と赦しのまとめ
一人の男が、もう一人の男を殺した。
それだけ聞けば、ただの殺人事件だ。
けれど「大追跡」第5話が描いたのは、その奥にある“人が人を想う物語”だった。
“悪い父親を殺す”ことは本当に“救い”なのか
倉田一郎という人間は、父親であることを放棄し、暴力と恐喝でしか他者と関われない人間だった。
そんな父を、純一は「守るために」殺した。
守った相手は、自分自身ではなく、弟の響だった。
これは「救済」としての殺人だ。
法的には裁かれる。
でもその動機には、どうしようもなく“人間的な正しさ”が漂っていた。
人を殺してしまうという絶対的な罪。
それでも、その罪の裏側にある感情を否定できない。
感情のグレーゾーンに深く入り込み、視聴者の倫理を揺さぶる構成。
この揺らぎこそが、「大追跡」の美しさであり、恐ろしさでもある。
ピアノの音が語る、もう一つの「無言の謝罪」
弟・響は、兄の犯罪を知りながらも、怒りをぶつけなかった。
彼はSNSでこう綴る。
「炎上している。でも僕は、もう一度あの人に聴いてもらいたい。音で伝えたいことがある」
そこにあったのは、言葉では語りきれない“愛情”と“痛み”だった。
兄は、響を守るために罪を背負った。
弟は、その罪に対して、怒ることよりも、音楽で応えることを選んだ。
これは、法廷ではなく心の中で行われた赦しだ。
兄が命を懸けて切り開いた未来を、弟が音で繋ぐ。
その関係性にこそ、“家族”という言葉の本当の意味があるように思えた。
誰が悪かったのか。
何が正しかったのか。
簡単に答えは出せない。
だからこそ、「大追跡」は忘れられない。
物語を追いかけたあと、自分自身の“感情”を追跡させられる。
それがこの第5話だった。
- 双子の兄・純一が弟を守るため父を殺害
- 「アンガーハンマー」の伏線が兄弟の断絶と再接続を象徴
- 八重樫自身も双子として事件に感情移入
- SNS炎上で描かれる現代社会の“二次加害”
- 響はピアノで兄に祈りを届けようとする
- 事件・家族・社会・倫理が交差する構造の妙
- 「正義」とは何か、視聴者に委ねられる結末
- 八重樫兄弟の対比がもう一つの未来を示唆

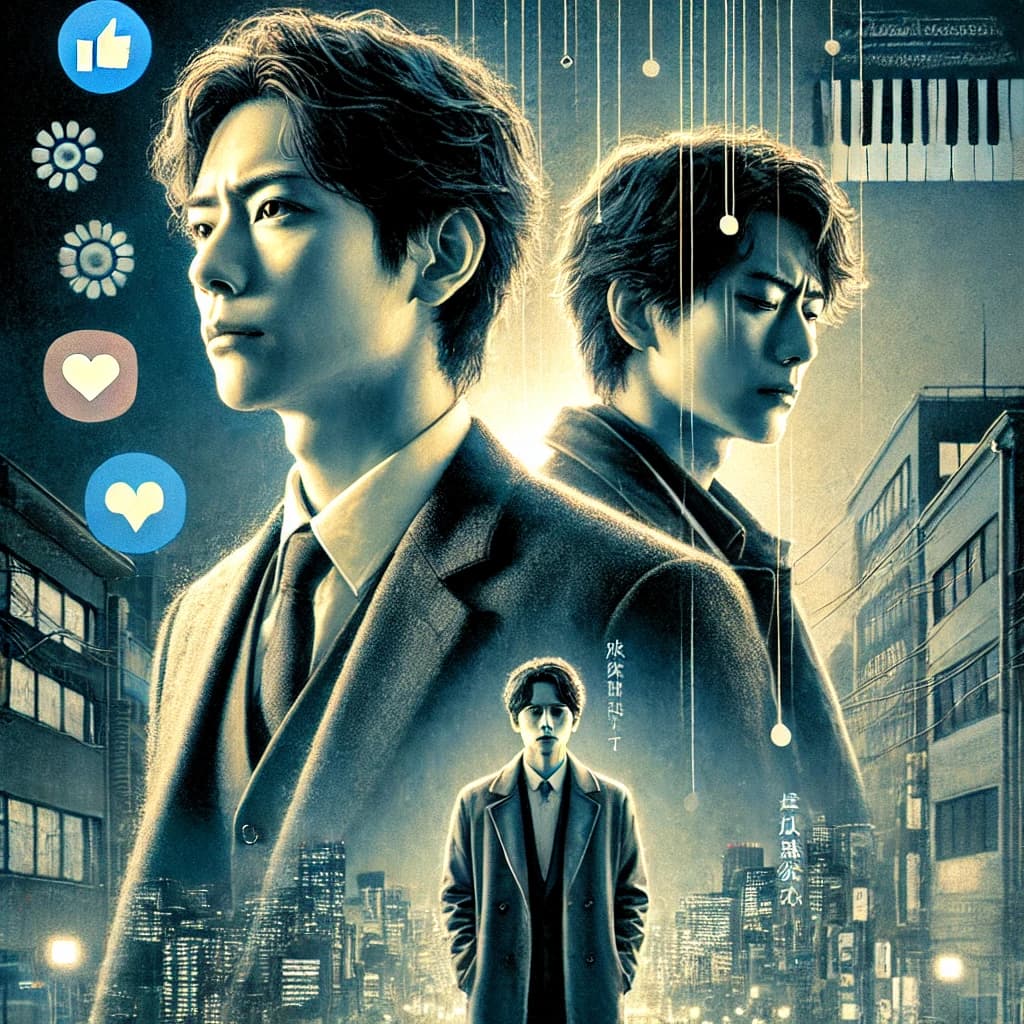



コメント