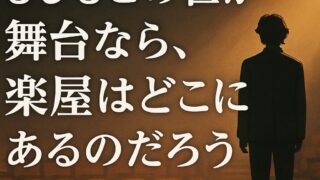もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう
もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう 「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」最終話ネタバレ考察—舞台と人生の境界が消える瞬間
11話にわたって描かれた『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』がついに幕を閉じた。三谷幸喜が描く“演劇的世界”は、芝居と現実の境界を曖昧にしながら、登場人物たちの「生き方」そのものを舞台に変えていく。久部(三谷幸喜作品らしい“愚かで愛しい男”)とリカ、樹里、蓬莱。彼らが抱えたのは、成功や夢の物語ではなく、「何を失っても立ち続ける理由」だった。この記事では、最終話の展開を軸に、“舞台”という比喩の中で三谷が描いた人間の業と希望を、構造と感情の両面から読み解いていく。