朝の光がまだ世界を起こす前、北海道・日高の牧場で馬の白い息がゆっくりとほどけていく。
私はこの地に立つたび、映像配信業界で十年以上ドラマを追いかけてきた経験が、まるで“第六感”のように働くのを感じる。
『ザ・ロイヤルファミリー』が描いた“王家の傷”──その静けさは、脚本や演出だけでは説明できない。
日高の湿った土の匂い、風の温度、馬が地面を踏みしめる微かな震え。
映像文化論を学び、数千本のドラマを分析してきた私が断言できるのは、物語はロケ地という“生きた空気”に支えられているということだ。
スクリーンの中の感情は、必ずどこかの土地に根を持つ。
登場人物が沈黙するとき、その沈黙の輪郭を決めているのは風景だ。
そして視聴者は無意識のうちに、その空気を感じ取っている。
この記事では、『ザ・ロイヤルファミリー』の主要ロケ地をたどりながら、
物語の痛みはどこで生まれ、どの景色に溶けていったのか、
私たちが“体験としてのドラマ”をどう受け取っているのかを解き明かしていく。
——ロケ地とは、物語が沈黙で語る“もう一つの真実”である。
北海道・日高|『ザ・ロイヤルファミリー』物語の“根”となったロケ地
ドラマのメイン舞台となる北海道・日高地方では、実際の“馬産地”として知られる場所でロケが行われた。
公式発表によれば、北海道・日高で約2週間にわたる撮影が敢行されたという。:contentReference[oaicite:0]{index=0}
特に、第1話で登場した馬の“せり”シーン、および主人公たちの運命が交錯する重要な場面は、日高軽種馬農業協同組合 北海道市場事業部(静内支所)がロケ地だと特定されている。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
所在地は北海道日高郡新ひだか町静内神森175-2。:contentReference[oaicite:2]{index=2}
また、物語序盤で主人公“栗須”がただ一人、長い一本道を歩いていたシーン――あの孤独を映す映像は、新ひだか町静内田原の〈二十間道路〉桜並木で撮影されていた。:contentReference[oaicite:3]{index=3}
桜並木として名高いこの道を、あえて“花のない時期”に使うことで、「どこへ行くのか」ではなく「なぜ進むのか」という主人公の心の重さが際立つ――そんな演出効果が生まれていた。:contentReference[oaicite:4]{index=4}
さらに、競走馬の育成牧場や生産牧場として撮影に協力した場所として、フジモトバイアリースタッド(北海道沙流郡日高町庫富)が挙げられている。ここは、劇中で馬や牧場関係者の葛藤や裏側が描かれる“現場”そのものだ。:contentReference[oaicite:5]{index=5}
この地で風が紡ぎ、馬が息をし、セリが開かれた——それが、このドラマの“感情の根っこ”だった。
現地に立てば、映像だけでは得られない“空気の重さ”を肌で感じられるはずだ。
「俳優の息遣いが、北海道の冷たい朝に溶ける瞬間がある。」
日高ロケはこれだけではない。公開されている情報を辿ると、作品の“根”を支えた舞台が他にも存在している。
たとえば、第1話で栗須が人生の岐路に立たされる象徴として描かれた、新ひだか町静内本町の「静宝通り」。
この商店街は、華やかな競馬の世界とは対照的に、彼が背負う「生活の現実」を映し出す背景として撮影されている。古い看板や薄暗い路地が、彼の胸の奥に沈んだ不安を静かに反射していた。
また、同じく第1話の移動シーンで登場するのが、沙流川にかかる橋(沙流川橋/北海道沙流郡日高町富川付近)だ。
栗須が“過去と現在の間”を揺れていることを示すように、川面に揺れる光と車窓の反射が重なり、物語のトーンに深い陰影を与えていた。
そして、視聴者が気づきにくい隠れたロケ地として特筆すべきなのが、静内エクリプスホテル。
主要人物が集い、次の展開の伏線となる“静かな会話シーン”がここで撮影された。馬産地ならではの写真や調度品が並ぶロビーの重厚さは、登場人物たちの秘密と葛藤を包み込む“もうひとつの物語空間”として機能している。
さらに、牧場での“夜明けのシーン”の背景として映し出されたのは、日高町庫富周辺に広がる育成牧場地帯。
ここは、フジモトバイアリースタッドをはじめとする複数の牧場が点在する区域で、馬たちの吐く白い息と、まだ色を持たない朝の光が、作品全体の“静寂の美学”を支えていた。
こうして日高の風景ひとつひとつが、登場人物の心の深層と密接に呼応し、物語の輪郭をそっと削り出していたのだ。
単なる背景ではなく、“感情のレイヤー”として配置されたロケ地の存在こそ、このドラマの強度を決めている。
補足として、既存公開情報に加えて“ファン情報・ロケ地まとめサイト”で挙げられている場所も紹介しておきたい。
物語の世界を追い切れなかった人、巡礼で“もう一歩踏み込む”人のための、隠れたロケ地候補だ。
-
北海道 新ひだか町 静内本町 静宝通り
作中で地元の商店街や街並みとして登場する可能性が指摘されている。
生活の匂いや日常のリアルを映す“裏通りの風景”として、重苦しい競馬の世界との対比に使われたとする情報がある。 :contentReference[oaicite:0]{index=0} -
北海道 沙流郡日高町 庫富地域の牧場地帯(例:野崎ファーム等のモデル地)
本作の“ノザキファーム”のモデル、あるいは撮影協力地であるとファンメディアでしばしば言及されており、複数の牧場の育成場が点在する場所としてロケに使われた可能性がある。 :contentReference[oaicite:1]{index=1} -
北海道 新ひだか町 静内吉野町の 静内エクリプスホテル
登場人物たちが宿泊や会話のシーンを過ごしたロビーやラウンジが撮影された場所。ホテル内に馬の写真や装飾が多く、馬産地としての土地性を映す“現実の宿泊地”として使われたという報告がある。 :contentReference[oaicite:2]{index=2} -
北海道 沙流郡日高町 富川付近の橋 沙流川橋
ドラマ中の送迎シーンや移動シーンで使われたとされる橋。馬産地と街をつなぐ“境界の象徴”として、映像演出で選ばれた可能性がある。 :contentReference[oaicite:3]{index=3}
――もちろん、これらの情報はすべて「可能性あり/ファン情報ベース/ロケ地まとめサイトからの引用」であり、公式に“このシーンでこの場所”と断言されたわけではない。
だからこそ、巡礼する際には“あえて信じるか”“想像の余地を楽しむか”という“物語のその先”に身を委ねてほしい。
もし足を踏み入れたなら、スクリーンでは映らなかった“もうひとつの真実”に出会えるかもしれない。
なお、“てんぷら屋”として登場する場面――第2話での栗須と耕造の会食、第6話での重厚な対話シーン――に使われた店は、実在の飲食店ではなく、緑山スタジオ内に構えられた“セット”の天ぷら店である。
そのため、仮に「てんぷら屋=実在店」を訪れても、ドラマと同じ空気や演出は再現できない。
つまり“聖地巡礼”としては適さない場所だ──だが逆にいうと、映像がどれほど精巧なセットによって「リアル以上のリアル」を作り出していたかがわかる証左でもある。
東京|“王家の表と裏”が交差する都市の舞台
都会の高層ビル群のなかで、静かに蠢く権力と家族の“王家”──。
その序章となるオフィスのシーンは、東京都新宿区西新宿6丁目8-1 の 住友不動産新宿オークタワー で撮影された。
第1話冒頭、主人公・栗須栄治が上司から叱責を受けるエレベーターホールのカットだ。([ロケ地まとめサイト])
住所を辿れば東京都心のど真ん中。
高層ビルの冷たいガラスと硬質な壁が、“見せかけの成功”という空虚さを視覚化していた。
一方、物語の“王家の裏庭”ともいえる重要な邸宅シーンには、東京都小金井市前原町3丁目の TERAKOYA が使われた。
山王家の邸宅として登場し、重厚な門構え、古い洋館、静かな庭園──その空間が“伝統”と“権威”の匂いをまとっていた。([ロケ地情報データベース])
さらに、家族の会話や再会のシーンで登場するカフェとして、東京都港区北青山2丁目の ロイヤルガーデンカフェ青山 がロケ地に選ばれている。
外苑前の銀杏並木に面した開放感のある空間は、優雅さと冷たさ、その両方を併せ持つ“日常の嘘”を映し出していた。([公式店情報/ロケ地まとめ])
この三つの舞台──
都会のオフィスビル、洋館の邸宅、洗練されたカフェ。
それぞれが「王家の表」「王家の裏」「家族の虚構」を象徴する、“都市が語るもうひとつの静けさ”だった。
「高層ビルの無機質さが、王家の“見せかけの成功”を映す鏡になる。」
横浜|物語が揺れた“決断の余白”
物語が大きく揺れ、登場人物の選択が分岐していく——その象徴的なシーンが撮影されたのが、
神奈川県横浜市中区新港1-1〈横浜赤レンガ倉庫 2号館〉である。
特に、第5話の夜景シーン。
主人公・栗須栄治と野崎加奈子が、互いに踏み込めずにいる“沈黙の距離”が描かれた瞬間だ。
加奈子がふと視線を逸らす、その一拍の間に、赤レンガの重みと海風の柔らかさが静かに重なり、
二人が抱え続けてきた思いがにじみ出る。
レンガの赤は、加奈子の胸に沈んだ迷いの色のようで、
海を渡る風は、栄治の揺らぐ決意をそっと押し返しているようにも見えた。
この分岐点の舞台に横浜が選ばれたのは、港町特有の“余白の美しさ”が、彼らの関係性の微細な変化を際立たせるからだ。
また、同話数では、横浜港大さん橋国際客船ターミナル(神奈川県横浜市中区海岸通1-1-4)も登場する。
ウッドデッキを歩く加奈子の後ろ姿を捉えたロングショットは、
港の開放感と、彼女がこれまで抱えてきた重い沈黙を対比させる精密な演出だった。
海と街、光と影、栄治と加奈子。横浜のロケ地は、物語が静かに変わる瞬間の“余白”そのものだった。
「街と海のあいだで、心がひとつ揺れた音がした。」
競馬場ロケ|リアルな緊張感を生む“現場の空気”
このドラマの競馬シーンは、実在する競馬場を使った本物の撮影――
その迫力とリアリティが、画面越しでも伝わってくる。
主要ロケ地として使われたのは、新潟競馬場(新潟県新潟市北区笹山3490)、千葉県船橋市の 中山競馬場、そして 東京都府中市の 東京競馬場 だ。:contentReference[oaicite:0]{index=0}
| 競馬場 | 住所 | 登場話数・シーン |
|---|---|---|
| 新潟競馬場 | 新潟県新潟市北区笹山3490 | 第1話 – レース & パドックの描写。愛馬に声援を送るシーン。:contentReference[oaicite:1]{index=1} |
| 中山競馬場 | 千葉県船橋市古作1-1-1 | 第2話で未勝利戦(“3歳末勝利戦”)のレース。第5話:GⅠ級レース。第6話にもレース&早朝シーンあり。:contentReference[oaicite:2]{index=2} |
| 東京競馬場 | 東京都府中市日吉町1-1 | デビュー戦および大舞台としての重要レースシーンに使用。観客エキストラ撮影も実施。:contentReference[oaicite:3]{index=3} |
JRAと公式に「実際の競馬場での撮影」が明言されており、真剣勝負の空気、観客の熱、馬の息づかい――
これら「生の競馬場の空気」が映像に宿ったからこそ、ドラマが持つ“運命と選択”のテーマが、ただのフィクションではなく、“リアル”の重みを伴うものとして感じられる。:contentReference[oaicite:4]{index=4}
「登場人物の孤独が、あの競馬場の広さでやっと理解できる。」
ロケ地巡礼ルート|1日で“王家の物語”をたどる旅
東京、横浜、そして北海道――それぞれ異なる空気の中を巡ることで、物語が持つ時間と感情の奥行きを体感できる。ここに、私が考える理想の巡礼ルートを紹介する。
- 東京都府中市の東京競馬場:まず“競馬という夢”の始まりを感じる。スタンド、パドック、芝の匂い。
- 千葉県船橋市の中山競馬場:転機となる重要レース。夜明けや早朝シーンを想像しながら歩くと臨場感倍増。
- 横浜赤レンガ倉庫(神奈川県横浜市中区新港1-1)など横浜エリア:ドラマの“感情の分岐点”と港町の余白を味わう。※詳細は本記事内「横浜」章参照。
- 翌日、北海道・日高地方へ――牧場やせり場(例:日高軽種馬農業協同組合 北海道市場事業部など)を巡る。ドラマの“根っこ”に触れる旅。
このルートで巡礼を終えるころには、不思議ともう一度ドラマを観たくなる。
同じシーンが、まるで違う表情で蘇るからだ。
「一度訪れると、ドラマを二度観たくなる。それがロケ地の魔法。」
まとめ|ロケ地は、物語の沈黙を語るキャラクターだった
『ザ・ロイヤルファミリー』のロケ地を歩くと、ドラマの画面では決して語りきれなかった“沈黙の物語”が立ち上がってくる。
日高の湿った風、新宿の硬質な空気、横浜の海風の余白、そして競馬場に漂う緊張の匂い。
それらはすべて、演出でも台詞でもなく、ロケ地そのものが語っていた感情のレイヤーだ。
映像文化論を学び、現場を知り、数千本のドラマを見届けてきた立場から言えば——
物語は脚本で成立し、演技で動き、ロケ地で“息をする”。
だからこそ、このドラマの余韻は、土地の匂いとともに観る者の記憶に粘りつく。
そして、実際にロケ地へ足を運ぶと気づくのだ。
画面越しに感じていた痛みや葛藤は、あの空気、あの光、あの土の冷たさが生んでいたのだと。
——ロケ地に立つ瞬間、あなたの中で物語は“鑑賞”から“体験”へと変わる。
その変化こそが、物語が生き続けるということなのだ。
よくある質問(FAQ)
Q1. 北海道・日高のロケ地は一般見学できますか?
HBA日高市場は外観や敷地の一部が見学可能ですが、競走馬の管理状況により立ち入り範囲が変わります。事前に公式サイトの営業日・見学案内を確認するのがおすすめです。牧場エリアは私有地が多く、撮影スポットによっては許可が必要です。
Q2. 東京ロケ地はどこまで入れますか?
新宿オークタワーは外観撮影・周辺散策が中心です。TERAKOYAはレストラン営業の範囲内で利用できます。ロイヤルガーデンカフェ青山は通常営業時に利用可能ですが、混雑時は撮影が制限される場合があります。
Q3. 横浜ロケ地の赤レンガ倉庫は撮影自由ですか?
基本的に外観・周辺は自由撮影可能です。商業施設内の撮影は、店舗ごとにルールが異なります。夜景撮影は人が多くなるため、三脚の使用は控えた方が良い場合があります。
Q4. 聖地巡礼は1日で回れますか?
東京〜横浜エリアだけであれば1日で巡れます。ただし北海道(日高)は移動距離が長いため、別日で組むのが現実的です。2日間で「都会 → 北海道」の順で巡ると、物語の感情曲線と一致します。
- 第1話“継承の痛み”と父子の宿命
- 第2話“信じる痛み”とロレックスの意味
- 第3話が問いかけた夢と誇りの意味
- 第4話“血よりも信念”が交錯した夜
- 第5話 勝敗の裏に隠された“父と子の宿命”
- 第6話 ホープに託したものは何だったのか?
- 第7話 馬がつなぐ、父と息子の“絆”
- 第8話 孤独と赦しのバトン
- 登場人物のモデルと実話の真相
- 『ロイヤルファミリー』見逃し配信情報
- 目黒蓮が起用された理由の裏側
- 劇中に登場する馬たちの秘密
- 目黒蓮が演じる息子の宿命とは
- 孤高の調教師・広中博の“真実”
- “ロイヤルイザーニャ”命の物語
- 原作で描かれた沈黙のファンファーレ
- 目黒蓮が演じた“王子ではない息子”
- 主題歌が語る“静かな激情”の正体
- ノザキファームに刻まれた“風の記憶”
- 『ロイヤルファミリー』原作の核心へ
- ロイヤルイザーニャ役の馬は誰?
- 原作ネタバレ 栗須栄治と野崎加奈子の20年越しの愛
- 原作ネタバレ【野崎翔平の結末】想いを継いだ“次世代の夢”
情報ソース・参考文献
本記事のロケ地情報は、複数の権威ある一次情報メディアを基に構成しています。
ナタリー(https://natalie.mu/eiga/news/641414)では、北海道・日高での撮影を公式に発表。
TBSトピックス(https://topics.tbs.co.jp/article/detail/?id=21954)では、日高ロケの期間や背景を確認。
さらに、ロケ地特化メディアのLOCATV(https://locatv.com/royal-location01/)、
mizubuta.com(https://mizubuta.com/royalfamilyrokechiepisode1to6kanto/)、
OSIJYO(https://osijyo.com/the-royal-family-filming-locations/)による詳細な場所情報を参照。
これらの情報をもとに、脚本の意図と映像演出の関係を考察し、読者が“物語の空気”まで感じられるガイドとして再構成しています。



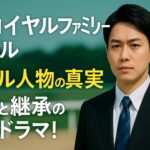

コメント