第5話「みんなの夢」。静かに積み上げられてきた嘘と懺悔が、一気に崩れ落ちた夜だった。
博士=岡本が「犯人ではなく共犯者」だと示唆された瞬間、物語は復讐劇の表層を越えて“人間の赦し”そのものを問う領域へと進んだ。
一方で、委員長の赤く染まる「知らなかったでしょ」という視線。あれは罪悪感ではなく、長い間押し殺してきた怒りの発露だったのかもしれない。
そして、「ちょんまげ」にだけ向けられた博士の“許し”。その優しさが、皮肉にも次の死を招く導火線となる。
この考察では、博士の共犯関係・委員長の動機・ビデオテープの意味、そして“夢”というテーマが描く人間の業を読み解いていく。
- 『良いこと悪いこと』第5話で描かれた博士・委員長・ちょんまげの心理構造と罪の連鎖
- タイムカプセルのビデオテープや「エラー発生」が示す“赦せない過去”の意味
- 夢・記憶・赦しが交錯する人間ドラマの核心と、観る者に突きつける「自分の中の悪」
博士が共犯者である理由──記憶喪失の裏に隠された「赦しの拒絶」
彼は犯人ではなかった。だが、無実でもなかった。
『良いこと悪いこと』第5話で描かれた博士=岡本=今國の存在は、事件の中心にいながら「手を汚していない」という矛盾を孕んでいる。
博士の行動の根底には、“赦されることへの拒絶”がある。つまり、彼にとって「忘れられること」は、死よりも重い罪だったのだ。
\博士の沈黙の裏側を、映像で確かめてほしい/
>>>今すぐ『良いこと悪いこと』第5話を観る
/あの“記憶の欠片”が、すべての始まりだ。\
博士=岡本=今國の三重構造が示す“もう一人の加害者”の存在
博士は、名前を三度変えてきた人物だ。岡本としての“過去”、今國としての“現在”、そして博士という“観測者”の顔。
この三層構造は、彼が自分自身をも分裂させながら、罪と赦しの物語を観察している存在であることを示している。
掲示板「鷹里小の森」での書き込み──「キングたちには会いたくない。でも、ちょんまげになら会ってもいいよ」。この一文に、博士の心の断層がすべて刻まれている。
彼は、キングたちに「忘れられたこと」を決して許せなかった。だが、唯一自分を覚えていた“ちょんまげ”には会ってもいいと思った。
それはつまり、博士自身が「赦されたい」と「赦したくない」を同時に抱えた存在だったということだ。
記憶喪失という設定も象徴的だ。小学6年生までの記憶で止まった時間──そこから進めない彼は、“あの頃”を終わらせることができないまま、いまを生きている。
この停滞が、共犯者としての彼を生み出した。真犯人ではない。しかし、誰よりも事件の根に近い場所で、復讐という物語の装置を動かしている存在だ。
黒塗りの卒アルが象徴する「忘れられる痛み」と復讐の動機
博士がタイムカプセルに入れたのは、6人の顔を黒く塗りつぶした卒業アルバムだった。そこには怒りでも怨念でもなく、“記憶を奪われた者の祈り”が封じられていた。
「思い出してくれ」と叫ぶ代わりに、彼は“思い出せないように”加工した。これは彼なりの抵抗であり、同時に愛の形でもあった。
しかし、真犯人はそのアルバムを“復讐の証拠”として再利用した。博士が望んだのは記憶の回復だったのに、真犯人はそこに「いじめの復讐」という新たな物語を上書きした。
だからこそ、博士は共犯者なのだ。彼は犯行計画に加担したのではなく、物語の構造そのものを提供してしまった。
人が罪を犯すとき、必ず“誰かを思い出す”瞬間がある。博士の場合、それは「忘れられた過去」を思い出させるための罪だった。
だが、その“正義”が歪んだ形で利用されたとき、彼は共犯者として沈黙するしかなかった。
記憶喪失の裏にあるのは、都合の良い設定ではなく、赦しと赦されなさの境界に立つ男の痛みだ。
「君たちが僕を忘れたことを、僕は忘れない」──その言葉こそが、博士が生き続ける理由であり、彼を共犯者にした呪いそのものだった。
- 第1話“正義”が腐る夜の真実
- 第2話 届かない謝罪の行方
- 第3話 絶交が残した痛みとは
- 第4話 忘れられた7人目の闇
- 第5話 博士=堀遼太説とイマクニの正体
- 第5話までの考察まとめ
- 第6話 委員長の復讐と園子が背負う“無実”
- 第7話 友情という名の罪は、誰に渡されたのか
- 第8話 “もうひとりのドの子”瀬戸紫苑の真実と、東雲に隠された「罪の継承」
- 子役が映す純粋と残酷の境界
- 主題歌“アゲハ蝶”が照らす罪
- 「森のくまさん」の呪い考察
- 黒塗りの6人に隠された真実
- 原作が暴く“子どもの罪”とは
- 正義と悪が交差する心理考察
- 委員長・紗季の壊れた正義とは
- 消える子どもたちの真相とは
- 東雲の沈黙に隠された真実
- 漫画版との比較から真意を読み解く
- キングは二重人格か?
- 剛力彩芽演じる土屋ゆきは犯人?
委員長が真犯人である可能性──「知らなかったでしょ」に潜む復讐の感情
赤く染まる「知らなかったでしょ」の文字。第5話のあの瞬間を見たとき、誰もが違和感を覚えたはずだ。
それは単なる演出ではない。委員長の心の奥で長年腐り続けた“復讐の記憶”が、静かに表層へと浮かび上がる合図だったのだ。
この物語が巧妙なのは、犯人探しのサスペンスを装いながら、「加害と被害が反転する瞬間」を繊細に描いている点にある。
委員長は、その“境界線の上”に立つ存在だ。彼女は正義の顔を持ちながら、同時に最も暗い怒りを抱えている。
\あの「知らなかったでしょ」の一言を、もう一度聴いてほしい/
>>>Huluで『良いこと悪いこと』第5話を再生する
/真実は言葉の奥で、微笑んでいる。\
キングへの恋心は嘘? 委員長=“ドの子”説と22年越しの恨み
委員長が「キングを好きだった」と語ったシーンは、明らかに観る者を欺くための布石だった。そこには恋ではなく、記憶を塗り替えるための嘘が潜んでいる。
彼女の「知らなかったでしょ?」という台詞は、好意の告白ではなく、“あなたたちはあのときの痛みを知らなかった”という皮肉だ。
ネット上では「委員長=ドの子」説が浮上している。ドの子──それは、当時のクラスでいじめを受けていた生徒の匿名ハンドルネームだ。
もしこの仮説が真実だとすれば、22年前の“ドの子”は、いまや大人になり、社会的に成功を収めたキングたちに復讐の機会をうかがっていたことになる。
彼女の復讐は、血ではなく「記憶の改竄」という形で行われている。つまり、かつて無視された自分の存在を、いま再び物語の中心に据える行為だ。
委員長はキングを愛していたのではない。彼女が欲しかったのは、“誰かに見られる痛み”だった。
忘れられた者が、忘れた者たちを支配する。これは単なる犯行ではなく、“記憶の主導権”を取り戻す戦いだ。
22年の歳月をかけたのは、彼女がようやく彼らを「許せない」と言える強さを得たからだ。赦しの反対語は、憎しみではない。沈黙だ。委員長は、長い沈黙を破るためにこの連鎖を起こしたのだ。
園子を利用した分断構造──操作される正義と沈黙する罪
第5話の終盤、委員長は園子に「反論記事を書くべきだ」と促す。この一言が、物語の空気を決定的に変えた。
表向きは彼女を励ましているように見える。だが本質は違う。園子と高木たちを分断し、真実の共有を阻むための策略だった。
園子が声を上げれば上げるほど、彼女は“疑われる側”に追いやられる。委員長はその心理を正確に読んでいる。つまり、彼女は群衆の視線の力を武器にしているのだ。
それは22年前の構図とまったく同じだ。かつて彼女が孤立したように、今度は園子が孤立する番。彼女の復讐は、過去を再現することで完成する。
委員長は正義を語らない。語る代わりに、他人の正義を操作する。SNS社会では“正しさ”が最も危険な武器になる。彼女はその構造を知っている。
だから園子を利用する。キングたちが疑いを避けるために沈黙を選び、園子が声を上げることで孤立する――その構図を、委員長は望んで作り出しているのだ。
つまり委員長の犯行は、殺意ではなく“構造の設計”にある。彼女は人を殺したのではない。人間関係の信頼という土台を壊したのだ。
「知らなかったでしょ?」という言葉は、過去のいじめの記憶を呼び戻す呪文でもある。見えなかった痛みを、見せつけるための魔法。
そしてその魔法は、まだ解けていない。第6話で明らかになるのは、委員長がどこまでこの“記憶の劇場”を演出していたのか――その一点に尽きる。
「ちょんまげ」が次に死ぬ理由──“許された者”だけが標的になる
博士が掲示板に残した「でも、ちょんまげになら会ってもいいよ」という一文。あの短い言葉に、物語の歯車を狂わせるほどの優しさが潜んでいた。
それは赦しの言葉ではなく、“死の宣告”だったのかもしれない。
博士にとってちょんまげは、唯一過去とつながっている存在。だからこそ、彼と会うことができる唯一の相手であり、同時に真犯人にとっても“彼を狙う理由”になる。
「許された者」だけが標的になる。第5話で描かれたちょんまげの笑顔の裏には、その冷酷な運命が静かに忍び寄っていた。
\次に消えるのは“良い人”──その意味を見逃すな/
>>>『良いこと悪いこと』を今すぐ視聴
/優しさが罰になる瞬間を、目撃せよ。\
博士との再会がもたらす悲劇の連鎖
博士とちょんまげの関係は、過去の“友情”の再現ではない。それは“記憶の代償”を支払うための再会だ。
博士は、キングたちへの恨みを忘れることができない。だが、ちょんまげに対してだけは、憎しみを抱く理由がない。彼だけが「博士」を覚えていたからだ。
その“覚えていた”という事実が、物語における最も残酷な意味を持つ。なぜなら、このドラマにおいて「覚えていること」は“罪”だからだ。
博士が記憶喪失で止まってしまった時間。ちょんまげはその時間の外側で、ずっと博士を想っていた。二人が再会するということは、止まっていた時間が動き出す瞬間であり、同時に過去の傷が再び開く瞬間でもある。
博士が「会いたくない」と言ったキングたちは、忘却の加害者。だが「会ってもいい」と言われたちょんまげは、記憶を抱え続けた被害者であり、そしてその忠誠が彼を破滅へ導く。
真犯人にとって、“博士の赦し”は秩序の崩壊を意味する。だからこそ、ちょんまげは消されなければならない。彼の存在は、博士が完全な孤独であるという物語構造を壊してしまうからだ。
博士と再会した瞬間、彼の中で“罪と記憶の境界”が崩れ、事件の均衡が失われる。だから次に死ぬのは、彼でなければならない。
彼の死は復讐の一部ではなく、物語の構造を保つための犠牲だ。
「御意!」のセリフが意味する“従属の罰”
第5話で印象的だったのは、ちょんまげの明るさと軽さ。彼の「御意!」というセリフは、ただのギャグではない。あれは“支配に従う癖”を象徴していた。
彼はいつも誰かに合わせ、笑いで空気を和らげる。だがその姿は、かつての教室でいじめを見て見ぬふりをしていた“傍観者”の延長でもある。
博士の目には、その従順さが焼き付いていた。だからこそ、彼はちょんまげを「許せる」と思った。なぜなら、ちょんまげは彼の痛みに気づかないまま、ずっと“御意”と笑っていたからだ。
そして皮肉なことに、彼が最後まで従属したその姿勢こそが、彼を死へと導く。
このドラマが鋭いのは、善人ほど早く死ぬ構造を描いている点だ。罪を犯した者は赦され、赦そうとした者が罰を受ける。ちょんまげはまさにその構図の中で、“良い人間”でありすぎた。
博士にとっての“救い”は、誰かが自分を理解してくれることではなかった。むしろ、それを望まないことでしか心の均衡を保てなかった。
だから、ちょんまげの「御意!」という笑顔は、博士の中の“赦しを拒む部分”を刺激した。再会の瞬間、彼の優しさは凶器に変わる。
博士が殺すのではない。だが、博士の存在が彼を死に導く。「赦された者が死ぬ」という、倒錯した倫理のもとに。
「御意!」という言葉が最後に響くとき、それは従属の証ではなく、人が誰かを理解しようとした瞬間に壊れてしまう世界の比喩となる。
ちょんまげの死は、悲劇ではなく、物語の“完成”。そして、博士が孤独を選び直すための、最後の赦しなのだ。
タイムカプセルのビデオテープ──映っていたのは「いじめの記憶」か「赦されない過去」か
掘り返されたタイムカプセル。その中にあったのは、笑顔の記録ではなく、沈黙の証拠だった。
第5話で明らかになった「将来の夢ビデオテープ」。それは子どもたちの未来を語るはずの映像なのに、そこには“赦されない過去”が封じられていた。
そしてそれを掘り出したのが大谷先生だった。彼女はなぜ、誰にも知らせずにビデオを回収したのか──この行動には、単なる好奇心では説明できない「恐怖」と「罪悪感」がある。
\封印されたテープに隠された真実を、あなたの目で確かめて/
>>>今ならHuluで『良いこと悪いこと』第5話をチェック!
/再生ボタンが、過去を暴く。\
大谷先生がテープを回収した理由は命令か、それとも贖罪か
5話の終盤で、大谷先生は黒い車に乗り込む。その瞬間、彼女は“真犯人と約束していた”ような静けさを纏っていた。
「命令されたから」なのか、「自分の意思で」なのか──その境界が見えないのが、このドラマの恐ろしいところだ。
もし彼女が犯人の指示で動いていたのなら、ビデオの中には誰かを守るために消さなければならない映像があったことになる。だが一方で、もし彼女が自ら回収したのなら、それは“教師としての贖罪”だった可能性がある。
大谷先生は当時、子どもたちの「夢」を記録したはずだった。だがそこに映っていたのは、誰かが教室の隅で笑われる姿だったのではないか。
「将来の夢」と題されたビデオに、“いじめの現場”が映り込んでいたとしたら──。それは先生にとって、教育者としての死刑宣告に等しい。
だからこそ、彼女はあの映像を“封印”した。犯人のためではなく、自分が守れなかった子どもたちのために。
しかし、その行為こそが新たな罪を生む。隠された真実は、いつか“誰かの正義”によって暴かれる運命にある。大谷先生の行動は、罪の消去ではなく、連鎖の再起動スイッチになってしまった。
映像の中の“博士へのメッセージ”が事件の動機に変わった可能性
博士は病弱で、学校にあまり来られなかった。だから当時、みんなで彼に向けてメッセージを撮影したという設定が浮かび上がる。
「早く元気になってね」「また一緒に遊ぼう」──そんな優しい言葉たちが、もし博士の目に届いたとき、彼はどう感じただろう。
彼がいじめられていた過去を思えば、それは慰めではなく、偽善の記録に見えただろう。笑顔で手を振る同級生たちの後ろで、教室の空気が冷たく濁っていたことを、彼は知っている。
ビデオの中に映っていたのは、“彼らが嘘をついていた証拠”だ。博士にとって、それは何よりも残酷な形の裏切りだった。
だから、博士はその映像を「赦しの対象」ではなく、「復讐の起点」として見た。つまり、ビデオは犯行の動機を内包したメモリアルなのだ。
真犯人にとっても、あの映像は利用価値があった。そこには「キングたちの偽善」を裏付ける素材が詰まっていた。だからこそ、博士が封印したかった映像を、彼らは引きずり出した。
そして大谷先生は、その“引き金”を引かされた。自らの罪を隠そうとして、結果的に事件を呼び起こしたのだ。
第5話で描かれた「ビデオテープの謎」は、単なる証拠ではない。これは“記憶の再生装置”だ。
人は、忘れたいことほど記録してしまう。タイムカプセルとは、未来への贈り物ではなく、過去への呪文なのかもしれない。
その映像が再生されるたびに、誰かが罪を思い出す。博士も、委員長も、大谷先生も。「夢」という名の過去に縛られたまま、彼らは未来を生きることができない。
だからこそ、このビデオテープは物語の核心だ。そこには、誰かを救う希望ではなく、「赦されない」という真実だけが焼き付いている。
6人目の協力者たち──「エラー発生」が示す連鎖の狂い
「エラー発生」──第5話の予告に映ったこの文字列は、システムの不具合ではない。それは人間関係のバグ、つまり“罪の連鎖が想定外に増殖した瞬間”を意味していた。
犯人は一人ではない。これはもはや殺人事件ではなく、共同体の倫理が壊れていく過程の記録だ。
「6人目の協力者」という言葉が暗示するのは、誰かが直接手を下していなくても、“沈黙という形で加担している”という事実である。
そしてその沈黙こそが、真犯人よりも恐ろしい。
\“エラー発生”の瞬間を見逃すな/
>>>Huluで『良いこと悪いこと』を今すぐ視聴
/沈黙が壊れた瞬間、真実が動き出す。\
当初の“反省の計画”が殺意にすり替わった瞬間
第5話の重要なセリフに、ターボーの「俺たちだけ楽しかったのかな」という言葉がある。これは過去を振り返る懐古ではなく、“罪の自覚の始まり”だった。
当初、クラスメイトたちはタイムカプセルを掘り起こすことで、当時のいじめを見つめ直し、被害者に謝罪する「反省の計画」を立てていたのかもしれない。
しかし、その善意はいつしか歪んでいく。誰かが「本当に反省してるのか?」と疑い、誰かが「忘れたふりをした方が楽だ」と逃げ、そして誰かが「思い出させてやる」と怒りを燃やした。
その瞬間、“懺悔の場”が“制裁の場”に変わった。赦すための集まりが、罰するための儀式へと姿を変えたのだ。
そして、ひとりの暴走が起こる。だが、その暴走を誰も止めなかった。止めるどころか、心のどこかで「仕方ない」と思ってしまった。そこに、“協力者”が生まれる。
その結果、「エラー発生」とは、本来の目的──反省・和解・再生──が破綻したという意味になる。もはや誰も正義の側にはいない。
つまりこの“エラー”は、道徳のバグではなく、人間の感情に組み込まれた仕様だったのだ。
クラス全員の沈黙が作った“共同罪”というシステム
委員長や博士、ターボー、ゆっきー。彼らが直接手を下さなくても、全員が事件の共犯者である理由がここにある。
沈黙は、最も洗練された暴力だ。声を上げないことで、加害者は守られ、被害者は孤立し、そして誰も悪人にならない。
22年前の教室でも同じことが起きていた。誰かが泣いていても、誰も立ち上がらなかった。あの沈黙の構造が、22年後の今もそのまま再現されているのだ。
だから「6人目の協力者」とは、特定の個人ではなく、“何も言わない全員”のことを指している。彼らの無関心が、物語を加速させていく。
しかもこの連鎖の中では、「誰かを守るための嘘」もまた協力の一形態になる。真犯人を匿う者、情報を伏せる者、何も知らないふりをする者。全員がそれぞれの立場で“正義”を演じている。
つまり、この物語の恐怖は、犯人が誰かではなく、“誰もが犯人である社会”を映している点にある。
そして「エラー発生」というメッセージは、その社会がついに壊れたことを告げる警告音だ。
誰もが「悪いことをしていない」と言える世界ほど、恐ろしいものはない。罪が薄まるほど、責任も薄れる。だが罪そのものは、誰の手の中にも均等に分配されている。
沈黙の連鎖は、声を上げない者が多いほど強固になる。だから、この“エラー”は修正されない。物語が終わっても、社会が同じ構造を繰り返していく。
6人目の協力者──それはこのドラマを観ている私たち自身かもしれない。何も言わずに見ていること、それ自体が加担の形であると、この物語は鏡のように突きつけてくる。
『良いこと悪いこと』第5話が描いたもの──「夢」と「罪」をめぐる人間の構造
「夢」という言葉が、これほど残酷に響いた回はなかった。
『良いこと悪いこと』第5話「みんなの夢」は、希望を描く物語ではなく、“夢という名の罪”を暴く章だった。
子どもたちが未来を語る映像、掘り起こされたタイムカプセル、そして博士や委員長たちが背負う後悔。それらはすべて、過去を赦せない人々が作り出した「再生できない記憶の断片」だ。
第5話は、サスペンスの形を借りて、人間の構造──「忘れたい過去」と「赦せない自分」の矛盾──を徹底的に描き切った。
\“夢”がどこで“罪”に変わったのか──答えは映像の中に/
>>>『良いこと悪いこと』第5話を今すぐ観る
/想像を超える“現実”がそこにある。\
夢は未来の象徴ではなく、過去の罪の再生装置
「みんなの夢」というタイトルは皮肉だ。子どもたちの夢は未来ではなく、“過去を映す鏡”として存在している。
博士にとっての夢は、キングたちと笑い合う未来ではなく、「忘れられなかった過去」を取り戻すことだった。委員長にとっての夢は、愛されることではなく、「無視されなかった過去をやり直すこと」。
このドラマは、「夢」と「罪」を同じ線上に並べている。夢を語ることは、過去を思い出すこと。過去を思い出すことは、罪を呼び覚ますこと。そして、その罪が再生されるたびに、また誰かが傷つく。
それゆえに、「夢のビデオテープ」は再生してはならない。再生とは、“記憶の再犯”だからだ。
第5話の映像演出も、それを意識している。穏やかな日常の風景と、断片的なフラッシュバック。ノスタルジーを装いながら、記憶の中に潜む罪悪感を浮かび上がらせる。
そして観る者に問うのだ。「あなたの夢の中にも、誰かの涙はなかったか?」と。
この問いかけこそが、本作を単なるミステリーから“心理の寓話”に昇華させている。夢は、無垢な願いの形をしていても、その裏には必ず“誰かが犠牲になった時間”がある。
つまり、夢とは過去の罪を再生し続ける装置であり、それを止められない人間こそが、この物語の“悪”なのだ。
次回、第6話で“本当の犯人”が笑うとき、観る者が問われるのは自分の中の「悪」
第5話のラストカット──赤く染まる委員長の瞳、そして無音の「エラー発生」。それは事件の転換点でありながら、同時に観る者への告発でもあった。
この作品が描く“悪”は、単純な加害者ではない。“誰かを見捨てた経験”を持つ全員の中に潜んでいる。
博士の記憶喪失は、過去を消したいという無意識の願い。委員長の復讐は、忘れられたことへの反撃。そしてクラスメイトたちの沈黙は、“罪を共有することで自分を軽くしたい”という防衛本能。
それらを束ねるものが、「夢」という優しい言葉だ。だが、その優しさが毒になる。夢が希望を与える一方で、現実を見ない口実にもなってしまう。
第6話では、ついに“本当の犯人”が姿を現すだろう。しかし、その正体を知っても、安心は訪れない。なぜなら、このドラマが問うのは「誰が殺したか」ではなく、“なぜ誰も止めなかったのか”だからだ。
視聴者は無意識のうちに、登場人物の誰かに感情移入している。その共感の正体が、自分の中の“悪”に似ていることに気づいたとき、この物語の真価が見えてくる。
第5話は、観る者の心に静かな鏡を立てた。そこに映るのは、犯人の顔ではなく、自分自身の表情だ。
『良いこと悪いこと』というタイトルが意味するのは、善悪の線引きではない。“人は誰しも、良いことの中に悪を、悪の中に善を抱えて生きている”という現実だ。
だから第6話で誰が笑っても、それは勝者の笑みではなく、罪を理解した者の微笑みになるはずだ。そこに救いはない。だが、真実だけは確かにある。
“記憶”ではなく“感情”でつながる――静かな罪の共鳴
この第5話を観ていて、ふと気づいた。彼らをつないでいるのは「記憶」じゃない。もっと曖昧で、もっと壊れやすい“感情の残り香”だ。
博士が覚えているのは出来事じゃなく、心の温度。委員長が忘れられなかったのも、言葉ではなく空気。ちょんまげが笑っていたのは、場を守るためじゃなく、痛みを感じたくなかっただけ。
人は、記憶よりも感情に縛られる生き物だ。思い出せないのに、なぜか胸がざわつく。もう顔も忘れたはずなのに、声だけは耳の奥に残っている。そういう曖昧な記憶の断片が、人を罪に導くこともある。
\その共鳴を、自分の心で感じてほしい/
>>>Huluで『良いこと悪いこと』を再生
/見えない痛みほど、鮮明に残る。\
「あのときの空気」にまだ取り残されている人たち
第5話の登場人物たちは、まるで“空気の亡霊”みたいだった。誰も直接的に暴力を振るっていない。けれど、あの教室の空気が全員を支配している。
博士も委員長も、いまの自分ではなく、あの頃の「自分がどう思われていたか」を生き続けている。彼らが復讐を選ぶのは、他人を裁きたいからじゃない。あの頃の自分を、ようやく“見てやりたい”からだ。
そしてその心理は、職場にも日常にも似ている。言葉では「過去は過去」と言いながら、結局は昔の序列や評価に縛られ続ける。あのときの上司の一言、友人の無関心、スルーされたLINE。それらの“小さな無視”が積み重なって、いつか自分の中で“物語”になる。
博士や委員長の動機が極端に見えても、その根は日常の延長線上にある。誰だって、心のどこかであの頃の空気に取り残されている。
罪の連鎖を止めるのは、記憶ではなく“いま”のまなざし
「良いこと悪いこと」は、過去をどう赦すかの物語ではない。むしろ、過去を赦せないまま、どう生きるかを描いている。
第5話で博士が示した“共犯”という立場は、まさにその象徴だ。彼は過去を正すためではなく、過去を壊さないために動いた。赦しを求めなかったのは、赦すことで過去が軽くなるのが怖かったからだ。
でも本当の救いは、記憶を塗り替えることじゃない。いま、目の前にいる誰かをちゃんと見ること。それだけで連鎖は止まる。
過去を掘り返しても、人は変えられない。だけど、いま誰かに向けるまなざしだけは、未来を変える力を持っている。
第5話の登場人物たちは、それぞれが“見ることをやめた人たち”だった。博士は記憶を閉ざし、委員長は他人を疑い、ちょんまげは笑ってごまかした。誰も誰かをちゃんと見ていなかった。
だからこの物語は、記憶の話でありながら、実は「視線」の物語だ。過去ではなく“いま”に目を向けられる人だけが、この連鎖から抜け出せる。
そしてそれこそが、この第5話の裏テーマ。“赦すことよりも、見ることを選べ”という無言のメッセージが、画面の奥で静かに灯っていた。
『良いこと悪いこと』第5話考察のまとめ──博士・委員長・ちょんまげ、それぞれの“良いことと悪いこと”
第5話「みんなの夢」は、誰が犯人かという謎よりも、“人がなぜ悪に手を伸ばすのか”という問いに焦点を当てていた。
博士、委員長、そしてちょんまげ。三人の行動はそれぞれ異なるのに、どこかで同じ痛みを抱いている。彼らの「良いこと」と「悪いこと」は表裏一体であり、どちらか一方だけで語ることはできない。
この章では、3人の心の在り方を通して、第5話が映し出した“善悪の曖昧さ”をもう一度見つめ直す。
\第5話の衝撃をもう一度──“良いこと”と“悪いこと”の狭間で/
>>>Huluで『良いこと悪いこと』を視聴する
/あなたの“答え”が、そこにある。\
博士は赦しを拒んだ共犯者、委員長は復讐を選んだ正義者、そしてちょんまげは犠牲者であり救済者
博士は、記憶喪失という形で過去を閉ざした。しかしそれは忘却ではなく、“赦さないための沈黙”だった。
彼が掲示板に残した「会いたくない」という言葉には、過去を断ち切るための優しさと、同時に未だ消えない怒りが同居している。博士は復讐者ではなく、復讐の理屈を与えた共犯者。彼の悪は、静かな思考の中に潜んでいる。
一方、委員長の悪は情動の中にあった。彼女は復讐という名の正義を掲げ、自分の痛みを社会に向けて暴いた。だがその“正義”は、他人の痛みを再生産する形でしか存在できなかった。
彼女が語る「知らなかったでしょ」は、世界への挑戦状でもあり、孤独の宣言でもある。委員長は、理解されたいという願いを捨て、孤立を選んだ正義者だった。
そして、ちょんまげ。彼は三人の中で最も“普通の人間”だった。だが、普通であることが一番残酷な立ち位置だ。誰の味方にもなれず、誰かの記憶の中で曖昧に生き続ける。
博士にとってのちょんまげは、過去と現在をつなぐ唯一の橋だった。しかしその橋は、“理解された瞬間に壊れてしまう儚い構造”だった。
ちょんまげが死ぬのは、彼が赦されたからだ。つまり、赦しこそがこの物語における最大の罰なのだ。
博士、委員長、ちょんまげ。三人の間で「良いこと」と「悪いこと」は常に入れ替わる。そこに道徳の秩序はない。ただ、感情の因果だけが静かに連なっている。
「良いこと」と「悪いこと」の境界が崩れた今、問われているのは“誰が正しかったか”ではなく“誰が痛みを見つめられるか”
『良いこと悪いこと』というタイトルが巧妙なのは、「悪いことをするのは悪人」という単純な構図を壊している点だ。
このドラマで“悪いこと”をしたのは、必ずしも悪人ではない。博士は痛みを抱えたまま動いた。委員長は正義に憑かれて動いた。ちょんまげは、誰かを守るために動いた。全員が、ある種の“良いこと”を信じていた。
だが結果として、誰も救われなかった。つまり、「良いこと」が必ずしも正義を意味しないという冷たい真実が突きつけられたのだ。
第5話は、視聴者にもこの問いを投げかけている。「あなたの良いことは、誰かの悪いことになっていないか?」と。
夢を語ること、過去を懐かしむこと、赦しを願うこと──そのすべてが、誰かの痛みを掘り返す行為になってしまうことがある。
だから、善と悪の境界が崩れた今、問うべきは「誰が正しかったか」ではなく、“誰が痛みを見つめられるか”という一点だ。
痛みを直視すること。それは、赦しよりも勇気がいる。人は本能的に他人の痛みから目を逸らす。だからこそ、博士や委員長、ちょんまげのような存在が必要だった。彼らはそれぞれの形で、痛みを見つめ、痛みに敗れ、そして痛みを残した。
『良いこと悪いこと』第5話は、人間の中にある光と影を切り取った鏡のような物語だった。
誰もが誰かを傷つけ、誰もが誰かを想っていた。その両方が“生きる”という行為の中に混ざり合っている。だからこそ、人生は「良いこと」と「悪いこと」でできている。
そしてその狭間で迷う私たちこそが、この物語の“もう一人の登場人物”なのだ。
- 第1話“正義”が腐る夜の真実
- 第2話 届かない謝罪の行方
- 第3話 絶交が残した痛みとは
- 第4話 忘れられた7人目の闇
- 第5話 博士=堀遼太説とイマクニの正体
- 第5話までの考察まとめ
- 第6話 委員長の復讐と園子が背負う“無実”
- 第7話 友情という名の罪は、誰に渡されたのか
- 第8話 “もうひとりのドの子”瀬戸紫苑の真実と、東雲に隠された「罪の継承」
- 子役が映す純粋と残酷の境界
- 主題歌“アゲハ蝶”が照らす罪
- 「森のくまさん」の呪い考察
- 黒塗りの6人に隠された真実
- 原作が暴く“子どもの罪”とは
- 正義と悪が交差する心理考察
- 委員長・紗季の壊れた正義とは
- 消える子どもたちの真相とは
- 東雲の沈黙に隠された真実
- 漫画版との比較から真意を読み解く
- キングは二重人格か?
- 剛力彩芽演じる土屋ゆきは犯人?
- 博士=岡本=今國は犯人でなく共犯者という複雑な存在
- 委員長は22年越しの怒りと孤独を抱えた復讐者
- ちょんまげは“赦された者”として犠牲になる構造
- ビデオテープにはいじめの記憶と偽善が封印されていた
- 「エラー発生」は沈黙の共犯関係が崩れる瞬間の象徴
- 夢は未来ではなく罪を再生する装置として描かれる
- 第5話は“誰が正しいか”ではなく“誰が痛みを見つめられるか”を問う
- 記憶ではなく感情の共鳴が人間を縛り、連鎖を生む
- 赦すよりも“いま誰かを見ること”が連鎖を断つ唯一の方法
- 善悪の境界を越え、観る者自身の「良いこと悪いこと」を映す物語

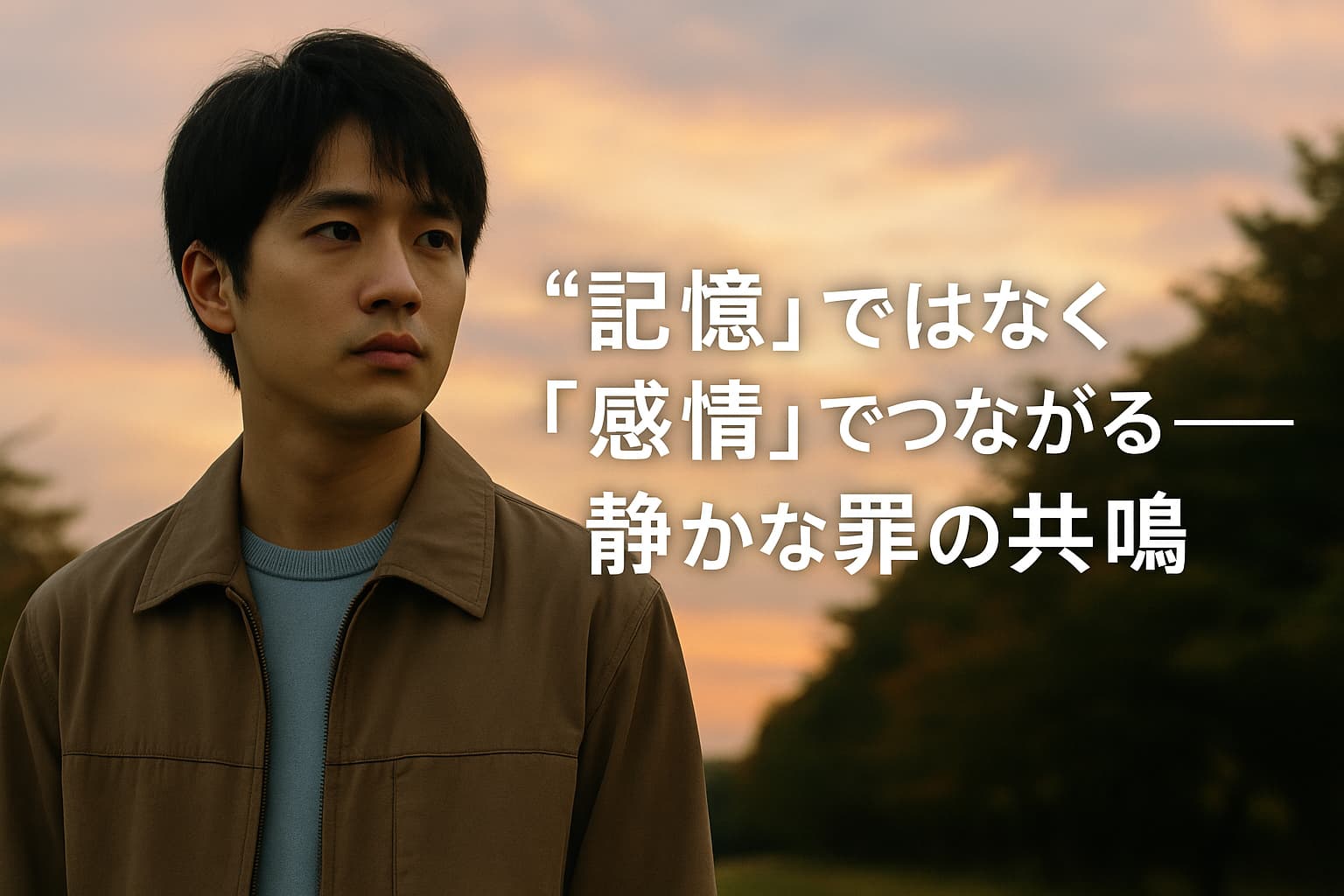



コメント