「光が死んだ夏」第7話は、いよいよ“日常の終わり”が始まった回だった。
よしきが選んだ「一緒にいる」という決意。だがそれは、ヒカルが「光じゃない」ことを認めた上での選択だった。
この回では、明るい町の風景と裏腹に、ヒカルという“ナニカ”の異物性と、よしきの人間らしい苦悩が鮮烈に描かれる。
スワンプマンの問いに対する“よしきなりの答え”がここにある。この記事では第7話の展開と演出をキンタ的視点で徹底解析する。
- よしきがヒカルを選んだ本当の理由
- ヒカルに生まれつつある感情の意味
- 共依存が生む静かなホラー演出の意図
よしきの「決意」は、愛か、それとも共犯か?
第7話のタイトルは「決意」。だがその言葉が示すのは、前向きな覚悟だけじゃない。
この回で描かれた“決意”は、誰かを守ると決めた瞬間に、自分自身の倫理や常識を殺すことでもある。
よしきが選んだのは、「光じゃない」と分かったヒカルと“それでも一緒にいる”という選択──つまり、それは“共犯”の始まりだった。
ヒカルを受け入れるという“選択”の重さ
第7話、最も衝撃だったのは、よしきがヒカルの正体に気づいた上で、それでも共にいると決めたことだ。
つまり、彼は“本物の光”がもういないことを理解している。
それでも、目の前のヒカルに「また一緒に遊ぼう」と言った。
このシーンは、ただの“友情の再確認”なんかじゃない。
彼が受け入れたのは、人間のふりをした「何か」との日常であり、日常の延命処置でもある。
普通なら「逃げる」か「拒絶する」べきところで、よしきは“継続”を選んだ。
この選択には、「ヒカルの孤独を理解したい」という気持ちと、“もう取り戻せないものにしがみつく”執着が同居している。
彼は、自分の感情を守るために、事実を飲み込んだのだ。
それはある意味、優しさではなく「共依存」の始まりともいえる。
倫理観を捨てたのか、それとも超えたのか?
ここでひとつ問いたい。
よしきの決意は、人間として正しいものだったのか?
「ヒカルは人を襲った」と言われている。
その“何か”と知りながら一緒にいるということは、被害者の存在を無視していることになる。
つまりよしきは、人間としての倫理よりも、自分の感情を優先した。
彼の「決意」は、美談ではない。
むしろ、「倫理の放棄」だ。
これは少年の一途な想いなどという甘いものではなく、現実と向き合うことをやめた結果としての、感情の暴走とも言える。
だが一方で、視点を変えれば、それは“常識の超越”とも言える。
「相手が人間じゃなくても、自分が愛した存在ならそれでいい」──この思想は、倫理と感情の対立軸の中で、人間らしさの“本質”を問うてくる。
倫理に従うべきか、感情に従うべきか。
その問いは、第7話の根底に流れる静かな恐怖でもある。
「正しさ」ではなく、「気持ち」を選んだよしき。
その姿に僕らはゾッとしながらも、共感してしまう。
それが、この作品の一番怖いところなんだ。
ヒカルの“ごめん”に潜む、理解不能な感情構造
第7話のもう一つの核心は、ヒカルの「ごめん」という言葉にある。
これは、ただの謝罪のセリフじゃない。
むしろその言葉の裏にある「感情の構造」こそが、この物語が問いかける“人間性”の核心なのだ。
「ごめん」と言える存在は、果たして本当に“怪物”なのか?
「襲った」ことを謝るヒカルは、人間に近づいたのか?
ヒカルは、過去に人を襲ったことを自覚している。
そしてその事実を踏まえて、よしきに「ごめん」と謝る。
ここにあるのは、明らかに自己の行為に対する反省であり、罪悪感という人間らしい感情のように見える。
この瞬間、視聴者の感情は揺れる。
「怪物のくせに、そんなことを言うのか?」
「いや、怪物だからこそ、その一言が重いのかもしれない」
ここで興味深いのは、謝るという行為が、倫理や道徳の理解に基づいているように見える点だ。
つまり、ヒカルは「善悪」の境界を知り、その上で「自分が悪いことをした」と判断しているように見える。
これは、単なる擬態では説明しきれない。
そしてこの“矛盾”が、視聴者を困惑させる。
それは人間なのか?
それとも、人間に似せて作られた“なにか”が、感情を模倣しているだけなのか?
この“曖昧さ”こそが、本作の真の恐怖だ。
よしきの無条件な許しに見える“壊れ始めた正常”
ヒカルの謝罪を受けて、よしきは怒るどころか「一緒にいよう」と言う。
この反応こそが、第7話最大の違和感であり、よしきというキャラクターが壊れ始めた兆候だ。
普通、人を襲った存在に対して「もう一度一緒にいたい」とは思わない。
それでもよしきは、「いいよ」と言う。
それは恐怖の否定でも、道徳の赦しでもない。
ただ、ヒカルと一緒にいたいという欲望だけが、感情の中で暴走している。
この無条件な受容は、よしき自身が「日常という名のフィクション」にしがみついている証拠だ。
彼の「一緒にいよう」は、ヒカルのためではなく、自分のための呪文でもある。
だがその選択が、この先どういう結末を導くのか。
それはきっと、“誰かがもう戻れなくなる”形で描かれるはずだ。
第7話の「ごめん」には、言葉にならないノイズが混ざっていた。
それは、“感情を持ってはいけない存在”が、「感情らしきもの」を発したときの奇妙な不協和音だった。
そして、その音に耳を塞がなかったのが、よしきだった。
日常の中に潜む異常──映画館シーンが語る「見えない不安」
第7話における映画館のシーンは、一見するとただの“日常”の一コマだ。
しかしその裏には、静かに忍び寄る違和感と、不安の種が潜んでいる。
ホラーとは、何かが起きる瞬間ではなく、何も起きていない“はず”の中に恐怖がある──そう思い知らされる演出だった。
2人きりで過ごす時間の意味とその“薄ら寒さ”
よしきとヒカルは、誰もいない映画館で隣り合って座る。
画面では笑い合い、時には無言で過ごす時間。
だがその穏やかな描写の中に、明らかな「異物感」がある。
観客がいない、という空間の不自然さ。
まるで世界に2人しか存在しないような閉鎖感。
ここに来て、日常は完全に“仮想空間”のような手触りを持ちはじめる。
これはつまり、2人が既に「現実」から切り離された存在であることを象徴している。
現実の中にいるのではなく、「かつての記憶をなぞるように生きている」ような空虚な時間。
映画の上映内容すら描かれないことで、“そこに意味はない”ことが暗示される。
日常のように見える時間が、実はただの殻でしかない──そんな「気づき」を、視聴者に突きつけてくる。
視線・演出・間の“違和感”が生む静かなホラー
この回で最も不気味なのは、明確な恐怖描写がほとんどないことだ。
それにもかかわらず、見ていて胸の奥がざわつく。
その原因は、“視線”と“間”の演出にある。
ヒカルが一瞬よしきの顔を無表情で見つめる。
その目には、喜びも、怒りも、悲しみもない。
ただ「そこにいる」という事実だけが映し出されている。
まるで“ヒカル”という存在は、感情を持ったふりをして、ただ隣に座っているだけのようにも見える。
だが、よしきはその違和感に気づいていない(もしくは気づかないふりをしている)。
この“間”の演出がじわじわと心を締めつける。
言葉がない、音もない、動きもない──そこにあるのは、“感情が止まった世界”だ。
恐怖とは「何かが起きる」ことではない。
「何も起きないまま、何かが壊れていく」ことが、本当のホラーなのだ。
映画館という密室、世界から切り離されたような空間、会話が噛み合わない微妙なズレ。
それらが全て、「もう元には戻れない」という空気を作り出している。
そして何より恐ろしいのは、それをよしき自身が心地よく感じているように見えること。
彼はもう、「光が死んだ夏」の現実ではなく、“ヒカルが隣にいる夏”に生きている。
その切り離された夏が、永遠に続くことを願っている。
第6話から続くスワンプマンの問い:ヒカル=光なのか?
第6話のラストから提示され続けている哲学的な問い──「ヒカルは本当に光なのか?」
この問いは第7話でも引き継がれ、より重く、より曖昧な形で描かれる。
それは単なる正体の問題ではなく、「存在」と「感情」と「記憶」が交錯する、極めて人間的な迷路だ。
記憶・姿・関係性──“魂”はどこに宿るのか?
ヒカルは、外見はかつての光そのもの。
声も、口癖も、話し方も、幼なじみだった光の記憶と一致する。
だが、彼の中にある「自我」は、明らかに別物だ。
これは哲学でいう“スワンプマン問題”を彷彿とさせる。
沼に落ちて死んだ人間が、同じ姿・同じ記憶で複製されたとき、それは本人と呼べるのか?
――ヒカルとは、まさにそのスワンプマンだ。
「記憶が同じでも、自我が違えばそれは別人」なのか。
それとも、「関係性を再構築できるなら、それもまた同一性」と呼べるのか。
この問いに対して、よしきは“個人的な答え”を出した。
彼にとっては、「誰であれ、ヒカルが隣にいること」が重要であり、その存在の本質よりも“関係性の持続”を選んだのだ。
つまり、魂があるかどうかは、もはや重要ではない。
「自分が光と思いたい存在が、今そこにいる」ことに意味を見出している。
「一緒にいたい」が生まれるなら、もうそれはヒカルなのか
第7話でヒカルは、たびたび“感情らしき反応”を見せる。
「ごめん」と言い、よしきを襲わないように抑えている。
感情を持たないはずの存在が、“感情のふり”をし、それが次第に本物のようになっていく。
ここで重要なのは、「ふりであっても、繰り返せばそれは感情になるのか?」というテーマだ。
人は誰かを好きになるとき、理由ではなく“過ごした時間”で関係を築いていく。
つまり、「一緒にいたい」と思った時点で、その存在はもう“他人ではない”。
よしきがヒカルと関係性を再構築しようとする様は、まるで“再定義”の儀式のようだった。
姿も声も光。記憶もある。
そして、感情も生まれ始めている。
ならばそれは、もう「ヒカル」ではなく、「新たな光」なのではないか。
この回の結論は出ていない。
だが、“人間性”というものが記憶と感情と関係性の総体であるならば、ヒカルはその輪郭を獲得しつつある。
そしてそれを受け入れたよしきは、もはや「失った夏」に生きているのではなく、「偽りでも隣に光がいる夏」を選んでいる。
その選択が、いつか自分自身を壊すと知りながら。
“人ならざる存在”ヒカルに芽生えた疑似感情の正体
第7話を通して、ヒカルが見せる感情らしき“何か”は、見る者に強烈な違和感と、かすかな希望を同時に与える。
人ではないはずのヒカルが「ごめん」と言い、「一緒にいたい」と願う。
それは感情なのか?それとも、模倣か?
この曖昧な“感情のようなもの”が、本作最大のミステリーであり、同時に感動の核でもある。
「死にたくない」は誰の想い?光の記憶か、ヒカルの本心か
ヒカルが呟く「死にたくない」というセリフ。
それは単なる恐怖ではなく、生存欲求と、孤独の拒絶に満ちていた。
ここで重要なのは、この言葉が“誰の意志”として発せられたのかという点だ。
もしそれが、かつての光の“記憶”に基づくものなら、それはただの反射行動。
だが、ヒカル自身が「存在し続けたい」と思っているなら、それは“自我”の芽生えを意味する。
このセリフは、哲学的にも非常に重い。
「私は死にたくない」と思う主体がいる限り、それはもはや“物”ではない。
それは、“存在の意思”を持った何かだ。
そしてその想いを、よしきが否定しなかったことが、ヒカルに“確信”を与えてしまう。
つまり、「存在していいのだ」と。
その一言が持つ力は、人間にとっても、そうでない存在にとっても、同じくらい重い。
感情を持たない存在が“孤独”を感じた瞬間
第7話の中で、ヒカルが見せる表情は終始どこか不安定だった。
人を襲う本能を持ちながらも、よしきのそばにいることで何かを学びつつある。
特に印象的だったのは、「ごめん」と言ったあとの無言のシーン。
あの一瞬、ヒカルが“理解されない孤独”を抱えているように見えた。
それは光の記憶ではなく、ヒカルという存在が初めて感じた「個」の意識かもしれない。
“人ならざる存在”が、人間と触れ合うことで疑似的な感情を生み出す──これはSFではよくあるモチーフだが、「光が死んだ夏」が描くのはもっと繊細だ。
“感情”と“プログラム”の境界線が、にじんでいく様子。
まるで、コピーされた人格が、模倣の積み重ねの中で本物に変化していくような感覚。
ヒカルが光ではないとわかっていても、彼の「孤独」は現実だ。
それをよしきが肯定したことで、ヒカルの中に“心のようなもの”が生まれはじめた。
それは偽物かもしれない。
だが、それを偽物だと断言できる人間は、もうこの物語の中にはいない。
第7話のホラー演出に隠された“共依存”の兆し
「光が死んだ夏」第7話は、血が飛び散るような直接的な恐怖はない。
だが、じわじわと胸を締めつける不気味さが、画面の隅々に染み込んでいた。
その正体は何か?
それは、“共依存”の兆し──つまり、「一緒にいたい」という純粋な願いが、狂気に変わっていく兆候だ。
黄昏のビジュアルが示す「日常と非日常の境界線」
この回の後半、印象的に使われていたのが“夕暮れ”のビジュアルだ。
橙色に染まる空、長く伸びる影。
まるで「現実と非現実の境目」が視覚化されているようだった。
黄昏は「日常が終わり、夜=未知に呑まれる直前の時間」だ。
その空気感は、第7話におけるよしきとヒカルの関係にぴったりと重なる。
もうすぐ何かが壊れる、でもまだ壊れていない。
2人は“まだ正常”というフィクションを共有している。
夕暮れのシーンは、その“ギリギリのバランス”を視覚で描く演出だ。
明るさと暗さの中間、希望と不安の間、そして「光」と「偽のヒカル」の間。
そして視聴者は、その曖昧な境界に足を踏み入れたまま、出られなくなる。
笑顔の裏にある「正気の喪失」──よしきの変質
第7話で、最も恐ろしかったのは“よしきの笑顔”だった。
ヒカルと過ごす時間に、確かに幸せそうな表情を見せる。
だが、その笑顔にはどこか“虚ろな色”があった。
普通なら怯えるべき存在を、あたかも何事もなかったかのように受け入れている。
これは愛なのか、それとも狂気なのか。
よしきは、既に「ヒカルの正体」と「倫理的違和感」を飲み込んでいる。
つまり、彼の中では“正しさ”より“関係性の維持”が優先されている。
その代償として、心が少しずつ壊れている。
ここで浮かぶキーワードが“共依存”だ。
ヒカルがよしきに依存する構図は既に見えていたが、
実はその逆、よしきこそが「失われた光」に依存しているという構造が、第7話で顕著になる。
これは一方的な関係ではない。
「自分を必要としてくれる存在がいる」ことで、ヒカルは人間らしくなり、
「失った存在を取り戻せる幻想」にすがることで、よしきは心の安定を保っている。
だがその均衡は、異常なものだ。
狂気の土台の上に築かれた擬似的な日常は、
何か小さなきっかけで崩れ去る可能性を常に孕んでいる。
第7話のホラーは、叫び声でも怪物でもない。
“優しい日常”が、静かに狂気に侵食されていく怖さだ。
ヒカルの正体に怯えていたのは、本当に“人外”だったからじゃない
よしきは第6話で気づいてた。目の前のヒカルが“光”じゃないってこと。
なのに、なぜ第7話で「一緒にいたい」と言えたのか。
怖くなかったのか?――いや、怖かったはずだ。だから震えたし、逃げなかった。
でも、その恐怖は「人じゃない何か」へのものじゃなかった。
もっと深くて、もっとどうしようもない、“もう戻れない”という事実への恐怖だった。
“変わってしまった”のが怖かったんじゃない、変わらない自分が怖かった
光が死んで、ヒカルが現れて、すべてがぐちゃぐちゃになった。
でもよしきは、あの日の「光との関係性」だけは変えずに持ち続けていた。
記憶の中で、光はいつもそこにいた。
だけど、目の前のヒカルは「違う」。
そのズレが怖かった。
でも本当の恐怖は、ヒカルが変わってしまったことじゃない。
“自分がまだ、あの日のまま”だと気づくことのほうだった。
人は喪失を経験すると、少しずつ“更新”していく。
「もういない」と受け入れて、何かを上書きして、生きていく。
でもよしきは、それができなかった。
彼はまだ、あの夏のまま止まってる。
だからヒカルを受け入れたんじゃない。
受け入れることで、「自分は変わらなくていい」と思いたかっただけなんだ。
この物語の本当の怪物は、“ヒカル”じゃない
ホラー作品は多くの場合、異形の存在を“怪物”として描く。
だが『光が死んだ夏』の真の怪物は、それとは別の場所にいる。
それは、「喪失から更新されずに、過去の関係にしがみついてしまう人間」だ。
つまり、よしき。
ヒカルは確かに恐ろしい存在だ。
でも、何も知らずにただ存在してるだけ。
怖いのは、“知ってるのに選ぶ”側の人間のほうだ。
倫理を知り、違和感を感じ、それでも目を逸らして受け入れる。
この選択は、ホラーではなく、よしきの「生存戦略」だったのかもしれない。
だとすればこの物語は、“怪物と人間”の話じゃない。
「変われなかった人間が、変わってしまった存在と共に堕ちていく」話なんだ。
『光が死んだ夏』をABEMAで“今すぐ”体験しよう
\“あの決意”の瞬間を見逃すな!/
▶ 第7話「決意」──よしきの選択を、映像で体感せよ
/お得に観るなら今しかない!\
『光が死んだ夏』第7話の重厚な空気、ヒカルの無言の“視線”、黄昏に沈む町の色彩。
そのすべてを最大限味わうなら、ABEMA独占無料配信を活用するしかない。
- ABEMA独占・無料先行配信:放送直後の最新話が1週間無料!
- ABEMAプレミアム:過去話を一気見できる見放題プラン(月額1,080円)
- スマホでもPCでもOK。ダウンロードして移動中に視聴も可
よしきの「一緒にいよう」の声の震え。
あれを“文章じゃなく、音と表情で”感じたい人へ。
今すぐABEMAで、背筋が凍る夏を体験しよう。
\最新話が無料!今すぐチェック/
>>>『光が死んだ夏』をABEMAで無料視聴する!
/“次の決壊”を見逃すな!\
『光が死んだ夏 第7話』感想のまとめ:これはもう“友情”じゃない
「一緒にいたい」。
その言葉がこんなにも重く、こんなにも狂気じみて聞こえる作品が、これまでにあっただろうか。
第7話は、ただのホラーでも、ただの青春ドラマでもない。
人と“それ以外”の存在が織りなす、共存とも共犯とも言える関係性の物語だ。
共にいることの意味を問い直すエピソード
第7話は、よしきがヒカルと「共にいる」ことを選ぶ物語だった。
しかしそこにあるのは、決して美しいだけではない“現実逃避”の選択でもある。
ヒカルが“光ではない”と理解したうえで、なお「一緒にいたい」と願うよしき。
それは友情なのか?
それとも、もう別の“何か”なのか。
失われた人間関係を、擬似的な存在で埋めようとするその姿は、悲しみよりもむしろ、強烈な執着に近い。
このエピソードは、「一緒にいるとはどういうことか?」を静かに、しかし鋭く問いかけてくる。
同じ空間にいるだけで「一緒にいる」と言えるのか。
心が通じなくても、記憶があるなら、それでいいのか。
この問いは、視聴者に向けられたものでもある。
私たちが「一緒にいる」と感じる関係性には、どれほどの真実と、どれほどの幻想があるのだろうか。
次回以降、よしきの“覚悟”が何を壊すのかに注目
第7話の終盤で、よしきの覚悟は明確に描かれていた。
それは「ヒカルと共にいる」ことを選び、「光の死」を受け入れることでもあった。
その選択は、誰かを守るためではなく、自分の心を守るための“決壊”だったように見える。
よしきは壊れかけている。
それでも笑う。
それでも傍にいる。
だが、それが続くはずがない。
この物語がここまで“丁寧に異常”を描いてきたということは、次に来るのは「破壊」のフェーズだろう。
それは、よしきの心かもしれない。
ヒカルの存在かもしれない。
あるいは、彼らの関係そのものかもしれない。
いずれにしても、この“決意”は代償を伴う。
そしてその代償を支払うのは、ヒカルではなく、よしきの方だ。
友情という言葉ではもうくくれない。
第7話は、「喪失」と「受容」と「狂気」のクロスロードで、彼らがどちらへ進むのかを静かに見せつけた回だった。
次回以降、よしきの選んだ“隣にいるという罪”が、何を壊すのか。
その結末を、目を逸らさず見届けたい。
- 「光じゃない」と知りながらヒカルを選んだよしきの決意
- ヒカルに芽生える“感情のようなもの”の正体を考察
- ホラー演出の中に浮かび上がる共依存の構造
- スワンプマン的問い「ヒカル=光なのか?」の哲学性
- 夕暮れや視線など、演出から読み取れる異常の兆し
- よしきの選択が倫理か狂気かを問う構成
- 「喪失から更新されなかった人間」という独自視点を追加
- “友情”では語れない、破滅へと進む関係性の描写

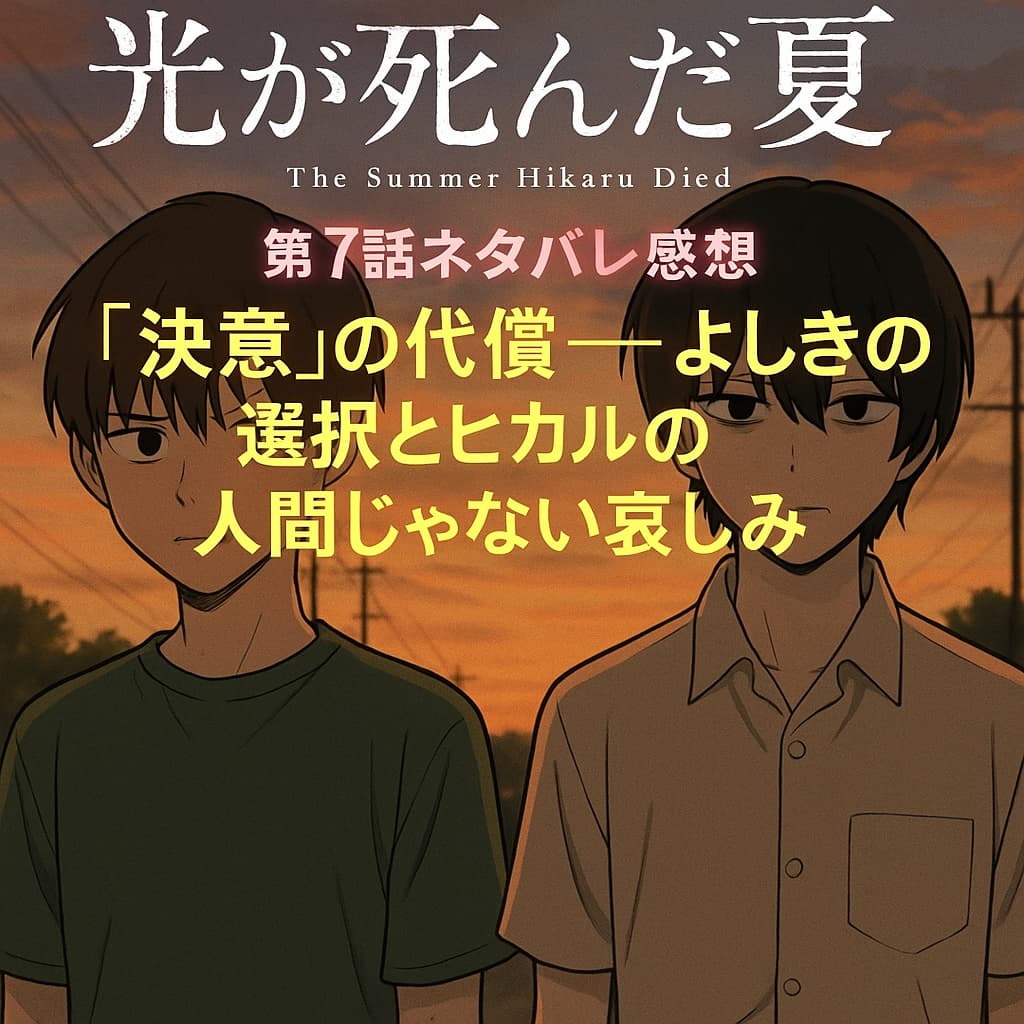



コメント