「良いこと悪いこと」第9話「カノン」。それは、犯人の名前よりも、ひとつの言葉が心に残る回だった。
“お前はいつまでも悪い子でいろ”。
宇都見啓の声は、怒りではなく祈りに近かった。赦すことも忘れることもできないまま、彼は愛した人の代わりに世界へ罰を下す。瀬戸紫苑の沈黙が音を失った瞬間、誰もが加害者になり得る現実を突きつけられる。
この記事では、第9話が描いた「復讐と赦しの境界線」を、感情と構造の両面から紐解く。
- 宇都見啓と瀬戸紫苑が背負った“赦されない記憶”の意味
- 「カノン」に込められた復讐と赦しの構造
- 誰もが「キング」になり得るという現実への警告
宇都見啓の“復讐”は、愛ではなく記憶の呪いだった
宇都見啓の復讐は、激情ではなく静かな絶望から始まった。
彼が殺したのは人ではなく、「忘却」そのものだった。
瀬戸紫苑がピアノを弾けなくなり、人生の音を失っていく過程を、彼は隣で見続けた。愛していた人の指先から音が消える瞬間、宇都見にとってこの世界はすでに壊れていたのだ。
\この男の「目」、文字だけで想像しきれる?/
>>>宇都見啓の復讐を、映像で確かめる
/言葉になる前の感情が、そこにある。\
彼が殺したのは、人ではなく「忘却」だった
紫苑の死の引き金は、過去のいじめを思い出す“音”だった。
小学生の頃、リコーダーの「ド」が出せなかっただけで「ドの子」と呼ばれ、世界から排除された。そのときの教室の空気、嘲笑のリズム、机に刻まれた傷。すべてが、音と共に彼女を閉じ込めていた。
大人になり、ピアニストとして再生したように見えた紫苑。しかし、ある日玄関のチャイムが鳴る。高木将——かつて彼女を“ドの子”と呼んだ男が、娘を連れてピアノ教室を訪れた瞬間、すべての音が再び止まった。
宇都見にとって、それは“殺人よりも残酷な事件”だった。
彼が怒りを抱いたのは、高木の無自覚だった。加害者は忘れる。被害者は、一生思い出す。その非対称を埋めるために、宇都見は一人ずつ、記憶の順に人を裁いていく。
それは復讐ではなく、「世界の記憶を修正する行為」だった。
婚約者・瀬戸紫苑がピアノを弾けなくなった理由
紫苑にとってピアノは“救い”であり“逃げ場”だった。鍵盤の上だけが、彼女が自分を許せる場所だった。だが、玄関越しに高木の声を聞いたあの日、彼女は再び小学五年の夏に戻った。
指先が震え、鍵盤の音が歪む。過去が現在に侵食していく。トラウマとは、時間を奪う病だ。
宇都見は、その変化を知っていた。ピアノの音が止まった夜、彼女の肩は細く震えていたという。けれど、彼は何もできなかった。恋人を支えるふりをして、同じ時間に沈んでいった。
そして一年後、紫苑は命を絶った。ピアノを失った彼女に、世界はもう音を返さなかった。
宇都見の“動機”とは、理屈ではなく喪失の果てに生まれた衝動だ。誰もが忘れた罪を、彼一人だけが生々しく覚えていた。その記憶こそが、彼を生かし、そして壊した。
だからこそ彼は、復讐ではなく“記憶の再演”として人を殺した。順番も方法も、すべてあの替え歌「森のくまさん」の順に沿って。
彼にとってそれは罪ではなく、“記憶の正義”だった。
最期、宇都見はキングに向かって言う。「お前はいつまでも悪い子でいろ」。その声には、怒りも悲しみも混ざっていなかった。ただ一つ、赦せないまま生きる痛みを知ってほしいという祈りだけが残っていた。
宇都見啓は悪人ではない。だが、彼が信じた正義は誰も救わなかった。彼が壊したのは命ではなく、“無関心という名の平穏”だったのだ。
- 第1話“正義”が腐る夜の真実
- 第2話 届かない謝罪の行方
- 第3話 絶交が残した痛みとは
- 第4話 忘れられた7人目の闇
- 第5話 博士=堀遼太説とイマクニの正体
- 第5話考察 博士の共犯関係・委員長の動機・ビデオテープの意味
- 第5話までの考察まとめ
- 第6話 委員長の復讐と園子が背負う“無実”
- 第7話 友情という名の罪は、誰に渡されたのか
- 第8話 “もうひとりのドの子”瀬戸紫苑の真実と、東雲に隠された「罪の継承」
- 子役が映す純粋と残酷の境界
- 主題歌“アゲハ蝶”が照らす罪
- 「森のくまさん」の呪い考察
- 黒塗りの6人に隠された真実
- 原作が暴く“子どもの罪”とは
- 正義と悪が交差する心理考察
- 委員長・紗季の壊れた正義とは
- 消える子どもたちの真相とは
- 東雲の沈黙に隠された真実
- 漫画版との比較から真意を読み解く
- キングは二重人格か?
- 剛力彩芽演じる土屋ゆきは犯人?
- 7人目の同級生=博士こと森智也の考察
- 森先生の正体
- ドの子とターボーの伏線を総まとめ
瀬戸紫苑の沈黙──音を失った少女の再生と崩壊
瀬戸紫苑の物語は、誰かを恨む話ではない。むしろ彼女の中では、世界を赦したいという思いがずっと燻っていた。
しかし、音を失った人生は、赦しの言葉を持てなかった。
リコーダーの「ド」が出せなかった、たったそれだけで始まった地獄。教室という狭い世界の中で、紫苑は“ドの子”という名前に閉じ込められた。誰かの笑い声が、刃物よりも鋭く響く。彼女にとって、音は恐怖の象徴となった。
\彼女がピアノに触れる「一瞬」を見たら戻れない/
>>>瀬戸紫苑の物語を、今すぐ体験する
/沈黙が、こんなに重いなんて。\
リコーダーの「ド」が狂わせた、少女の世界
小学生の紫苑は、純粋に音楽を愛していた。リコーダーもピアノも、音の一つひとつが心を満たす“魔法”のようだった。
だが、その「魔法」が一瞬で呪いに変わった。音楽のテストで「ド」の音が出なかっただけで、教室の空気がざらついた。クラス全員の笑いが連鎖し、先生の沈黙が肯定に変わる。その瞬間、紫苑の世界は壊れた。
いじめは形を変えて続いた。机の落書き、名前の書き換え、無言の視線。音楽が“罰”になった。彼女は学校に行けなくなり、やがて転校した。
転校先で彼女は再びピアノに出会う。鍵盤の白と黒は、世界の善悪のように見えた。弾くたびに、自分がまだ生きていることを確かめる。そうして彼女は、音楽で再生を果たしたかのように見えた。
“カノン”は救いの曲ではなく、過去を閉じ込める檻だった
大人になった瀬戸紫苑は、ピアニストとして舞台に立っていた。演奏曲は「カノン」。彼女にとって“カノン”は希望であり、祈りだった。
しかしその曲こそが、最も深い傷を呼び覚ますものだった。あの頃、誰も聞いてくれなかった“音”を、今は世界中が聞いている。だが拍手の音が、彼女にはまたあの日の笑い声に重なって聞こえた。
やがて、ピアノ教室を開いた紫苑の前に、高木将が娘を連れて現れる。「新規の人は受け付けていません」と言った彼女の声は震えていた。その直後、紫苑の中で音が再び止まった。
過去は終わっていなかった。忘れたはずの「ド」の音が、記憶の奥で鳴り響いたのだ。
それから紫苑はピアノを弾けなくなり、薬に頼るようになる。“カノン”は救いではなく、記憶を閉じ込める檻になってしまった。
そして、音楽を愛した彼女の世界から、音が完全に消えた夜。宇都見は何もできなかった。ただ隣で、鍵盤の上に落ちる涙の音を聞いていた。
瀬戸紫苑の沈黙は、社会の沈黙でもある。誰も助けない。誰も声を上げない。“いじめ”という言葉で終わらせるにはあまりに重い現実がそこにある。
そして、彼女の死後に流れた「カノン」は、もはや追悼曲ではなかった。それは、赦されなかった少女の遺言だった。
瀬戸紫苑は死んでもなお、音で世界を問い続けている。彼女の沈黙は、今も私たちの耳の奥で鳴り続けているのだ。
キングを生かした理由──赦しではなく、罰としての生
宇都見啓が最後に殺さなかった男——高木将、通称キング。
彼は瀬戸紫苑の人生を狂わせた“過去の加害者”でありながら、唯一命を奪われなかった人物だ。
宇都見の口から放たれた言葉はたったひとつ。「お前はいつまでも悪い子でいろ」。
この台詞には、復讐を越えた哲学が宿っている。生かすことこそが最大の罰。
\「悪い子でいろ」この一言の重さ、知ってる?/
>>>キングが壊れる瞬間を、見逃さない
/生きることが、罰になる夜。\
「悪い子でいろ」──生きることこそ、最大の懲罰
宇都見は他の加害者をすべて殺した。けれどキングだけは、死を与えなかった。
それは単なる情けではない。むしろ冷酷な選択だった。彼が望んだのは、キングに罪の時間を生きさせることだ。
人は死ねば終わる。しかし生き続けることでしか、償いは始まらない。
宇都見の復讐は「死」ではなく「記憶の持続」だった。
キングは、紫苑をいじめた過去を完全に忘れていた。彼にとって“ドの子”は名前ではなく、ただの笑い話の一つに過ぎなかった。
その“無意識の残酷さ”が、宇都見にとって最も許せないものだった。だから彼は、キングを殺す代わりに、「永遠に記憶を失わせない罰」を選んだ。
キングが今後どんな人生を送ろうと、あの言葉は一生離れない。「お前は悪い子のままでいろ」——それは呪いであり、同時に希望でもある。
宇都見は知っていた。罪を知ることは、痛みを知ることだと。
彼が殺さなかったのは、罪を永遠に続けさせるため
キングは紫苑の死をきっかけに、初めて過去の記憶を“思い出させられた”。
それまでは家族を持ち、父親としての顔を持ちながら、自分が加害者であった事実を完全に封じ込めていた。
宇都見の行動は、そんな彼の心の奥に埋まった“忘却”を掘り起こすための儀式だった。
人を殺すことよりも、記憶を殺すことの方が残酷だ。だから宇都見はその逆を選んだ。記憶を生かしたまま、魂を地獄に沈める。
追悼コンサートで流れた「カノン」は、紫苑の祈りでもあり、宇都見の復讐の完成でもあった。
彼は舞台でピアノを弾きながら、心の中でこう言っていたのかもしれない。
「これは罰だ。だが同時に、お前に残された最後の贈り物だ」
キングはカッターナイフを手に宇都見に向かう。しかし警察が突入し、刃は届かなかった。その瞬間、宇都見はすべてを理解していたのだろう。
——これでよかった。彼は生き続ける。紫苑と俺の罪を、永遠に背負って。
宇都見が望んだのは、死ではなく継承だった。罪を忘れない者が一人でも生き残ること。それが、紫苑の存在をこの世界につなぎとめる唯一の方法だった。
キングを生かすことは、宇都見にとって紫苑を殺さないことと同義だった。
“赦し”は存在しない。けれど、痛みを抱え続けることでしか生まれない“贖罪”がある。
キングはこれからも生きる。紫苑の笑い声と、宇都見のピアノの音が交錯する記憶の中で。
その生は苦しみそのものだが、同時に、たった一つの救いでもある。
共犯者の影──“知らなかったふり”が罪を拡張する
「犯人は宇都見啓だった」──真相が明らかになったあとも、この物語には不穏な“空白”が残っていた。
それは、彼一人で成し遂げられたとは思えないほどの緻密さと、誰もが「知らなかったふり」をしていたという沈黙の構造だ。
宇都見が復讐を遂行するには、情報を持つ“誰か”の存在が不可欠だった。だが本当の共犯者とは、彼に手を貸した者ではない。見て見ぬふりをしたすべての大人たち、そして過去を忘れた同級生たちなのだ。
\本当の共犯者、気づいてしまったら最後/
>>>空気が凍る第9話を、今すぐ見る
/沈黙もまた、暴力になる。\
イマクニ・東雲・トヨ…沈黙の中で誰が情報を流した?
ドラマの第9話では、宇都見が“替え歌の順番”に沿って殺人を繰り返したことが示されている。だが、彼は6年1組の生徒ではなかった。つまり、替え歌の順番や当時の出来事を知るには、内部の情報源が必要だった。
ネット上では、イマクニが有力な共犯候補として挙げられている。彼の店に掲げられていた「T」のロゴ──それは、紫苑が通っていたタクト学園のマークと一致していた。偶然か、それとも意図的か。
さらに、東雲が同じフリースクールの出身である可能性も示唆されている。宇都見が彼女から断片的な記憶を受け取り、事件の順番を構築していったと考えると、あの整然とした犯行にも納得がいく。
もう一人の影──トヨ。校外学習のシーンで見せた不審な動き、森の掲示板に関わる書き込み。これらが宇都見に情報を渡す“橋渡し”になっていた可能性も高い。
けれど、ここで最も重要なのは「誰が情報を渡したか」ではない。
本当の焦点は、“なぜ誰も止めなかったのか”ということだ。
真の共犯は、事件を消費して忘れていく視聴者かもしれない
このドラマが問いかけるのは、単なる犯人探しではない。
それは「記憶の責任」をめぐる物語だ。
教師・大谷はイジメを黙認した。周囲の大人たちは気づかぬふりをした。そして同級生たちは、紫苑の痛みを“懐かしいエピソード”に変えた。
その構造は、現実の私たちが日々目にしているものと同じだ。誰かが傷ついても、ニュースになれば数日で忘れる。事件が終われば、感想を語り合い、SNSで分析して、次の話題へ移る。
忘れることが、最大の共犯行為だ。
宇都見の復讐は、社会全体へのメタファーでもある。彼の行為は狂気に見えるが、その根底にあるのは「無関心」という怪物への反抗だった。
紫苑が死に、宇都見が捕まり、事件が終わる——それでも、何かが残る。
視聴者が涙を流し、怒り、そして数日後に日常へ戻っていく。その過程そのものが、彼らの“物語”を現実にしてしまう。
このドラマは、観客をも共犯にする。
「良いこと」と「悪いこと」の境界は、画面の中だけの話ではない。私たちが見て、忘れるたびに、どこかでまた一人の紫苑が沈黙していく。
だからこそ宇都見の言葉は、視聴者への最後の警告でもある。
「お前はいつまでも悪い子でいろ」——その“お前”には、きっと私たちも含まれている。
この物語の共犯者は、もうスクリーンの中に閉じ込められてはいない。
“カノン”が問いかける、赦されない社会
『良いこと悪いこと』第9話のタイトル「カノン」。
その曲名は、単なるBGMでも、瀬戸紫苑の思い出の象徴でもなかった。
それは、このドラマ全体を貫く“赦しなき世界の旋律”そのものだった。
音楽の中で繰り返される旋律——同じメロディが重なり、ずれて、再び戻る。それはまるで、人間が繰り返す過ちのようだった。
誰かを傷つけ、忘れ、また誰かが泣く。時間だけが進んで、痛みだけが置き去りになる。
\この「カノン」、ただのBGMじゃない/
>>>旋律の意味を、映像で受け取る
/繰り返されるのは、音か、罪か。\
加害者は忘れ、被害者は記憶に閉じ込められる
「カノン」の旋律が流れるたびに、紫苑と宇都見の過去が重なり合う。
紫苑にとっての音は“赦し”だった。彼女は音を奏でることで、自分の過去を超えようとした。だが社会は、そんな彼女を赦さなかった。
キングは、何気ない笑いで彼女の記憶を呼び覚ました。園子は「過去のことだから」と目をそらした。先生は沈黙した。
誰も悪気がない。だからこそ、誰も止められない。“悪意のない暴力”こそが、この社会の最も冷たい顔だ。
宇都見はそれを知っていた。だから彼は、「悪い子でいろ」と命じた。
それは赦しではなく、忘却への抵抗だった。
紫苑が命を絶ったのは、自分の弱さではなく、社会の無関心に押し潰された結果だ。彼女の死を“個人の悲劇”として片づけることが、この物語にとって最大の侮辱になる。
誰が正義で、誰が悪なのか──線はもう引けない
このドラマの恐ろしさは、犯人が誰かではなく、「誰も完全に無実ではない」という現実を突きつけたことにある。
紫苑を追い詰めたのは、キングたちの子ども時代の残酷さだけではない。大人になっても続く“見なかったことにする力”が、彼女の存在を再び消していった。
社会全体が「いいこと」と「わるいこと」を曖昧に混ぜ合わせながら、罪を薄めていく。
だが、薄められた罪は、消えたわけではない。
それは静かに、別の形で再生する。いじめの現場、SNSの炎上、あるいは誰かの無視。どの時代にも“カノン”は鳴り続けている。
この旋律が終わらないのは、誰も拍子を変えようとしないからだ。
宇都見は、その事実を最も深く理解していた。だからこそ彼は、世界を壊すしかなかった。
彼にとって復讐は、社会への告発であり、沈黙への反逆だった。
“カノン”の旋律が終わるとき、観客は拍手する。しかしその拍手の音の中に、彼女の泣き声は紛れていないだろうか。
赦されない社会とは、拍手の音で罪をかき消す社会のことだ。
この第9話は、その音を止めようとする一つの試みだった。
そして、「良いこと悪いこと」というタイトルの真意はここにある。
“いいこと”をしたつもりの沈黙が、“悪いこと”を育ててしまう。
その繰り返しが、社会の「カノン」なのだ。
誰もが「キング」になり得る──日常に潜む、無自覚という暴力
ここまで読んで、「キングは最低だ」と思った人は多いはずだ。
けれど、この物語が本当に怖いのは、キングが特別な悪人ではないところにある。
彼は怪物じゃない。普通に働き、家庭を持ち、笑って生きている。その“普通さ”こそが、このドラマの核心だ。
キングは、あまりにも私たちに近い。
\他人事だと思った瞬間、もう始まってる/
>>>自分の中の「キング」を、直視する
/この物語は、あなたの話でもある。\
悪意がなくても、人は誰かの人生を壊せる
キングは紫苑を殺そうとしたわけじゃない。
大人になってからも追い詰めようとした覚えすらない。ただ、娘を連れてピアノ教室を訪れただけだ。
それでも紫苑の世界は崩れた。
ここに、この物語の残酷な現実がある。
人は「何もしていない」ことで、誰かを深く傷つけてしまう。
職場でも、学校でも、同じ構図は繰り返されている。
昔、軽く言った一言。笑いながら流したあだ名。空気に合わせて黙った瞬間。
それらは記憶の中では「大したことのない過去」になっていく。でも、受け取った側の人生では、現在進行形の傷として残り続ける。
加害者に自覚がないからこそ、謝罪も償いも起きない。
そして被害者だけが、「もう終わったこと」に一人で取り残される。
「良い大人」でいるために、切り捨ててきたもの
キングは“ちゃんとした大人”になった。
家庭を持ち、仕事をこなし、社会の中で役割を果たしている。
でも、その過程で彼が切り捨てたものがある。
過去の自分と向き合う痛みだ。
人は前に進むために、都合の悪い記憶を整理する。「あれは子どもの頃の話」「みんなやってた」「もう時効だ」。
そうやって自分を守りながら、大人になっていく。
でも紫苑は、その“整理”からこぼれ落ちた。
彼女は前に進めなかったわけじゃない。必死に進もうとした。音楽を選び、夢を叶え、過去を乗り越えようとした。
それでも、過去を忘れた側が無邪気に現れた瞬間、すべてが巻き戻される。
この構造は、決してドラマの中だけの話じゃない。
「もう大人なんだから」「いつまで引きずってるの?」という言葉が、どれだけ簡単に人を追い詰めているか。
だからこの物語は、復讐譚で終わらない
宇都見の行動は、決して肯定されるものじゃない。
けれど彼が暴いたものは、社会の奥深くに沈んでいた真実だ。
「悪い人」よりも、「悪気のない人」の方が、ずっと多くの傷を生んでいる。
キングを責めて終わるのは簡単だ。でもそれでは、この物語は他人事のまま終わってしまう。
本当に突きつけられているのは、「自分は誰かの紫苑になっていないか」「知らないうちに誰かの宇都見を生んでいないか」という問いだ。
何気ない一言。沈黙の選択。思い出さないという態度。
それらが積み重なった先に、「カノン」は生まれる。
同じ旋律が、形を変えて何度も繰り返される。
だからこのドラマは、事件が解決しても終わらない。
日常に戻った瞬間から、もう一度、静かに始まっている。
——次に誰が忘れ、誰が壊れるのか。
その問いだけが、重く残されている。
良いこと悪いこと 第9話「カノン」まとめ──沈黙の旋律が告げた真実
『良いこと悪いこと』第9話「カノン」は、復讐の物語でありながら、“記憶と赦しの不可能性”を描いた現代の寓話だった。
誰もが何かを忘れようとし、誰かがそれを思い出さざるを得ない。この非対称な世界の中で、宇都見啓と瀬戸紫苑の存在は、“沈黙に抗う者”として最期まで音を奏で続けた。
復讐の果てに待っていたのは、勝利でも破滅でもない。「忘れさせない」という誓いだった。
\読み終えた今だからこそ、観てほしい/
>>>第9話「カノン」を、今すぐ再生する
/答えは、映像の中にしかない。\
復讐は終わっても、痛みは止まらない
宇都見は捕まり、事件は終わる。だが、その瞬間に物語が静かに問いかけてくる。
「この世界の誰かが、また紫苑のように傷つくとしたら——それでもあなたは何も変えないのか?」
彼が生きている限り、キングはその問いを抱え続けるだろう。日常に戻っても、娘の笑い声の裏で紫苑の泣き声が響く。
宇都見の復讐は終わらなかった。彼の代わりに、罪を思い出す人々が生きている限り。
だからこそ、この物語は悲劇であると同時に、赦されぬ祈りでもある。
人が人である限り、痛みは受け継がれていく。
それが“カノン”という曲が持つ本当の意味なのだ。
“悪い子でいろ”という呪いは、誰の中にもまだ生きている
宇都見の最後の言葉、「お前はいつまでも悪い子でいろ」。
その“お前”には、キングだけでなく、この世界に生きるすべての傍観者が含まれていた。
「良い子」でいるために、私たちはどれだけ多くのことを見過ごしてきただろう。
職場で、学校で、SNSで。誰かの声を聞かなかったふりをするたびに、世界のどこかでまた紫苑が沈黙する。
“悪い子”とは、罪を見つめる者のことだ。
痛みに目をそらさない者のことだ。
宇都見が望んだのは、その意味での「悪さ」だった。
それは、赦しを求めるのではなく、痛みと共に生きる勇気だったのかもしれない。
第9話「カノン」は、物語の終わりではない。
それは視聴者一人ひとりが“次の旋律”を奏でるための始まりだった。
宇都見のピアノが止まっても、紫苑の声が聞こえなくても、世界のどこかでまた同じメロディが始まる。
繰り返される“カノン”のように、痛みも、記憶も、忘却も、続いていく。
だからこそ私たちは問われている。
「良いこと」と「悪いこと」を、どこで区切るのか。
そして、その問いに答えるための旋律は、もう私たちの中で鳴り始めている。
- 第1話“正義”が腐る夜の真実
- 第2話 届かない謝罪の行方
- 第3話 絶交が残した痛みとは
- 第4話 忘れられた7人目の闇
- 第5話 博士=堀遼太説とイマクニの正体
- 第5話考察 博士の共犯関係・委員長の動機・ビデオテープの意味
- 第5話までの考察まとめ
- 第6話 委員長の復讐と園子が背負う“無実”
- 第7話 友情という名の罪は、誰に渡されたのか
- 第8話 “もうひとりのドの子”瀬戸紫苑の真実と、東雲に隠された「罪の継承」
- 子役が映す純粋と残酷の境界
- 主題歌“アゲハ蝶”が照らす罪
- 「森のくまさん」の呪い考察
- 黒塗りの6人に隠された真実
- 原作が暴く“子どもの罪”とは
- 正義と悪が交差する心理考察
- 委員長・紗季の壊れた正義とは
- 消える子どもたちの真相とは
- 東雲の沈黙に隠された真実
- 漫画版との比較から真意を読み解く
- キングは二重人格か?
- 剛力彩芽演じる土屋ゆきは犯人?
- 7人目の同級生=博士こと森智也の考察
- 森先生の正体
- ドの子とターボーの伏線を総まとめ
- 第9話「カノン」は、宇都見啓と瀬戸紫苑の“赦されない記憶”を描く物語
- 宇都見の復讐は、愛ではなく「忘却」への反逆として行われた
- 瀬戸紫苑は音楽に救われながらも、過去の記憶に再び沈んでいった
- キングを殺さず生かしたのは、罪を永遠に続けさせるための罰だった
- 共犯者の影は、沈黙し忘れていく社会そのものを映している
- “カノン”は希望の曲ではなく、赦しなき社会の反復を象徴する旋律
- 誰もが「キング」になり得るという警告が、物語の核心にある
- 「悪い子でいろ」という言葉は、痛みを見つめ続ける者への祈り
- この物語は終わらず、私たちの日常の中で今も鳴り続けている

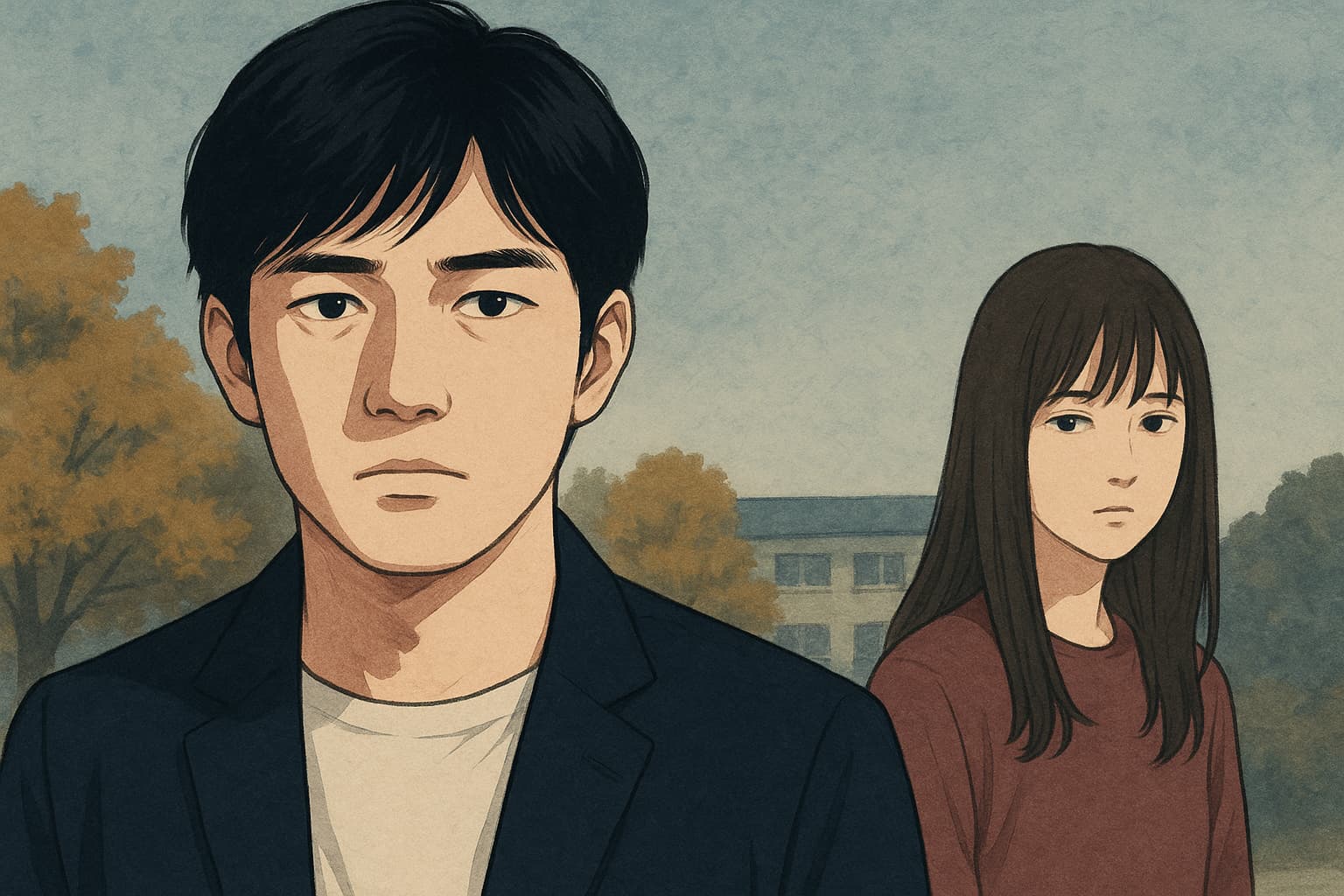



コメント